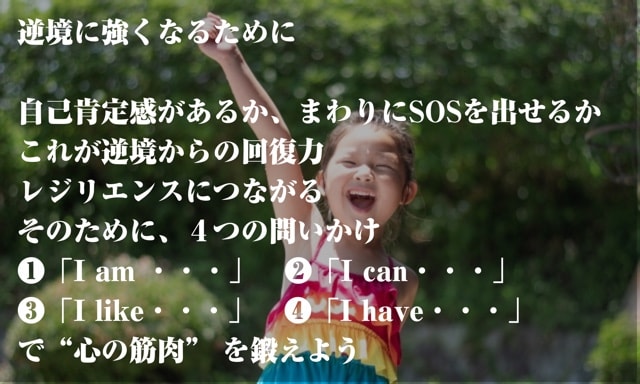こんにちは、四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、勉強中の子どもの頭の中について書きます。
自分の子どもが学んでいる時に、
頭の中で何が起こっているのかを見てみたいですよね。
❤︎同じ問題なのに、答えられない
子どもが、
ある問題の類題を解いている時、
親から見ると、
「同じ問題」だから簡単と思っても、
子どもから見ると、
「同じ問題」には見えず、
全く答えることができないという場合があります。
なぜか、
それは「抽象化能力」に問題があります。
❤︎うさぎの抽象化
例えていえば、
「耳が長くて、ぴょんぴょん飛び跳ね、鼻をピクピク動かす生物」が、
「うさぎ」であるというように抽象化ができず、
ただ「ふさふさしていて、4本の足で走り、ヒゲがある」と捉えてしまって、
うさぎか猫か犬か何かわからないでいるような感じです。
❤︎「抽象化能力」自体は、人間特有の「情報を統合して解釈する力」
スーパーコンピュータは、
1000万個の「具体」を暗記できても、
抽象化の確率は75%だそうです。
コンピュータは、
それぞれ「具体的」に別々に判断し暗記していきますので、
「抽象化能力」は苦手です。
われわれ人間は、
そんなにたくさん具体数を見なくても、
抽象化できますね。
このように、
「抽象化能力」は、人間特有の「情報を統合して解釈する力」です。
❤︎発達段階にある子どもの頭は、コンピュータと同じ
子どもは、
「抽象化思考」を用いずに、
あたかもコンピュータのように
「問題を、別々のものとして大量に暗記して」いきます。
だから、
発展段階にある子どもは、
大量の問題を解くことをしなければ、
抽象化できないのです。
❤︎「地頭」がよいことと「抽象化能力」
この抽象化能力は、
一般的に「地頭」と言われるものと近い関係にあります。
ものごとを、
抽象化された知識と高度に関連づけて考えられることが、
地頭が強いということになります。
だから、
発達途上の小学生の子どもたちにとっては、
いかに「抽象化思考」ができるようになるかが、
直面している学びの世界なのです。
❤︎「抽象化能力」とは何か
「抽象化能力」とは、
「無駄な情報を省いて、その具体の問題に『ラベルづけ』を行う力」
「関係が弱い要素を無視して、関係が強い要素を抽出して、判断する力」
「共通している要素をくくっていく力」
です。
❤︎学びにおいて、抽象化能力は重要
「学び」において、
この「抽象化能力」は非常に重要になります。
「抽象化能力」が高ければ、
具体的な問題を解くだけで、
その問題で取り上げられている論点を理解することができます。
逆に、
「抽象化能力」が低ければ、
非常にたくさんの問題を解かなければ、
なかなか論点を理解することはできません。
更に、
記憶に関しても、
抽象化できると、
まとめて記憶することができますが、
抽象化できないと、
一問一問を別の問題として覚えるので、
忘れやすく、
復習の頻度や量も必然的に増やさなくてはならなくなります。
抽象化能力で、
学習効果が大きく変わってくることが
わかると思います。
❤︎子どもの頭の中で「抽象化能力」を育てるために
子どもは、
生まれてから、
いろいろなことを学んでいきます。
最初は、
耳で聞き、目で見て、手で触り……
五感を使って、
具体的なことを学ぶ中で、
たくさんの同じ
たくさんの似ている
たくさんの違い
を体験して、
だんだんと抽象的なことを理解していきます。
体験がなく、
抽象的なことを説明しても、
子どもには理解できないということです。
❤︎まとめ。勉強中の子どもの頭の中
大人にとって類題でも、
子どもにとって違う問題に映ることがあります。
それは「抽象化能力」が発展途上だからです。
たくさんの「具体」を体験して、
子どもが共通点に気づいて
初めて「抽象化」できるようになります。
そして、たくさんの「具体的」実体験が
地頭の強い子どもに育てる土台になります。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、勉強中の子どもの頭の中について書きます。
自分の子どもが学んでいる時に、
頭の中で何が起こっているのかを見てみたいですよね。
❤︎同じ問題なのに、答えられない
子どもが、
ある問題の類題を解いている時、
親から見ると、
「同じ問題」だから簡単と思っても、
子どもから見ると、
「同じ問題」には見えず、
全く答えることができないという場合があります。
なぜか、
それは「抽象化能力」に問題があります。
❤︎うさぎの抽象化
例えていえば、
「耳が長くて、ぴょんぴょん飛び跳ね、鼻をピクピク動かす生物」が、
「うさぎ」であるというように抽象化ができず、
ただ「ふさふさしていて、4本の足で走り、ヒゲがある」と捉えてしまって、
うさぎか猫か犬か何かわからないでいるような感じです。
❤︎「抽象化能力」自体は、人間特有の「情報を統合して解釈する力」
スーパーコンピュータは、
1000万個の「具体」を暗記できても、
抽象化の確率は75%だそうです。
コンピュータは、
それぞれ「具体的」に別々に判断し暗記していきますので、
「抽象化能力」は苦手です。
われわれ人間は、
そんなにたくさん具体数を見なくても、
抽象化できますね。
このように、
「抽象化能力」は、人間特有の「情報を統合して解釈する力」です。
❤︎発達段階にある子どもの頭は、コンピュータと同じ
子どもは、
「抽象化思考」を用いずに、
あたかもコンピュータのように
「問題を、別々のものとして大量に暗記して」いきます。
だから、
発展段階にある子どもは、
大量の問題を解くことをしなければ、
抽象化できないのです。
❤︎「地頭」がよいことと「抽象化能力」
この抽象化能力は、
一般的に「地頭」と言われるものと近い関係にあります。
ものごとを、
抽象化された知識と高度に関連づけて考えられることが、
地頭が強いということになります。
だから、
発達途上の小学生の子どもたちにとっては、
いかに「抽象化思考」ができるようになるかが、
直面している学びの世界なのです。
❤︎「抽象化能力」とは何か
「抽象化能力」とは、
「無駄な情報を省いて、その具体の問題に『ラベルづけ』を行う力」
「関係が弱い要素を無視して、関係が強い要素を抽出して、判断する力」
「共通している要素をくくっていく力」
です。
❤︎学びにおいて、抽象化能力は重要
「学び」において、
この「抽象化能力」は非常に重要になります。
「抽象化能力」が高ければ、
具体的な問題を解くだけで、
その問題で取り上げられている論点を理解することができます。
逆に、
「抽象化能力」が低ければ、
非常にたくさんの問題を解かなければ、
なかなか論点を理解することはできません。
更に、
記憶に関しても、
抽象化できると、
まとめて記憶することができますが、
抽象化できないと、
一問一問を別の問題として覚えるので、
忘れやすく、
復習の頻度や量も必然的に増やさなくてはならなくなります。
抽象化能力で、
学習効果が大きく変わってくることが
わかると思います。
❤︎子どもの頭の中で「抽象化能力」を育てるために
子どもは、
生まれてから、
いろいろなことを学んでいきます。
最初は、
耳で聞き、目で見て、手で触り……
五感を使って、
具体的なことを学ぶ中で、
たくさんの同じ
たくさんの似ている
たくさんの違い
を体験して、
だんだんと抽象的なことを理解していきます。
体験がなく、
抽象的なことを説明しても、
子どもには理解できないということです。
❤︎まとめ。勉強中の子どもの頭の中
大人にとって類題でも、
子どもにとって違う問題に映ることがあります。
それは「抽象化能力」が発展途上だからです。
たくさんの「具体」を体験して、
子どもが共通点に気づいて
初めて「抽象化」できるようになります。
そして、たくさんの「具体的」実体験が
地頭の強い子どもに育てる土台になります。