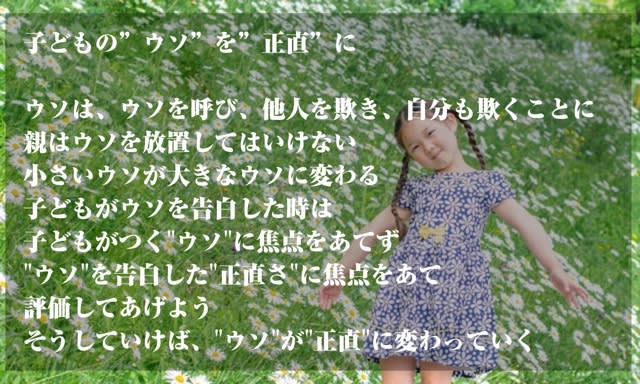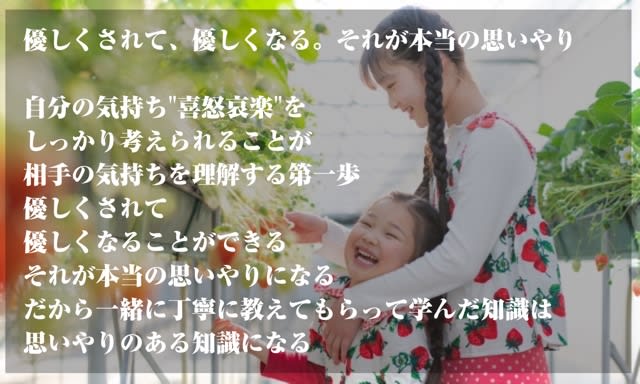こんにちは、
四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、現場主義について書きます。
❤︎現場主義とは
現場主義とは、
実際に行われている場所で、
実行の中から生じる問題点を捉えて、
それを改善し、質の向上を計ることです。
子どもにとって教室は現場です。
勉強も、
テストを受けることも現場です。
❤︎算数学習の現場主義
算数の学習の現場主義とは、
①計算力を徹底的に磨くことで、数字感覚をつかでいくとこと
②問題の設問を正しく理解していくこと
③図形をイメージすること
これらは算数学習のポイントでもあります。
❤︎算数の現場主義①計算を繰り返す
いろいろな計算を繰り返していると、
数と計算の感覚がどんどん身についてきます。
❤︎算数の現場②主語を表す助詞"は"を大切に読む
算数が苦手な子どもたちは、
問題文の内容を正確につかめていないことがほとんどです。
だから、
設問で述べられている条件や
求めたいものを
図式に描いて理解することが大切です。
その際、
主語を大切に読むのがポイントです。
❤︎整数の文章問題
2桁の整数Aがあります。
この整数の各位の数の和は12で、
十の位と一の位を入れ替えた整数Bは整数Aより36大きいそうです。
このとき整数Aを求めなさい。
❤︎主語に注目する
文章問題は、
主語を表す助詞"は"に注目をします。
日本語での"は"は、
数学では=(イコール)の役割をします。
そのため、
まずは問題を読みながら"は"が出てきたところに丸を付けます。
丸をした左側が方程式の左辺、
右側が右辺になることが決まります。
この問題では
「この整数の各位の数の和“は”12」、
「十の位と一の位を入れ替えた整数B“は”整数Aより36大きい」となります。
整数Aの十の位を○、一の位を□とすると、
「○+□=12」、
「10×□+○=10×□+○+36」となります。
問題文に書かれていることを正確に理解し、
正しく推論と計算をしていけば
誰でも解答にたどり着けます。
❤︎算数の現場主義③図形を具体的にイメージする
図形問題は、
公式を覚えて当てはめるだけでは、
基本問題は解けても、
応用問題となると解けません。
平面や立体の図を
具体的にイメージしながら、
どうすれば求めたい値にたどり着けるか
を考えていくことで
算数的な思考力、応用力が伸びていきます。
❤︎平行四辺形を長方形に変える
平行四辺形の面積の公式は、「底辺×高さ」です。
しかし、
内角の大きい一つの角から垂直に補助線を1本引いて、
できた三角形を反対側に移動させると、
長方形になります。
こうすれば、
平行四辺形の面積を求める公式を知らなくても、
長方形の面積の公式の縦×横で面積を割り出せます。
図形を頭のなかで描いたり動かし、
自分がもっている知識を組み合わせて
対応していけるようになります。
❤︎算数の現場主義④図形の証明問題は等しいを書き込む
「何を書けばよいのか分からない」のが証明問題です。
証明問題に取り組むときは、
問題を読みながら、
長さが等しい辺や大きさが等しい角を
図に書き込みます。
問題を図に再現するため、
図とにらめっこをして書き込み、
確認していきます。
そうすることによって解決策が見えてきます。
そして、
証明を書き始めることができるようになります。
1つでも2つでも書き始めることで
ほかにも書けることはないかと前向きな姿勢に変わっていきます。
❤︎まとめ。算数の現場主義で、知識をアップデートし、粘り強さを磨く
子どもにとり、教室・勉強・テストは現場です。
算数の現場主義は、
①計算力を徹底的に磨いていくこと
②問題の設問を正しく理解していくこと
③図形をイメージすること
たとえ、公式を知らなくても
今持っている知識を最大限利用して考えてぬく姿勢は、知識をアップデートし、粘り強さを磨きます。
四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、現場主義について書きます。
❤︎現場主義とは
現場主義とは、
実際に行われている場所で、
実行の中から生じる問題点を捉えて、
それを改善し、質の向上を計ることです。
子どもにとって教室は現場です。
勉強も、
テストを受けることも現場です。
❤︎算数学習の現場主義
算数の学習の現場主義とは、
①計算力を徹底的に磨くことで、数字感覚をつかでいくとこと
②問題の設問を正しく理解していくこと
③図形をイメージすること
これらは算数学習のポイントでもあります。
❤︎算数の現場主義①計算を繰り返す
いろいろな計算を繰り返していると、
数と計算の感覚がどんどん身についてきます。
❤︎算数の現場②主語を表す助詞"は"を大切に読む
算数が苦手な子どもたちは、
問題文の内容を正確につかめていないことがほとんどです。
だから、
設問で述べられている条件や
求めたいものを
図式に描いて理解することが大切です。
その際、
主語を大切に読むのがポイントです。
❤︎整数の文章問題
2桁の整数Aがあります。
この整数の各位の数の和は12で、
十の位と一の位を入れ替えた整数Bは整数Aより36大きいそうです。
このとき整数Aを求めなさい。
❤︎主語に注目する
文章問題は、
主語を表す助詞"は"に注目をします。
日本語での"は"は、
数学では=(イコール)の役割をします。
そのため、
まずは問題を読みながら"は"が出てきたところに丸を付けます。
丸をした左側が方程式の左辺、
右側が右辺になることが決まります。
この問題では
「この整数の各位の数の和“は”12」、
「十の位と一の位を入れ替えた整数B“は”整数Aより36大きい」となります。
整数Aの十の位を○、一の位を□とすると、
「○+□=12」、
「10×□+○=10×□+○+36」となります。
問題文に書かれていることを正確に理解し、
正しく推論と計算をしていけば
誰でも解答にたどり着けます。
❤︎算数の現場主義③図形を具体的にイメージする
図形問題は、
公式を覚えて当てはめるだけでは、
基本問題は解けても、
応用問題となると解けません。
平面や立体の図を
具体的にイメージしながら、
どうすれば求めたい値にたどり着けるか
を考えていくことで
算数的な思考力、応用力が伸びていきます。
❤︎平行四辺形を長方形に変える
平行四辺形の面積の公式は、「底辺×高さ」です。
しかし、
内角の大きい一つの角から垂直に補助線を1本引いて、
できた三角形を反対側に移動させると、
長方形になります。
こうすれば、
平行四辺形の面積を求める公式を知らなくても、
長方形の面積の公式の縦×横で面積を割り出せます。
図形を頭のなかで描いたり動かし、
自分がもっている知識を組み合わせて
対応していけるようになります。
❤︎算数の現場主義④図形の証明問題は等しいを書き込む
「何を書けばよいのか分からない」のが証明問題です。
証明問題に取り組むときは、
問題を読みながら、
長さが等しい辺や大きさが等しい角を
図に書き込みます。
問題を図に再現するため、
図とにらめっこをして書き込み、
確認していきます。
そうすることによって解決策が見えてきます。
そして、
証明を書き始めることができるようになります。
1つでも2つでも書き始めることで
ほかにも書けることはないかと前向きな姿勢に変わっていきます。
❤︎まとめ。算数の現場主義で、知識をアップデートし、粘り強さを磨く
子どもにとり、教室・勉強・テストは現場です。
算数の現場主義は、
①計算力を徹底的に磨いていくこと
②問題の設問を正しく理解していくこと
③図形をイメージすること
たとえ、公式を知らなくても
今持っている知識を最大限利用して考えてぬく姿勢は、知識をアップデートし、粘り強さを磨きます。