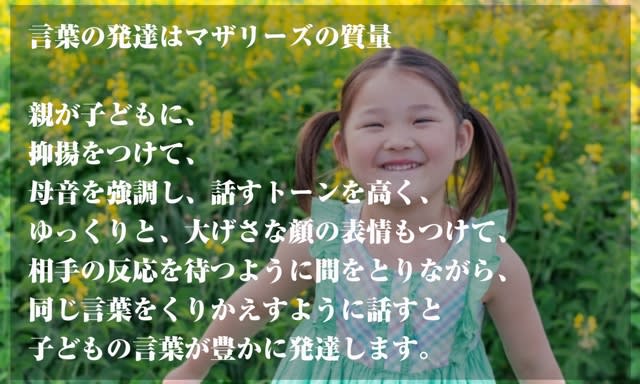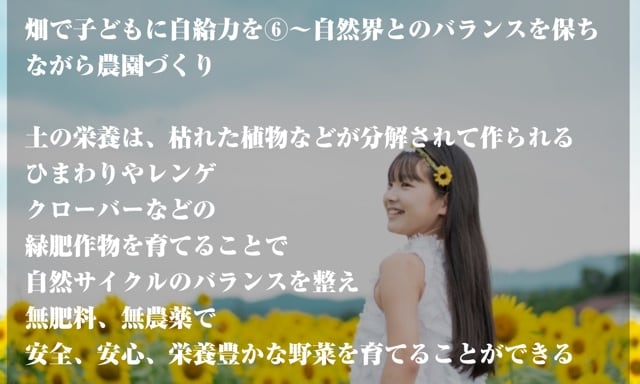こんにちは、
四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、子どものウソについて書きます。
❤︎子どものウソ
子どものウソは本当に「嘘」なのだろうか?
子どもは他人をだますことができるのであろう か?
ウソはいつから「嘘」になるのか?
❤︎"嘘"が起こるて原因
記憶の中から
特定の記憶を思い出す過程を
想起過程といい、
その過程で起こる
歪曲や加工作用が、
"嘘"をもたらす原因です。
注意できるスパンの多さ、長さ、深さが、
意図的な"嘘"を生み出しています。
❤︎注意できるスパンが小さい子ども
注意のスパンの小さな幼児期中期頃までは、
相手の視点に立って、
相手の意図を推測することは難しいです。
したがって、
子どもが相手の意図を裏切ってだましたり、
自分の身を守るために
相手の目を欺いて嘘をついたりするわけではありません。
❤︎子どもの"ウソ"は、"嘘"ではない
幼児期では、
現実と虚構の区別がつかず、
ウソとは知らずに、
思い出しの誤りから、
ウソをつこうとしてつくのではなく、
何気なくウソをついてしまいます。
しかし
そのウソは、本当の嘘ではありません。
❤︎子どものウソを、大人が知らず知らずに本当の嘘にしてしまう
子どもウソを本当の嘘に変えるのは、
大人です。
大人が
子どもの心身の発達の視点に立った
ウソのメカニズムを知らず、
大人自身の基準で子どもを見てしまうのです。
❤︎なじられ、非難される
幼い頃から、
身近な大人たちによって、
「嘘ついた」となじられ、
「だましたな」と非難されてきた子どもは、
幼児期の終わりには、
戦略的に「嘘」をつき、
他人を意図的に「だます」
ようになっていきます。
❤︎自我の芽生えた時期にしっかり愛情を
乳幼児期、
とくに自我が芽生える2歳から、
親に認められ、
承認され、
何よりも愛されて育った子どもは、
決して嘘をつきませんし、
他人をだましたりしません。
❤︎まとめ。子どものウソは、本当の"嘘"でない
子どもは、注意できるスパンが短く、
現実と虚構の区別がつかず、
ウソとは知らずに、
何気なくウソを言います。
そのウソが本当の嘘に転化するのは、
大人の基準から発する「嘘をついたな」
という言葉や態度です。
子どもをウソを認め、愛情を注ぐと、
四谷大塚NETフォーラム塾上本町教室塾長・学びスタジオ®︎代表の奧川えつひろです。
ご訪問いただき、ありがとうございます。
今回は、子どものウソについて書きます。
❤︎子どものウソ
子どものウソは本当に「嘘」なのだろうか?
子どもは他人をだますことができるのであろう か?
ウソはいつから「嘘」になるのか?
❤︎"嘘"が起こるて原因
記憶の中から
特定の記憶を思い出す過程を
想起過程といい、
その過程で起こる
歪曲や加工作用が、
"嘘"をもたらす原因です。
注意できるスパンの多さ、長さ、深さが、
意図的な"嘘"を生み出しています。
❤︎注意できるスパンが小さい子ども
注意のスパンの小さな幼児期中期頃までは、
相手の視点に立って、
相手の意図を推測することは難しいです。
したがって、
子どもが相手の意図を裏切ってだましたり、
自分の身を守るために
相手の目を欺いて嘘をついたりするわけではありません。
❤︎子どもの"ウソ"は、"嘘"ではない
幼児期では、
現実と虚構の区別がつかず、
ウソとは知らずに、
思い出しの誤りから、
ウソをつこうとしてつくのではなく、
何気なくウソをついてしまいます。
しかし
そのウソは、本当の嘘ではありません。
❤︎子どものウソを、大人が知らず知らずに本当の嘘にしてしまう
子どもウソを本当の嘘に変えるのは、
大人です。
大人が
子どもの心身の発達の視点に立った
ウソのメカニズムを知らず、
大人自身の基準で子どもを見てしまうのです。
❤︎なじられ、非難される
幼い頃から、
身近な大人たちによって、
「嘘ついた」となじられ、
「だましたな」と非難されてきた子どもは、
幼児期の終わりには、
戦略的に「嘘」をつき、
他人を意図的に「だます」
ようになっていきます。
❤︎自我の芽生えた時期にしっかり愛情を
乳幼児期、
とくに自我が芽生える2歳から、
親に認められ、
承認され、
何よりも愛されて育った子どもは、
決して嘘をつきませんし、
他人をだましたりしません。
❤︎まとめ。子どものウソは、本当の"嘘"でない
子どもは、注意できるスパンが短く、
現実と虚構の区別がつかず、
ウソとは知らずに、
何気なくウソを言います。
そのウソが本当の嘘に転化するのは、
大人の基準から発する「嘘をついたな」
という言葉や態度です。
子どもをウソを認め、愛情を注ぐと、
嘘をつかない、正直な子どもに育ちます。