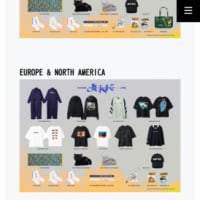Forbes-フォーブスは、アメリカ合衆国で発行されている経済雑誌である。隔週で発行され、金融、業界、投資、マーケティングなどのトピックについての記事を掲載している。また、技術、通信、科学、政治、法律などの関連記事も掲載している。本社はニュージャージー州ジャージーシティにある。ウィキ
Kenshi Yonezu Talks World Tour, Music Styles And The Future Of A.I.
米津玄師がワールドツアー、音楽スタイル、そしてAIの未来について語る
米津玄師は口数が少ない人だ。
彼は世界有数の日本人アーティストかもしれないが、そのことについて語るのではなく、むしろ音楽を通して自らを代弁する。それが、彼が国内外で成功を収めた多くの理由の一つなのかもしれない。2009年にはハチ名義で実験的なボーカロイド楽曲を制作し、その後はアカデミー賞を受賞した長編アニメーション映画『少年とサギ』や人気アニメシリーズ『チェンソーマン』の主題歌など、自身の楽曲も手掛けている。
Jポップ、ロック、エレクトロニックサウンドを融合させた音楽で知られる米津玄師の音楽は、魅惑的なメロディー、卓越したビジュアルコンセプト、そして深く思慮深い歌詞で、リスナーを「ユニークでダイナミックな音楽の旅」へと誘うと言われてきた。34歳の「シャイ」なアーティストである彼は、人と会話をするのが苦手で、自分の返答に迷いがちだと認めており、音楽は彼にとって表現の入り口となっている。しかし、ステージ上やスタジオにいる時は、彼は別人になる。最も「オープンで自由」だと感じられる時なのだ。
「演奏している時は、自分が長年作り、演奏してきた音楽なんです」と米津玄師はZoomの通訳を通して語る。「音楽を(作りながら)自分の気持ちを整理する時間がありました。自分の気持ちにとても正直に向き合える音楽なんです。だって、それが自分を慰めてくれるって分かっているから。」
先週、ニューヨークとロサンゼルスで行われたJUNKワールドツアーのソールドアウト公演で、アメリカのファンは米津玄師のそんな一面を垣間見る機会を得た。彼のセットリストには、シングル曲や多くのアルバムからの楽曲が含まれ、その中には『チェンソーマン』のオープニングテーマで、日本の楽曲として初めてRIAAゴールド認定を受けた「キックバック」が収録された最新アルバム『Lost Corner』(2024年)も含まれていた。
米津は、アメリカのファンの前で演奏できることに「大喜び」していた。ロサンゼルスを訪れたのは14~15年前だが、ニューヨークを訪れるのはラジオシティ・ミュージックホールが初めてだった。彼はうなずき、軽く微笑みながら「とても楽しいです」と言った。
以下、J-POPスターが、ついにヨーロッパと北米をツアーするという決断、日本のファンとの違い、自身の音楽スタイルの定義、J-POPの人気の高まり、そして芸術と音楽における人工知能(AI)についてどう感じているかについて語っています。
ローラ・シリクル:最終的にヨーロッパと北米をツアーすることに決めた理由は何ですか?
米津玄師:ご存知の通り、最近は日本の音楽が海外でも徐々に受け入れられるようになってきました。それが今の現状です。僕自身もずっとボーカロイドをやってきたので、待っていてくれる方もいらっしゃいましたし、そういう方々に向けてライブをさせていただくタイミングだと思いました。
シリクル:あなたの音楽のサウンドは、ポップからR&B、ロック、そしてジャズの要素も少し加えながら、プロジェクトごとに変化してきましたね。ご自身のサウンドや音楽のテイストをどのように定義していますか?
米津:僕は自分のスタイルを追求することにあまり興味がないんです。というか、決まったスタイルを追求することにあまり興味がないんです。昔から、自分が興味のあることをどんどん追求していくタイプなんです。今、自分が楽しいと感じているのは、
ずっと好きだった音楽、オルタナティヴ・ロックです。最初から好きだったのはまさにそれでした。バンドをやっていた時期もありましたが、残念ながらバンドは私には向いていませんでした。一人で活動し始めてから、特定のスタイルに囚われることなく、本当に自由に活動できるようになりました。一人で活動していると、何をしなければいけないという制約がなく、何でも自由にやれるんです。もし自分を定義づけるなら、J-POPを追求していると思います。
一つのスタイルがあなたを定義するわけではありません。あなたは実験や新しいことに挑戦するのが大好きです。ぜひ試してみたいスタイルはありますか?将来やってみたいスタイルはありますか?
米津玄師:僕は曲を作る人間なので、メロディーはすごく大事にしています。それが僕の仕事の核なんです。それを作れたら面白いかもしれないですね。
メロディーに頼りすぎない音楽。ラップも面白いかもしれない。
シリクル:あなたは2009年から「ハチ」として音楽業界に携わり、2012年にデビューしました。音楽業界はどのように変化しましたか?また、デビュー以来、あなた自身はどのように変化しましたか?
米津:僕の音楽キャリアはインターネットから始まったので、当時の新しいテクノロジーであるボーカロイドの恩恵を受けました。今ではボーカロイドは日本の国境を越えて世界中で受け入れられています。でも、僕がボーカロイドの音楽を制作していた頃は、それは本当に日本のシーンの中の文化で、僕のルーツはそこにあったんです。最近は日本の音楽シーンがますます国内志向になってきています。悲しいことに、海外の音楽を聴く人はそれほど多くありません。たいていは日本の音楽かK-POPのどちらかを選ぶという状況です。それが今の日本の現状です。僕は洋楽の影響を受けてきたので、今の状況は寂しいですね。一方で、日本人が自分たちのアイデンティティに満足しているという側面もあるのかもしれません。そういう意味で考えると、それは悪いことではないと思います。もちろん、今、日本の人口は減少傾向にあるので、日本の音楽業界が急激に成長しているわけではありません。これからどんな変化が起こるのか、私には分かりません。ミュージシャンとして、変化が起こるか起こらないかに関わらず、これから先どの方向へ進んでいくのか、常に考え続けなければなりません。
アメリカ文化には日本の影響が波のように押し寄せ、消えていきました。日本のアニメや映画の人気、そして日本のミュージシャンやアーティストの増加などです。音楽と(あなたの楽曲が)人気アニメに関わってきたあなたは、西洋における日本文化やコンテンツの評価の変化をどのように見ていますか?
(西洋の)変化や転換を強く感じています。新型コロナウイルスのパンデミックは、日本のアニメが世界の舞台でさらに活躍するきっかけとなり、大きな助けとなりました。私が活動を始めた頃はボーカロイドのシーンでした。ですから、インターネットはそういった意味で非常に大きな存在であり、私の音楽と他の国の人たちとの文化交流の場として機能していました。それも一因でしょう。インターネットは常に良い面ばかりではありませんが、悪い面もあるとはいえ、良いことに活用できることもあります。それでも、海外の人たちが私の音楽を聴いてくれるのは、とても嬉しいですね。
シリクル:あなたは、宮崎駿監督のアカデミー賞受賞作品『鷺の子』をはじめ、数々の美しいアニメシリーズや映画に携わってきました。また、自身のアルバムやシングルのジャケットにも美しいイラストを描かれています。近年、スタジオジブリ作品をはじめ、AIによるアートワークの模倣が盛んになっています。AIを用いてアート作品を制作するという、こうしたトレンドの高まりについて、どのようにお考えですか?
米津: AIに関しては、音楽に携わる人にとっては大きな問題、あるいはテーマです。インターネットでAIを使って私の歌を真似した曲を耳にしたことがあります。本当によく出来ています。そういう曲を聴くと、自分の声だと言われているのに、本当に自分で歌ったんじゃないかと思うこともあります。本当に私が歌ったのかな?AIに取って代わられるので、もしかしたら私自身が必要なくなるのかもしれません。もちろん、ほとんどの人は何か有益なものや簡単にアクセスできるものに出会ったら、それがあるからこそ使うでしょう。だから、なぜ使わないのか?でも、私の世代はAIが作ったものに嫌悪感を抱いています。いずれ、それを心から受け入れる世代が出てくるでしょう。今の私たちとは違う気持ちになるかもしれません。もちろん、私がボーカロイド界に足を踏み入れた頃は、「そんなのは歌じゃない」「歌を貶めている」と(些細な言い方で)言われていました。馬鹿げた話でした。今となっては、私の世代の若者にとって、それはとても興味深い出来事でした。AIとボーカロイドを同一視することはできません。全く異なるものであり、同じ言葉で語ることはできませんが、必ずしも正しい方法とは言えません。しかし、文化においては、私たちが今当たり前のこととして受け入れていること、あるいは(彼らが慣れ親しんでいること)が習慣化してしまうのです。それは時代によって大きく異なります。西洋の室内楽はブルジョワ階級から始まり、やがて私たち一般の人々に浸透していきました。私は貴族階級の出身でもなければ、高潔な人間でもありませんが、もし(当時)そのようなことが起こっていなければ、日常的な音楽として受け入れられることはなかったでしょう。彼らは室内楽を聴くことなど到底受け入れられなかったでしょう。私がこれをAIを擁護しているという意味に捉えてほしくはありませんが、AIは不道徳だと強く感じています。でも、ミュージシャンとして、それと共存していく方法を見つけないといけない。今はそう感じています。自分の中にどうしても手放せない核心的な部分があるけれど、それと健全に共存し、前進していく方法を見つけないといけない。
シリクル:ヨーロッパで西洋の観客の前で公演をされましたが、西洋文化と東洋文化の違いにはどのような点を感じますか?
米津:個人的に一番驚いたのは、観客の歓声に合わせて足踏みする音でした。まるで地底深くから響くような音でした。東アジアでのコンサートではあんな音を経験したことがなかったので、驚きました。
シリクル:あなたは6枚のスタジオアルバムをリリースし、数々のチャート入りを果たし、ツアーはソールドアウト。 『チェンソーマン』や『少年と鷺』など、世界的に成功を収めた数々のプロジェクトにも参加してきました。今後、挑戦したい目標はありますか?
米津:今は、いつまで創作を続けられるかという意識の方が強くなりました。具体的な目標があるわけではないのですが、今回のワールドツアーを通して、海外でこんなにたくさんの人が自分の音楽を聴いてくれているんだと実感しました。こんなにも熱烈に歓迎してもらえて、本当に感動しました。だから、今後はもっと海外の人たちを意識しながら音楽活動を続けていきたいですね。