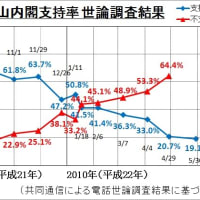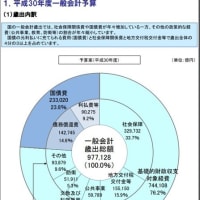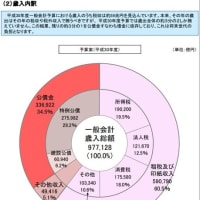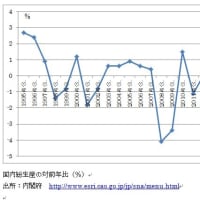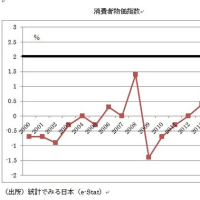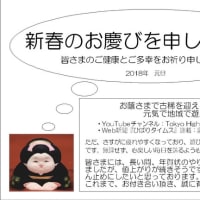毎週土曜日の朝日新聞の「be」を楽しみにしている。3月26日の「フロントランナー」には、台湾の建築家 黄聲遠さんが取り上げられていた。代表作として、台湾北東部の街、イーラン(宜蘭)に隣接する街に建つ「羅東(ルオトン)文化工場」が紹介されていた(台北を間に電子工業などで有名な新竹が中国側にあり、その反対の海側に位置するようだ)。
その記事によると「中空に浮かぶように設計されたギャラリーでは展覧会、巨大キャノピー(天蓋〈てんがい〉)の下ではコンサートや台湾オペラが催され、中華圏で最も権威ある映画祭「金馬奨」の会場にもなった。周囲の住民にとっては、日の光や雨露をしのぎながら時間を過ごせる憩いの広場であり、付近の学生の通学路でもある。足を踏み入れると威圧感がなく開放的だ。ゆったり犬を散歩させる人、健康のため裸足で後ろ向きに歩くおじいさん、キャッチボールをする子供たち、自転車をとめておしゃべりをする主婦。撮影の日も、様々な人々が思い思いの時間を過ごしていた。」とある。
イメージが湧かないのでHPを見たが、それでも分からないので、FBを見てみた。そうしたら、いくつかの写真があり、ようやくなんとなくイメージができた。空中に浮いていて、ちょっと不安だし、外部に開いているので、なんだか寒そうだけれど、女性が中から外を見ている写真を見ると落ち着く感じだ。








黄さんは、「台湾の大学を卒業後、米国に留学。一流建築事務所で働き、大学の教壇にも立った。そんなキャリアを捨て、山と海と川、そして美しい田園風景に囲まれた宜蘭に移住したのは1994年。従来の作品主義的な建築設計に疑問を抱き、別の可能性を探り始めた中での決断だった。住民の声に耳を傾けながらの再出発。最初に手がけたのはバスケットボールコートの整備や牛小屋の改装だった。人のつながりが濃い土地柄が少しずつ仕事の輪を広げてくれた。以来、地域の生態系や歴史、時に古い建物を生かしながら、生活に根ざした建物を生み出し続けた。やがて、周囲に開放された社会福祉センターや車用の橋の脇に設置した遊歩道など、公共建築を手がけるようになり、高い評価を得る。」
「地元の行政には新しい建物を建てる予算はあるが、古い建物を改修する予算はない。プロジェクトを立案する時、近くに壊れそうな壁や用水路があったら、工事規模を少し広げることで一緒に直してしまう。過去に手がけたものも含め、建物同士をつなぐ回廊(小道)を整備して、点を面に変え、地域全体をつなげていく。生まれるのは快適な公共空間と新しい人の流れ。このつながりを植物になぞらえ「維管束」と呼んでいる。宜蘭に拠点を構え二十数年。地域全体に無数の点が広がり、「維管束」同士もつながり始めた。気が付けば、壮大な街づくりが進行中だ。」と書かれている(「 」は、フロントランナーの記事から。以下も)。
黄さんは、「自分の建物は人にプレッシャーを与えるものであってほしくない。建築家が深刻な人間で深刻な建物を建てると、人も影響を受けるもの。私は、自分の設計に接した人が「私の人生は幸せだ」と確認してくれたらそれで十分なのです。」
記者の「時間をかけた地域密着の街づくり。アイデアはどこから来るのですか」という問いに、「難しいことではありません。地域の人に話を聞くんです。困っていること、改善してほしいこと、希望を集め覚えておく。宜蘭は農業が盛んですが、市の人口は10万人以下。地域ではみんなが顔見知りです。車を運転中、歩行者を見かけたら、車をとめておしゃべりをする。聞いた話と地域に残る資産をどう結びつけ、発展させるかを考えます。私は建築家なので建物を建てることが仕事です。でも建てることが目的ではなく、建物を通して地域に貢献することが重要だと考えています。建物を回廊で結ぶのも住民のためです。」と答えている。
FBページを見ると、ここでは、さまざまな文化的な催しが行われているようだ。椅子の展示会や籠の展示会、映画祭などなど。これが人口10万人のまちで行われ、観光客を呼び込んでいるらしい。
日本は、人口減少・高齢化に対し、無理やり経済活性化や人口減少を食い止める方策を取っている。格差が拡大し、貧困世帯が増えているという問題もある。限界集落という問題もある。
だけど、無理やり経済成長を望むより、満たされた生活を目指した方が良いのではないだろうか。日本の自然は「放射能汚染などがなければ」強い。水も豊かで、放っておいても草木が育つ。身の丈にあった生活をし、自然に逆らわない暮らしをすればよいのではないだろうか。
衣食住足りて、人々は、文化やおしゃべり(発信)を求めているのではないだろうか。 分からないけど、ヒントが詰まっているような気がする。