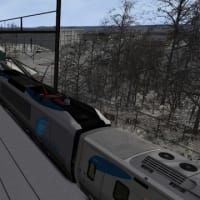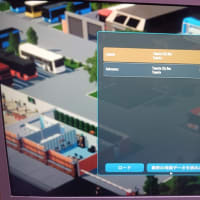鉄道ピクトリアル誌 2014年3月号「ワンマン系特集」です。
通巻887号・定価は950円

まずは表紙の紹介
京王5000系と思いきやの「50歳で故郷の電車運転士に転職したビジネスマン」の映画「Railways」の舞台になった一畑電鉄ですね(妙に説明が長いぞ?)
特集前半、「ワンマン運転の歴史的過程」「鉄道ワンマン運転のきのう・きょう・あした」などで、ワンマン運転について概論的に述べられています。
この中で特筆すべきは「ワンマン運転の法的要件」かなと。
ワンマン運転というのは鉄道の基本である運転士・車掌の2人乗務から車掌を省略した形態。
車掌の役割としてドアの開閉・車内放送など接客に関わる部分ともう一つ、運転保安、安全管理に関する部分があります。
鉄道趣味界であっても、この辺りへの言及はあまり見ない状況。前者の部分さえ自動化・機械化すればワンマン運転が出来る(回送列車はワンマン運転し放題)のように思われている部分があるので、運転保安や安全管理面など法規制的な部分も含めて記述されているのは意義があります。
回送列車のワンマン運転については数行触れているのみで、「ワンマン運転=営業列車の車掌省略」のようなまとめ方になっているのが残念。
ネット上のダイヤ・施策議論サイト等で「○○線は回送列車が多い。どうせ走らせるんだから客扱いして欲しい」のような書き込みに対して、その路線の回送列車がワンマン運転なのかどうか確認もせずにイメージで「客扱いすると車掌コストがかかるので無理だ」のようなイメージレスをする人がたまにいますが、「回送=ワンマン運転し放題」という認識は違うわけで。
本誌記事の不満点として、JR九州の都市圏区間の電車列車で行われているという「無人駅・早朝夜間無人駅など集改札を行わない駅を含む都市型ワンマン運転」に関する記述が全くないのが残念というか不手際感が。
特に冒頭の「ワンマン運転の歴史過程」の記事など運賃収受に関する記述が散見する中で、九州のような半信用乗車形都市型ワンマン運転に関しての記述が皆無なのはちょっと・・・今特集がワンマン運転の中でも都市型をメインにしているだけに残念ですね。

36~38ページ「ホームドア・ホーム柵いろいろ」
長編成列車のワンマン運転を行うに当っての必須装備ともなっているホームドアに関するミニ記事
新タイプ可動式ホーム柵の実験にも触れいて、つきみ野駅のタイプは韓国光州地下鉄の一部の駅で実用例があるみたいですね。ということはつきみ野駅(日本信号)タイプがリード??

これは私が撮影したつきみ野駅の新型ホーム柵の写真
沢山のセンサー類で見張られていて??列車接近中以外も柵に触れると「黄色線の後ろにおさがりください」のような放送が流れました。
ピクトリアル誌本文の話から反れますが、長編成でのワンマン運転での隠れた問題だと思うのが「ドア閉め操作」にに関する問題があります。
ツイッターの方で書きましたが、5月中旬頃、御殿場線の2両ワンマン列車に無人駅から乗車した時のこと。
いわゆるバス型ワンマンで、この時は100人近い乗客がホームで列車を待っている状態。
私は1両目後方の入口ドアから前の人に続いての乗車中、自分が最後になってしまったものの、満員状態で混んでる車内に頑張って乗り込もうとしたら、突然ドアを閉められて身体半分ドアに挟まれました

顔は外に出ていたので運転手の方を見ると、運転手は乗務員ドアの窓から顔を出してこちらを見ている状態。
「早く再開閉しろよ」と思い運転手の方を見ていても一向にドアが開かない・・・運転手がなにか車内放送を入れていたようですが、内容は聞き取れず不明。
結局、周囲の乗客がドアをこじ開ける形でドアを開けて助けてくれました。本当に腹が立っていた私は、助けてくれた乗客へのお礼もそこそこに「馬鹿運転手何か考えてるんだ?」と思わず叫んだぐらい。
数駅先の下車駅も無人駅だったので、一言文句を言おうと下車時に運転手にきっぷを渡しながら、もう「お前、どこ見てドア閉めてるんだよ

 」と怒鳴りつけるぐらいの形で文句を言ったのですが・・・運転手の方は「すみません」と謝るどころか、ドアに挟んだことも自覚しているのかどうか・・・ぐらいの調子で、もう本当に腹立たしかったです。
」と怒鳴りつけるぐらいの形で文句を言ったのですが・・・運転手の方は「すみません」と謝るどころか、ドアに挟んだことも自覚しているのかどうか・・・ぐらいの調子で、もう本当に腹立たしかったです。実際のところ2両編成の前の車両の後方ドア(約15m先)で立席で後方確認。かつ見通しのいい直線ホームでの出来事なので、見ていたのは事実なんでしょうが・・・
とりあえずここは好意的に解釈するとして、
乗車客が多く入口・出口ドアの2つでは、45秒の停車時間以前に乗り切るのに限界に近い人数な状態。所定の発車時刻からが超過している中で、後3人・・2人・・1人・・「まだかまだか」と乗車が終わるのを待っている中で、ドアボタンに指を掛けながらいたら、誤ってドア閉めボタンを押してしまったのが実際のところかなと。
仮に挟んでしまったものは仕方がないとしても、すぐに再開扉するべきだし、車内放送で「申し訳ありませんでした」ぐらいお詫びを入れるべきじゃないのかと思うわけで・・(社内規定でマニュアル外の勝手な放送は出来ない可能性もありますが・・そんなのは、私の知ったこっちゃないわけで)
今回は特に被害はありませんでしたが、ノートパソコンやタブレットなど大きめの電子機器を持っていたのが破損したとか、怪我をしていたりとかだったら、「不注意での事故」だとしても、とても許せるようなものではないのではないかと??
昨今の公共交通機関のバリアフリー対応が叫ばれている中で、もうバリアフリーどころかバリアフルな状態。よく「地方のローカル線は車を運転できないお年寄りなどにも重要な交通手段で・・・」というテンプレを語る人もいますが、このようなことではオチオチ乗っていられません。
そもそも私は御殿場線におけるワンマン運転のシステム自体に問題があると考えているので、今回の件は運転手の問題以前にJR東海の企業としての問題であり責任だと考えているので、JR東海や国交省に投書したりということはしなかったのですが・・・。
はっきり言ってこのような事故は、故意でなく不注意だとしても、鉄道設備を用いた乗務員から乗客への暴行(障害)に他ならないのではないかと思います。
昨今、「乗務員・駅係員への暴力防止キャンペーン」なども耳にしますが、このような乗務員から乗客への暴行行為が平然と許され、不注意だとしてもお詫びもないという状態では、「乗務員・駅係員への暴力防止」といわれても白けるというか、正直「いいぞ、もっとやれ」とは決して言いませんが、「同情も出来ない」というのが実感です。
さて私が遭遇したケースは「見通しのいい直線ホーム駅で、2両編成の前の車両の後方ドア。更に運転手は立席で後方確認でドア扱い」という安全確認上ではかなり恵まれているであろう条件下でのこと。
昨今の都市型ワンマン運転でよくある、運転台上に並ぶ小さいモニター画面を見ながら着席でドア扱いを行う。という形態が一般的ですが、果たしてこれでどこまで正確な安全確認が出来るのか?
この方式は、以前はせいぜい6両編成(120m程度)だったのが、現在では東京メトロ・副都心線では8両(160m)・10両編成(200m)でも採用されています。
あのモニターで見える範囲というものを考えると、整列乗車で前の人に続いて乗車している途中にドアを閉めて乗客をドアに挟む。という事故が一定数起きているのではないかと想像します。
少なくても副都心線クラスの長編成の場合、最低でもホームへの安全確認の係員配置を「運転士着席でのドア扱い」の条件にするべきではないかと・・・。
車掌乗務列車も含めてこのような「ドア閉め事故」というのは、現状「乗客」「乗務員」「鉄道事業者」の中で責任の所在が曖昧になっているからか、鉄道事業者側がそもそも「事故」と自覚しているかも疑問な状態。JR東日本の「ベビーカー引きづり事故」の様にマスコミで叩かれて多少対策をする程度の非常に遅れた状態。
現代の日本の鉄道では脱線や車両同士の衝突といった運転上のシステムに起因する事故が安全装置の進化により起きづらくなっている中で、日常的に頻発する「鉄道事故」としてもっとクローズアップされてしかるべきではないのでしょうか??
(起きづらくなっているといっても今年は結構起きてますが・・)
このような状況を察知しているのかどうか、ダイヤ面での動きとして、
メトロ南北線・都営三田線白金高輪駅での同時接続の廃止や、東急東横線・目黒線の武蔵小杉駅での東横線特急・目黒線急行の相互接続の廃止など、列車間の乗継ぎを重視した一見美しいダイヤを止めて乗換え時間に余裕を持つダイヤに改められている例を散見します。






 武蔵小杉駅での相互接続
武蔵小杉駅での相互接続目黒線日吉開業時の日中ダイヤでは、
武蔵小杉駅では東横線特急と目黒線急行が同時到着・同時発車。
横浜方面の場合、
A)渋谷発の特急から隣のホームの急行に乗り換えることで急行が通過する日吉駅へ
B)目黒方面からの急行から隣のホームの特急に乗り換えることで菊名・横浜方面に。
それぞれ待ち時間なくスムーズに乗り換えることが出来るダイヤ。
現在のダイヤでは
A)は急行に4分乗換え。1本前の目黒線各停が同時発車
B)は特急には11分乗換え。横浜方面へは4分後の急行に乗換え。
に変更






この背景に、「美しい乗換えダイヤ」の前提となる「30秒・1分単位での定時運転確保」が都市鉄道において難しくなっている。ということ以外にも、「発車時刻間際・超過時に乗換え元列車から結構な人数の乗客が、駆け込みで乗り換える」というのはドア閉めを行う乗務員への負担が大きく、またドア閉め事故に関するクレームが一定数集中しているという背景があるのではないかと感じます。
都市型ワンマン運転のダイヤ面への影響として、ホームドアの開閉時間により駅停車時間が長くなることでの所要時間増がありますが、もう一つこのような短い乗換え時間を前提としたダイヤ。も難しくなるのではないかと思います。

52~57ページ「乗務員からみたATOシステム」
ホームドアがある駅では停止位置に対してかなり正確に停止させる必要があるわけで、ホームドア設置路線で多く設置されているATOやTASCと呼ばれる自動運転システム。この項ではつくばエクスプレス(と思われる路線)を舞台に、その詳細や実際の運転操作について解説されています。
ATO運転での運転操作を運転席後ろから見ていると、駅発車時に「マスコンハンドルを引いて発車ボタンを押すだけ」という全くしてないじゃん
 と思ったりするわけですが・・その実際のところを??
と思ったりするわけですが・・その実際のところを??特筆する部分としては、「強風下の長大橋梁で25キロ以下の速度制限を実施」した場合など、ATOによる自動運転下では、プログラム上の指示速度より低い速度での定速運転。というのが非常に相性が悪いそうで・・。そのうち、これが遠因で事故でも起きるんじゃ?という気がしてきますね。
鉄道ピクトリアル誌でのワンマン運転特集はかなり以前にもあったと思いますが、今号では全体的にホームドアやATO・TASCなどの周辺分野の話題など、昨今の大都市圏路線に広がる都市型ワンマン運転とその周辺を主体とした内容になっているのかなと思います。

特集絡み以外の記事では64~72・92・93ページの「フィリピン国鉄南方線の日本型車両」の記事
首都マニラのあるルソン島を走るフィリピン国鉄(PNR)南方線のJRからの譲渡車両に関する車両面でのレポートが掲載されています。
フィリピン南方線のレポートは以前に私が鉄道ピクトリアル誌を紹介した時(2012年12月)にも掲載

雑誌-鉄道ピクトリアル(2012年12月号)211・213系特集
全長500キロ近い路線なものの幾度もの災害による長期不通区間が多く、マニラ近郊の60キロ弱の区間は元203系を改造した客車を主力として近郊輸送が行われているもののそれ以外では・・。
という状況のよう。
203系は色々大変な中、近郊輸送の主力として活躍しているものの・・・、元JR東日本仙台支社の「こがね」(団体貸切・臨時列車用)車両は、前回の記事では「豪華な設備もあって夜行急行列車で人気が高い」と安泰な紹介だったのが、その後にトラックとの衝突事故にあいの、路線自体が台風で不通と今や再起も不安な状態。となんとも切ない状態になっているようで・・・。
私も実際に行ってみれれば凄いんでしょうけど・・・予算どうこう以前にセブなどリゾートではない、マニラなどは治安が悪く観光客がふらふら行ける場所ではないようで。
他の記事では、新車紹介でJR九州77系(ななつ星車両)や阪急1000・1300系が登場しています。
ちなみに余談ですが、私がお世話になっている先生が今年度下半期内頃に鉄道ピクトリアルに寄稿されるそうで・・、詳細が分かったら紹介したいと思います。
今回の3月号はブックオフで200円で買ったもので
 その際は定価で買います・・というかこの間京王特集の臨時増刊号を書店で定価で買ってますが
その際は定価で買います・・というかこの間京王特集の臨時増刊号を書店で定価で買ってますが
【PR】amazon.co.jpで「鉄道ピクトリアル」を検索
【PR】楽天市場で「鉄道ピクトリアル」を検索
2014/7/30 2:23(JST)