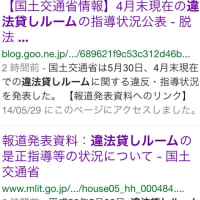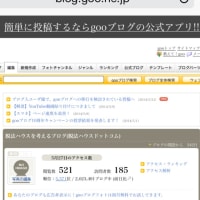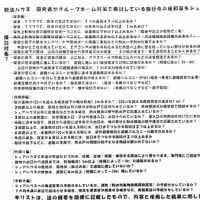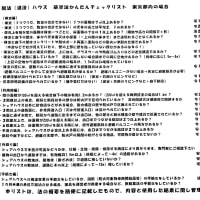1) 利用者に不利な契約形態
多くのシェアハウスの契約形態は、
賃貸マンションやアパートのような
「建物賃貸借契約」でなく「使用貸借」
になっています。
これは、建物賃貸借契約では、賃借人の
居住の権利が強すぎて、賃貸人からの
契約解除の申し入れがしにくく、大家
の気に入らない賃借人を追い出しにくい
制度です。それを逆手にとって、部屋の
一部使用という、レンタカーやレンタ
ルビデオのような契約形態を取ってい
るのです。このことで、契約更新を短い
サイクルにしたり、予告なしでの値上げ
や、いきなりの契約解除が可能である等
大家の都合に合わせたシステムにしてい
るのです。
シェアハウス契約も通常と同じ建物賃貸
借契約とし、居住者の利益を最大限確保
すべきなのです。また、国土交通省が
指導すべきは、間仕切りの防火性能など
の建築基準法といった観点よりも、利用
者が安定した居住を確保できるような、
契約形態となるよう宅建業法などの視点
から、契約そのものを改めさせるように
指導すべきなのです。
契約に際しても、シェアハウスの場合は
宅地建物取引士などの専門家の関与がな
いケースが多く、契約上の必要な情報が
得られにくくなっていたり、契約と実態
が違ったなどのトラブルへの対応も、
当事者同士で解決しなければならなかっ
たりするのです。これは面倒な宅建業法
を関与させたくないという事業者側や
オーナー側の理論と言えるでしょう。
この点では「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
(もっとも、借地借家法や宅建業法の
規制により、居住者の居住権を優先した
結果が、敷金礼金保証人の三点セットを
産んだり、入居審査が厳しかったり、
例えば建替えまでの短期間だけ貸すとい
うフレキシブルな住宅供給を阻害している
といったマイナス要因も無視できません)
2)初期費用が安いという罠
シェアハウスは初期費用がかからない事
がメリットと盛んに宣伝されています。
また、初期費用1万円やフリーレント
などと称して、最初の一ヶ月から数ヶ月
の利用料金を無料又は大幅値引きする
事例も見られるようです。
一般の賃貸住宅が、何らかの法規制に
よって礼金や敷金、保証人を取っている
義務ではなく、取るも取らざるも大家や
不動産屋の考え方次第なのです。
「シェアハウスだけが初期費用が安い」
のではなく、後述のような安全対策に係
る費用を惜しんだり、家賃設定に値引き
分を上乗せしていたり、光熱水費をピン
ハネしているから初期費用を安くできて
いるのです。
(もっとも、敷金礼金無のいわゆる
「ゼロゼロ物件」は保証料や即刻退去な
どトラブルも多いようなので注意。)
シェアハウスの初期費用ゼロは、結果
その費用が月々の家賃に含まれていたり
退去時の清算(一般の賃貸借契約では、
クリーニング費用などを徴収できない
が、使用貸借では契約次第である)だっ
たり、デポジット制などわかりにくい
ネーミングで退去時に費用がかかったり
するなど、初期費用を工面するよりも、
割高になるケースも多いのです。
保証人を取らないことと合わせて、今日
の住宅に困っている人、住宅を借りられ
ない人の足元を見たビジネスなのです。
保証人を取らない事で、オーナーや事業
者は、延滞や騒音苦情などのトラブルが
あれば、簡単に契約を解除したり違約金
をとったりすることができる契約です。
シェアハウスの安い初期費用は、シェア
ハウス独自のものや、事業者の努力でも
何でもなく、ただ利用者の犠牲や負担の
上に成り立っているのです。
先ほどの初月一ヶ月の無料サービスも、
最低半年間の入居が必要であって早期に
退去すると罰金を取られたりします。
まるで、携帯電話並のブラックさです。
この点では「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
最近は賃貸の空き家も増えています。
通常の賃貸マンションでも初期費用無、
wifi込み、保証人不要といった、より
借り易い物件が増えて行くかもしれま
せん。
3)下宿に劣る安全性と快適性
昔は、たくさんの下宿がありました。
子供世帯が独立した夫婦などが、学生や
季節労働者を相手に下宿を開いていた
ものです。
シェアハウスに住宅以上の規制がかかる
事に反対を示す人たちの中には、シェア
ハウスは現代版の下宿であり、規制を強
めるべきではないという人もいます。
しかしながら、下宿は旅館の一形態とし
て保健所の許可が必要であるとともに、
法律的にも、安全性や各室の界壁などの
プライバシーに、厳しい規定を満たす
必要があるのです。今のシェアハウスの
ように「法規制がかかるかどうかすら
確認せずに開設」したものとは根本的に
異なるのです。
この点では、「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
(もぐりでの「貸し間」など保健所など
の手続きをしていないものもあったで
しょうが)
4)無手続きで開設
先にあげたような下宿や、学生寮、企業
の従業員宿舎などは、寄宿舎という法律
上の枠組みに入ります。これは、複数の
人同士が暮らす施設にあっては、プライ
バシーも確保しなくてはいけない、万一
火災があっても赤の他人の財物まで燃え
る事は極力避けなければならないといっ
た視点から高い防火性や静粛性が求めら
れています。「一家が運命共同体」、
「住戸内の財物は共有財産である」とい
う戸建住宅やマンションの一室とは事情
が異なります。
ごく初期のシェアハウスは、使われなく
なった社員寮や学生寮をシェアハウスに
転用したため、こういった安全性は充分
確保されていました。消防法などの防火
設備もバッチリでした。その後シェア
が普及するにつれ、こういった寮の供給
は底を突き、新たに新築する例も出て
来ました。名古屋などで展開されている、
D-FLATさんなどは、新築時から充分に
検討されているめ、消防法や建築法に
適合する安全な建物を作ることができ、
開設に必要な書類も整いました。
ところがこういった遵法性の高いシェア
ハウスの表面だけを真似した多くの業者
は、消防法や建築法を無視してシェア
ハウスを作りました。昨年以降、住居を
倉庫として偽ったシェアハウスでの貧困
ビジネスやシェアハウスでの火災が問題
となり、初めて法の規制を受けることを
知りました。そして、法が悪い、規制の
後だし、9.6ショックだ、空き家対策に
水を差すとマスコミや議員を使って大騒
ぎをしています。
こうして見てみるときちんと法を守っ
ているD-FLATさんや元々安全性の高い
社員寮や学生寮を改修した業者が正しく、
法を見逃したり無視して利益を上げてき
た人達に非があることは明らかでしょう。
この点では、「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
管理人は、真っ当な手続きを踏み、高い
安全性を備えたシェアハウスを提供して
いる、D-FLATさんや、社員寮や学生寮を
きちんと転用しシェアハウスを運営して
いる事業者さんを応援したいと思います。
5)火災やトラブルの責任に無頓着
先に記述しましたが、シェアハウスが
戸建住宅やマンション、ルームシェアと
根本的に異なる部分として
「他人を住まわせそこから利益を得る」
という事業性と、事業性から発生する
責任の度合いが違うと思っています。
そして、その責任の重さに対し、大家や
事業者は「普通のアパート経営と同じ」
くらいの責任しか感じていないのではな
いかと感じています。
つまり、「利益は得たいが、責任は取り
たくない」ということでしょう。
具体例で言えば、事業者・管理者たる者
は火災について、例え放火であっても、
管理責任が付いて回ります。
ルームシェアであれば、火災があっても
「居住者同士の連帯責任」で済みますが
シェアハウスであれば、事業者すなわち
大家の「管理責任」が問われるのです。
歌舞伎町や高円寺での雑居ビル火災は、
放火やテナントからの出荷であっても
所有者責任・管理者責任が問われ、
執行猶予付きの実刑判決となりました。
今回の違法貸しルーム問題においても、
シェアハウスのオーナーは、防火対策を
講じ、指揮命令を行う、「防火管理者」
を選定する、あるいはオーナーよして
自らなるように指摘されたのではない
でしょうか。
そして、その防火管理者は消防法により
施設に常駐するか、それに準じた体制を
執らなければなりません。
そういった責任感や、使命感はもはや
「一間貸し」のレベルではなく、人を
預かる病院や福祉施設のようなイメージ
に近いと言えるでしょう。
そういった責任感を持って運営し、実際
に防火管理者が出動体制をとっている
シェアハウス事業者やオーナーは、相当
少数派ではないでしょうか?
この点では、「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営になって
います。
6)「うまみ」は事業者とオーナーに
ここまで見てくるとわかるように、
シェアハウスは、宣伝やテレビでいう所
の「他人同士が互いに助け合って暮らす」
理想論や、「初期費用を安く」という
利用者側よりも「大家や事業者の利益」
が優先して出来ていると言えます。
確かに、他の居住者との共同生活は他
では経験できないものがありますし、
初期費用の安さや、連帯保証人不要など
気軽に利用できるといったメリットは
あります。
それ以上に、事業者やオーナーにうまみ
があり、小分けにすることで利益を得て
いるのが、今のシェアハウスの現状です。
例えば、光熱水費が1ヶ月15000円定額の
シェアハウスというのが、よくあります。
しかし、よく見るとひと月の光熱水費が
3戸合計で45000円を越えたら罰金と書い
てあるのです。これでは、15000円未満の
場合は搾取されオーナーの利益になって
しまいます。こういう理不尽が、優良物件
が比較的多くて質が高いとされる、某干支
の名前のシェアサイトで堂々と紹介されて
います。
シェアハウスやサイト運営者にとって、
シェアハウス居住者は、生活を共にする
パートナーという素敵なものではなく、
「金のなる木」と考えているのかもしれ
ません。
生活保護費を搾取し、人権を奪うような
「貧困ビジネス」とシェアハウスは異なる
とPRされていますが、その実態や利益を
産み出す構造、貧弱な安全性、遵法性の
低さなどからみると、報道されている
「脱法ハウス」と通常のシェアハウスと
の違いは、
「住宅かどうかを偽っていないこと」
「部屋に窓があるか、狭いか広いか」
くらいのもので、そのビジネスモデルや
管理意識の根底にあるものは、変わらな
いことがお判りになるでしょう。
日本は資本主義を取り、持つものが、
持たざる者に勝つという世の中となって
います。
しかし、住居を生命維持の場と考えた時、
本当にこのような市場原理や管理者意識
だけで良いのか、読者の皆様も改めて
考えていただきたいと思います。
多くのシェアハウスの契約形態は、
賃貸マンションやアパートのような
「建物賃貸借契約」でなく「使用貸借」
になっています。
これは、建物賃貸借契約では、賃借人の
居住の権利が強すぎて、賃貸人からの
契約解除の申し入れがしにくく、大家
の気に入らない賃借人を追い出しにくい
制度です。それを逆手にとって、部屋の
一部使用という、レンタカーやレンタ
ルビデオのような契約形態を取ってい
るのです。このことで、契約更新を短い
サイクルにしたり、予告なしでの値上げ
や、いきなりの契約解除が可能である等
大家の都合に合わせたシステムにしてい
るのです。
シェアハウス契約も通常と同じ建物賃貸
借契約とし、居住者の利益を最大限確保
すべきなのです。また、国土交通省が
指導すべきは、間仕切りの防火性能など
の建築基準法といった観点よりも、利用
者が安定した居住を確保できるような、
契約形態となるよう宅建業法などの視点
から、契約そのものを改めさせるように
指導すべきなのです。
契約に際しても、シェアハウスの場合は
宅地建物取引士などの専門家の関与がな
いケースが多く、契約上の必要な情報が
得られにくくなっていたり、契約と実態
が違ったなどのトラブルへの対応も、
当事者同士で解決しなければならなかっ
たりするのです。これは面倒な宅建業法
を関与させたくないという事業者側や
オーナー側の理論と言えるでしょう。
この点では「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
(もっとも、借地借家法や宅建業法の
規制により、居住者の居住権を優先した
結果が、敷金礼金保証人の三点セットを
産んだり、入居審査が厳しかったり、
例えば建替えまでの短期間だけ貸すとい
うフレキシブルな住宅供給を阻害している
といったマイナス要因も無視できません)
2)初期費用が安いという罠
シェアハウスは初期費用がかからない事
がメリットと盛んに宣伝されています。
また、初期費用1万円やフリーレント
などと称して、最初の一ヶ月から数ヶ月
の利用料金を無料又は大幅値引きする
事例も見られるようです。
一般の賃貸住宅が、何らかの法規制に
よって礼金や敷金、保証人を取っている
義務ではなく、取るも取らざるも大家や
不動産屋の考え方次第なのです。
「シェアハウスだけが初期費用が安い」
のではなく、後述のような安全対策に係
る費用を惜しんだり、家賃設定に値引き
分を上乗せしていたり、光熱水費をピン
ハネしているから初期費用を安くできて
いるのです。
(もっとも、敷金礼金無のいわゆる
「ゼロゼロ物件」は保証料や即刻退去な
どトラブルも多いようなので注意。)
シェアハウスの初期費用ゼロは、結果
その費用が月々の家賃に含まれていたり
退去時の清算(一般の賃貸借契約では、
クリーニング費用などを徴収できない
が、使用貸借では契約次第である)だっ
たり、デポジット制などわかりにくい
ネーミングで退去時に費用がかかったり
するなど、初期費用を工面するよりも、
割高になるケースも多いのです。
保証人を取らないことと合わせて、今日
の住宅に困っている人、住宅を借りられ
ない人の足元を見たビジネスなのです。
保証人を取らない事で、オーナーや事業
者は、延滞や騒音苦情などのトラブルが
あれば、簡単に契約を解除したり違約金
をとったりすることができる契約です。
シェアハウスの安い初期費用は、シェア
ハウス独自のものや、事業者の努力でも
何でもなく、ただ利用者の犠牲や負担の
上に成り立っているのです。
先ほどの初月一ヶ月の無料サービスも、
最低半年間の入居が必要であって早期に
退去すると罰金を取られたりします。
まるで、携帯電話並のブラックさです。
この点では「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
最近は賃貸の空き家も増えています。
通常の賃貸マンションでも初期費用無、
wifi込み、保証人不要といった、より
借り易い物件が増えて行くかもしれま
せん。
3)下宿に劣る安全性と快適性
昔は、たくさんの下宿がありました。
子供世帯が独立した夫婦などが、学生や
季節労働者を相手に下宿を開いていた
ものです。
シェアハウスに住宅以上の規制がかかる
事に反対を示す人たちの中には、シェア
ハウスは現代版の下宿であり、規制を強
めるべきではないという人もいます。
しかしながら、下宿は旅館の一形態とし
て保健所の許可が必要であるとともに、
法律的にも、安全性や各室の界壁などの
プライバシーに、厳しい規定を満たす
必要があるのです。今のシェアハウスの
ように「法規制がかかるかどうかすら
確認せずに開設」したものとは根本的に
異なるのです。
この点では、「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
(もぐりでの「貸し間」など保健所など
の手続きをしていないものもあったで
しょうが)
4)無手続きで開設
先にあげたような下宿や、学生寮、企業
の従業員宿舎などは、寄宿舎という法律
上の枠組みに入ります。これは、複数の
人同士が暮らす施設にあっては、プライ
バシーも確保しなくてはいけない、万一
火災があっても赤の他人の財物まで燃え
る事は極力避けなければならないといっ
た視点から高い防火性や静粛性が求めら
れています。「一家が運命共同体」、
「住戸内の財物は共有財産である」とい
う戸建住宅やマンションの一室とは事情
が異なります。
ごく初期のシェアハウスは、使われなく
なった社員寮や学生寮をシェアハウスに
転用したため、こういった安全性は充分
確保されていました。消防法などの防火
設備もバッチリでした。その後シェア
が普及するにつれ、こういった寮の供給
は底を突き、新たに新築する例も出て
来ました。名古屋などで展開されている、
D-FLATさんなどは、新築時から充分に
検討されているめ、消防法や建築法に
適合する安全な建物を作ることができ、
開設に必要な書類も整いました。
ところがこういった遵法性の高いシェア
ハウスの表面だけを真似した多くの業者
は、消防法や建築法を無視してシェア
ハウスを作りました。昨年以降、住居を
倉庫として偽ったシェアハウスでの貧困
ビジネスやシェアハウスでの火災が問題
となり、初めて法の規制を受けることを
知りました。そして、法が悪い、規制の
後だし、9.6ショックだ、空き家対策に
水を差すとマスコミや議員を使って大騒
ぎをしています。
こうして見てみるときちんと法を守っ
ているD-FLATさんや元々安全性の高い
社員寮や学生寮を改修した業者が正しく、
法を見逃したり無視して利益を上げてき
た人達に非があることは明らかでしょう。
この点では、「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営形態になっ
ています。
管理人は、真っ当な手続きを踏み、高い
安全性を備えたシェアハウスを提供して
いる、D-FLATさんや、社員寮や学生寮を
きちんと転用しシェアハウスを運営して
いる事業者さんを応援したいと思います。
5)火災やトラブルの責任に無頓着
先に記述しましたが、シェアハウスが
戸建住宅やマンション、ルームシェアと
根本的に異なる部分として
「他人を住まわせそこから利益を得る」
という事業性と、事業性から発生する
責任の度合いが違うと思っています。
そして、その責任の重さに対し、大家や
事業者は「普通のアパート経営と同じ」
くらいの責任しか感じていないのではな
いかと感じています。
つまり、「利益は得たいが、責任は取り
たくない」ということでしょう。
具体例で言えば、事業者・管理者たる者
は火災について、例え放火であっても、
管理責任が付いて回ります。
ルームシェアであれば、火災があっても
「居住者同士の連帯責任」で済みますが
シェアハウスであれば、事業者すなわち
大家の「管理責任」が問われるのです。
歌舞伎町や高円寺での雑居ビル火災は、
放火やテナントからの出荷であっても
所有者責任・管理者責任が問われ、
執行猶予付きの実刑判決となりました。
今回の違法貸しルーム問題においても、
シェアハウスのオーナーは、防火対策を
講じ、指揮命令を行う、「防火管理者」
を選定する、あるいはオーナーよして
自らなるように指摘されたのではない
でしょうか。
そして、その防火管理者は消防法により
施設に常駐するか、それに準じた体制を
執らなければなりません。
そういった責任感や、使命感はもはや
「一間貸し」のレベルではなく、人を
預かる病院や福祉施設のようなイメージ
に近いと言えるでしょう。
そういった責任感を持って運営し、実際
に防火管理者が出動体制をとっている
シェアハウス事業者やオーナーは、相当
少数派ではないでしょうか?
この点では、「脱法ハウス」も「シェア
ハウス」もほとんど同じ運営になって
います。
6)「うまみ」は事業者とオーナーに
ここまで見てくるとわかるように、
シェアハウスは、宣伝やテレビでいう所
の「他人同士が互いに助け合って暮らす」
理想論や、「初期費用を安く」という
利用者側よりも「大家や事業者の利益」
が優先して出来ていると言えます。
確かに、他の居住者との共同生活は他
では経験できないものがありますし、
初期費用の安さや、連帯保証人不要など
気軽に利用できるといったメリットは
あります。
それ以上に、事業者やオーナーにうまみ
があり、小分けにすることで利益を得て
いるのが、今のシェアハウスの現状です。
例えば、光熱水費が1ヶ月15000円定額の
シェアハウスというのが、よくあります。
しかし、よく見るとひと月の光熱水費が
3戸合計で45000円を越えたら罰金と書い
てあるのです。これでは、15000円未満の
場合は搾取されオーナーの利益になって
しまいます。こういう理不尽が、優良物件
が比較的多くて質が高いとされる、某干支
の名前のシェアサイトで堂々と紹介されて
います。
シェアハウスやサイト運営者にとって、
シェアハウス居住者は、生活を共にする
パートナーという素敵なものではなく、
「金のなる木」と考えているのかもしれ
ません。
生活保護費を搾取し、人権を奪うような
「貧困ビジネス」とシェアハウスは異なる
とPRされていますが、その実態や利益を
産み出す構造、貧弱な安全性、遵法性の
低さなどからみると、報道されている
「脱法ハウス」と通常のシェアハウスと
の違いは、
「住宅かどうかを偽っていないこと」
「部屋に窓があるか、狭いか広いか」
くらいのもので、そのビジネスモデルや
管理意識の根底にあるものは、変わらな
いことがお判りになるでしょう。
日本は資本主義を取り、持つものが、
持たざる者に勝つという世の中となって
います。
しかし、住居を生命維持の場と考えた時、
本当にこのような市場原理や管理者意識
だけで良いのか、読者の皆様も改めて
考えていただきたいと思います。