
真夏の、痛いほどに明るい陽射しが
美術館の入り口前では間接照明になって。

庭園は、“光の楽園”。

庭園の一角で。
久保紀波さんの、白い日傘を入館時に預けてしまったので、
別の晴雨兼用傘になってしまったのが、心残り。
-----------------------------
さて、この日聴講したのは、
「手紙-こころを伝える-」の展示に因んだ、
展示物の解説と、昔の手紙の鑑賞の仕方などについて。
手紙も含め、書の鑑賞ではつい、何が書かれているか一所懸命
読みたくなってしまうものだが、
この日ご説明くださった、学芸部長の松原茂氏いわく
「作品として書いたものならともかく、個人宛に書いた手紙は、
専門家でも読めないものが多い。字の崩し方も自己流だし、『それ』『あれ』と
当人同士しかわからない指示語が多かったりすると、解読もお手あげ。
なので、字を鑑賞したり、手紙の形式を鑑賞したり、という方が楽しめる」
(大意です)
とのこと。
たとえば800年前の僧侶、明恵上人は
「仏教に没頭するため、自分で左耳を削いでしまうなど、激しい性格で知られる。
手紙の文字も、力強い」
江戸時代の武家茶道家で知られる小堀遠州は
「手紙の中で和歌を詠むのが特徴。手紙はたくさん残っているが
鑑賞に値するいい手紙は少ない」んですって!
手紙の形式とは、例えば文章の順番。

これは展示物ではないのですが、江戸時代の手紙。
実は右から順番に読んでいっても、意味は通じない、というか、読めない。

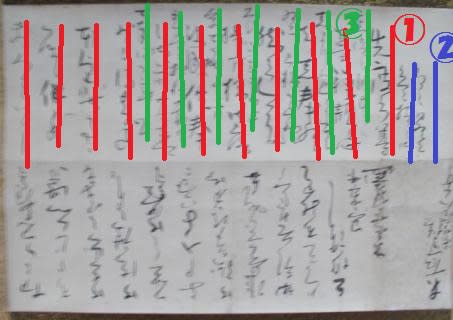
まず、紙を横に二つ折りにし、上半分に書いていき(写真赤字)、
上半分が終わると、紙を天地返して下半分に書く
(なので下半分は、さかさまに)、
それで書ききれないと、最初に戻って前の方の余白に書く(写真青字)、
それでも書ききれないと、何と行間に書く!(写真緑字)
つまり、受け取った側は上の①、②、③の順に読む、というワケ……。
紙の大きさも
「地位の高い人ほど大きいなど、身分によって使える紙は決まっていた。」(松原氏)
今回の展示で紙がもっとも大きかったのは
江戸前期の後水尾天皇で、
もっとも小さかったのは
万葉集を研究した国学者の契沖。
→この方、身分が低かったというわけではないのですが、
展示されていた手紙にはちょっと可哀想なエピソードが。
実は、自分の研究成果を、水戸藩にいいように利用されそうになっていることがわかり
「私は日の目を見ない、野の桜なのでしょうか・・・」と、
なよなよした字で不安を書きつづったのが、この小さな紙に書いた手紙、というワケ。
実物をお見せできず、残念ですが……。
その他、
幕末の絵師、東東洋(あずまとうよう)は、上の写真のように上下に折った紙の
折り目を切って横につなげ、巻紙の体裁にしたとか
(幕末以前を扱った時代劇で、巻紙をぱーっと開く、なんてシーンがあったら、
それは時代考証ができていない、と松原氏はおっしゃっていました)
やはり幕末の書家、米庵は、冒頭に時候のあいさつを書いていて、
それが今の体裁(マナー)につながっているとか
(つまりそれまでの手紙は、いきなり本題に入っていた)
江戸後期の画家 谷文二は、アート性の高い二色に染め分けた紙を使っていたとか
「この人、実はお金に細かくてね」
「この人は、朝廷にうざらがれて、島流しに遭っちゃってね」
「この人はすごい自意識過剰で……」
展示物の内容の解説、というよりは、
手紙を書いた人々の人となりを、かなり赤裸々にお話くださったのが
印象的だった。
 そうか、そんなにかしこまって見なくても、いいんだな
そうか、そんなにかしこまって見なくても、いいんだな
ということがわかったのが、一番の収穫かな。
見られる方は、今ごろ天かどこかで、「たまったものではない」と
焦っているかも知れないけれど、
そんなヒューマンな部分を知ることができるのは、私にとっては
楽しいことだ。
※根津美術館のサイトはコチラ
※こちらは“観賞用の”書ですが、王羲之展でも似たような感想を持ったことを
思い出しました。記事はコチラ






















