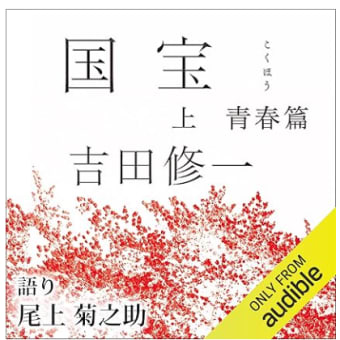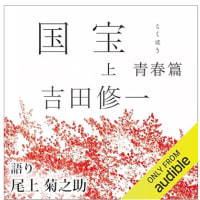祖母の形見の綿麻に、秋テイストを加えてお出かけした
週明けのこと。

(何だか顔が不自然に小さく撮れていますが、カメラの角度の問題‥?)
横浜駅のディスプレイはすっかり、秋模様。

東口方面のエスカレーターにて。
さて、横浜そごう美術館で10月16日まで開催中の
オールドノリタケ展。この展示では
ジャポニズムからアールヌーヴォー、そしてアールデコまでの
大きな流れをおもに、俯瞰することができました。

明治の陶器と言えば私は
宮川香山に代表される超絶技巧ばかりが印象に残っていましたが、
↓

こういうの。
でもこういうテイストが欧州で大うけしたのは
1800年代後半のことで
1900年代に入ると同じ自然モチーフでも、
もっと優雅でやさしい曲線遣いに特徴のあるアールヌーヴォーに
人気がうつっていったそう。
そんな中、すでにニューヨークに活動の拠点を築いていた
ノリタケ創始者の森村市左衛門の弟、豊氏は
1800年代の終わりに横浜で、実業家 大倉孫兵衛と出会い
その影響でアールヌーヴォー様式を取り入れた
食器の生産に力を入れるようになったそう。
そして1920年代に入ると米国で、より幾何学的な(当時はモダン)
はっきりした色彩のアールデコが流行るようになり
ノリタケのラインナップも幅広くなって、たくさんのシリーズが
展開されたとか。
技法の紹介もたくさんありましたが、特に目立ったのが
「盛上げ」
金彩や、エナメルが文字通り、盛ってあって
リッチな立体感を出す技法です。
こちら、欧州でも人気で「MORIAGE」として知られていたそう。
日本語がそのまま海外にとっての外来語として使われる例って
「スキヤキ」とか「カラオケ」とか「ボンサイ」とか
いくつもありますが、
「モリアゲ」はもしかして、そのさきがけ!?
また、1900年代前半の高級な飲み物としてチョコレートが
上流階級に流行ったので、
チョコレート用のポットとか、カップなどのセットがいくつも。
(注ぎ口がやや上の方にあるのが特徴だそう)
昔ならではの灰皿とか、
ジャムポット、トースタースタンドなど
ノリタケはピンポイントの用途の食器が多く
そんなところもリッチな富裕層の暮らしを、想像させるような展示でした。
展示数も多く、食器好きには特におすすめの展示です。
さすがに、ずらりと目の前にしても高級すぎて「欲しいなー」とまでは…

でも、いつまでも眺めていたい美しさでした。