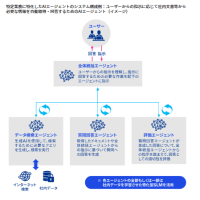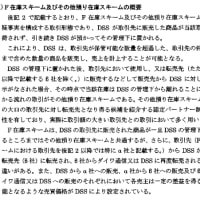【再掲】キャッツ事件再審請求の細野祐二さんインタビュー「公認会計士をクビになって本当の会計士になれた」(2016年11月11日)
だいぶ前の記事の再掲載ですが、元公認会計士の細野氏(最近、キャッツ事件の再審請求を行いました)へのインタビュー記事。
今の会計監査を批判した部分
「── 企業経営者と密接なコミュニケーションが取れず、信頼関係を築けなくなったということですか。
細野 そうです。以前は、特にベンチャー企業の場合ですが、店頭公開や上場にこぎつけるには、財務諸表の作成方法、資金調達、提携先選びなど、経営者と一緒に汗をかいて、まさに会計士が企業を育て上げるという醍醐味(だいごみ)がありました。
今は経営者と会計士との間で、そんな泥臭い付き合いはなく、大企業になればなるほど機械的で無機質な監査業務・体制になってしまっています。大手監査法人に入社してくる若手や中堅幹部は大過なく過ごそうとするサラリーマン会計士だらけです。
クライアント企業からは「寄生虫」と見下され、それに甘んじているような現状では、不正会計を正すなんて夢のまた夢。不正会計や粉飾決算の防止と発見こそ、公認会計士の社会的存在意義ですが、今やそれが認められない深刻な事態に陥っています。」
「── 企業の業績が悪くなり経営が不安定化すると、監査のリスクが高まるとして契約を解除する大手監査法人があります。
細野 経営が不安定な会社ほど、質の高い監査が必要です。監査の意義も高くなります。リスクが高いからと、大手が監査契約を解除するのはプロとしての責任回避です。大手が断れば中小や個人の公認会計士が監査を行わざるを得ず、監査の質が落ちます。その結果、不正の防止は難しくなり、それが発覚するとさらに企業会計に対する投資家や消費者の不信が強まるという悪循環に陥る。」
キャッツ事件にもふれています。
「── キャッツの元幹部らは、1審では細野さんが粉飾決算に加担共謀したと証言したのに、2審では一転して逆転証言を行いました。また、細野さんが粉飾決算に加担共謀したという会議の日に、海外主張中だった事実も提示されましたが、結局、有罪が確定してしまった。
細野 私も2審では逆転無罪を確信していただけにショックでした。判決では、会計原則の根拠や理由を一切示すことなく、粉飾決算は疑う余地がないと結論付けているのですから、もうどうしようもありません。
── 細野さんにとって、キャッツ事件とは何だったのでしょうか。
細野 日本の司法では、一度嫌疑をかけられてしまうと、それを強硬に否定したり抗弁したりするほど、嫌疑が強められてしまうという怖さを知りました。いくら私が「会計原則にのっとって適切な会計処理をした」と説明しても、司法は理解しようとしません。
裁判官には会計の基礎知識がないため、理解力に乏しいうえに会計士と法律家では、その使用言語が異なるため言葉が通じないのに等しい。日本では、検察官によって逮捕・起訴されれば、裁判は推定有罪を前提に進むという典型的な事例だったと思います。
── 逆転無罪の可能性はほぼ絶望的なのに、なぜ最高裁に上告したのですか。
細野 私は常に適正な決算を指導してきており、決算は適正だったからです。適正な決算を粉飾と誤認する判決は、人類の英知である企業会計原則の否定にほかならず、これを国家の判例としてはならないと、強い危機感を抱きました。」
インタビュアーには、細野氏が、適正な決算だったと主張する根拠を、検察や判決と比較して、詳しく聞いてほしかったと思います。
この部分は正しい。
「── ほかに一般市民の感覚とのズレを感じることはありますか。
細野 会計に明るくないビジネスマンに、日本航空の会計処理を説明していた時です。航空機を170億円で購入したが、名門の日航だから170億円で買えたはずで、他の航空会社なら200億円はかかったという理屈で、30億円の値引き(リベート)があったと同じことにして、日航は航空機を200億円で資産計上すると同時に、30億円を利益計上するという粉飾をやっていました。説明を受けたビジネスマンが「買い物をしてもうかるというのは、どう考えてもおかしい」と漏らした感想が新鮮でしたね。広く一般社会の常識と照らし合わせて、不自然で説明のつかない取引は不正なのです。」