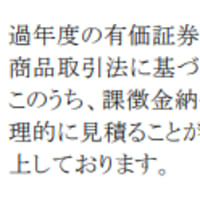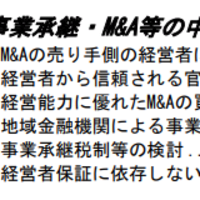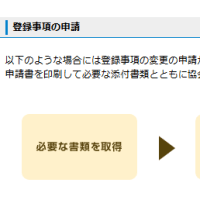日本郵政グループのかんぽ生命に巨額の「隠れ損失」があるという記事。
有価証券の含み損の話で、不正ということではありません。
「順を追って説明すると、まず今回の含み損が発生した背景には、前述したようにかんぽ生命が保有している日本国債の価格暴落がある。一方、これらの国債の多くは、前述した資料に〈満期保有目的の債券〉と書かれている。
「国債には20年、30年などの満期があり、その満期まで売却せずに保有し続ければ、元本がそのまま返ってくる。
かんぽ生命からすれば、満期保有する予定の国債に現時点で含み損が出ていても、その国債を売却したわけではないから実際に損失が発生しているわけではない。だから、それを損益計算書に反映する必要はない――という理屈が成り立つわけです。実際、それは会計処理上も認められている」(大手生保幹部)
言うなれば、表向きにはあらわれない「隠れ損失」ということ。
そのため、多くの人には気づかれないままスルーされているが、その持つ意味は重大かつ深刻である。
「今回の事態は、総資産約80兆円の半分以上を日本国債に投資しているかんぽ生命が、その価格変動に直撃される国債リスクが顕在化した形といえます。
いまのところ金融機関としての信用性に重大な影響を及ぼすとは考えづらいですが、仮に将来的に悪性のインフレなどで長期金利が大きく上昇していけば、マイナス金利以降に買った長期国債の損失はさらに膨らみ続ける可能性がある」(前出・窪田氏)
当然、将来的に膨れ上がる含み損に耐えかねて国債売却に踏み切れば、その損失は一気に表面化し、会社全体が巨額赤字に陥りかねない。そんな重大な経営リスクを、かんぽ生命は抱え込んでいるということだ。」
たしかに問題はありそうですが、金利が上がれば、保有債券の評価が下がる一方で、負債である責任準備金も縮む方向でしょうから、バランスしているようにも思えますが。保険会社の会計に詳しい人に聞いてみたいところです。
保険の本業もだめだそうです。会計学者がコメントしています。
「京都大学大学院経済学研究科の藤井秀樹教授は言う。
「かんぽ生命の売上高にあたる経常収益のうち約3割は、過去に積み上げた『責任準備金の戻入額』というものが占めています。責任準備金というのは保険金の支払いに備えて積み立てることが法的に義務付けられた準備金のこと。
かんぽ生命の社名にもなっている簡易生命保険の過年度契約が続々と満期を迎える中、満期を迎えた保険契約は保険金の支払いが不要となり、それに対応した責任準備金が取り崩されている形です。
そして、この戻入額を控除して計算すると、かんぽ生命は実質赤字。つまり、かんぽ生命は過去の遺産で食い繋いでいる状態でしかない。
実際、本業である保険事業を見ても、新契約の増加が旧契約の減少をカバーするには至っていない。保険商品の開発に制約がかけられていることが大きく影響して、契約総数も純減の状況が続いている」」
2017年3月期 日本郵政グループ決算の概要(日本郵政)
最近の「企業会計」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事