企業会計基準委員会は、企業会計基準公開草案第23号「資産除去債務に関する会計基準(案)」とその適用指針(案)を、2007年12月27日付で公表しました。
基準案の概要は以下のとおりです。
1.「資産除去債務」の定義
「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます。
2.資産除却債務の負債計上(認識)
資産除去債務は、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって発生した時に負債として計上(認識)します。
ただし、その金額を合理的に見積ることができない場合には、合理的に見積ることができるようになるまで計上しません。
3.資産除却債務の算定(当初測定)
資産除却債務は、有形固定資産の除去に要するキャッシュ・フローの割引価値(現在価値)で算定します。
4.資産除去債務に対応する除去費用の資産計上と費用配分
資産除去債務に対応する除去費用は、関連する有形固定資産の帳簿価額に加えます。
資産計上された除去費用は、減価償却を通じて、当該有形固定資産の耐用年数にわたり、各期に費用配分されます。
時の経過により資産除去債務は増加しますが、その増加額(基準案では「調整額」といっています)は、その発生時の費用として処理します。(退職給付費用の利息費用のような考え方だと思いますが、当初の割引率を使って計算するので、資産除却債務の発生時期により、異なる割引率になるのでしょう。)
また、この「費用」は、関連する減価償却費と同じ区分に計上します。
5.資産除去債務の見積りの変更
資産除却に要する将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合は、それに応じて資産除却債務は見直されます。見直しによる資産除却債務の増減額(基準案では「調整額」といっています)は有形固定資産の帳簿価額に加減します。結果としてそれ以後の減価償却費に反映されることになります。(過年度にさかのぼって修正はしない。)
6.開示
貸借対照表上の表示、損益計算書上の表示、注記事項が定められています。
資産除去債務は発生しているが、その債務を合理的に見積ることができないため、貸借対照表に資産除去債務を計上していない場合には、当該資産除去債務の概要、合理的に見積ることができない旨及びその理由を注記することになっているので、計上は免れたとしても、債務の存在自体を隠しておくことはできません。
7.適用時期等
2010年(平成22 年)4 月1 日以後開始する事業年度から適用されます。早期適用も可能です。
適用年度における過年度償却分は特別損失として一気に計上します。
--------------------------------
この基準も工事契約会計基準と同様に比較的シンプルな内容です。要するに、マイナスの残存価額(その分だけ償却額全体が増える)を考えようということでしょう。
しかし、具体的にどのような除却費用まで対象にするのか、実務的に判断が難しいケースもあるかもしれません。
原子力発電所や再処理工場、大量のアスベストを使った建物などが、思い浮かびますが、その他にも、解体や廃棄に多額の費用がかかる資産であれば、対象にする必要があるでしょう。
また、除却債務の金額を固定資産の帳簿価額に上乗せするという考え方なので、債務の金額が大きいと、帳簿価額が膨らんで、減損会計にひっかかる可能性も出てきます。
土壌汚染がある場合の浄化費用などは土地の帳簿価額に加算され、簿価が膨らむことになります(そのかわり減損会計を適用する際の土地の時価は、浄化後の評価額になるはずです)。(ただし、基準案では土地のような償却しない資産についてはふれていないようです。)
あまり議論になっていない基準ですが、へたをすると政治問題化するおそれのある難しい基準だと思います。
最近の「企業会計基準委員会」カテゴリーもっと見る
「継続企業及び後発事象に関する調査研究」の公表(企業会計基準委員会)
IFRS財団が3名の新しいIFRS解釈指針委員会メンバーを選任(企業会計基準委員会)
IASBが金融商品についての分類及び測定の要求事項の狭い範囲の修正を公表(企業会計基準委員会)
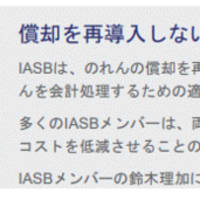
IASB公開草案「企業結合 ― 開示、のれん及び減損」の和訳(企業会計基準委員会)
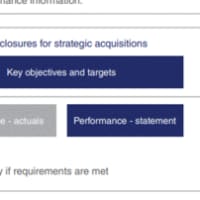
IASBが取得の報告を改善する提案について公開協議(「企業結合 ― 開示、のれん及び減損」)(企業会計基準委員会)
【解説文の掲載】「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」等の概要/「グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の概要(企業会計基準委員会)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事


