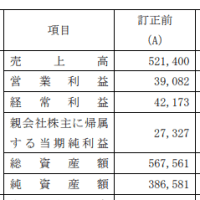SmartTimes セントリス・コーポレートアドバイザリー代表取締役 谷間真氏
上場を目指す企業の「監査難民」問題への対処方法をとり上げたコラム記事。
「IPOを成功に導く上で、大手監査法人との契約はそれほど重要ではないということをお伝えしたい。むしろ、金融庁や日本公認会計士協会の検査による大手監査法人の審査体制の強化により、現場での判断が後の審査で覆り、支障が出るケースもある。その点、中小監査法人は、現場の会計士と審査担当との距離が近く、事前に懸案事項の検討・判断が容易だ。」
「中小監査法人では、大手監査法人を退職し税務業務やコンサルティングを行っている独立した公認会計士が監査を兼業で行っていることが多い。個々の会計士としての能力・知見はサラリーマンばかりである大手監査法人よりも、中小監査法人の方が高いとも感じる。
中小監査法人の監査でのIPOに不都合な点は見当たらない。私が社外取締役を務めるバルニバービは、それまでIPO実績のなかったかがやき監査法人の監査だったが、困ったことはなかった。当初は主幹事証券会社もIPO実績がないことに懸念を示していたが、個々のパートナーの実績等を説明したところ納得し、審査プロセスにおいても監査法人の選定理由などで質問がある程度だった。
ベンチャー企業は、大手監査法人に固執することなく、中小監査法人であっても個々の会計士に経験・能力があれば監査契約して問題ないと言っていい。」
たしかに、こういう中小監査法人のメリットはありそうです。会社の規模などによっては、監査人候補を大手に絞る必要はないでしょう。
ちなみに、昔は、大手監査法人でも、兼業が認められていたようですが、今はたぶんどこも認めていないでしょう。
記事の最後の方で、独立している会計士などがIPO監査業務に参入することを願うといっています。しかし、監査、特に上場会社の監査をやるということは、協会や金融庁の厳しい監督にさらされることを意味しますから、会計士側からすると、せっかく大手監査法人から独立して自由な立場になったのに、また、監督下に戻るのか(しかも、大手のように品質管理といった協会・金融庁対応をしてくれる部門もない)という抵抗感もあるでしょう。中小というよりは、ある程度体制が整っている準大手クラスの監査法人にがんばってもらうのがよいのではないでしょうか。
最近の「会計監査・保証業務」カテゴリーもっと見る
監査人交代事例3件(大東銀行(新日本→太陽)ほか)(2025年5月13日)
監査人交代事例3件(日本証券金融ほか)(2025年5月12日)
監査人交代事例3件(テ イ ン、ナンシン、S A A F ホ ー ル デ ィ ン グ ス)(2025年5月9日)
監査人交代事例3件(ニフコ、TOKAIホールディングス、ラ ン シ ス テ ム)(2025年5月8日)
特別調査委員会の設置及び 2025 年9月期第2四半期(中間期)の決算発表延期に関するお知らせ/会計監査人の異動に関するお知らせ(監査法人やまぶきより就任辞退届)(アルファクス・フード・システム)

内部統制報告書の評価結果不表明、内部統制監査報告書及び監査報告書における意見不表明に関するお知らせ(クシム)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事