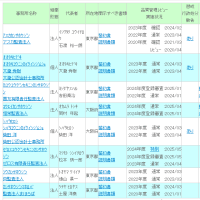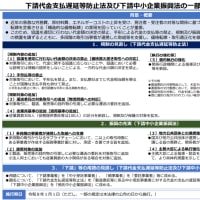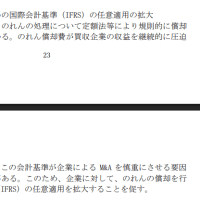日本公認会計士協会は、監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」と同第11号「違法行為」の一部改正の公開草案を、2008年2月19日付で公表しました。
改正金融商品取引法において、法令違反等事実発見への監査人の対応が規定されたことに対応する改正です。
35号の改正案では、「監査人は、不正を識別した場合、法令等の規定により、監査役等に対し報告する責任があるかどうかを判断しなければならない」、「監査人は、不正を識別した場合、法令等の規定により、第三者に対し報告する責任があるかどうかを判断しなければならない」という文言が加えられています。
11号では、17項が「発見した違法行為が会計処理に影響を及ぼす場合の監査上の取扱いは、監査基準委員会報告書第35号「財務諸表の監査における不正への対応」など関連する監査基準委員会報告書による」という文言に変更されています。(会計処理に影響を及ぼさない違法行為を発見してしまった場合は?)(会計処理には注記も含む?)
ちなみに、会計・監査ジャーナルの3月号の金融庁担当官の公認会計士法改正の解説では、「「法令違反等事実」は、仮に監査人や被監査会社において何らの対応も図られず、当該事実が放置された状態のまま当該財務書類が提出された場合に、重要な事項についての虚偽記載等が生じるような事実を指すものと解される」といっています。しかし、これでは、監査対象である財務諸表だけの話なのか、財務諸表以外の部分に虚偽記載がある場合も該当するのかなど、あいまいです(「財務書類」の定義がどこかに規定されているのかもしれませんが・・・)。「等」が何を指すのかもわかりません(虚偽記載は法令違反ですから、それ以外に該当する事項はないはずでは?)。例えば、脱税は違法行為ですが、未払法人税等の過少計上という財務諸表の虚偽記載でもあり、該当するのかもしれません。
また、「法令違反等事実」に該当するかどうかについては、監査人が被監査会社の規模・特性やその財務書類の内容などを総合的に勘案の上、職業的専門家として当然に求められるその専門的知識・技能・経験に照らして判断する必要がある」といっていますが、判断に迷うようなケースでは、監査事務所内の審査などにかけるのでしょう。
さらに、同じ解説では、この制度は「当局が情報収集を行うことを主眼としたものではないと解されており、この点を踏まえた運用が求められる」ともいっていますが、監査人は、監査契約破棄を覚悟してまで金融庁に意見を申し出るわけですから、当局側も当然それにきちんと対応する責任があると「解される」と思います。会社と監査人の意見対立が金融庁に直接持ち込まれることになる可能性もあるので、金融庁も意見申し出があった場合に迅速に対応する体制がなければならないでしょう。そうでないと、そうした会社の開示がストップしてしまうおそれがあります。
最近の「日本公認会計士協会(監査・保証業務)」カテゴリーもっと見る
会員の懲戒処分について(「品質管理レビューの実施結果に基づく措置を正しく伝達せず...」)(日本公認会計士協会)
会員の懲戒処分について(「事後的に作成した監査調書を監査ファイルに差し込むなどした上で、その旨を秘したまま、検査官に当該監査ファイルを提出」)(日本公認会計士協会)
「投資事業有限責任組合における会計上及び監査上の取扱い」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)
「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正(公開草案)(日本公認会計士協会)

【解説】ISA 570(2024年改訂)「継続企業」の概要(日本公認会計士協会)
「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」【令和6年基準】・【平成20年基準】新設・改正(案)(日本公認会計士協会)
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
2000年
人気記事