■この日、番組の会議後、午後が空いた。さてどうする?
まだ見つからない難関本、特に、海外ミステリーの
ピーター・ガドル『長い雨』早川ミステリアスプレス文庫
~などがありそうな、郊外の「ブックオフ大型店」を探るか、
それとも、一般の古本屋さんを探すか。
でも、遠出は面倒やなー。
と思いつつ、近辺でネット検索していたら、
錦糸町に「ブックオフ ロッテシティ錦糸町店」と、
「ブックパイレーツ」という古書店が!
「ブックパイレーツ」さんは、僕が探しているような文庫本も
しっかり置いている模様。
美術系とか哲学系、社会派系などの専門系古書店さんは
表に100均台があっても、店内に入ると敷居が高く(笑)、
かといって、ざっと見て何も買わずに出るのも申し訳なく、
「北上さんの解説本は無い……さて、どうしよう?」
と、お邪魔した記念に買う本を探すのに苦しむことがありまして(笑)。
そんな中、「ブックパイレーツ」さんは、結構、新古書の文庫も置きつつ、
古い単行本類などもある様子。
錦糸町で降りて「ブックオフ」を見てから、ちょっと歩いて覗くには
うってつけやん!
■ということで、行ってみたこのお店が大当たりだったんです!
入ると、結構奥行きがあり、
(名古屋の「千代の介書店」さんほどではないですが 笑)
左手の壁がズラッと文庫棚。
あいにく、僕が好きな70~90年代の文庫はほとんど無かったのですが、
ここで、偶然、
「阿佐田哲也がある」
と目に留まりました。
双葉文庫の『麻雀放浪記』全4巻です。
このシリーズは、角川文庫版を持っているんですが、
他にも、文春文庫などから出ていて、超人気作品ですよね。
双葉文庫版の1、2巻で北上さんが解説を書いているのは
「北上次郎文庫解説リスト」に載っているので知っていて、
もちろん買ってありました。

で、その時、ふと思ったんです。
「全4巻なのに、なんで解説が1、2巻だけなの?」
普通、シリーズものに解説を付けるなら1巻か最終巻。
1,2巻に付けるなら、
「3、4巻も解説を付けるんじゃないの?」
と思ったわけです。
双葉文庫は、あまり解説を付けない傾向(※個人の見解 笑)ですが
さすがに1、2巻に解説を付けるなら全巻に付くのが自然。
そこで、3巻を手に取ってみたら……
「解説 北上次郎!!!」
おお! やっぱり!
しかも、その最後に
「北上次郎氏の解説は第4巻も続きます」
と丁寧に書いてある!
慌てて4巻もめくってみたら
「解説 北上次郎!!!!」
リストに無い、北上さん解説文庫、発見の瞬間であります!
しかも、一気に2冊!!
嬉しかったぁ。
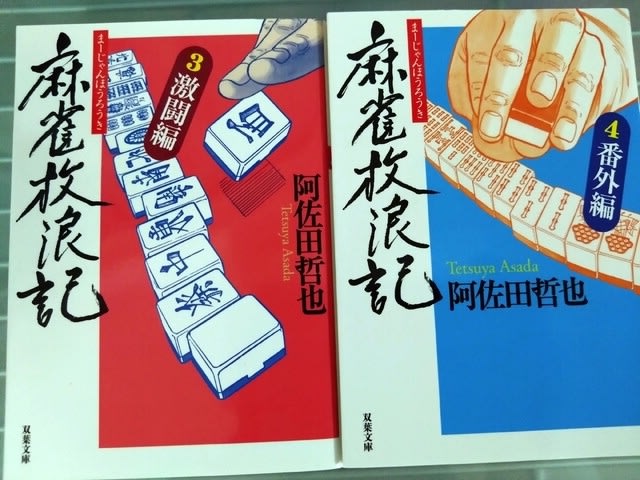
★ちなみに、この「ブックパイレーツ」さんは、北上さんの解説作品捜索と
ご縁が深いのか、後に2回もお世話になることになります。
■北上さんの解説を読むと、もう、阿佐田哲也作品、『麻雀放浪記』への愛が
あふれている。
『麻雀放浪記』は4巻が番外編なので、実質、3巻が最終巻なんですが、
「絶妙なのは、最終編たる『激闘編』だろう。
これはなんと、怒りと苦渋の書だ」
その白眉として、坊や哲が、ラッシュアワーの電車で、OLに足を踏まれたのを
機に、サラリーマンらと喧嘩になるシーンを挙げています。
男たちにメチャクチャにされながらも、
なぜ、坊や哲は、怒りをこらえきれなかったのか。
実はその少し前、哲は旧制中学の同級生とばったり会い、麻雀で大勝ちした後、
その同級生にこう言われる。
「せめて定職につけよ。
そばに寄ると臭くて。まるで犬か豚のようだぜ」
それを読んだ北上さんは……
「ようするに、組織に属さず、みんな一匹狼で、くたばるまで闘った時代は
終わったのである。
その苦渋が、電車の中で爆発するのだ。
『激闘編』は、そういう怒りと苦渋の書である」
なるほど!
僕は、この坊や哲の怒りとコンプレックスに強く共感してしまいました。
そして、北上さんの言う「怒りと苦渋」が蘇ってきたんです…
■僕は、放送作家という仕事で、いわば個人営業。
一応「てれすこ・ライターズ」という放送作家集団の会社に所属していますが、
基本、個人で仕事を取り、個人でこなしています。
一匹狼、というほど強くはありませんが(笑)。
だから、同窓会などで、昔の仲間と会ったりすると、
引け目を感じることがありました。
特に、大学を出てすぐの頃。
僕は、在学中に、日本放送作家協会の「フリーライター教室」に通い、
物書きになる勉強をしていました。
その際、講師をしていらしたシナリオライターの西条道彦先生に
「テレビの台本書き、やってみないか?」
と紹介されたのがこの世界に入ったきっかけです。
番組は、朝のワイドショー『ルックルックこんにちは』。
岸部シローさんがMCをやっていた番組ですね。
「突撃!隣の晩ごはん」という人気コーナーでご存知の方も多いかも。
1988~9年頃だったでしょうか。
当時、日本テレビで『午後は○○(まるまる)おもいっきりテレビ』
という番組が始まった時期。
正午からの午後を丸々生放送にする、という大きなチャレンジ。
そんな大型生番組のスタートに伴って、生放送の台本やVTR構成に慣れた、
手練れの構成作家さんがそちらに駆り出されたようで、
朝の生ワイドショー『ルックルックこんにちは』の作家陣が手薄になり
それで僕が、お手伝いとして入る余地ができた、ということだったのではないか。
僕なりの推察です(事情は分かりません)。
■当時、僕は、早稲田大学に通いながら、『ルック』の仕事をしていました。
小説を書く才能が無いことは、痛感していたものの、
本とか雑誌、物書きの周辺には携わりたい。
出版社や新聞社など、メディア関連に就職したいなぁ、という願望はありました。
まあ、日テレで仕事を続けていれば、あわよくば採用の声がかかるんじゃないか
なんて淡い期待も抱いていましたが、
甘かったです(笑)
日本テレビはしっかりした企業ですから、そういう採用の仕方はしません。
いや、僕の才能が無かっただけか(笑)
大学3年の秋頃から、なんとなく就職を考え出して、動き始めたものの、
正直、完全に出遅れていました。
みんながメディア向けのセミナーに通って、
「就職試験に出るメディア用語」とか「時事ニュース」の講座に通って
テキストも読み込んでいるようでしたが、僕は、全くチンプンカンプン。
「自民党の党三役の役職と役割とは?」
なんて初歩的な問題すら、全くわからず。赤面です。
そのくせ、「ぴあ」とか「講談社」などの面接を受けたり。
面接では「東大」など一流国立大組が最優先で僕らは後回し。
就職面接のヒエラルキーを見せつけられました。
一方で、TVというメディアの片隅に関わっている感じは楽しくて、
本気で面接には臨まず、気づいたら就職のシーズンは過ぎていました。
■今思うと、親は、よく何も言わずに見守ってくれたな、と思います。
高い学費を払って、早稲田大学まで通わせた挙句、就職せず。
実質プータローですから。
卒業後の当時、僕の仕事と言えば、『ルックルック』一本だけ。
木曜日の担当だったので、水曜午後に、当時は麹町にあった日テレの
スタッフルームに行き、ラテ欄(テレビ欄のその日の番組内容ですね)の案を書いて、
その後、ディレクターさんが取材から帰ってきた後、VTRの構成を
一緒に考えて、スタジオの簡単な台本の叩きを書いて先輩作家さんに託して。
生放送でオシマイ。
あ、そうそう、人手が足りないのとディレクターの見習いとして
フロアアシスタントもやらされました(笑)
ほぼ毎週やっていたので、インカムを付けて、自分用の
「1分前」「30秒前」「15秒前」などのカンペも持っておりました(笑)
カメラさんに
「そのコップ、はけろ!」
と言われて、よくわからずに
「はけろ?」
と聞き返してどやされるという、絵に描いたようなポンコツ体験もしました(笑)
はける、というのは、片付ける、という業界用語ですね。
水はけがいい、と言いますが、水がたまらず、消える、ということから
人や物がスタジオなどから消えたり、どかすことをこう言うらしいです。
まあ、そんな状況なので、
大学を卒業した頃は、一週間で出勤日は一日だけ。
水曜に行って泊まって木曜に帰ってくる以外は、何もすることが無い。
あとはたまに、先輩作家やディレクターさんから「ネタ出し」のためのリサーチを振られることくらい。
マジ、暇。
でもお金が無いので、出かけたくても出かけようがない。
だから、高校や大学の仲間と会う時は、辛かったなぁ。
なるべく目立たないようにしていました。
皆がスーツを着て「○○の研修が凄かった」
「○○課に配属された」
「営業は地獄だわ」
なんて言いつつ、キラキラしているのを羨ましく思ったりしたものです。
何してるの、と聞かれると、
「テレビの仕事やってる」
といって、一見華やかそうな振りをして誤魔化してました。
貰ってるギャラは、悲しいほど貧相でしたけど、それは言わず(笑)
そんな中、一番つらかったのは、自宅でのある体験です。
ある日、何もすることが無く、家の2階の自室にいたら、
母親の友達軍団が来て、1階の居間でカラオケが始まった。
これが、盛り上がって一向に終わりそうもない。
そんな中、わたくし、小を催してしまったんですな。
悲しいかな、我が家のトイレは、母たちが歌いまくっている居間を通らないと
行けない構造。
近所の人は、皆、顔見知りだし、僕が大学を卒業したことも知っている。
なのに、平日、何もせずに家にいたら、
「え、早稲田出て、何してんの?」
となる。
それは避けたい。
が、膀胱はひっ迫してくる。
「はよ、帰ってくれ…」
祈る思いでしたが、階下は盛り上がるばかり。
ついに観念して、下へ行きました。
平日の昼下がりです。
僕が居間に現れた時のおばちゃんたちの顔は
一生忘れられないですね。
「あら、あっちゃん…」(敦司、なので、そう呼ばれてました)
と言ったきり、みんな、どう声をかけたものか、困った挙句の沈黙…
重かったなぁ。
母親は、適当に誤魔化したそうですが、
多分、しばらくの間、
「橋本家の穀つぶし」として、格好の噂話となったことは間違いありませぬ。
ま、今でも大した差はないか(笑)
■……と長い話になりましたが、
坊や哲のシーンと、北上さんの解説を読んだ時、
そんなほろ苦い体験が一瞬で蘇りました。
だから、坊や哲やドサ健の感じた悔しさを、他人事とは思えないんです。
リストに無い北上さんの解説文庫を2冊見つけた喜びの直後、
まさか、30年前の苦い記憶と悔しさを追体験することになるとは…
こうして、読者の心を揺さぶるのが、小説の力なんですね。
そして、『麻雀放浪記』3巻には麻雀の熱い勝負シーンが幾つもある中、
北上さんが、この、哲の葛藤と悔しさのシーンを、
一冊の中の白眉として挙げる、読み方の深さ。
さすがです。
どのシーンより、心が揺れて、前へ読み進められませんでした。



















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます