

「一握の砂」に詠まれている、たぶん啄木のもっとも有名な歌であろう。
「この歌の舞台はどこか?東海とはどこか?小島はほんとうにあるのか?」という鋭い質問が、かささぎくんから飛んできた。
この歌は、「蟹に」という詩と同じ着想により創られていると思っていたので、先日「蟹に」をご紹介したわけである。
「蟹に」のコメントにも書いているが、この詩は、「ハコダテの歌」という中に納められている。したがって、この詩の舞台が函館というのは、間違いないであろう。
かささぎくんの情報で、「東海の小島の磯の・・・」は、「青森県下北半島の大間崎」が舞台という説の紹介があった。そういえば、小生も、そんな話を何かで読んだ気がします。小島は大間崎近くの弁天島というのだ。
この説によると、「蟹に」という詩と「東海の小島の磯の・・・」は、舞台が違うことになる。
でも、大間崎説の根拠になっている「函館の大森浜には砂浜がない」というのは間違いである。写真は大森浜である。小島がないというのも、あえていえば、立待岬の近くにないことはないようだ。
しかし、そもそも「小島の磯の白砂」というのが、地勢的にみられる光景なのかという感じもする。大間崎説の弁天島には砂浜があるのであろうか。また、弁天島は東海の小島というのは少し無理がないか。言うならば北海の小島であろう。
小生は、どちらの説が正しいのかは分からないが、「蟹に」とこの歌が関係を持っているとは思う。
そのような関係であると思われる啄木の詩と歌は、ほかにもあったように思う。
そして、この詩と歌がどちらが先に創られたか分からないが、イメージを共有しているのは間違いない。
まあ、そもそも詩や短歌というものはルポではない。啄木の想像たくましさにより、情景、感情を膨らませることは、ある意味芸術家の能力であろう。
はたらけど
はたらけど猶わが生活(くらし)楽にならざり
ぢつと手を見る
この歌も有名な歌であるが、彼はこのように一生懸命働いた形跡はあまりない。
というより、さぼりまくっていたようだ。
2~3週間前に朝日新聞に載っていたが、朝日新聞の校正係に職を得ても真面目に勤務することはなく、ずる休みが多かったのである。他の同僚に迷惑ばかりかけていた。
でも、啄木はこのような歌が詠めるのです。
東海の小島の磯の白砂に
われ泣きぬれて
蟹とたはむる
この歌は、たとえば
夕暮れにたどり着きたる砂浜で
われ泣きぬれて
蟹とたはむる (あけがらす)
としても、ある程度の情感が伝わるのではないかと思う。いえいえ、元歌と比較にならないのは分かっています。
「砂浜」、「泣く」、「蟹」の道具立てが最も重要なのではないだろうか。
啄木の根性のない女々しさが好きなのでそう思いますね。













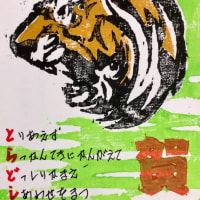


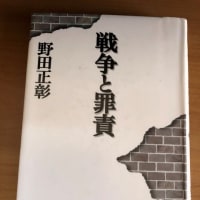
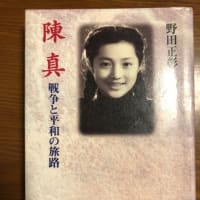


何も知らないうちは神奈川か千葉を何となく想定していましたが、
どうもしっくり来ない。
東海の小島は、人っ子一人やってこない砂浜である必要がある。
函館であろうと下北の大間町であろうと
やっとしっくり来ました。
でも、もし函館の大森浜だとしても
写真のような壮大な砂浜は似合わない
スポットはここではないでしょう。
単なる可能性としては、その逆もあり得る。
彼は16歳の盛岡中学時代に下北を歩いたという。
その時のモチーフをその後醸し続けて、函館で形になった可能性もありましょう。
言う程のことではないですが、私も高校1年の時のある情景を
その後に繰り返し引っ張り出して歌にしたことがあります。
ましてや早熟な啄木のこと、モチーフの刻印がかなり早期にあった可能性は十分にありましょう。
何も具体的に下北説を支持する証拠はもちませんが。
東海の/小島の/磯の/白砂に
は、場所の比定を拒絶する創作の匂いがしませんか?
写真のような壮大な砂浜は似合わない
スポットはここではないでしょう。
仰るとおりですね。この砂浜は、いじいじと蟹と遊ぶ雰囲気ではないですね。まあ、当時もっと松林が迫っていたとか、今のこの景色と状況が違っていたのなら別ですが、ここではないでしょう。ここだと、坂本竜馬の桂浜のように威勢のいい感じになってしまいます。
>単なる可能性としては、その逆もあり得る。
彼は16歳の盛岡中学時代に下北を歩いたという。
その時のモチーフをその後醸し続けて、函館で形になった可能性もありましょう。
>東海の/小島の/磯の/白砂に
は、場所の比定を拒絶する創作の匂いがしませんか?
小生もそう思います。それで
「まあ、そもそも詩や短歌というものはルポではない。啄木の想像たくましさにより、・・・
・・・としても、ある程度の情感が伝わるのではないかと思う。」
と書いたのです。彼にとっては、大間崎と函館大森浜の区別などどうでもよかったのかもしれません。
小生もちょっと楽しみました。