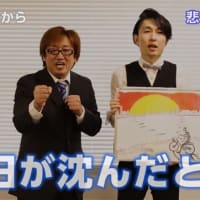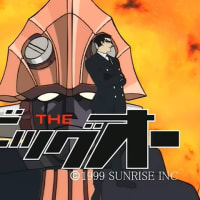送りバントや進塁打によって、チームに貢献するだけがチームプレーではありません。
私が常々言っている(言っていないかも?)、直接プレーしていない、ベンチにいる選手を含めて試合に臨んで、一つひとつのプレーに、一球一球に全員がプレーしていることです。
その教科書となるような話です。
1979年11月4日大阪球場で行われた広島東洋カープ対近鉄バファローズの日本シリーズ第7戦。
後に「江夏の21球」(山際淳司著)として、オールドプロ野球ファンには有名ですね。
話はその場面です。
カープが4対3と1点リードして迎えた九回裏。
バファローズ先頭バッターの六番・羽田がセンター前ヒットで出塁。
ここでピンチランナーとして藤瀬と交代し、藤瀬が二盗を試み、キャッチャーの水沼が悪送球し、ノーアウト三塁となります。
この時、古葉監督はヘッドコーチをマウンドに行かせ「ボールが続き、フォアボールになっても構わん。そのあと走られて、二、三塁になったら、それはそれで仕方がない。満塁で勝負しようじゃないか」とピッチャーの江夏に伝えます。
七番C・アーノルドフォアボールを選ぶと、西本監督はここでもピンチランナーを吹石に変えます。
このとき、三塁側ブルペンへ池谷と北別府が走って行くのを江夏は目にし「わしがそんなに信用できんのか」と思ったそうです。
しかし、古葉監督の仕事は最悪のケースを含め、あらゆる場面を想定し、準備すること。これは監督として当然の事。
「日本シリーズの引き分けは4時間半。まだ1時間以上あった。同点になったら、攻撃して点を取らなくてはならない。当然、江夏に代打を使うケースも出てくる。そういうとき、次の投手を用意していなかったら、指揮官失格ですよ。ただ、9回裏の場面で江夏を代えようという気持ちは皆無だった」
八番・平野の3球目に一塁ランナーの吹石がスタート。キャッチャーの水沼は三塁ランナー藤瀬の本塁突入を警戒し、二塁へは送球しない。
ノーアウト二・三塁となり、カープは満塁策として、平野を敬遠します。
ここで、西本監督は切り札・佐々木をピンチヒッターに送ります。
このとき、カープの衣笠がマウンドに向い、「おれの気持ちは同じだ。ベンチやブルペンのことは気にするな」と声をかけます。
この一言で落ち着きを取り戻した江夏は佐々木を三振に仕留めます。
1アウト満塁になると古葉監督は相手のスクイズを警戒し、ベンチの選手たちに「三塁走者の藤瀬が早く飛び出したら、みんなで“はずせ!”と大きな声を出そう」と声をかけます。
すると、選手たちはベンチ最前列に移動。グラウンドに体を乗り出さんばかりの姿勢をとります。
一番・石渡に対する2球目、江夏がスローカーブを投じ、三塁ランナーの藤瀬がスタートを切ると、広島ベンチは全員が絶叫します。
「はずせ!」
もちろん、古葉監督も、ありったけの大きな声を出します。
石渡のバットは空を切り、藤瀬は慌てて三塁に戻ろうとしたが、タッチアウトになります。
そして、石渡は三振となり、カープは初めての日本一となったのです。
後日、古葉監督はこう語ったそうです。
「日本一より、グラウンドとベンチの選手が一つになったことが嬉しかった。ベンチの選手全員が“はずせ!”と叫んだことが、何よりの証拠です……」
コメント一覧

まっくろくろすけ

eco坊主
最新の画像もっと見る
最近の「プロ野球」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事