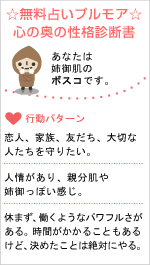「太乙神数」( 副題 諸葛亮孔明、四式占「太乙神数」「六壬神課」「奇門遁甲」「雷公式」 )
「太乙神数」は、諸葛孔明が大成したといわれる占術です。
諸葛孔明は、望龍術を駆使し、宇宙の神秘を悟った道教の秘伝を受け修煉を積んだ預言者でした。
また、諸葛孔明は、中国後漢末期から三国時代の蜀漢の武将・政治家です。
字は、孔明、亮は諱です。
司隷校尉諸葛豊の子孫で、泰山郡丞諸葛珪の子です。
諡は、忠武侯です。
蜀漢の建国者である劉備の創業を助け、その子の劉禅の丞相としてよく補佐しました。
三国志演義では、草蘆時代「伏龍」「臥龍」とも呼ばれます。
為政者は、天文地象や政治軍事地理人情に詳しく、また占い師でもありました。
諸葛孔明は、そのような人の代表格であり、また、望龍術を駆使したことでも知られます。
今も成都や南陽には、諸葛亮を祀る武侯祠があります。
現代では、諸葛孔明のことは、その出自によく知られていないことがあります。
何千年も前の古い伝承では、諸葛孔明は若い時に、天文学に詳しい殷馗という人に天文学を学びました。
その後、鄷公玖に師事し、用兵の奥義である「三才秘籙、兵法陣図、孤虚旺相」等を学びました。
その紹介により武當山で道教の教主である北極教主に師事して易と左道である術奇門と兵法である法奇門を学びました。
「琅書、金簡、霊符(六甲秘文、五行道法、奇門遁甲天書)」を授かったとあります。
この当時、「風鼓六甲」、「文解六甲」等々の記述が「漢書芸文誌」五行の部にあります。
左道とは、右道が常識、論理の道であるならば、その対極にある帰結である宗教または呪術のことです。
諸葛孔明は、術奇門という呪術を使用したとあります。
「正統道蔵秘蔵通玄変化六陰洞微遁甲真經」にそのような方術があります。
昔、蚩尤の乱のときに九天玄女により授けられたという占術と共通の伝説の記述があります。
別の經では、「六甲、六丁神」を雷法の符籙により用いたと記述があります。
「馬前課」という歴代、王朝の移り変わりの預言詩も神霊の力を借りて著しています。
また、歴史上の「太乙神数」は、中国、北宋時代の沈括、「夢渓筆談」に十神太一(乙)、五福太一(乙)云々という記述があります。
「太乙神数」は、太平興国時代に始まったことを暗示しています。
貴神太一の運行を示しています。
諸葛孔明の伝承にあるように、前漢末~後漢にかけて、既にその祖形はあったようです。
漢書、五行大儀には、その説明があります。
唐代においては、盛んに行われ、神事としての祭礼が宮中において執り行われています。
その中において、李淳風の太乙式占が後世に伝聞されています。
元々はそのような由来のあったものですので、各種様々な占法が生じたようですが、現在伝えられているものは寡少です。
文献には散見されますが、伝承は現在台湾にはなく、遼東半島にごくわずかに伝承されています。
過去の文献「旧唐記」によると水旱を司る神として祀られたようです。
貴神太一と北斗の7星の16神を祀ったとあります。
唐代、王希明、「太乙金鏡式経」によると、貴神に対応する中国、各州と16神、(例)文昌将、太乙、始撃、客大将、主大将、宿大将、…等の名称が見受けられます。
貴神太一(乙)と十神太一(乙)との相違は、祭祀の日が春秋二仲、四立(四門)です。
干支と易を用います。
このような式占は、占いの特徴として計算を行うときに、式盤を使用するところにあります。
式盤は天地盤と呼ばれ、その原理は自転と公転に由来します。
「太乙神数」は、国家の将来を予見するために用いる占術です。
そのような占術は、「測局占」と呼びます。
また、代表的な式占には、「太乙式」の他に「遁甲式」「六壬式」があります。
「太乙神数」「六壬神課」「奇門遁甲」を合わせて、「三式」と呼びます。
なお、これら「三式」の他に名前だけが伝わっている「雷公式」があります。
「雷公式」は、具体的な内容が不明です。
「三式」に「雷公式」を加えて四式と呼ぶことがあります。
また、「式占」は、占いの一種です。
特徴は、占うをするに当たり、計算を行うとき、「式盤」あるいは、栻と呼ばれる簡易な器具を使用します。
「式盤」は、天地盤と呼ばれることもあります。
天盤と呼ばれる円形の盤と、地盤と呼ばれる方形の盤を組み合わせたものが、基本形です。
円形の天盤が回転する構造となっています。
天盤や地盤の形状は、天は円く、地は四角いとする中国の天地観に基づいています。
天盤や地盤には、十干、十二支、という、占うために必要な文字や記号が記入されております。
天盤の文字や記号を、地盤の文字や記号と合わせることで、計算を行ったのと同様の効果が得られます。
「太乙式」「遁甲式」「六壬式」の三式それぞれで異なる形態の「式盤」を使用します。
以下に、その式占と意味を述べます。
1.「太乙神数」
「太乙式」の式盤は、十二支に四隅の門を加えた16の要素を基本としています。
「太乙神数」は、国家、社会の運気を読むための為政者の占術です。
「太乙神数」は、「六壬神課」「奇門遁甲」と同じく、諸葛孔明が大成しました。
「太乙神数」は、国家の将来を予見する占術です。
「太乙神数」は、「測局占」と呼ばれます。
「測局占」は、他に「皇玉経世」があります。
漢代には、太一(乙)式の祖形が、「随書経籍」によると後代、唐代に天式が太一(乙)式に、また、地式が雷公式、ひいては明代の遁甲式にと変遷していったようです。
四門は、天門、地戸、鬼門、人門の総称で、八卦と対応付けられております。
天門(四 門)乾 (八卦 )(意 味)北西 秋から冬の移行期間
地戸(四 門)巽 (八卦)(意 味)南西 春から夏の移行期間
鬼門(四 門)艮 (八卦)(意 味)北東 冬から春の移行期間
人門(四 門)坤 (八卦)(意 味)南西 夏から秋の移行期間
「太乙神数」は、測局、命理、風水に太乙式として使われています。
まず、積年と呼ばれる年盤局数の起点の計算があります。
「太乙風水」は、「三式」のなかの天の時を知る「天式」と呼ばれています。
測局といった国の政治、経済といった「国家の大事」を占うことを目的としています。
太乙神数の盤は、内側にある九つの宮と外側にある十六の宮から成り立っています。
十六宮にはそれぞれ十六神が定められています。
また、各宮に入る星は全部で十六種類あります。
2.「六壬神課」
「六壬式」の式盤では、地盤の十二支に天盤の十二神や十二天将を合わせるので12の要素を基本とします。
「六壬神課」は、事件を的確に予測する雑占です。
ある特定の時間を機に、式盤を作成し、判断します。
日本への伝来は古く、平安時代では貴族の間で盛んに用いられました。
「六壬式」は、平安時代、陰陽師にとって必須の占術でした。
安倍晴明は、子孫のために『占事略决』を残しました。
六壬式式盤では、地盤に十二支、十干、四隅の門、東西南北の四方の門が記入されております。
風水羅盤の二十四山の原型です。
六壬式式盤の地盤中央に天盤の代わりに匙形の方位磁石を置いたものである『指南』が、後に風水で使用される羅盤の原型です。
3.「奇門遁甲」
「遁甲式」の式盤は、八卦で表される8の要素を基本としています。
三国時代、軍師の諸葛孔明が、この奇門遁甲の術を大成したと伝えられます。
諸葛孔明は、この奇門遁甲を用いて、戦において、連戦連勝したと伝えられます。
奇門遁甲は、兵法として用いられた占術です。
諸葛孔明著といわれる遁甲書が現代にまで残っています。
実際のところ、明代以降に書かれたものです。
諸葛孔明著と伝えられるものを収集したものです。
封建時代、奇門遁甲は、国禁とされ学問でした。
一般人は、軍学で学ぶことを禁じられました。
平和な時代、奇門遁甲は、人生を戦い抜く術としての方面から、注目され、活用されます。
その意味は、ある特定の時間に特定の方角へ移動することにより、運命を改善することです。
人の運命を改善し、凶運を吉運と変える開運の王者と称される術です。
4.「雷公式(小法局式調伏法、式盤をまつる修法、聖天式法、頓成悉地法)」
雷公式は、その名称以外はほとんど知られていません。
雷公式は、式占の一種とされているが、詳しいことはわかっていません。
雷公式は、太乙式、遁甲式、六壬式と合わせて四式と総称されますが、唐の制度では雷公式は皇帝専用であり、一般での使用は禁止されていました。
そのためか、資料の散逸が他の式占術よりも早く、これまで名前のみが知られて、詳細は不明でした。
最近では、雷公式が単なる卜占ではなく、呪術の側面があり、雷公式では六壬式の式盤を神格化して祭儀を行ったとされます。
雷公式で使用する式盤の制作法や、式盤に神を降ろす道教的な修法(醮)に関する記録が『永楽大典』の巻一九七八二に「小法局式」として収録されています。
5.その他
門派五術、その他大陸五術についても、様々な門派五術があります。
ご希望の方には、実際の占いでご提供します(ただし、別サイトです。また、有料です。)。