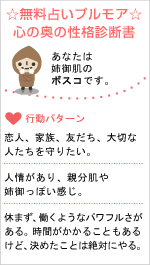ペルシャ,バビロニア占星術( 副題 占星術の起源の世界 )
西ユーラシアの人々の間では、占星術の最も古い証拠は紀元前 3 ,000年頃にまで遡り、そのルーツは季節の変化を予測し、天の周期を神聖なコミュニケーションの兆候として解釈するために使用される暦法にあります。
星座は季節とともに夜空に現れ、特定の星団の出現は毎年の洪水や季節活動の前兆となりました。
この時代、特にメソポタミア(シュメール語,アッカド語,アッシリア語,バビロニア語)で書かれた文書の一部に選択占星術の初期の使用を示す記録があります。
また、メソポタミア第一王朝 (紀元前 1,950 ~ 1,651 年) 頃の記録にあると考えられています。
バビロニア占星術は、紀元前 2 ,000年頃まで遡る記録された最古の体系的な占星術体系です。
紀元前 1,600年頃までに『エヌマ,アヌ,エンリル』は、7,000 もの天の前兆が刻まれた 70 枚の楔形文字板からなります。
また、紀元前500年頃のバビロニア(現イラク)では太陽の軌道を示す「黄道十二宮」が考案されました。
そして、紀元前300年頃以降には計算によって月食を予測するまでになりました。
「黄道十二宮」は、春分点に始まり, 白羊宮, 金牛宮, 双子宮(双児宮), 巨蟹宮, 獅子宮, 処女宮, 天秤宮, 天蝎宮, 人馬宮, 磨羯宮, 宝瓶宮, 双魚宮と呼び、黄道上の12星座である, おひつじ, おうし, ふたご, かに, しし, おとめ, てんびん, さそり, いて, やぎ, みずがめ, うおの各星座に当たります。
古代オリエントに始まり中世ヨーロッパで流行した出生時の天界のありさまが人間の運命を占うというホロスコープ占星術において、太陽月,5惑星の位置を示すのに使われました。
星辰信仰は、ペルシャ,バビロニア占星術の起源として、古くはペルシャが起源です。
星の観測は、暦や農耕といったものに必要であり、王族や神官たちにとって、民衆を支配する有力な武器でありました。
今日の中東の地域で生まれた占星術は、その後エジプトに渡り、文化の華を開きヨーロッパに伝わりました。
ギリシャでの天文学の発展とともに占星術も進歩し、ギリシャやローマの神話とも結びつき、現代に伝えられている占星術の形態が整えられていきました。
古代エジプト人は国家の運営上、ナイル川の氾濫を予測することに費やし、ナイル川の増水を告げます。
ヘリアカル・ライジング、すなわち太陽とともにシリウスが地平線を昇るという天文現象が起る日時を導き出し、そこから夏至を割り出して、一年の長さを決めていました。
こうした天文観測の技術と観測記録は長年にわたってエジプトに蓄積されました。
古代エジプトの星図の中には紀元前4,200年につくられたものもあります。(デンデラ神殿)
エジプト文化とカルデア文化との接点をもつきっかけとなったのは マケドニアのアレキサンダー大王(紀元前336~323年)によるエジプト征服でした。
西アジアの天文学は、その後、ギリシャ世界に受け継がれ、当時の学問の中心地であったエジプトのアレキサンドリアで発展していきます。
高度天体観測技術をもつエジプト人とカルデア人がつくっていた黄道12星座と占星術を含めたオリエントの文化が潜入し、大都市アレキサンドリアを中心に発展をとげます。
「ホロスコープ占星術」と呼ばれました。例えば下図のようなものです。

古代の占星術は、国家の命運を読む事が命題でした。
ヘレニズム時代に基礎が形成された西洋占星術は、その後ギリシャ哲学と融合して生活や文化の中に入っていきました。
その後、ヘレニズム時代が過ぎ、ギリシャがローマ帝国の領土となった後も、アレキサンドリアを中心に占星術を発展していきます。
代表的な人物は、 占星術師 クラウディオス・プトレマイオス(83~168年)です。
トレミーとも呼ばれています。
7つの惑星と星座について、一般に占星術といえば、太陽の星座で占うものと思われていますが、本来は、古代から観測されていた惑星を使って詳しくみていきます。
占星術は、天道説(地球を中心に他の惑星が回っていて、また、太陽と月も惑星として扱う)の立場から成り立っています。
今ではおかしいと思いますが、現実に地球も太陽系の惑星のひとつとして太陽を中心に回っているのですが、地球を中心と仮定し考えています。
古代メソポタミアの占星術師(主に神官)達は、星の神々がこの世のすべての支配者であると考えました。
そして、神聖なるものとして、それぞれに象徴する意味を与えました。
・太陽 生命と光の神
・月 不規則で変化する神
・水星 知恵の神
・金星 愛の女神
・火星 死と病の神
・木星 死者を甦らせる創造の神
・土星 狩猟の神
この7つの星は、今日の一週間のそれぞれの曜日となりましたし、また7を特別な数としてラッキーナンバーとすることも、実は3,000年以上のペルシャの歴史があります。
天体と数に神秘的な結びつきを考えたことは、のちに数の神秘学や錬金術、カバラなどにも大きな影響を与えました。
次に太陽の通り道である黄道12星座ですが、現在の星座が確定したのは、ヨーロッパに入ってからです。
アレキサンドリアで活躍した学者の1人、プトレマイオスが記した天文書『アルマゲスト』は、 古代ギリシャ天文学の到達点と位置づけられています。
古代ギリシャの高度な学問は、5世紀以降、すっかり廃れてしまいました。
西ローマ帝国が滅亡し、東ローマ帝国でも国教となったキリスト教が重視されたためです。
キリスト教では、神の前では平等ということで、個々人の自由と努力を尊重し、占星術のような宿命論を嫌います。
星が神というのも気に入らない理由の一つです。
そして、存続の危機にあった古代の英知を積極的に吸収し学問として発展させたのが各地のイスラーム王朝でした。
アッバース朝による9世紀の翻訳事業がよく知られています。
首都バグダードでは、あまたのギリシャ語文献がアラビア語に翻訳され、様々な分野の学者が古代の学問を洗練させていきました。
ペルシャ人の占星術師アブー,マーシャルもその一人で、プトレマイオスの『アルマゲスト』を翻訳しました。
アラビア語の写本として残された『アルマゲスト』は、天文学の基本書であり続け、16世紀に登場するコペルニクスの地動説の基礎資料にもなっています。