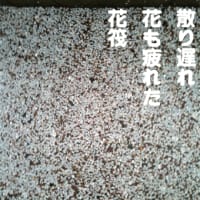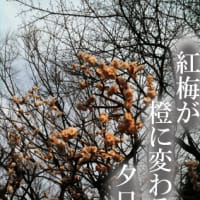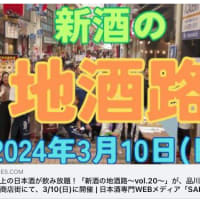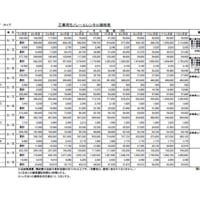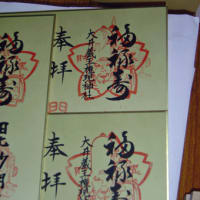その確信は、大きな展示ホールで現実のものとなった。日本書紀の時代から明治維新までの出来事を登場人物を菊人形ならぬ宝石人形で表している。着ている衣装が、水晶やアメジストやなんかの宝石ぽい石でできてるわけさ。すごいね。すごいよ。微妙の嵐である。ようやく、自分たちがなにげに使っている「微妙」という言葉の意味がここで分かったのだ。
そして、微妙の真骨頂はこの地獄道。中は所謂、地獄絵図の模型版であるが、暗くて一応センサーがあるらしく突然、光ったり音がでて正直、意外と恐かったのだ。ここの展示の怖さは小鬼どもの獰猛さなのだ。閻魔は飾り物のような存在で、存分に人を苦しめて楽しんでいるのは小鬼達。閻魔より、小鬼が生き生きして(地獄絵の人間は、当たり前だが死に死にだよ)いたのだ。主役が小鬼の人間料理教室が連続しているといった展示であった。つまり、権威の否定である。さっきの歴史的な登場人物に宝石の装飾をかぶせられると、皆その歴史的な意味を見失う。しかし、この登場人物に対しての興味は逆に増すのである。地獄道の小鬼達にも個性が見られる。人の料理をしている小鬼の一人一人に興味を持つのである。閻魔よりもよっぽど人間らしい。つまり、非常に俗人的に見せる役割を果たしている。他の展示でも宝石でできた着物を着ているバカらしさ効果から、かえってその人物をしっかり見るような微妙な演出しているのではないかと思えるのである。
ここの観音様から始まる微妙探検の特徴は、すべての材料を平等に、思想の押しつけのない教科書のような展示物の攻勢であったね。実は、微妙というのは大事な感覚なのかなと、微妙さがまったくない小泉内閣を見ている思った次第である。とま、お近くに行かれた場合はぜし、ご覧あれ~