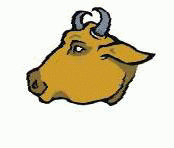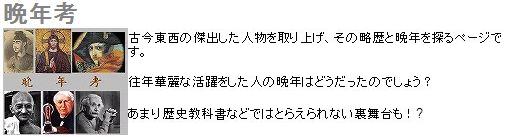
秋山真之(1868~1918)
 ○略歴
○略歴秋山 真之(あきやま さねゆき)は、大日本帝国海軍の軍人。最終階級は海軍中将。位階勲等は従四位勲二等旭日重光章。幼名は淳五郎(じゅんごろう)。母は貞。実兄に陸軍大将の秋山好古ほか、実業家となった兄など。松山城下の中徒町(現在の愛媛県松山市)に松山藩の下級武士秋山久敬の5男として生まれる。親友の正岡子規の上京に刺激され、愛媛県第一中学(現在の松山東高校)を中学5年にて中退、明治16年(1883年)に将来の太政大臣を目指すために東京へ行き受験準備のために共立学校(現在の開成高校)などで受験英語を学び、大学予備門(のちの一高、現在の東京大学教養学部)に入学。明治23年(1890年)に海軍兵学校を首席で卒業し、海軍軍人となる。明治25年(1892年)海軍少尉。日清戦争では通報艦「筑紫」に乗艦。明治29年(1896年)、報知艦「八重山」に乗艦し、海軍大尉となる。明治34年(1901年)海軍少佐。明治35年(1902年)には海軍大学校の教官となる。明治36年(1903年)8月に結婚、妻はすゑ。明治37年(1904年)からの日露戦争では連合艦隊司令長官東郷平八郎の下で作戦担当参謀となり、第1艦隊旗艦「三笠」に乗艦、日本海海戦の勝利に貢献、日露戦争における日本の政略上の勝利を決定付けた。大正2年(1913年)には海軍少将、大正6年(1917年)、海軍中将に昇任。 子は4男2女。民主党参議院議員大石尚子は、真之の孫(次女・宜子の長女)。
●晩年考
大正5年(1916年)3月には、第一次世界大戦を視察するためにヨーロッパへ渡る。朝鮮半島からシベリア鉄道でロシア、フィンランドなど東欧などを視察。晩年は霊研究や宗教研究に没頭するようになった。大正6年5月に虫垂炎を患い箱根で療養に努めたが、翌大正7年再発、悪化して腹膜炎を併発、2月4日小田原の山下亀三郎別邸にて死去した。享年49。死去する直前には般若心経を唱えていたという。墓所は東京都港区の青山墓地。海軍では長らく秋山は神秘的な名参謀として考えられ、崇拝の対象になっていった。

戦艦三笠艦橋(日本海海戦)
中央左より加藤、東郷、秋山
★軍服の袖で鼻水を拭いたり、作戦を練り始めると入浴せずに数日過ごすなど、身なりを全く気にしない性格であったと伝えられる。・・・幼少時代よりの友人・正岡子規もそうだった?