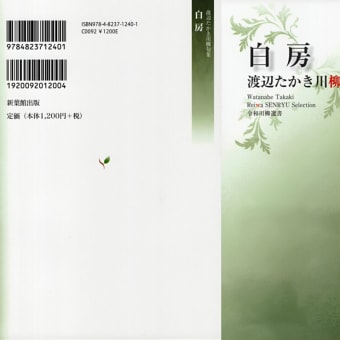□本日落語一席。
◆林家はな平「錦の袈裟」(衛星劇場『衛星落語招待席』)。
紀伊國屋ホール、令和6(2024)年3月19日(第705回「紀伊國屋寄席」)。
与太郎が女房の入れ知恵で寺に錦の袈裟を借りに行くときの口上が「親戚の息子に狐が憑きました。偉い和尚の錦の袈裟を掛けると治る……」と。
はて?と思って気づいたことがある。「親戚の息子に……」のところは「親戚の娘に……」ではなかったか。
あらためて昭和の落語家で確認してみると、十代目柳家小三治は「息子」だったが、古今亭志ん朝は「娘」で演っていた。どうやら、ここは古くから二系統があったようだ。
これ、たとえば、柳家と古今亭といった一門での型かと思うと、たとえば、同じ古今亭の十代目金原亭馬生はやはり「娘」で演っているが、柳家一門の喬太郎も「娘」で演っていた。
まあ、「息子」と「娘」で、とくに噺の展開がかわるわけではない。でも、何かちょっと気になりはする。また、注意しておこう。
◆林家はな平「錦の袈裟」(衛星劇場『衛星落語招待席』)。
紀伊國屋ホール、令和6(2024)年3月19日(第705回「紀伊國屋寄席」)。
与太郎が女房の入れ知恵で寺に錦の袈裟を借りに行くときの口上が「親戚の息子に狐が憑きました。偉い和尚の錦の袈裟を掛けると治る……」と。
はて?と思って気づいたことがある。「親戚の息子に……」のところは「親戚の娘に……」ではなかったか。
あらためて昭和の落語家で確認してみると、十代目柳家小三治は「息子」だったが、古今亭志ん朝は「娘」で演っていた。どうやら、ここは古くから二系統があったようだ。
これ、たとえば、柳家と古今亭といった一門での型かと思うと、たとえば、同じ古今亭の十代目金原亭馬生はやはり「娘」で演っているが、柳家一門の喬太郎も「娘」で演っていた。
まあ、「息子」と「娘」で、とくに噺の展開がかわるわけではない。でも、何かちょっと気になりはする。また、注意しておこう。