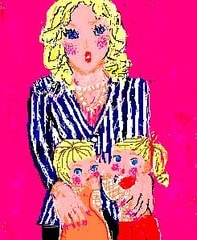----子供の育て方1-A ( 6~12歳)-----
------------CONTENTS-------------
「父親の無力化」 「9才で大学生に 」
「引きこもりの親」 「問題児」
「社会性」 「セロトニンの重要性」
--------父親の無力化(父性不在)------
多くの人と交わる社会体験が不足、
、他者が存在しないので、
子供は「唯我独尊的」になり、
これが原因でさまざまな問題行動に
エスカレートしていきます。
★声が枯れるほど、よく泣き、よく笑い、野原を
縦横に走り、よく食べて、よく眠って身も心も
全開にして感情の発散する、この子供時代の経験
が“生きる力”を養います。
最近の子供の特徴は、実体験に乏しく現実感が不足
して幼稚で、幼児期に養われる“生きる力”を持って
いないのが特徴です。
★特にテレビは実体験を阻害します。
★テレビゲ-ムで長時間遊ぶ子供ほど暴力的に
なります。
テレビは実物でないので五感が育たず、受け身で
意思への働きかけがなく、画面変化が早くて模倣
できない、リアル感がなく想像性が育たなくて、
幼児には、弊害が多い媒体です。
★テレビは、親の語りかけのない状態で一人で
見せてはいけません。
★テレビや、テ-プより、対話するほうが言葉の
理解は、豊富になリます。
「手塩にかけて育てる」( 手を抜かない)目をかける
ことは、教育の原則です。
★現代は、要領よく生きる脳が重視されすぎて
「強く生きる脳」が弱いままです。
1日1回は、汗をかくような、PQ(社会的、感情的
知性の統合)を発達させる体験が知育教育の機軸です。
-----現代は、以下の3つが不足しています-----
1. 「自然などの遊びの空間」
遊べる空間は、20年前の1/10に減っています
今の学生は感情が熱くなる事が少なく、さめて
います.。
生きているという、生々しい経験をもたないと、
破壊、衝動的な感情表出しかなくなります。
これが「学校破壊」に結びつきます。
2. 「家族と会話する時間と空間」
行動と、感情の制御をする脳の前頭前野を鍛える
には、母子間、家族の会話がポイント。
家のつくりも関係します(住育)。
今、テレビの「エチカの力」で放送中。
3. 「近隣の人や友人などの仲間とすごす時間
と環境」脳を鍛えるには、声を出す、人との
コミュニケーションをすること。
--9才で大学生になった子をもつ親の教育法--
「僕9才の大学生」(祥伝社)
1、出来ない事を無理にさせない。
2、同じことをくり返しやらせない。
3、ミスを、つつかない。
4、勉強の目的を明確にする。
5、IQが高いだけでは、無意味な人生を送ること
を教える。
★ 反抗などした事のない、[ おとなしい 「いい子」]
は思春期、社会人になる過程で、不適応を起こ
します。参考文献:
「人生の悲劇はよい子」に始まる」(フォー・ユー)
自由な発想、感情表現、積極性を押し殺して親の
期待にそうような自己束縛をした子は、心の怒りが
体の反応となって、衝動的な行動としてある時に、
爆発する可能性を秘めています。
(交流分析のセミナーより)
( 例、家庭内暴力、警官、教師、大学教授の破廉恥
行為など)
※青年期の「うつ」は暴力を伴うのが特徴。
※事件を起こした子は、教師に反発する事など
全くない、几帳面な子だった。
(よくテレビでおとなしい子だったという教師の
会見があります)。
※息子の家庭内暴力で息子を殺した父親は、感情
を押し殺した内向的な性格だった。
----------- 引きこもりの親の特徴----------
親に不安傾向があり、自信がなく、自罰的で子供に、安心感や存在感を与えられない。
母親がいつまでも、子供を仕切ろうと未熟さを内包する信念を持っている。
両親は、高学歴で、まじめで、やさしい。
父親が子に無関心。
----------------問題児----------------
3F行動
1、Freeze、引きこもり、登校拒否。
2、Flight、家出。
3、Fight、暴力。
子供の不満や怒りの原因を聞いてやることにより、
成績に対し良い影響をあたえる。
”問題児”は「自分の言う事を親がはじき返す」
と言うのが子供が受ける実感です。
最近の子供は、心のもやもやを周囲に表現でき
ない内閉性と「病的な攻撃性」をもっています、
※これは危険なことです。
子供は、家庭や親の保護という「安全な自分の逃げ場」ががないと、反社会的になリます。
問題児にとって「安全な自分逃げ場」とは、
親の干渉のない深夜、これが生活習慣を壊し、引きこもりの原因に。
(引きこもり対策のセミナ-より)
※3~12歳に「叱られた経験(脳の訓練)」 がないと、子供は問題行動を起こします。
※小学校1~2年は、衝動的行動と、善悪の折 り合いをつける重要な分れ道です。
周囲の目を気にしない行動を起こす子は、
※厳しさの不足によるPQ(社会的、感情的知性の統合)の不足、知性障害。
ex: 再近の成人式で暴れる未成熟な成人。
最初の子は、親真似をする傾向が強く、独断的で支配的になり、下の子は型破りで冒険的になる傾向があります。
─ストレス耐性をもつ子を育てるには--
「母性的な母」に育てられると、子供の体内の セロトニンの代謝が増えてストレスにうまく対応したり、成人後、階層の上位になれます。
「セロトニンの重要性」特に現代社会において!
セロトニンは、衝動を抑制する作用があリます。 セロトニンの代謝が悪いと、急にキレたり、衝動的な行動をする子になります。
セロトニンが不足した母親は、うつ的で
「母性愛が弱く」、満足な子育てができません。
朝の太陽の光はセロトニンを増やし、体内時計を調整します。
----社会性(生きる力)を養う事の重要性----
恐いおやじ、近所のおばさん、厳しい先生、ワルガキにもまれ、遊びの中で、けんかをして仲直りしたりして、人間関係の機微、生き方の原則を学び、自然の驚異など、厳しい社会環境との対応の経験が、前頭葉の発達に役立ちます。
★前頭知性(PQ)とは、
知性の中でもっとも重要なのは、社会性や、人格を作る、前頭知性(自我)。
自分の感情を コントロ-ルして、社会関係をうまく処理し、前向きに生きていく
--------------- 「思春期」----------------
早ければ、小学4年から、一般的には14歳から20歳。
親と距離をおこうとする、自立感の表れ。
小学校4年生から、「くそばばあ」という表現をします。
※問題といわれている小学校4年生も、対処の 仕方で、可能性拡大のチャンスです。
※親は、14歳からは子育ては終わったと考え るべき。
子供には、徐々に、大人である事の証明をしようとするプレッシャーがかかる。
★親が、まだ子供であることを証明しようとす るほど、反発する。
子供の趣味をけなさないで、理解する、価値観を肯定する。
友人を評価しないと、( 自分を批判されたと思う)。
男女の協力関係や役割を教える(異性に対する学習期)。
命令され、批判されるほど、自分の自信を無くす、勇気付けることが必要。
自信がないと、自分を閉ざす。自己肯定感がないと”荒れる”。
※本当の勇気をもっていない時に、大人の悪い 真似をしたがる。
★問題を起こす子の問題は、子供の時の甘やか し、無視、身体的欠陥からくる。
登校拒否の問題は「学力」、80%は社会復帰。これを過ぎると、引きこもり。
「引きこもり」まず、今の状態を肯定し、共感 する。
そして自己否定のゆがみを正す。
手紙による相談、東京都国立郵便局私書箱11号。ティンズポスト。
----子供の育て方1-B ( 6~12歳)----
につづく!
�