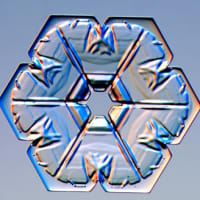団塊おやじでも!!日米安保がなかっら?
【コラム】 「日米安保」がなかったらどうなってしまうの?(R25) - goo ニュース

写真は9.11の航空写真
「日米安保」が改定されてちょうど50年になるらしい。
簡単にいうと、
日米安保とは、
日本が武力攻撃を受けたときには米国に守ってもらい、
そのかわり米軍の駐留を認めて基地を提供する約束のことをいう。
いわば日米関係の重要な柱なのだが、
最近は沖縄の基地移転問題で米国とモメたりと、
日米安保を見直そうという声もあったりする。
では、かりに日米安保がなくなったとしたら、
日本はどうなるのか。
「日本の安全は自国で確保すべき、
との考え方もあります。しかし、
そのためには日米安保体制による抑止力をカバーするだけの
防衛力の増強が必要になります。
防衛費の大幅な増大は高齢化時代を迎える国の財政を圧迫し、
国民の生活に確実にしわ寄せをもたらすことになります。
また近隣諸国も日本の軍事大国化には大きな不信感を抱くはずです」。
こう説明するのは外務省北米局。
じつは、
旧安保条約が締結された1951年当時、
日本の再軍備を主張する人たちもけっこういたのである。
その代表的なひとりが鳩山首相のお父さん、
鳩山一郎。それに対し、
日米安保を推進したのが当時の吉田茂首相で、
そこにはこんな考えがあったという。
当時の日本の優先課題は戦後復興。
経済発展を実現するには自国の防衛を米国に委ね、
日本は軍備にお金をかけないことが重要である─と。
「吉田ドクトリン」といわれるもので、
実際、
日本はその後急速な復興を遂げ、
世界第2位の経済大国となったのだ。
逆にいえば、
日米安保がなければ日本の発展も遅れたかもしれないわけだが、
とはいえ、
現在、日米安保のあり方が変わってきているのも事実。
たとえば、
経済大国となった日本に対して米国は防衛費の負担増を要求し、
その結果、いまや日本の防衛費は軍事大国並みにまで拡大。在日米軍の駐留費用も肩代わりさせられ、
冷戦や9・11以降は米国の軍事行動にどんどん引きずられてしまっている。
今後も従来のように米国と行動をともにするのか、
あるいはそろそろ一線を引くべきなのか。
日米間でこれから議論されるのはそういうことなのである。
国対国の関り、資本主義経済の倦怠期も含め、
日本の新しい経済(?主義)を{旧来の制度(師弟制度など)も見直し}
立て直すべく方向へ、
導いて頂きたい。
【コラム】 「日米安保」がなかったらどうなってしまうの?(R25) - goo ニュース

写真は9.11の航空写真
「日米安保」が改定されてちょうど50年になるらしい。
簡単にいうと、
日米安保とは、
日本が武力攻撃を受けたときには米国に守ってもらい、
そのかわり米軍の駐留を認めて基地を提供する約束のことをいう。
いわば日米関係の重要な柱なのだが、
最近は沖縄の基地移転問題で米国とモメたりと、
日米安保を見直そうという声もあったりする。
では、かりに日米安保がなくなったとしたら、
日本はどうなるのか。
「日本の安全は自国で確保すべき、
との考え方もあります。しかし、
そのためには日米安保体制による抑止力をカバーするだけの
防衛力の増強が必要になります。
防衛費の大幅な増大は高齢化時代を迎える国の財政を圧迫し、
国民の生活に確実にしわ寄せをもたらすことになります。
また近隣諸国も日本の軍事大国化には大きな不信感を抱くはずです」。
こう説明するのは外務省北米局。
じつは、
旧安保条約が締結された1951年当時、
日本の再軍備を主張する人たちもけっこういたのである。
その代表的なひとりが鳩山首相のお父さん、
鳩山一郎。それに対し、
日米安保を推進したのが当時の吉田茂首相で、
そこにはこんな考えがあったという。
当時の日本の優先課題は戦後復興。
経済発展を実現するには自国の防衛を米国に委ね、
日本は軍備にお金をかけないことが重要である─と。
「吉田ドクトリン」といわれるもので、
実際、
日本はその後急速な復興を遂げ、
世界第2位の経済大国となったのだ。
逆にいえば、
日米安保がなければ日本の発展も遅れたかもしれないわけだが、
とはいえ、
現在、日米安保のあり方が変わってきているのも事実。
たとえば、
経済大国となった日本に対して米国は防衛費の負担増を要求し、
その結果、いまや日本の防衛費は軍事大国並みにまで拡大。在日米軍の駐留費用も肩代わりさせられ、
冷戦や9・11以降は米国の軍事行動にどんどん引きずられてしまっている。
今後も従来のように米国と行動をともにするのか、
あるいはそろそろ一線を引くべきなのか。
日米間でこれから議論されるのはそういうことなのである。
国対国の関り、資本主義経済の倦怠期も含め、
日本の新しい経済(?主義)を{旧来の制度(師弟制度など)も見直し}
立て直すべく方向へ、
導いて頂きたい。