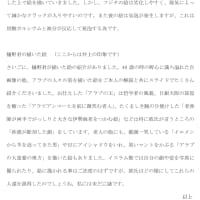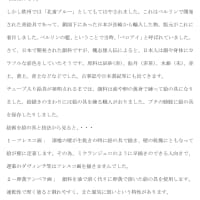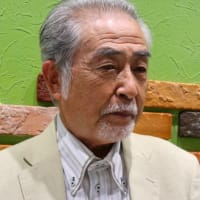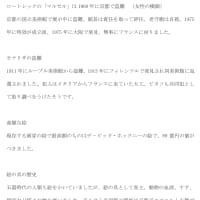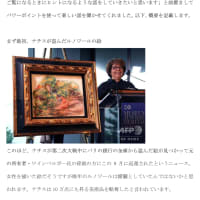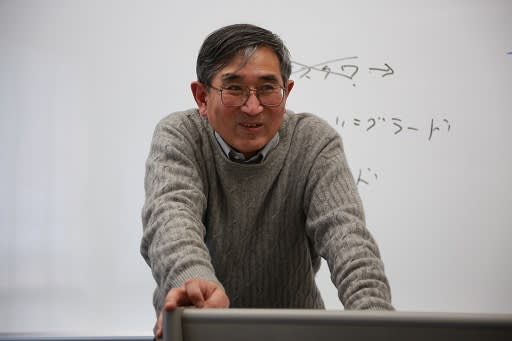
(写真はいずれも海野隆氏撮影)
はじめに
終戦より今年は七十年、もう周りには戦争経験者がほとんどいなくなり、いま60歳以下の世代では、父母、祖父母の戦争体験談を断片的に聞くだけで、時代が下るにつれ単なる活字の歴史に埋没してしまう。
人間の真価は、死んでから決まるという、蓋棺事定(がいかんじてい)という聞き慣れない四字熟語がある。歴史も「棺(かん)を蓋(おお)て百年、評定まる」と言えるのではないか?それでは昭和の戦争についてはどうか? 評は定まったのであろうか?
ある人は太平洋戦争といい、侵略戦争であったと定義する。またある人は大東亜戦争と称して欧米帝国主義諸国からのアジア解放に力点をおいて語る。
昭和の戦争は簡単に総括できない厚みと深さをもつ
材料はいくらでもある、好きなところ、自分に都合のよい真実だけを取り上げれば侵略戦争にでも聖戦にでも自由自在に表現し得る。現代から振り返って歴史を評価すると言うのはすべて結果が分かっており、裁きの視点で当時を振り返る事になる。
幸い、日本は比較的自由に研究できる有難い国である。近隣の国々とちがって権力者が歴史を決める訳でもなく、世論が歴史家に圧力をかけ史観をゆがめさせる訳でもない。
「春秋に義戦無し」(孟子 人心・下)と言って戦争は、相対する国それぞれが大義を掲げて戦いを始める。そして大義を掲げた戦争も、時をおいて冷静な目でみれば、そこには孟子の言うとおり、一方が完全に善でもう一方が完全に悪であることはない。
今般、まとまりはないが、公平中立な立場で、昭和の戦争の原因と結果とその影響を考察する。
第Ⅰ部 二十世紀のアジア
1.重点の置き方が間違っている学校の近代史、まず日露戦争の世界史的意義を!
用語の解説が主の教科書、別の観点を導入すれば、面白いし、よくわかる。従来の日本史教科書や坊間の歴史書の日露戦争、第二次世界大戦の取り扱い方は主従が逆である。
「君死にたもうなかれ」や大塚楠緒子の「お百度まいり」、満州国は「傀儡国家」を強調するだけでは所謂「針の穴から天をのぞく」で全体が見えない。
当時の独立国家でない国は委任統治、植民地、傀儡国家、名前は変わっても、何れも宗主国の意向に沿った統治がなされている。
この欧米帝国主義に対するアジアの反抗、独立をメインにして時代背景を記述すれば歴史の流れが「くっきり」と浮かび上がる。
150~200年間、欧米の帝国主義支配にアジア・アフリカが苦しんでいた。白人以外は虫けら同然、かろうじて独立していたのはトルコ、タイ、日本のみでトルコ、タイは 年月とともに領土をけずられていく。
近代化を進めた日本が日露戦争で世界中の被支配国の人々に希望を与えた。一例として、少し長くなるがインド、ネール首相のその時の感激は次の通り
「私の子供の頃に日露戦争というものがあった。世界中は、ちっぽけな日本なんかひとたまりもなく叩き潰されると思っていた。アジア人は西洋人には、とてもかなわないと思っていたからだ。ところが戦争をしてみると、その日本が勝ったのだ。私は、自分達だって決意と努力しだいではやれない筈がないと
思うようになった。そのことが今日に至るまで私の一生をインド独立に捧げることになったのだ。私にそういう決意をさせたのは日本なのだ。インドをヨーロッパの隷属から救い出す事を思い、私自身が剣をとってインドのために戦い、インドを解放する英雄的行為まで夢見た。
アジアの一国である日本の勝利は、アジアの総ての国々に大きな影響を与えた。『アジア人のアジア』の叫びが起きた。日本が最も強大なヨーロッパの一国に対して勝利を博したとするならば、どうしてインドがなしえないといえるだろうか?」
こんなに褒められていいのかと思うほどだが、「君死にたもうなかれ」では主客転倒で日本の歴史教科書にネールの「剣を採って英国人を追い出したい」という情熱について記述する必要がある。
このナショナリズムが直ぐ後インドの「スワラジ(自治要求) スワデシ(国産品愛用)」運動になり、更にベトナムでも東遊(トンズー)という運動に繋がる。ベトナムのファン・ボイ・チャウは、「日露大戦の報、長夜の夢を破る」「日露戦役は実に私達の頭脳に、一世界を開かしめた」と回想録に書いている。中国、朝鮮、インドからの留学生で東京は溢れていた。「日本に学べ」と、宮崎滔天、犬養毅らの支援も受け、ボイ・チャウは、若者を日本に留学させる「東遊運動」を始め、ハノイには慶応義塾に倣って「トンキン義塾」も創設された。
東京同文書院は留学生のために教室や寮を増設し、軍事教練も組み込んだ特別科をつくってベトナム留学生を受け入れ最盛期の1908年(明治41)には、200名に及ぶベトナム青年が日本で学んでいた このような反仏の動きに危機感を持った仏統治政府は、この時期留学生の親族や支援者に対し摘発を進めた。日仏同盟の締結で仏政府の強い要請を受けた日本政府は、条約改正の途上でもあり、やむをえず1908年(明治41)秋、留学生に解散命令を出す。
2.太平洋戦争(終わってみれば日本は廃墟、アジアの欧米支配は終焉)
今次の戦争でも、欧米帝国主義国に日本が、初戦痛打を与えた。200年来、白人にはかなわないと思っていたアジアの人々に、目の前で白人が敗退する姿をみて「おれたちも独立出来る、独立は近いぞ」と思わせた。
日本の敗戦で終わってみると「大東亜共栄圏」と言うスローガンは「羊頭狗肉」で幻であったことは間違いない。日本が、軍政を引き、軍票の乱発によるインフレや徴発などで原住民の信頼を失い国土を戦場にした。原住民を巻き添えにしてしまったり、敵がたに廻してしまったゲリラを討伐したこともある。
日本の敗戦で、一旦は欧米人がいなくなって、アジアの人々は、これで「いよいよ独立」と思ったが、それは甘い幻想でしかなかった。
戦前も戦後も欧米の本音は「独立なんぞ出来るだけさせないようにする」との考えであった。この点日本はアジアを独立させようと本気になった人々が少なからずいた。
日本の敗戦後、インドネシア側の独立戦争に参加した日本人も数多い。
戦前・戦中、日本が大東亜共栄圏、東亜新秩序を打ち出していたことから、欧米からのインドネシア解放・独立の為に「共に生き、共に死す」を誓いあった者、日本に帰国したら戦犯として裁かれることを恐れたためにインドネシアに残留した者、また日本軍政期、教官としてインドネシア人青年の訓練にあたり、その教え子たちに請われて武装組織に参加した者もいる。一日千秋の思いで自分の帰国を待っている両親、妻子に早く帰国して会いたいと言う想いを絶って、一命を現地の独立に奉じたのである。
インドネシアだけでなくビルマでもベトナムでも同様である。欧米はインドネシア、ビルマ、ベトナム、アルジェリアと再び旧植民地を奪回すべく軍隊を送り込んだ。しかし新時代になり旧宗主国が植民地を回復する事は著しく困難であった。この様に日本は日露戦争、第二次世界戦争と何時もシテ(主役)を演じ、日本の犠牲でアジア、アフリカの独立が早まったことは間違いない。百年、二百年、時がたてばたつほど、日本の評価は増すだろう。
現在、日本はフィリピン、韓国、中国でこそ評判が悪いが、その他の国ではそれなりの評価がされている。
3.中国の状況
1946年以前の中国
満州族に中国は支配されていたが、この「清」の時代、盛世三代と言われた康熙帝、雍正帝、乾隆帝の後は、帝国主義列強に蚕食され、亡国の道を歩むこととなる。
アヘン戦争、太平天国、アロー戦争が起こり、高杉晋作が1862年(文久二年)、上海にみた光景はアヘン中毒者が蔓延する清国の姿であった。その後、国運を挽回しようと曾国藩、李鴻章が1860年頃より「中体西用」のスローガンのもとに(清朝の専制政治のまま西洋の科学技術を導入)洋務運動を行いそれが失敗に終わるや1895年より康有為が政治体制の改革に着手し立憲君主制をめざし変法運動により近代化を推進しようとした。しかしこれも三年で西太后など保守派に潰され失敗した。
時代認識が甘く、近代化する意欲が国全体に行き渡らず、やがて1900年、山東省で外国人を襲撃する外国排斥運動義和団の乱(北清事変,拳匪の乱)が起こりたちまち全土に広がり、地獄図のような光景が眼前で繰り広げられていた。この時、清国政府は何もせず、義和団の勢いが良いと見るや、致命的に判断を誤り、義和団に味方し参戦した。
そこで列強8ヵ国イギリス、アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、オーストリア(=ハンガリー)と日本による連合軍が出動し、約2ヵ月後、8ヵ国の連合軍は首都北京及び紫禁城を制圧し、乱を鎮圧した。北京を占領した連合軍は各所で略奪を開始し、(頤和園も略奪と破壊の対象になったが日本軍だけは略奪に参加しなかった)
その後日清戦争にやぶれ、家臣の袁世凱に裏切られ、辛亥革命に屈することとなる。孫文は中華再興をめざしたが道半ばで没し各地に軍閥が跋扈する混沌状況となる。つまり中国全体を統治するまともな政府がない状態が(現在のシリア、イラクに近い状態が)1949年まで続く。
最近の中国
中国は以前から国力充実と共に覇権主義にもとづく拡大路線を推し進めて来ている。しかも得意の「孫子の兵法」を使うので厄介千万である。大概の日本人は中国の術中に陥り、頼みのマスコミや国会議員などもだまされたり、脅されふるえあがっている。マスコミの常套句は「日本は毅然たる姿勢を示さなければいけない」という半面「この重要な時期に相手を刺激するようなことは避けよ」とも言う。
靖国参拝をやめたから、ODAを増やしたから、教科書の記述を迎合させたから、平和憲法を守ったからといって彼らの方針が変わる事はない。
そもそも敵対する相手も居ないのに軍部を増強し、国際法を無視、海洋を侵略する中国に日本の軍国主義の反省を求めるのは筋違い。
さてその孫子の兵法とは何ぞや?中国は領有権問題でも、相手の力が弱ければ強く出るが、強ければ「棚上げ」にして静かに時を待つ。
南シナ海での領有権問題については、ベトナム、フィリピンの軍事力が弱いと見るや、軍事力を行使して領有権を奪取した。だが尖閣諸島については、威嚇や示威行為は盛んであるが、軍事力を行使しようとはしない。これは日本の自衛隊が強く、しかも日米同盟を結んでいるからである。いざ戦争となった場合、必ず勝つという勝算がない。そのため、勝てるようになるまで時間を稼ぐしかない。これが中国の主張する「棚上げ論」なのだ。
戦争とは「自国の意思を相手に強要する行為」である。相手に自分の言うことを飲ませるためには、手段は軍事力行使とは限らない。軍事力を背景にした外交も戦争なのである。 最もうまいやり方は敵の謀を破ること、つまり抵抗を諦めさせることであり、これがだめなら同盟関係を崩壊させる。軍隊同士が戦うのは最低の策だと述べる。
中国は沖縄への米軍オスプレー配備反対派を陰で支援していると云われる。またメディアに反米記事を書かせるため金を流しているとも聞かれる。反米の政治家や学者達を支援し、新聞やテレビを使って反米世論を盛り上げ、日米同盟に楔を打ち込む。中国は「孫子」を忠実に実行しているわけだ。
4.小中華朝鮮の状況
李朝時代
徳川三百年、李朝五百年と言われるが、地方を開発した日本の大名に対し、李朝では中央から派遣された両班の地方長官は、同じところには五年ほどしかいないのが普通で当然その土地の愛着も薄く、税を搾りとる。さらに庶民にとって不幸だったのは両班どうし派閥にわかれ抗争に明け暮れ、民を思いやることはまれであった事だ。
18世紀以降、西欧諸国の外圧が強くなると、キリスト教や新しい技術を受け入れようとする開化思想に対して、朱子学者を中心とする儒学者(儒生)は朱子学の道徳を守り、欧化や開化を否定して排除するという「衛正斥邪」(えいせいせきじゃ)を強く主張するようになった。
その根底は「明滅亡後、中華の正統後継は夷狄の清でなく、李朝」つまり中華文明は朝鮮にだけ残って他は野蛮人というプライドの高さである。
江戸時代中期、日本に来た通信使が日本の都会の豊さに驚き「民家が二階建てで、屋根に瓦があるなんてありえない」と更に驚く。最後に「穢れた血を持つ獣の様な人間がこんなに豊かなのはけしからん」と怒ったと「日東壮遊歌」という記録に残っている。
(1764年 1月22日大阪)大したものよ!倭人らは千間もある邸を建て中でも富豪の輩は、銅をもって屋根を葺き黄金をもって家を飾りたてている。その奢侈は異常なほどだ。北京を見たという訳官が一行に加わっているが、この地大阪には及ばないという。穢れた愚かな血を持つ獣のような人間が次第に増え、このように富み栄えている。知らぬは天ばかり。嘆くべし恨むべし。
(1月28日 京都)沃野千里をなしているが、惜しんであまりあることは、この豊かな金城湯池が倭人の所有するところとなり。帝だ皇だと称し 子々孫々に伝えられていることである。この犬にも等しい輩を、みな悉く掃討し四百里六十州を朝鮮の国土とし、朝鮮王の徳を持って礼節の国にしたいものだ。
この朝鮮、近代になり、外圧にたいして大院君(国王高宗の父)を中心として、攘夷鎖国で国を守ろうとした。しかし、高宗に閔妃が嫁してからは(閔妃は大院君の妻の口利きで、王妃となった 後年亡国の悪女とも言われている)、閔妃と大院君(高宗の嫁と高宗の父)の争いとなり閔妃が優勢となり開国したが、閔妃の政策も、ある時は清国に接近し、ある時は日本に擦り寄り、日本を捨てると、ロシアと結んだ。高宗の実父であり、恩人であった大院君を追放し、袁世凱をそそのかして逮捕させるなど、智謀家ではあったが、背恩忘徳の生涯であった。高宗も、閔妃も、大院君も、力がある外国と結んで利用し、政治をもてあそんだ。
朝鮮には憂国の士はいたが、朝鮮では大同団結し国をひとつに纏める事ができなかった。日本の朝鮮への勢力拡張が進み、日露戦争後の第2次日韓協約で保護国化が決定的となり、第3次日韓協約で軍隊の解散が命令されると、激しい義兵闘争が朝鮮各地で起こった。この闘争の理念的正当性は、初期の義兵の先頭に立っていた衛正斥邪思想を掲げる儒生たちであった。
現代の韓国
現代の韓国は民主主義,法治国家であるはずだが、しばしば、世論や反日が法や憲法より上位となる。そして時折、信じられない主張をする。例えば、戦前の測量杭を日帝が韓国の風水を乱す為わざわざ打ち込んだ杭と主張する(当時測量に携わった韓国人がまだ生きていて、これは測量の杭ですと真実を述べても無視)。
また、劣等感の裏返しの自民族優越主義の韓国起源説は世界中を唖然とさせている。世界中のすぐれたものを自国起源と宣伝する韓国の特異な点は、対象分野が広く、頻度も高い上、宣伝活動が国内のみならず世界を意識したものであるが故に組織的・大規模で、文化の発現、革新、発展、継承を無視しており、事実誤認、歴史歪曲、捏造が多い。 朝鮮日報・東亜日報・中央日報のような大手マスコミや、学者や有名作家が韓国起源説を堂々と主張・報道したりして仮説や希望的観測に基づいた虚構が「歴史的事実」として流布されている。最近は、恥ずかしくもなく「イギリス人」、「マヤ文明」、「メソポタミヤ文明」まで韓国起源と主張している。
5.アメリカの行動原理
アメリカの行動原理はなんだったのか?
それはキリスト教文明の国を築き異教徒の野蛮人を追放またはpurifyする事が神から受けた使命「マニュフェクト デスティニィ(明白なる使命)」である。
インデアンを征服したあと 更に西へ進み 次の目標は ハワイとなる。ハワイの王朝もアメリカからの移民、アメリカの資本により現地人が分断され 王国は、風前のともしびであった。来日した国王カラカウアは明治天皇に謁見した際、ハワイ王国の安泰のため日本とハワイの連邦化を提案した。さらに姪のカイウラニ王女を山階宮(やましなのみや)に貰ってほしいとの縁談を頼み込んだ。日本の皇室との結びつきを強くしてアメリカに対抗しハワイ王国の存続を考えていたとされる。当時山階宮定麿王は13歳、カイウラニは5歳この年齢だけ考えても国王の必死さが解る。しかし首を長くして朗報を待っていたハワイ王にたいし明治天皇は「国力増強に努めている明治新政府にはそこまでの余力はない」として断っている。
このハワイも1893年にアメリカ系移民がクーデターを起こし国王を幽閉してハワイ王国が滅亡した。余談になるが、英国留学中だったカイウラニは
渡米してクーデターの不当性を訴え、「律儀者」 と言われた 24代クリーブランド米大統領との面談に成功し、徹底調査する約束を取り付ける。
留学先のイギリスでイングランドの青年との恋、祖国を襲うクーデターなど、短い人生を生き抜いたカイウラニはわずか23歳で亡くなったが 郷土の星であった。
ハワイ王国を滅ぼし次の目標はフィリピンである。フィリピンの独立運動家アギナルドに「アメリカと一緒になってスペインと戦おう」などともちかけながら、スペインからフィリピンを割譲される協定がまとまるとアギナルドとの当初の約束が邪魔になり、アギナルドを逮捕、ゲリラは皆殺し、これがアメリカの言う「マニュフェクト デスティニィ(明白なる使命)」による?フィリピン解放である。
この行きつく先が中国であり、モンロー主義(他国への干渉を行わない)を掲げていたアメリカはその分割に出遅れ、中国の分け前を分捕ろうとしたのが1899年のジョン ヘイの 「機会均等」、「領土保全」という「門戸開放」宣言である。その内容は
領土保全…列国による中国領土分割に反対する。(自分の取り分が無いから列国は中国に領土を返せ)
機会均等…各国の商業、産業面での機会を均等にする。(アメリカ製品も売らせろ)
というアメリカらしい要求である。
この遅れてきた帝国主義国アメリカと満州を基盤とする日本とぶつかったのが太平洋戦争である。
駐日ポルトガルの外交官モラエスは、第一次世界大戦前に「日米両国は近い将来、恐るべき競争相手となり対決するはずだ。広大な中国大陸は貿易拡大を狙うアメリカが切実に欲しがる地域であり、同様に日本にとってもこの地域は国の発展になくてはならないものになっている。この地域で日米が並び立つことはできず、一方が他方から暴力的手段によって殲滅させられるかもしれない」と祖国の新聞に伝えている。


休憩時間での剣術の実技指導
6.満州国
満州事変前の状況
満州では、清は滅びてしまっているし、中国の統治が及ばない状態で、馬賊や軍閥が思い思いにおさめ、まともな統一して使える通貨が流通していなかった。日本に協力的で有った張作霖が最大の有力者で、それを利用して関東軍が勢力をのばしていた。日露戦争後日本とロシアは急速に接近し、1,2,3,4次の日露協約により外蒙古、北満州はロシア、南満州、朝鮮は日本とし、共同でアメリカの進出を押さえようとした。アメリカの満鉄線共同経営案や満鉄平行線敷設に反対したため不満が高まり1924年アメリカでは排日移民法の成立となる。
満州国
関東軍は、1931年(昭和6年)9月18日、満州事変(柳条湖事件)を起こして満洲全土を占領した。
事件直後参謀本部は石原莞爾らに溥儀を首班とする親日国家を樹立すべきと主張し、1932年3月1日、元首として清朝最後の皇帝愛新覚羅溥儀を満洲国執政とする満洲国の建国を宣言した。
傀儡国家と悪名高い満州国とは実際はどうだったのか?
前近代的統治をしていた馬賊や軍閥の土地に世界一の高速アジア号が走り、治安は安定し毎年100万の人口流入する近代国家に生まれ変わる。
満鉄本社では電話はダイヤル即時通話。大豆の集荷量・運搬距離・運賃はIBMのパンチカードで処理されていた。
さらに東洋で最初の本格的な高速道路、水洗トイレまで備えた近代都市、東洋一の埠頭、世界でも有数の巨大ダム、自動車工場や飛行機工場までがあった。
あるものは満州で一旗揚げようとしたし、溥儀や川島芳子は関東軍を利用して満州族の再興を夢見た。石原莞爾はアメリカとの世界最終戦までこの地から出ず国家の実力を蓄えることに思いを寄せた。また、あるものは帝国主義的支配、あるものは五族協和の王道楽土の夢、様々な思いを満州国に託したのが実情で、概していえば初期は王道、後期は覇道と考えてよい。
7.リットン調査団
満洲事変の端緒となる柳条湖事件が起こると、中華民国は国際連盟にこの事件を提起し、国際連盟理事会はこの問題を討議し、1931年12月に、イギリス人のリットンを団長とするリットン調査団の派遣を決議した。1932年3月から6月まで中華民国と満洲を調査し、同年10月2日に至って報告書を提出し、満洲の地域を「法律的には支那の一構成部分なりと雖も」としたものの「本紛争の根底を成す事項に関し日本と直接交渉を遂ぐるに充分なる自治的性質を有したり」と表現し、中華民国の法的帰属を認める一方で、日本の満洲における特殊権益を認め、満洲に自治政府を建設させる妥協案を含む日中新協定の締結を提案した。欧米は国際連盟の意向で満州国にだけリットン調査団を送り込みその結果、満州国自体は否定しないで、先進国の共同管理にすると提案した。(リットンは犬養などが軍部の独走を苦々しく思いそれに苦慮していたのを知っているだけに調査後東京の雰囲気は一変、驚くとともに、親軍内田外務大臣の高飛車な態度に憤慨した。)
松岡洋右代表は、翌1933年連盟の対日勧告案に反対し連盟脱退。
この10年前、1920年代英国がエジプトやイランでおこなった欧米の植民地、属国はそのままにして何故日本だけなのか?欧米の植民地と満州とどう違うのか?なぜ欧米はおとがめなしで日本だけ非難されるのか?欧米人とアジア人の差別の根源は何処から来るのか?松岡ならずとも理解に苦しむ。
ただ、欧米本位では有るが、この報告書に則った満州国の運営であれば、戦争になり至らなかったのではないか?大きな戦争へ至る分岐点であった。
8.恐慌から恐慌へ
不況にあえぐ人々への義憤が青年将校の行動の原点。5.15事件の将校に寄せる国民の同情、減刑願いが政党否定、青年将校の暴走へ
1920年代 第一次世界大戦の反動不況
震災恐慌 1923年
金融恐慌 1927年 取り付け騒ぎ
1930年代 大恐慌の余波が1930年に来るが、その最悪期に金解禁
特に東北では娘の身売り、青年将校の財界、政党不信といきどおり
高橋是清の財政政策が成功し、景気立ち直る。
9.戦争への分岐点
1937年 盧溝橋事件
現地で停戦協定が成立していたが、一週間もたたないうちに参謀本部、政府は出兵し、武力行使の方針に変わる。 盧溝橋から「以後国民政府を相手にせず」と蒋介石を黙殺した近衛は、軍部以上に好戦的になり、和平の機会を逃す。日中戦争 泥沼へ
三国同盟
近衛も松岡も三国同盟にソ連もひきいれて(四国同盟)、アメリカがヨーロッパ戦線に参戦するのを防ぐ狙いであったが結果は裏目。これ以後、日本に対する不信感を抱かせた(このため交渉時に誠意が通じなくなった。)
仏印進駐 (日米戦争の回避の最後の分岐点)
イギリスのアイスランド侵入、アメリカのアイスランドとグリーンランド進駐、オーストラリアとオランダによるチモール島占領など同様な軍事進駐を行なった欧米であるが、日本が進駐すると協定に基づく平和進駐であっても、欧米の不信感はぬぐえなかった。
株の世界に「見切り千両」ということわざがある。損をしている株はなかなか売れない人間の心理をいうのだ。
私見ではあるが、日本も仏印進駐の代わりに、満州以外中国からすべて撤兵、三国同盟からも脱退を宣言していれば、それこそ「千両役者」で、日米が戦う事がなかっただろう。しかし日本は「損を取り返そう」とする投資家と同じ行動にでてしまう。
松岡・アンリ協定に基づき、1940年9月23日に日本軍は北部仏印進駐を開始した。これはフランス・ビシー新政府との合法的協定であったにもかかわらず、日本のやることに、なんでも反対する姿勢を見せていたアメリカは、この協定を認めなかった。しかもなお悪い事に「平和進駐で」との陛下の希望も、陸軍の強硬派には通じず一部で戦闘がおこってしまう。
国務長官のコーデル・ハルは、日仏協定不承認声明を発した上で、屑鉄、屑鋼の対日輸出を禁止する方針を発表した。
日本軍は1941年7月28日に仏印南部への進駐を開始した。
南部仏印進駐後のアメリカの態度は極めて強硬なものとなった。アメリカは在米資産の凍結と対日石油禁輸を発表した。またイギリスも追随して経済制裁を発動した。これらの対応は日本陸海軍にとって想定外であった。当時の石油備蓄は一年半分しか存在せず、海軍内では石油欠乏状態の中でアメリカから戦争を仕掛けられることを怖れる意見が高まり、海軍首脳は早期開戦論を主張するようになった。
第Ⅱ部 人に教えたくなる昭和史理解のキーワード
1.情報戦
近代戦は人、物、兵站以外に士気、情報、戦略の総合力により勝敗が決する。
「暗号が解読されているかも知れない」と考えるよりも、「暗号は解読されない」と考えたほうが楽で「ここに敵は来ない」「敵の戦闘力はこちらよりも低い」等々の思い込み、さらに情報を共有べき仲間内にも都合の悪い事項は隠す事実さえあり、これが日本の情報戦の実態である。
一方アメリカにおいてもブラックチェンバーにより日米の暗号電報は解読され、野村全権大使と日本政府のやり取りが筒抜けになって居た。しかし肝心なところが誤訳され、日本の真意が恐ろしく曲げられて首脳につたえられ国務省に対し生半可な知識、ある時は真逆な知識を与え両国にとり救い難い悲劇となった。
ミッドウェー海戦と暗号
昭和天皇はミッドウェー海戦をまえに「どうも暗号が解読されている気がする ミッドウェーはとりやめたらどうか」とさえ仰せられていた。しかし海軍は予定を変更せず大敗北となった。
日本の「海軍暗号書D」系統は乱数表を用いて二重に暗号化した複雑な暗号であったものの、作戦前に行われる予定であった暗号の更新も遅れ、ミッドウェー作戦概要や主力部隊以外のすべての参加艦艇などの作戦全体像がアメリカにほぼ察知されていた
海戦の直後、米国の新聞 「シカゴトリビューン」 が一面トップに 「海軍は日本軍の攻撃を事前に察知」 と云う見出しで、この事実を掲載した。また、ラジオのニュースも二度にわたって、その事を放送した。 従って日本は、暗号が解読されていることに容易に気づくことができたにもかかわらず、 日本はそれすらも知らず、暗号を変更しようともしなかった。
山本五十六連合艦隊司令長官の戦死と暗号
昭和十八年四月の山本五十六連合艦隊司令長官の戦死もまた、 日本海軍の暗号を解読した米軍の待ち伏せ攻撃によるものであった。 四月十八日、山本長官は零戦六機に守られて、 ソロモン群島のラバウル基地を出発し、前線兵士を激励しようとした。その旅程を手配するための無線電信は米軍側で傍受され、直ちに暗号解読され、 米軍はブーゲンビル島上空で待ち伏せ、 司令長官の乗る一番機に集中的に機関砲を浴びせて撃墜した。日本側は二週間まえ乱数表を変更していたが、最近のアメリカの公開資料によると、このときは旧乱数表を使用したという。(いままでは 改訂した乱数表も解読されたとされていた)
撃墜の翌日、サンフランシスコ放送は山本長官の名前を出すことなく、一式陸上攻撃機撃墜の事実のみを簡単に報じた。米軍は日本軍の暗号解読に成功している事実を日本側に悟られないよう、偶然の撃墜であったかのように発表を装っている。
チャーチルの非情
山本撃墜に関し、イギリスのチャーチルは戦争遂行の上で米国は解読の秘匿を敵方にばらして取り返しのつかない失敗をしたと苦虫を噛んでいた。
なぜならチャーチルは以前イギリスが暗号を解読していることをドイツに知られたくなかったから、コベントリーと言う小さな町をドイツが爆撃するにまかせ、重大な暗号解読情報をあえて伝えず、数百人の住民が犠牲としてしまったからである。
辰巳栄一駐英武官の警告
駐英武官の辰巳栄一は早くも昭和16(1941)年10月初め、大本営に向けて英国から見た独ソ戦の帰趨を打電した。
「作戦の当初、快進撃を続けた独軍も、現在は諸種の悪条件によって戦勢振るわず、冬将軍の到来と共に益々不利となり、年内のモスクワ攻略は困難と判断せらる」
すると、東京の参謀本部の逆鱗に触れた。東京電は、「貴官が年内、モスクワ攻略困難と推断する根拠を再電せよ」と要求してきた。しかし、独ソ戦の形勢は日を追うごとにドイツ不利に傾いていた。辰巳は10月下旬になって、独ソ戦の趨勢から判断してドイツ側に立って戦争を遂行することの危険を報告した
小野寺信(まこと)駐在武官の無念
中立国スウェーデンのから打たれた小野寺信(まこと)駐在武官の機密電も、国家の命運を左右するものだった。 ソ連はドイツ降伏の後、三ヶ月をめどに対日参戦する――。小野寺信は亡命ポーランド政府のユダヤ系情報網から、ヤルタ会談(1945.2.4 米英ソ)の密約を入手し東京の参謀本部に打電した。だがヤルタ密約電を受け取りながら、あろうことか参謀本部の中枢部は抹殺してしまった。
また小野寺信はスウェーデン王室を頼りに終戦工作も進めていた。日本は天皇制の存続さえ保障されれば降伏する――ポツダム会談に臨むトルーマン大統領に伝えられた情報の背後にはスウェーデン国王グスタフ五世の影が動いていた。さらに全体主義国家ソ連は新たな領土への野心を隠していないと警告し、終戦の調停をソ連を頼むことの愚を説き続けた。だが大本営の参謀たちは、貴重なインテリジェンスのことごとくを無視し、スターリンの外交的詐術に思うさま操られていった。
2.昭和天皇
戦前の明治憲法のもとでは天皇陛下の権限が絶対で、何もかも陛下の思いのままに決められると誤解しておられる方もおられるが、政治の事も軍事のことも、陛下の権限は、質問やご要望、と言う形で示すのが精一杯で、御前会議に至っては単なる報告会であつた。
元老で元総理西園寺公望が若き昭和天皇を「天皇は独裁者ではない。政治に口をはさまないように」とたしなめた事がある。昭和三年(1928年)はじめは日本に協力していた満州の軍閥張作霖が、中国本土にまで野望を持ち日本の満州駐留軍隊「関東軍」にとって協力的でなくなったので、関東軍河本大作以下に爆破された。これが 日本では満州某重大事件と当初いわれた、張作霖爆破事件である
天皇はこの際、軍の規律を糺しておかなければ、将来軍隊が暴走すると思われ「国際的な信用を保つために容疑者を軍法会議 によって厳罰に処すべき」と主張。しかし総理の田中義一は、小川平吉鉄道大臣、等の親軍派や陸軍の強い反対に遭った為、どうにもならなくなった。
再三の天皇の厳罰の督促にたいし何もしない田中儀一にいらだちを感じ、田中総理に対し「お前の最初に言ったことと違うじゃないか総辞職してはどうか」と叱責された。
田中は恐懼し、内閣総辞職した。これに対し 西園寺は「日本は 立憲君主国天皇は独裁者ではない。政治に口をはさまないように」とたしなめた。
これ以降、政治、軍事、外交、人事にはご希望をのべられるだけであった。したがって陛下には開戦、終戦の決定権はなかつた。
開戦の詔勅に、米英と開戦となり「洵(まこと)に已(や)むを得ざるものあり。豈(あに)、朕が志ならんや」とあるが陛下が詔勅発令の直前に、「豈(あに)、朕が志(こころざし)ならんや どうして私の志であろうか いや決してそうではない」とわざわざ東条首相に加筆させた。是などが開戦の時点で陛下がなし得る限界である。
一方ポツダム宣言を受け入れるかどうかの終戦直前の御前会議は、会議が賛成三名、反対三名でどうにも決せられず、慣例の無いことではあったが、鈴木貫太郎首相が昭和天皇の御聖断を仰いだのである。
3.終戦の詔勅 千載に残る悔い
昭和20年8月15日に玉音放送されてしまったが、安岡正篤(漢学者終戦の詔勅の推敲者)は前日、詔勅を「かならず修正すべし」と内閣書記官長 迫水久常に何度も念を押した
問題の個所は「時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以テ萬世ノ爲ニ太平ヲ開カムト欲ス」の太字のところ。これでは成り行きで仕方なしにポツダム宣言を受け入れるという表現である。
四書五経のひとつ「春秋」に左氏伝という解説書があるがここはその字句「義命の存するところ」がぴったりである。「義命の存するところ堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ」でないと陛下の日本の国と人々を滅亡から救済する為、無条件降伏を受け入れるという血涙の思いが表現されない。
訂正するよう三度も朱筆で要請するも無知なのか、無頓着なのか、時間がなかったのか(定説では国民に難しすぎるとの理由)で無視され、安岡正篤は「後世に禍根を残した」と悔やんだ。
成公八年の条に「信以て義を行い、義以て命を成す」とある。従って、普通にいわれる大義名分よりもっと厳粛な意味を持っている。
国の命運は義によって造られて行かねばならない。その義は列国との交誼においても、国民との治政においても信でなければならない。その道義の至上命令の示す所によって終戦の道を選ぶのである。
4.植民地不要論
石橋湛山 東洋経済新報社 専務は、戦後内閣総理大臣を務めたが病気のため総理を辞任、無欲でそのあざやかな身の引き方はいまだに語り草になっている。
戦前 帝国主義に対抗する平和的な加工貿易立国論を唱えて、台湾・朝鮮・満州の放棄を主張する等(小日本主義)、リベラルな言論人であった。
東洋経済新報社で部下の高橋亀吉と共に経済論壇の一翼を担い、金解禁(円に金のうらづけをさせ 円は何時でも金に変えられる)には、実態の反映した新平価解禁を主張し(政府より円安)旧平価(円を過大評価)での解禁論論者井上準之助と論争している。
行政では、中央集権・画一主義・官僚主義との訣別を主張した。日中戦争勃発から敗戦に至るまで『東洋経済新報』誌上にて長期戦化を戒め、植民地を開放返却すべしとの論陣、を張っている。戦後の日本の発展を考えると「植民地は持ち出し、植民地お荷物」は正しい指摘であった。
5.終戦後も続くソ連侵攻
1945年8月のソ連軍の満州侵攻は、8月15日の日本降伏後も止まらず、同地域に滞在していた同胞4万人の命が危機に晒されていた。
終戦時の駐蒙軍司令官の根本博は武装解除に応じたら住民たちがいかに悲惨な目に逢うか知っていた。ソ連軍への抗戦は罪に問われる可能性もあったが、根本は一切の責任を負って自分が腹を切れば済む事だと覚悟を決め、「陣地に侵入するソ軍は断乎之を撃滅すべし。責任は一切司令官が負う」と、日本軍守備隊に対して命令を下した。途中幾度と停戦交渉を試みるもソ連軍は攻撃を止めず、部下将兵は必死にソ連軍の攻撃を食い止めながら、すさまじい白兵戦をも乗り越え、更に八路軍(中国共産党軍の前身)からの攻撃にも必死に耐え、居留民4万人を乗せた列車と線路を守り抜いて在留邦人の内地帰還はもちろん、北支那方面の35万将兵の復員を終わらせ、最後の船で帰国した。
第Ⅲ部 戦争の体験談
有名、無名の人々の体験談、過ぎ去った「あの時」の人や出来事を紹介し、当時の状況を再現し考察の一助にしたい。個々の戦闘では耳も目も覆いたくなる悲惨、残酷な話は数知れないが、一方ぎりぎりの局面での感動的な人間の生きざまや友情、武士道、「やまとごころ」の発露も多い。
1.鈴木敬司陸軍大佐(南機関機関長)
海南島三亜の海軍基地の一角、特別訓練所で極秘裏に独立を志すビルマ青年の軍事訓練を実施、開戦と同時に南機関も第15軍指揮下に移り日本軍第15軍はタイへ進駐した。昭和16年12月28日、140名の「ビルマ独立義勇軍」(Burma Independence Army, BIA)が誕生、鈴木大佐がBIA司令官となる。1941年3月7日 日本軍進軍を前に英印軍はラングーンを放棄し脱出、3月8日第33師団がラングーンを占領した。次いでBIAも続々とラングーンへ入城した。このときBIAの兵力は約1万余まで増加していた。
この間、ビルマへの独立付与をめぐって、早くも南方軍および第15軍と南機関との間に対立が生じていた。鈴木大佐は一日も早くビルマ独立政府を作り上げることを念願とし、早期の独立を約束していた。アウンサン(スーチーの実父)たちも、ビルマに進入しさえすれば当然、独立は達成されるであろうと期待していた。ところが、南方軍および第15軍の意向は、彼らの願いを根底から覆すものだった。鈴木大佐は6月18日付をもって近衛師団司令部付への転属が命じられた。鈴木もいなくなりアウンサンは失望し、終戦前の3月にはイギリス側につき日本をうらぎる。それでも敗戦後、鈴木大佐が英軍からBC級戦犯に指定され、ビルマに連行されたが、アウンサン将軍の抗議により釈放された。
2.光山文博少尉 卓 庚鉉(タク・キョンヒョン)朝鮮人の特攻志願者
東映 映画 ほたる 金山文隆のモデル。知覧に特攻の母と呼ばれていた「鳥濱トメ」という人がいた。特攻隊員の溜まり場となっていた富屋食堂を経営し、特攻隊員のいろんな悩みや相談を真心で受け止めていた。そのトメさんが光山少尉に「今夜が最後だから、光山さんも歌わんね。」と勧めると、
「そうだね、最後だからね。それでは僕の故郷の歌を歌うから、聞いてね。」とアリランを歌いだした。
この時、トメさんは、特攻隊員の中に韓半島出身者がいることを初めて知った。アリランを歌う光山少尉は、次第に涙でくしゃくしゃになって、二番を歌うときはもう歌にならず、いじらしく思ったトメさんは、光山少尉の手を取り、娘二人も手を取り合って泣きだした。
このように、韓半島出身の特攻隊員は、光山少尉を含めて全部で十四名いる。徴兵制は、内地では初めから実施されていたが、韓半島ではそれまでずっと免除されていた。しかし、このとき、同じように、これまで徴兵を免除してきた韓半島の青年たちに対しても徴兵制が実施され、飛行兵にも採用され、光山少尉も、それを志願し、多くの志願者の中から選ばれて特攻隊員となった。日本人でない光山がどのような気持ちで志願したかは、とても日本人には分からぬが 祖国では「日本軍に協力した者は称えられない」、「特攻隊員は犠牲者かもしれないが加害者でもある」死んでいった朝鮮人特攻隊員には実に気の毒としか言いようのない扱いである。
光山少尉は、二十四歳で戦死し、二階級特進して大尉となり、ご両親と一緒に眠っているが、光山少尉(大尉)のお父さん(アボジ)は、息子を誇りに思い、その墓碑には、「日本陸軍隼大尉」と刻んだ。これは、「卓大尉」の誤記ではなく、光山少尉の特攻乗機は、陸軍一式戦闘機、通称「隼」であり、息子を称えるために隼大尉と刻ませたのである。
3.千玄室 裏千家前家元 特攻隊熱望?(水戸黄門 西村晃との友情)
千家に伝わる利休所用 粟田口吉光を授けた父は長男の戦死を覚悟していた。母は内心の辛さを押しかくして一言だけ「あなたはあわてものだから、あわてないでね」と一言だけ同志社大学の学徒出陣に際し、別れの言葉を口にした。その言葉には「死なないで」という願いがこもっている。それを直接口にできる時代ではない。海兵団には学徒がおおかったが軍隊生活は厳しかった。試験に合格すれば一気に士菅になれる予備学生にたいして叩き上げの教官は厳しく事あるごとに殴られた。一年以上に感じた四十日の舞鶴生活がおわり飛行科に合格したので土浦、ついで徳島に転属、不思議な縁で西村晃(水戸黄門役)とは舞鶴、土浦、徳島と一緒であった。昭和二十年にはいると急降下爆撃の訓練もふえてきた。三月末特別攻撃隊を編成すると言う司令官の説明の後「熱望」「希望」「否」と書かれた紙がくばられた。
どれでもいいからマルをつけて名前を書いて提出しろと言う。もう逃げられないと思い熱望に「二重丸」をつけて提出した。やがて西村に出撃命令がでた「なんでおまえだけ待機なんだ。何か手をまわしたんやないか?一緒に死のうといったのに、俺は一人で死ぬのはいやだ。お前も志願しろ」その言葉にわたしもカッとなり上官へ直訴したが相手にされない。数日過ごすうち松山に転属し特攻に出撃しなかった。戦友西村のことが気にかかっていたが戦後初のメーデーで西村と再会し無事を喜び合った。(西村は不時着とわかる)
4.升田幸三 ポナペ守備隊 将棋棋士
関西将棋界希望の星、升田六段に再び召集令状が来た。このころの升田は時節柄ほとんど将棋が指せずに25歳を迎え気持ちがすさんでいた。しかも、今度は内地入営ではない。 配属されたのは陸軍の「菊水部隊」だった。早く言えば特攻隊と同じで、升田は、生きて日本に帰る日は来ないと観念した。アメリカ潜水艦の魚雷攻撃を奇跡的にかわして南太平洋へ出た。目的地のウエーキ島までは行けず、ポナペ島に上陸し、そのまま守備隊になった。
木の根や草の実、トカゲなどを食って、爆撃されないとみたキリスト教の教会の中で生き延びる升田は、ひたすら「打倒名人」を思い続けた。空襲のない夜は紙の盤に駒を並べ、過去1勝1敗の名人との対戦棋譜を月明かりで再現した。負ける気がしない。死ぬ前にもう一度、木村名人と指したい。
仮に生きて帰れても、木村が死んでいたらどうする。「木村名人よ、死なずにいてくれ」
将棋の実力はどんどん落ちていき名人をやっつけるどころではない。将棋のさせない自分と東京の木村との落差はなんだと毎日自分の不運を嘆いていた。ある晩 「ええい 運試しだ」と敵の爆弾が、雨のように、降り注ぐ中にわざわざ被爆しに行った。バカなことだが「これで爆弾にやられるようでは、オレの運もそれまで天佑あれば、この升田幸三を助ける」と確信した。破れかぶれのすごい思い込みではあるが、それで運よく日本に引き揚げてきて、復員服のまま殆ど連戦連勝、木村名人とは名人戦では敗れたが、王将戦では気の毒になるぐらい完璧にヤッツケた。木村名人も一勝四敗で升田に王将位は奪われもっと屈辱なのは、当時の王将戦独特の決まりで、時の名人が 升田に香車を落としてもらってさすことであった。
何年も実戦から遠ざかる人間がどうして全盛の木村義雄名人に勝てたのか、勝負事もどうしても勝ちたい負けたくないという勝負は、安全主義ではダメである。剣術と同じで、恐れ、驚き、迷い、疑いが生じる。将棋もこの一番の真剣勝負ともなれば、心の戦いで刀が交わるところからは切って下さいと言うくらい平気で危ない所へわざと死にに行かなければ刀が届かない。升田はこの四病(驚、擢 、疑、惑)を戦場の修羅場である程度、克服したのであろう。
最後に
現代の視点から見れば経済開発や民度が上がるまで有利な利権を獲得したいという日本の野望も侵略といえば侵略だが満州国以外、アジアを本気で植民地や属国にする気などはなかった。日米の戦争の淵源はアメリカの中国への帝国主義的野望と山海関(万里の長城の一部を構成する要塞。河北省秦皇島市山海関区に所在。華北と東北の境界である)をこえて満州国から中国へ軍を進めてしまった日本との中国をめぐる覇権争いである。
ただ、東京裁判のパール判事の主張する様に、公平に先の戦争をふりかえると日本のみアジアを侵略した様に評価されているが、それは欧米の勝者の論理で、
インドや清国、タイを除くアジア、ハワイでの欧米支配こそ東京裁判で裁かれねばならなかったのではないか?
原爆の使用にしたところで「戦争を終わらす為にはやむをえなかった」と未だにアメリカは反省や謝罪さえない。広島、長崎で原爆を落とされ非戦闘員が数十万亡くなっている。東京裁判の影響なのか?「日本では原水爆は悲惨だから廃止しょう」という主張が主流である。「ナチのユダヤ人虐殺に匹敵する」とアメリカを非難し謝罪をもとめる事にはならなかった。
中には、「はだしのゲン」の中沢氏や原爆死没者慰霊碑など「軍国主義日本が悪かったので原爆を落とされても仕方が有りません」という理解しがたい主張をする人がいる。
昭和の戦争もあとから考えれば何回も避けるチャンスは有った。それぞれの国が「足るを知る」と言う徳目を弁えていれば、平和の方に舵を切る事ができた。
日中戦争も太平洋戦争も敵味方とも「何のために殺し合いをしているのか」大義名分も見出す事が出来ず、原住民の犠牲を強いた愚挙である。
しかし欧米支配からアジアが解放されたのはこの戦争の結果であると言わざるをえない。 もしこの戦争がなければ、まだ数十年、ことによると70年後のいまでも欧米支配にアジア人は苦しめられているかも知れない。欧米支配からの脱却は、「話し合い」など生易しい事ではなされるはずはなく、それが「70年前日本の敗戦によるアジアの独立」である。