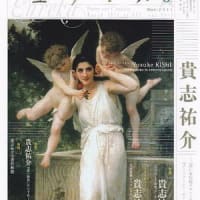ррр
[編集] 国内法
武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律- 日本
[編集] 日本
[編集] 敵に投降すること
例えば、日本陸軍で適用された陸軍刑法(明治41年4月10日法律第46号)では、
第40条司令官其ノ尽スヘキ所ヲ尽サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス
第41条 司令官野戦ノ時ニ在リテ隊兵ヲ率イ敵ニ降リタルトキハ其ノ尽スヘキ所ヲ尽シタル場合ト雖六月以下ノ禁錮ニ処ス
第77条 敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役又ハ禁錮ニ処ス
と定めて、濫りに投降することを制限していた。
しかしながら同時にこれは、然るべき場合においては投降する事が認められていた事をも意味している。
[編集] 日清・日露戦争
日清戦争においては、清軍兵士が捕虜である自覚が全く無く集団で反抗する事が日常茶飯事であったこと、清軍が日本の捕虜に対し残酷極まりない辱めを与えたことから、日本側でも清軍の捕虜の扱いは酷いものであった。
日露戦争、第一次世界大戦などでは、戦時国際法を遵守して捕虜を厚遇したことが知られている。ただし前述の経緯から、非白人の捕虜に対しては、白人の捕虜ほど厚遇はされなかった。そういう差別があったため、あくまで近代国家を目指す日本の欧米に向けたポーズでしか無かったという指摘もある。
また、日本側で捕虜となった人間の扱いも後世と異なっていた。例えば、旅順要塞降伏後、日本人捕虜101人(陸軍80名、海軍17名、民間人4名)が解放されたが、彼らは「旅順口生還者」と呼ばれ、冷遇されることは無かった。海軍捕虜の一人であった万田松五郎上等機関兵曹(第三次閉塞作戦で「小樽丸」に乗り込み、捕虜となる)は、解放後に上京し、連合艦隊司令長官東郷平八郎大将に面会して作戦状況の報告を行い、記念に金時計を授与されている。また、陸軍においても開戦直後の明治37年2月19日、義州領事館に所在して情報収集活動をしていた韓国駐在陸軍武官・東郷辰二郎歩兵少佐がロシア騎兵部隊の包囲を受けて部下の憲兵5名(中山重雄憲兵軍曹、坪倉悌吉憲兵上等兵、古賀貞次郎憲兵上等兵、牛場春造憲兵上等兵、山下栄太郎憲兵上等兵)とともに降伏、捕虜になり(日露戦争における捕虜第1号)、ペテルブルクの収容所で捕虜生活を送った後、戦後の明治39年2月14日に帰国したが、任務遂行中に捕虜になった不注意で軽謹慎30日の処分を受けたのみであり、東郷少佐は後に少将まで昇進して
いる。
[編集] 第一次世界大戦
詳細は「板東俘虜収容所」を参照
(同収容所のみならず同大戦中のドイツ兵捕虜の取扱いについて詳述されている。)
[編集] シベリア出兵
この戦いは国家対国家の正式な戦争ではなかった事、日本側の軍人、民間人が虐殺行為を受ける事がしばしばあった事(尼港事件)もあいまって、捕虜の厚遇などは全く見られなくなる。特にボリシェヴィキが組織した赤軍や労働者・農民からなる非正規軍、パルチザンの存在が兵士たちを困惑させ、時には虐殺行為すら生じた。これが日本軍における捕虜の扱いにおいての転換点となった。
[編集] 日中戦争・第二次世界大戦初期
日中戦争やノモンハン事件では、人事不省の状況などで捕虜となった日本兵が救出されて生還する例があったが、その一部は帰国後に自決を強要されたり懲罰的に戦死に追い込まれたりすることもあった。また、帰国を拒否したり、そもそも投降より自決を選んだ兵士もあり、捕虜になるよりも死を選ぶようになる。
[編集] 太平洋戦争
日本軍兵士自身の投降については戦陣訓により厳しく戒められるようになった。その原因は敢闘精神の不足と敵への情報の漏洩を恐れた事と言われる。捕虜となれば本人や家族が厳しく糾弾されるため兵士は戦死よりも捕虜になることを恐れ、しばしば自決や玉砕の動機となった。日本軍は竹永事件などきわめて少数の例外のほか組織的投降を行わず、個人の投降者も稀であった。この事は欧米と比べとても異質であるため海外から見た日本軍のイメージに大きな影響をあたえている。
一方で、捕虜となった際に敵による尋問や強要を切り抜けるための教育がなされなかった上、捕虜となったことを日本軍に通知されることを極度に恐れた日本兵捕虜は、投降前や投降直後の態度とは一転して積極的な対敵協力者になる例が多くあった。また集団心理から恐慌状態となり、カウラ事件のように絶望的な反乱を起こした例もあった。
また、投降を認めない事により、不利になった戦線をあえて見捨てるという非情の決断が不可能になり、作戦の自由度を大きく削ぐという問題も生じている。キスカ島撤退作戦が「奇跡の作戦」として特筆されているが、裏を返せば他の撤収作戦は失敗している事と、救出を諦め守備兵の降伏を認めるという選択肢が当時の日本軍には無かった事をも意味している。
海軍乙事件のように、遭難した高級将校がゲリラに捕縛され、後に解放され帰還した事件で、これを敵の捕虜となったと看做すかどうかという事のみが重要議題となり、機密文書を奪われたという重大事についての議論がおざなりになるという、滑稽な事態も起きている。
連合国側は、開戦直後から日本にジュネーヴ条約の相互適用を求めた。日本は陸・海軍の反対でジュネーヴ条約を批准しておらず、調印のみ済ませていた。日本側は外務省と陸軍省などの協議の結果、ジュネーヴ条約を「準用」すると回答した。回答を受けたアメリカ・イギリス側は批准と同等と解釈した。そのため、捕虜とした連合国兵士の扱いについては戦時中から連合国側から不十分と非難されていた。
太平洋戦争では、特に緒戦において連合国軍軍隊の大規模な降伏が相次ぎ、日本側は相当数の捕虜を管理することとなった。大規模な捕虜が出た戦いとしては、フィリピンの戦い、蘭印作戦、シンガポールの戦い、香港の戦いなどがある。これら多数の捕虜の取扱いについて、必ずしも十分な保護が与えられず、バターン死の行進、サンダカン死の行進などの事件が生じた。その原因は捕虜への考え方の違いもさることながら、日本の予想人数を大幅に超えたことや、日本軍自身の兵站が十分ではなかったことや、劣勢のため捕虜の保護が十分ではなかったことがあげられる。また、捕虜の扱いを軽視していたため、俘虜管理部の軍での地位は低く、ジュネーヴ条約の内容について、管理者に指導することもなかった。
戦後にポツダム宣言により、捕虜を不当に取り扱ったとされた軍人等が連合国による東京裁判、軍事法廷で裁かれ、処刑される者が多かった。代表的な人物として、比島俘虜収容所長(1944年3月-)となった洪思翊中将などがいる。その他、憲兵にも戦犯とされた者が多かった。
東京裁判は判決で、日本の捕虜になったアメリカ・イギリス連邦の兵士132,134人のうち35,756人(約27%)が死亡したと指摘している。
捕虜となった連合国将官としては、米国軍では、ジョナサン・ウェインライト中将(フィリピンの戦い)、エドワード・P・キング少将(フィリピンの戦い)、ウィリアム・シャープ少将(フィリピンの戦い)などがいる。英国軍では、アーサー・パーシバル中将(シンガポールの戦い)、クリストファー・マルトビイ少将(香港の戦い)などがいる。蘭国軍では、ハイン・テル・ポールテン中将(蘭印作戦)、ペスマン少将(蘭印作戦)などがいる。
1945年(昭和20年)9月2日に調印された降伏文書では「下名ハ茲ニ日本帝国政府及日本帝国大本営ニ対シ現ニ日本国ノ支配下ニ在ル一切ノ連合国俘虜及被抑留者ヲ直ニ解放スルコト並ニ其ノ保護、手当、給養及指示セラレタル場所ヘノ即時輸送ノ為ノ措置ヲ執ルコトヲ命ズ」とあり、俘虜の取扱いは日本と連合国との間で重要な事項とされた。そのため、1945年(昭和20年)12月1日に発足した第一復員省にも大臣官房俘虜調査部(初代部長は坪島文雄中将)が置かれた。
第二次世界大戦主要国別捕虜数
ドイツ 9,451,000人
フランス 5,893,000人
イタリア 4,906,000人
イギリス 1,811,000人
ポーランド 780,000人
ユーゴスラビア 682,000人
ベルギー 590,000人
フランス植民地 525,000人
オーストラリア 480,000人
アメリカ合衆国 477,000人
オランダ 289,000人
ソビエト連邦 215,000人
日本 208,000人
[編集] 第二次世界大戦後
日本国憲法第9条は自衛権を放棄していないという政府見解はあったものの、人道に関する国際条約(いわゆるジュネーヴ4条約)の国内法制については、有事法制研究においても所管省庁が明確でない法令(第3分類)とされており、自衛隊法第76条の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊による捕虜の取扱い等を具体的に定める法制は未制定であった。
この変則的な状態を解消するため、2004年(平成16年)に行われた一連の事態対処関連法制の整備に際して、国際人道法の的確な実施のための法制として、「武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律」(平成16年6月18日法律第117号)(以下「捕虜取扱い法」という。)が制定された。捕虜取扱い法は、その第1条で「この法律は、武力攻撃事態における捕虜等の拘束、抑留その他の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、武力攻撃を排除するために必要な自衛隊の行動が円滑かつ効果的に実施されるようにするとともに、武力攻撃事態において捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(以下「第三条約」という。)その他の捕虜等の取扱いに係る国際人道法の的確な実施を確保することを目的とする。」と謳っている。
その主な内容は、捕虜等の人道的な待遇の確保、捕虜等の生命、身体健康及び名誉に対する侵害又は危難から常に保護すること、その他捕虜等の取扱いに係る国の責務を定めた「総則」、捕虜等の拘束、抑留資格の確認等に関する手続、権限等を規定した「拘束及び抑留資格認定の手続」、「捕虜収容所における抑留及び待遇」、捕虜等の抑留資格認定及び抑留中の懲戒処分に対する不服申立ての審理手続等を規定する「審査請求」、捕虜等の送還等について規定する「抑留の終了」、及び捕虜等の拘束及び抑留業務の目的達成に必要な範囲での自衛官による武器の使用の規定、捕虜等が逃走した場合の再拘束の権限並びにそのために必要な調査等に関する規定を設けた「補則」等からなっている。
また捕虜取扱い法の附則により自衛隊法が改正され、捕虜取扱い法の規定による捕虜等の抑留及び送還その他の事務を行う自衛隊の機関として、(武力攻撃事態に際して)臨時に捕虜収容所を設置することができるようになった(自衛隊法第24条第4項、第29条の2第1項)。 この捕虜収容所の所長は、第三条約の規定を踏まえ幹部自衛官が任じられる(第三条約第39条第1項、自衛隊法第29条の2第2項)。