「ある貴婦人の恋」というタイトルだけでは分からなかったが、原作がゲーテで、登場人物が貴族の夫婦と友人の男と姪の4人、というあらすじを読んで、ピンときた。
これって、ゲーテの「親和力」だ!
ゲーテというと、18~19世紀のドイツの偉大な医学者であり文学者!世界が違うー!なんて敬遠する人も多いかもしれないけど…。
こんなことを言ったらお怒りになる方もおられるかもしれないが、これはある意味、現代のメロドラマ(昼メロとか)に通じる、「禁じられた愛の物語」のはしりなんじゃないかな、と思う私。
もちろん今のような軽いノリではなく、ゲーテ先生ならではの深い人間への洞察力と、19世紀初頭という時代やキリスト教というモラルの「しばり」があるから、もし同じシチュエーションが現代に起きたとしても、もっと自由な恋愛、自由なハッピーエンドへ向かうのだろうな、とは思うのだけれど。
お話はこんな感じ。(原作+映画バージョンで、ネタバレ全開なのでご注意)
19世紀初頭。
20年前に引き裂かれた恋人同士、裕福な男爵エドゥアルトと、シャルロットは偶然再会し、再び恋に落ちて結婚した。
イタリアの片田舎の館で幸せな生活を送っていたある日、エドゥアルトは妻に、才能があるのにチャンスに恵まれない建築家の友人「大尉」を館に呼びたい、と打ち明ける。
やってきた大尉はすぐに二人の生活に溶け込み、やがて妻のシャルロットも、女学校になじめずにいる姪のオッティーリエを呼び寄せたい、と言いだした。
エドゥアルト、シャルロット、大尉、そして年若い美少女のオッティーリエ。4人は美しい田園の中の館で親しくなり楽しい生活を送っていた。
だがある日、何かが変わっていくのを4人は感じていた。
エドゥアルトとオッティーリエ。
シャルロットと大尉。
エドゥアルトとオッティーリエは一途に思いを伝えあうが、シャルロットと大尉は自分たちの気持ちを自制しようとする。
そしてシャルロットは夫と姪が愛し合っていることを確信した。
だが彼女は夫との子供を身ごもっていた。逃げるように戦地に行ってしまった夫。大尉もベネチアで仕事のチャンスを得て旅立った。
オッティーリエと二人きりで過ごすシャルロットはやがて子供を産んだ。夫と自分の子供なのに、その赤ん坊はオッティーリエそっくりの目元と、大尉そっくりの赤毛をしていた。
やがてオッティーリエの過ちから起きた事故がもとで、赤ん坊は短い生を終える。誰も彼女を責める者はいなかった。
エドゥアルドがオッティーリエを迎えに来て、4人は再び前と同じような生活を始める。 しかしオッティーリエは自分を罰し、ひそかに絶食して命を絶ってしまう。
エドゥアルドも思わぬ形で彼女の後を追うことになってしまった。
シャルロットは、ついに結ばれた二人を、丘の上に並んで埋葬し、大尉もまたシャルロットに別れを告げて旅立っていくのだった。
…暗い話だ 。映画も決して明るくないんだけど、でも美しかったし、4人が仲良く幸せに暮らしてるシーンは素敵だった。
。映画も決して明るくないんだけど、でも美しかったし、4人が仲良く幸せに暮らしてるシーンは素敵だった。
多分、これが現代が舞台でハリウッド映画あたりだったら、最後にお互い「運命の本当の相手」にスイッチしてめでたしめでたし なんだろうけど…。
なんだろうけど…。
ちなみに、タイトルの「親和力」というのは、化学反応のこと。つまり4人の男女という異なる化学物質が、それぞれに引きあって化学反応を起こしていくかのように人間関係や恋愛関係が変わっていく、ということなのだろう。
私はこの本を19歳の時に初めて読んだ。よく研究室に遊びに行かせていただいていたドイツ語の教授がこんなふうにおっしゃっていた「私がゲーテの作品で一番好きなのは実は「親和力」なのですよ。大人の恋愛小説ですけどね、やはり老境に入ったゲーテだからこそ書けた不思議な力があるんですよ」
ドイツ語の本がぎっしり並んだ大学の研究室で、私はふーん、と思って話を聞いていた(けど結局専攻したのは英語でした…でもなぜかずっと仲良しだったのだ、この先生とは)。
ツタが窓の外で風に揺れている、そんな古い校舎の静かな研究室で、先生が入れてくださった外国製の紅茶やコーヒーを頂きながら、古いドイツの映画や本についていろんなお話を聞かせていただいた、不思議な空間での「少し背伸びした」思い出である。
で早速図書館で借りて読んだ「親和力」。 19歳の私にはとても大人な雰囲気であった。一番年が近いはずのオッティーリエの気持ちもよくわからなかった(っていうかゲーテ先生、この美少女を一番美化して描いてたような気がする ) 。
) 。
シャルロットだって、最後に大尉に「行かないで!」って言って一緒にいてもらえばいいのにー。(もしかしたら数年後、そうなるかもしれないけど?いやいやゲーテ先生は女性に厳しいからなー)なんて無理やりハッピーエンドに終わらせたくなるお年頃だったのであった。
そして、今は。。確かにあの時とは違う感覚でこの物語をとらえている。(今でもハッピーエンドのほうが好きだけどね)
「好きだからこそ、自分の思いに対して沈黙を保つこと」を貫こうとするシャルロットと大尉、「愛しているから妻(叔母)を裏切ること」になってしまうオッティーリエとエドゥアルド。でも4人とも、相手をののしったりは絶対しないんだよね。静かに、淡々と、相手の気持ちも認めているというか。それがこの物語の世界に不思議な調和を醸し出しているのかもしれない。
ちなみに映画版では「大尉」役のジャン・ユーグ・アングラードが素敵でございました
そのうち、原作ももう一度読み直してみようかな。こんなふうに、何年かに一度読み直すことで自分の価値観や感じ方の変化を試すことの出来るような本。それを本物の名作と言うのかもしれない。
ちなみにゲーテ先生、結構ロマンティックなお話を書かれてまして。
この「親和力」の前の話になる「若きウェルテルの悩み」は恋焦がれちゃって自滅してしまう一途な男の子の話だし(あ、でもこれも悲劇だわね・・・)。
ハッピーエンドは「ヘルマンとドロテーア」かな?
あれは、戦争に巻き込まれて家財道具だけ持って家族と一緒に難民になって街へやってきた美少女ドロテーアに恋をした気持ちのいい青年ヘルマンが、周りから何と言われても「僕は彼女が好きなんですー!」と説得しまくり最後には二人で幸せになるという話だったような・・・?(記憶では)
「ヴィルヘルム・マイスターの修業時代」だってこのタイトルの名前のお兄ちゃんの成長物語は、「ヴィルドゥングス・ロマン(つまり少年の成長物語)」の元祖でもあり、ロードムービーのはしりでもあるようなお話だし。
つまりあのマンガの「ワンピース」だって「Dragon Ball」だって、ひとくくりにすれば、ご先祖様はこの「ヴィル」と言えるかも???
やっぱりゲーテ先生は、今の小説体系のお父さんのような人だったのかも(もっとまともに言うなら「現代文学の父」?)












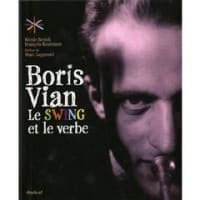






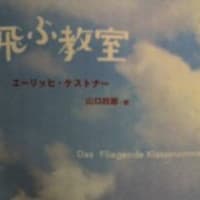
誰も幸せになっていないじゃないの…
道ならぬ恋はやはり不幸しか生まないのか…
今、ハマっているTVドラマ『同窓会』を思い出しました。
みんなどんどん不幸になっていきそうなのに、面白いんです(^^;)
たまらんとデス
私は「同窓会」は見ていないのですがみんなどんどん不幸になっていきそうなのに面白いんですか!
まさに「人の不幸は蜜の味」ってやつですかね^^;?
この「親和力」は今から200年くらい前に書かれた小説ですが、まさに「同窓会」もその曾孫的作品と言えそうですね。
このカップル、どちらもお互いに好きあってるのになんで素直にならんのだ?
いずこの時代も「じれじれ不幸ラブモード」は、自分じゃなくて他人話なら興味深い???ってことでしょうか。
たまらんとデスねー(笑)。
イヒヒヒヒッて感じとは、ちょっと違うんですよね。なんつーたらいいんでしょ。。。
若い人達の恋愛とは違っていて、
リアルなんです。失業とかホント、自分の周りの人たちとダブって、話にのめり込んでしまいます。
45歳のW不倫だったりするんだけど、すぐに関係をもつっていう軽いものでもなく、淡い恋がじれったいというか、イライラヤキモキでもあるけど、その真面目な2人を周りの人たちが追い込んでいくっていう、、、
う~ん、書くわ!ブログ書くわ!!
なるほど、人の不幸は…ではなく、感情移入してしまうようなお話なんですね。
「親和力」(訳文がかなりくらしっくなので、万人向けとしてのお勧めはできないですが…)と映画もそんな感じだったかもしれません。大人で社会人としての常識があるから自分の気持ちを抑えなければならない、でも本当は淡い思いがある、でもやっぱり自制しないと…みたいなようすがやっぱりイライラヤキモキだったような気がします。
そういうヤキモキした「ゆらぎ」を、ドラマや小説を通して、結構私たちって擬似体験しているのかもしれませんね。
そーです!感想ブログ書いてください!お待ちしてます!!