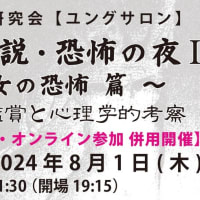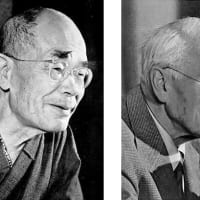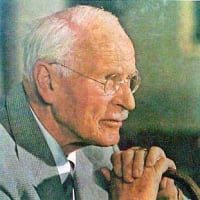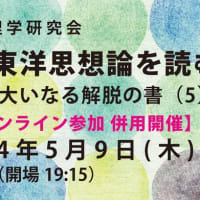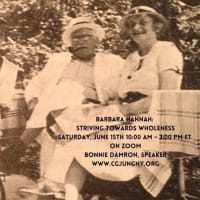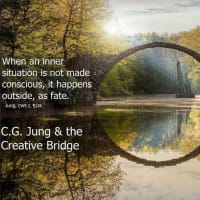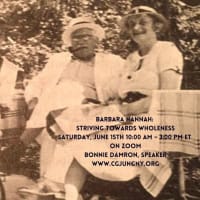聖ゲオルギウスと竜(王女の救出)
聖ゲオルギウスの伝説は、英雄ペルセウスの流れをくみ、このテーマのもとに中世末から近世に様々な作品が描かれた(日本では、八岐大蛇(ヤマタノオロチ)を倒し、草薙 剣(くさなぎのつるぎ)と櫛名田比売(くしなだひめ)を得た須佐之男命(すさのおのみこと)が対応。
英雄が囚われの女性を救出するために戦う怪物(竜)を、ユングは基本的には超個人的な恐るべき母と考えたのに対して、ノイマンはは母(自然)と同時に恐るべき父(文化:集合的意識)でもある、と考えた。つまり、この戦いによって、固定化した古い価値基準(父)を否定して、再生のの近親相姦的退行が敷衍され、恐るべき母の殺害による囚われの女性の(「たましい」)との結合が可能になる。これは、古代の豊穣儀礼の発展形態であり、これによって英雄はたましいの創造性をわがものとする。(ノイマン1954)
ユング心理学辞典P23・ アンドリュー・サミュエルズ著 その他。
英雄が囚われの女性を救出するために戦う怪物(竜)を、ユングは基本的には超個人的な恐るべき母と考えたのに対して、ノイマンはは母(自然)と同時に恐るべき父(文化:集合的意識)でもある、と考えた。つまり、この戦いによって、固定化した古い価値基準(父)を否定して、再生のの近親相姦的退行が敷衍され、恐るべき母の殺害による囚われの女性の(「たましい」)との結合が可能になる。これは、古代の豊穣儀礼の発展形態であり、これによって英雄はたましいの創造性をわがものとする。(ノイマン1954)
ユング心理学辞典P23・ アンドリュー・サミュエルズ著 その他。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E3%82%B2%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%AE%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%81%A8%E7%AB%9C_(%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%AD)
聖ゲオルギオスと竜"我々が最も必要とするものは、我々が最も探したくないところで見つかるだろう。"
怪物と戦う者は、その過程で自分が怪物にならないように気をつけなければならない。そして、あなたが深淵を長く見つめていれば、深淵はあなたを見つめ返してくる。- ニーチェ
英雄(hero)
人間の無意識的な自己に相当する神話モチーフである。ユングによると「魂をつかみとる、ないしは形成する諸理念、諸形態、諸力を象徴する疑似人間存在である」(CW5,para.259)。
神話の項を参照のこと。英雄のイメージは、人間のもっとも熱烈な願望を具現し、実現の理想的な方法を示す。
英雄は過度的な存在であり、一つのマナ人格である。英雄像に最も近い人間形態は僧侶(預言者)である。こころの内からみれば、英雄は、全体性や意味を得るためいくども追い求める経験する能力、意志をあらわしている。そのため、自我のようにみえることも、自己のように見えることもある。英雄は自我ー自己軸の人格化である。
英雄の全体性は、対立するものの恐るべき緊張に抵抗する能力のみならず、意識的にその緊張を保持する能力も示している。ユングによれば、これが達成されるのは退行の危険を冒し、「母性的な怪物に吞み込まれる」危険に意図的に身をさらすことによる。しかも、これは一度限りではなく、幼児期に始まり繰り返される生涯にわたるプロセスである。母性的な怪物をユングは集合的なこころと同一視した。
英雄モチーフについて論じる場合、ユングはその危険性を指摘しようと苦心した。この重要な形姿は、十二分に具体化して示しえないとしても、そのイメージを非常に注意深く分析的に描写し、分化させる必要がある。(分析)。
このイメージの価値は、こころの内部でのその機能にある。英雄のイメージと同一化することは明らかに危険であるが、この元型に直面するとき、ユーモアと平衡感覚が欠如しやすい。目的はその旅程よりも優位に立つとき、英雄イメージが熱烈に追いもとめられ、過度な知性主義にいたり、目標を意識的に得ようとすることもうわべだけのことになる。この目標の実現には、無意識との対話を通じて段階的にしか行なわれない。(個性化、分析家と患者、夢)。
ユングが適切に予見したように、ある元型にこのような広範囲にわたる集合的魅力が備わっているいる場合、必然的に、その集合的な表現があらわれ、投影を引き起こす。分析心理学は職業としては新しく、その初期の解釈者たちは活力に満ちていたので、この問題と直面せねばならなかった。このモチーフにはヌミノースな魅惑と感染力があるので、近年控えめに語ろうとする傾向にある。
ユング心理学辞典、p21~22 著者:アンドリュー・サミュエルズ
人間の無意識的な自己に相当する神話モチーフである。ユングによると「魂をつかみとる、ないしは形成する諸理念、諸形態、諸力を象徴する疑似人間存在である」(CW5,para.259)。
神話の項を参照のこと。英雄のイメージは、人間のもっとも熱烈な願望を具現し、実現の理想的な方法を示す。
英雄は過度的な存在であり、一つのマナ人格である。英雄像に最も近い人間形態は僧侶(預言者)である。こころの内からみれば、英雄は、全体性や意味を得るためいくども追い求める経験する能力、意志をあらわしている。そのため、自我のようにみえることも、自己のように見えることもある。英雄は自我ー自己軸の人格化である。
英雄の全体性は、対立するものの恐るべき緊張に抵抗する能力のみならず、意識的にその緊張を保持する能力も示している。ユングによれば、これが達成されるのは退行の危険を冒し、「母性的な怪物に吞み込まれる」危険に意図的に身をさらすことによる。しかも、これは一度限りではなく、幼児期に始まり繰り返される生涯にわたるプロセスである。母性的な怪物をユングは集合的なこころと同一視した。
英雄モチーフについて論じる場合、ユングはその危険性を指摘しようと苦心した。この重要な形姿は、十二分に具体化して示しえないとしても、そのイメージを非常に注意深く分析的に描写し、分化させる必要がある。(分析)。
このイメージの価値は、こころの内部でのその機能にある。英雄のイメージと同一化することは明らかに危険であるが、この元型に直面するとき、ユーモアと平衡感覚が欠如しやすい。目的はその旅程よりも優位に立つとき、英雄イメージが熱烈に追いもとめられ、過度な知性主義にいたり、目標を意識的に得ようとすることもうわべだけのことになる。この目標の実現には、無意識との対話を通じて段階的にしか行なわれない。(個性化、分析家と患者、夢)。
ユングが適切に予見したように、ある元型にこのような広範囲にわたる集合的魅力が備わっているいる場合、必然的に、その集合的な表現があらわれ、投影を引き起こす。分析心理学は職業としては新しく、その初期の解釈者たちは活力に満ちていたので、この問題と直面せねばならなかった。このモチーフにはヌミノースな魅惑と感染力があるので、近年控えめに語ろうとする傾向にある。
ユング心理学辞典、p21~22 著者:アンドリュー・サミュエルズ
マナ人格