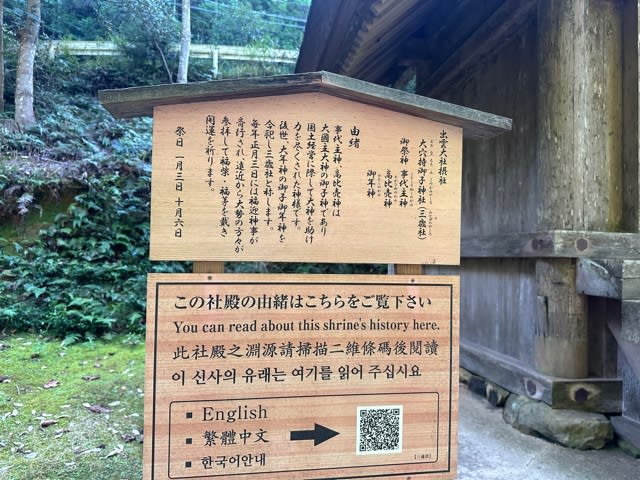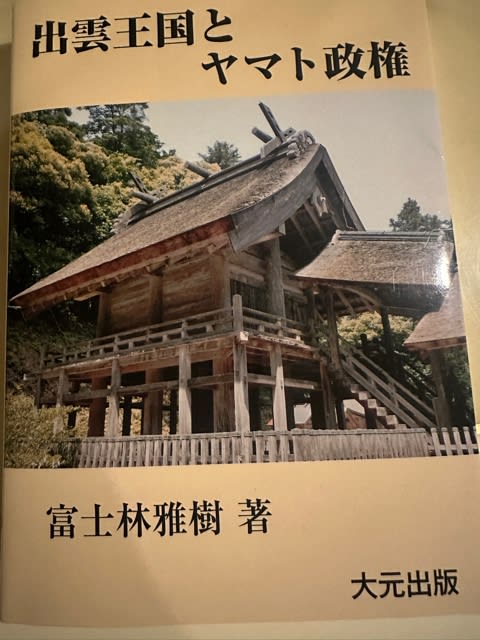大分県には民話や伝説が数多く残されており、臼杵石仏にまつわる真名野長者伝説は大分県内でも、よく知られる物語の1つのようです。
以下 HP臼杵めぐりより

時は大和朝廷(4世紀)の時代、豊後の国(大分県)大野郡三重の山里に、藤治という若者がいました。
藤治は、玉田の里の炭焼き又五郎にひきとられて育てられます。そして又五郎の跡をついだことにより炭焼小五郎すみやきこごろうと呼ばれるようになりました。

一方、奈良の都では久我大臣の娘で顔に醜いあざのある玉津姫という美しい姫がいました。
姫は「三輪の神」お告げに従って豊後の国の深田に住む炭焼小五郎(藤治)の許へ行き夫婦になりました。

金亀ケ淵で顔を洗ったら玉津姫のあざが消えてなくなるなど、夫婦は数々の奇跡により富を得て長者となります。
そして2人の間には1人の娘が誕生し「般若姫」と名付けられました。

姫は都にまで伝わるほどの美女に成長し、1人の男性と出会い結婚することになります。
実はその男性は都より忍びで来ていた皇子(後の用明天皇)でした。

その後、皇子は天皇の崩御にともない都へと帰らなければならなくなりました。
その時、般若姫のお腹にはすでに新しい命が宿っていたため、皇子は「男の子なら跡継ぎとして都まで一緒に連れてきないさい。もし女の子であれば長者夫婦の跡継ぎとして残し、姫1人で来なさい」と告げて帰京します。

産まれた子供が女の子であった為、姫は皇子との約束通リ1人で船に乗り都を目指しましたが、途中の周防灘で嵐に会い姫はついに帰らぬ人となってしまいます。

姫の死を悲しんだ長者夫妻は蓮城法師から、天竺にあるという祇園精舎ぎおんしょうじゃの話を聞きます。
そして臼杵深田の里に「満月寺」を造り、深田の岩崖には仏像を彫ってもらいました。

その仏像が現在も残る「国宝臼杵石仏」であると伝わっています。

九州への旅は、フェリーを使うと疲れもなく便利で、思いのほか近いと感じました。
四国の愛媛県八幡浜からフェリーで2時間弱で九州の臼杵港に到着です。
そして、臼杵港から車で15分ほどで石仏を観に行く事ができます。

こちら⇩の石仏、実際発見された時は、上の写真のように、仏様の頭が落ちてしまっていたようなのですが、修復されていました。

真名野長者伝説、般若姫のお話は、以前、姉に教えてもらい記憶にありましたが、実際こうして現地を訪れ、石仏を観ると、感慨深いものがあります。
老夫婦はお金を沢山手にしたものの、娘を失い深い哀しみを抱え、神に帰依することにより、心の救いを見出そうとしたのではないかなと、そんな事を考えてしまいました。



壮大な石仏を前に、日本の素晴らしさを感じました。