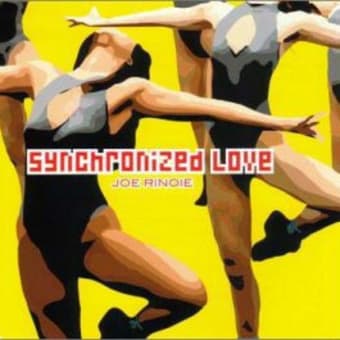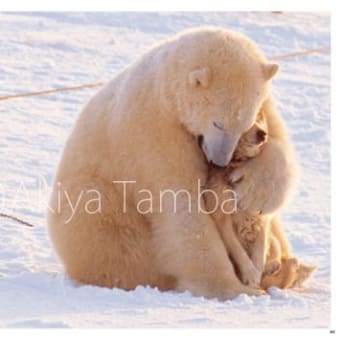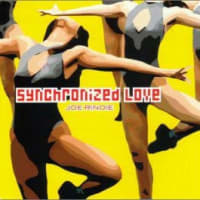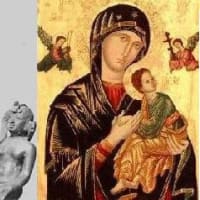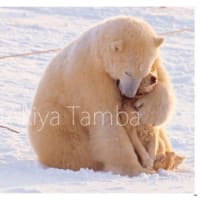管理人注:前の武蔵の記事,マキャベリの記事と併せて人たらしの極意をマスターすること.........そうすれば負けることはない。ロスチャイルド家の創業者アンセルムは12歳で父を亡くし13歳でオッペンハイム銀行に職を得て丁稚奉公しながら人たらしを見につけたのです。でもいつまでも人たらしを続けてはいけません。ハッセン公の財産を掠め取るまでの話。
今回のクリミアに対するプーチン大統領は「孫子 謀攻戦」であった。
前の記事のおさらい...............
武蔵の『独行道』21ヶ条
最後に「独行道」を書いたのが死の数日前。最後の力をふりしぼって書いたのが、自省自戒を込めた武蔵最後の書『独行道』21ヶ条、
①「世々の道を背く事なし。」世の中の不変の真理、道理に背くな。
②「身に楽しみをたしまず。」自分には娯楽を求めるな。
③「万に依怙の心なし。」えこひいきをするな。
④「身を浅く思い、世を深く思う。」自分の事は少々にして、世の為、人の為に尽くせ。
⑤「一生の間、欲心思わず。」人生において欲望を持つな。
⑥「我事において後悔せず。」いかなる事があっても後悔するな。
⑦「善悪に他を妬む心なし。」他人を決してうらやむな。
⑧「いずれの道にも別れを悲しまず。」いかなる場合でも、一切別れを悲しむな。
⑨「自他とも恨みか二つ心なし。」決して恨み心を持つな。
⑩「恋慕の道、思いよる心なし。」恋慕の心一切持つな。
⑪「物事にすき好む事なし。」物事において、風情を求めず、一切好き嫌いするな。
⑫「私宅において望む心なし。」自分の家に一切執着するな。
⑬「身一つに美食を好まず。」美食を求めるな。
⑭「末々代物なる古き道具所持せず。」骨董的価値のあるような道具を所持するな。
⑮「我が身に至り、物忌みする事なし。」迷信、不吉な事を一切気にするな。
⑯「兵具は格別、世の道具たしなまず。」兵法の為の道具以外にはこだわるな。
⑰「道においては、死をいとわず思う。」兵法の道を究めるのに死を恐れるな。
⑱「老身に財宝、所領用ゆる心なし。」財産、土地を所有する心を持つな。
⑲「仏神貴し、仏神を頼まず。」仏神は大切に崇敬するが、加護は一切頼るな。
⑳「身を捨てても、名利は捨てず。」身は犠牲にしても、名誉、誇りは捨てるな。
21、「常に兵法の道、離れず。」いついかなる時でも兵法の道を絶対離れるな。
心はすべて常に兵法に投入せよ。
人たらしの極意を教えよう
http://6707.teacup.com/gamenotatsujinn/bbs/index/detail/comm_id/340
何をするときでも,たくさんの人の意見を聞くのがよい。しかし,何をするかを決める時は,人と相談しない方がよい。(戦術論)
陰謀からわが身を守ろうとする君主は,これまで不当な扱いをしてきた連中よりも,いろいろ恩恵を与えてきた人たちの方を恐れるべきである。なぜなら後者には,前者にはない利用できる機会がふんだんにあるからである。支配欲は復讐の願望よりも大きいくらいだから,両者ともその意図は同じなのである。したがって君主は,友人たちにはあまり大きな権限は与えるべきではなく,彼らとの間にはつねに一定の距離を置いて,いつも彼らが望むものを何か残しておかなければならない。さもないと,彼らは必ず自分たちの無謀の餌食になる。(ローマ史論)
賢君として法を重んじたローマ帝政時代の皇帝たちは,それを軽く見た愚かな君主達と比べて,どんなにか称賛に値することだろう。それらの皇帝たちには,近衛兵も護衛の大軍団も必要なかった。なぜなら彼らは,みずからの立派な振る舞いと,民衆が寄せる好意と,元老院の後援によって守られていたからである。(ローマ史論)
従業員の待遇面では,彼らの野心の一部を達成する機会を与えてやることが大切である。彼らは自己実現ができて個人的なニーズを満たす機会を得ない場合には,あなたに害をもたらすことがあるからである。(ジェラルド・R・グリフィン 「管理者のためのマキャヴェリズム入門著者」
概して人間は中庸を選ぶ。だがそれは大変危険なことである。なぜならそれでは,どうしたら極端によくなるのか,もしくは悪くなるのかがわからないからである。(管理人注:多くの大企業では平均65点の人間を採用する)(ローマ史論)
戦いには二つのやり方がある。一つは法に従うもので,もうひとつは力ずくである。最初の闘い方は人間にふさわしく,二番目はけだものがそれに従う。しかし,最初の方法は無益なことが多いので,どうしても二番目の方法に訴えざるを得なくなる。したがって君主は,人間とけだものの両方の使い分けを理解する必要があり,片方だけでは安寧は得られないことを知るべきである。(君主論)
したがって,君主が優れた資質(真実を語ること,正々堂々と振舞うこと)をすべて持ち合わせている必要はない。しかし,それらを持ち合わせているように見せることは必要である。実際にそれらを持っていてたえず実行している場合には,かえって有害であり,持っているという見掛けの方が有益である。(君主論)
孫子 計篇
兵とは国の大事なり
軍事とは、国家の命運を決する重大事である。
これは見ての通りであるが、戦争というものは国家の存亡を賭けた戦いである。それゆえ、実際に戦争を起こす前には充分に互いの戦力を検討する必要がある。どちらの兵力が多いのか、規律はどちらがしっかりしているか等である。そもそも、軍隊というもの自体が消耗を前提とした非生産的な組織である。むやみに戦争をして戦力を浪費することは許されないのである。
孫子は彼我の優劣を計量する五つの基本事項として、次の5つを紹介している。それは道(民衆を統治者に同化させる、正しい内政のあり方)、天(日陰と日なた、気温の暑い寒い、四季の推移のさだめや、天に対する逆順二通りの対応、及び天への順応がもたらす勝利などのこと)、地(地形の高い低い、国土や戦場の広い狭い、距離の遠い近い、地形の険難さと平易さ、軍を敗死させる地勢と生存させる地勢などのこと)、将(物事を明察できる智力、部下からの信頼、部下を思いやる仁慈の心、困難に挫けない勇気、軍律を維持する厳格さなどの、将軍が備える能力のこと)、法(軍隊の部署割りを定めた軍法、軍を監督する官僚の職権を定めた軍法、君主が軍を運用するため将軍と交した、指揮権に関する軍法などのこと)である。
勢とは、利に因りて権を制するなり
勢いとは、その時々の有利な状況により従って、一挙に勝敗を決する切り札を自己の掌中に収めることをいう。
戦いの状況というのは固定的なものではなく、常に動く流動的なものである。戦場に臨む将軍は、機が訪れたら素早くものにしなければならない。機を掌中に収めた軍は強大となり、戦争の主導権を握ることができる。これがすなわち勢であり、将軍には俊敏な頭脳が求められるのである。
兵とは詭道なり
戦争とは、相手を騙す行為である。
戦争とはルールなき騙し合いが本質である。倫理や美徳などというものは仲間内においては成立するが、敵に対してそんなものは成立しない。徹底的に敵の裏をかき、騙していくことが戦争なのである。
算多きは勝ち、算少なきは敗る
勝算が相手より多い側は、実戦でも勝利するし、勝算が相手よりも少ない場合は、実戦でも敗北する。
戦争とはルールなき騙し合いが本質である。
倫理や美徳などというものは仲間内においては成立するが、敵に対してそんなものは成立しない。徹底的に敵の裏をかき、騙していくことが戦争なのである。 実際に相手との戦力を比較して、その勝算が立てば勝てるが、勝算が立たなければ負けるということである。勝算がないのに『やってみなければわからん』などと奇跡が起こることを頼っているような人間は、もとより指導者としての資格はない。
孫子 作戦篇
兵は拙速を聞くも、未だ巧久を睹ざるなり
戦争には、多少まずい点があっても迅速に切り上げるという事例はあっても、完璧を期したので長びいてしまったという事例は存在しない。
戦争というものは、国家の命運をかけた総力戦である。それゆえ、戦争を遂行するには莫大な費用と国力を要するのである。戦争が長引けばそれだけ国力を消費し、国民生活は貧しくなる。ゆえに、戦争というものは長期戦を避け、短期決戦を心がけるようにしなければならない。
智将は務めて敵に食む
遠征軍を率いる智将は、できる限り敵地で食料を調達するように務める。
先に述べたように、戦争は莫大な浪費である。軍隊を運用するにあたって、食料などの補給は重要な事項である。これを母国から調達しようとすれば、敵に襲われたり災害に遭うなど、全てを輸送することはできない。ゆえに、現地で食料などをまかなえば国家の疲弊の度も少なくなるし、同じ量を母国から輸送する数倍に匹敵するのである。
敵の貨を取る者は利なり
敵の物資を奪い取るのは、利益を得ようとする精神がそうさせるのである。
戦いを進めていけば、当然のことながら戦力を消費する。この穴埋めとして、いちいち母国から補給していたのでは国家はすぐに疲弊する。それゆえ、敵地にある物資を奪い取れば母国は疲弊させずに、自分の軍隊を増強することができるのである。
兵は勝つを貴びて、久しきを貴ばず
戦争では速やかな勝利こそを最高と見なして、決して長期戦を高く評価したりはしない。
戦争が、国力の単なる浪費でしかない以上は速戦速勝が求められる。これを、長期戦に持ち込まれた上に大した戦果も挙げられないというのは、最も忌むべきことである。
孫子 謀攻篇
戦わずして人の兵を屈するは、善の善なる者なり
実際に戦闘をせずに敵の軍事力を屈服させることこそ、最善の方策である。
戦争と戦闘は同義ではない。激しい戦闘の末に敵の軍事力を屈服させようとすれば、こちらの側も多大の犠牲が出る。このように、相手を屈服させるのに多大な犠牲を払うのは上策ではない。最も良いのは、戦うことなくして相手を屈服させることなのである 。
上兵は謀を伐つ
軍事力の最高の運用法は、敵の策謀を未然に打ち破ることである。
最も軍事力の有効な活用法は、敵の作戦を撤回させることである。そうすれば、敵味方両者に損害はないのである。ゆえに、軍を指揮する者はあらゆる策略を用いて、相手の計画を断念させるべきなのである。
小敵の堅なるは、大敵の擒なり
小兵力のくせに頑固に戦いを求めるのは、大部隊の捕虜となるのが落ちである。
軍を用いるためには、相手との兵力差を考慮しなければならない。仮に、兵力が少ないのに意地を張って戦いを挑んでいては、全滅するか敵の捕虜となるだけである。戦っても勝てそうにない場合は退却をして機をうかがったほうがいいのである。
将とは国の輔なり
将軍とは、国の補佐役である。
軍を率いる将軍は、国の補佐役である。よって、その国の君主と将軍が親密な関係であれば、その国は強いのである。逆に、君主が将軍に疑いを持っていたら、軍の運用に支障を来たしてしまうだろう。
彼れを知り己れを知をらば、百戦して殆うからず
相手の実情を知って自己の実情も知っていれば、百たび戦っても危険な状態にはならない。
一切の甘い考えや偏見を捨て、敵の実情と自分の実情を知ることが大切である。一見すると自己を知るのは簡単そうに見えるが、自己の願望とすりわわりやすく、自己を知るのは意外に困難である。思い込みの強い者や、反省心のない者は決して勝つことはできないのである。
孫子 形篇
先ず勝つ可からざるを為して、以て敵の勝つ可きを待つ
まず敵軍が自軍を攻撃しても勝てない態勢を作り上げたうえで、敵軍が態勢をくずして、自軍が攻撃すれば勝てる態勢になるのを待ち受ける。
戦闘を臨むにあたっては、負けない態勢(守備態勢)を作り上げることが第一である。負けない態勢というのは自軍に依存することであるが、勝てる態勢というのは相手に依存するのである。ゆえに、戦は守備を整えるをもって第一とすべきなのである。
勝兵は先ず勝ちて而る後に戦い、敗兵は先ず戦いて而る後に勝を求む
勝利する軍は、まず勝利を確定しておいてから、その勝利を予定通り実現させようとするが、敗北する軍は、まず戦闘を開始してから、そのあとで勝利を追い求めるのである。
戦というものは、あらかじめ作戦段階で勝利を確信した後に戦闘という形式を用いるのである。これは、計篇などにあるような実戦前の勝算を決める段階が最も重要であることを指摘しているのである。実際の戦闘は、勝って当然の態勢を作って臨むのが真の兵法家なのである。
善なる者は、道を脩めて法を保つ
戦闘に優れたものは、戦闘における勝敗の道理を実践し、勝敗の原則を忠実に守る。
戦闘をするにあたって考慮しなければならないことがある。まず第一には戦場が一体どこになるのか、である。次に考慮するのは、実際にどれだけの兵力を動員できるのかである。これらのことを不測の事態も考えながら運用するのが、本当の戦闘に優れた者なのである。
勝を称る者の民を戦わすや、積水を千仭の谿に決するが如き者は、形なり
彼我の勝敗を計量する者は、人民を戦闘させるにあたり、満々とたたえた水を千仭の谷底へ決壊さするように仕組む。それこそが勝利に至る態勢なのである。
将軍たるものは、兵士たちが濁流のようになだれ込む態勢を作らなければならないのであって、ただ単に兵士のやる気がないことを嘆いているだけのような人間や、兵士や民衆の多大な犠牲で自分の失敗を穴埋めしようとするの者は、もはや将軍たる資格はないということである。
孫子 勢篇
衆を治むること寡を治むるが如くするは、分数是なり
大兵力を統率していながら、小兵力を統率しているかように整然とさせることができるのは部隊編成の技術のせいである。
軍内部の統率の技量は、戦争全体の勝敗を決するくらい重要なものである。情報伝達が軍全体の隅々まで速やかに行えるか、軍内部の部署割りはちゃんと整理されているかなどを確認する必要がある。このように、軍全体を一つの有機体のように仕上げる技術は、将軍にとって必要な技術なのである。
戦いは、正を以て合い、奇を以て勝つ
戦争というものは、正法で敵軍と対陣し、奇法で勝利を得るのである。
戦争するにあたって重要なことは、敵に対して異質で有効な部隊を配置しているのを秘匿しながら、敵に臨むことである。敵がその部隊の存在に気付けば、その部隊は奇ではなく正の性質を帯びることになる。戦いでは敵に対して奇で臨むのが肝心であり、奇から正、正から奇を繰り出す方法は、円に終点がないように無限の変化なのである。
孫子は奇と正の解釈として、「奇=敵と異質の戦法を取ること」「正=敵と同質の戦法を取ること」であるとしている。
善く戦うものは、その勢は険にして、その節は短なり
巧みに戦うものは、その戦闘に突入する勢いが限度いっぱいにまで蓄積されて険しく、その蓄積した力を放出する節は一瞬の間である。
これは、勢の原理を示している。勢とは、弦を限度いっぱいまで引き、その後に矢を一瞬で放つようなものである。大きなエネルギーが短期間に放たれるほどその攻撃力は大きくなる。逐次投入というのは孫子の教えに反した稚拙な方法なのである。
紛紛紜紜、闘乱するも乱る可からず
部隊編成や指揮命令系統の軍律が徹底している軍隊は、まるで糸がもつれ合いからみ合うように、両軍入り乱れた混戦状態になっても、軍の組織や指令が混乱に陥ったりはしない。
軍の統制や兵士の戦意、軍の戦力などは常に一定なのではなく、激しい戦闘の中で絶えず変化するものである。軍を運用する者は、激しい戦闘になっても軍が乱れることがないように、常に気を配り、常に統制が取れているように努力することが肝心である。
善く敵を動かす者は、之れを形にすれば、敵必ず之れに従い、之に予うれば、敵必ず之を取る
巧妙に敵軍を移動させるものが、敵にあるはっきりした形を示すと、敵はきまってその形に対応しようと動いてくるし、敵に何らかの利益を与えると、敵はきまってその利益を取ろうと行動してくる。
この言わんとしていることは、自軍が敵に向かっていくのではなく、敵が自軍に向かうように仕向けよ、ということである。敵を自軍に向かわせることに成功すると、自軍は万全の状態で敵を迎え撃つことが出来るからである。
善く戦う者は、之れを勢に求め、人に責めずして、之れが用を為す
巧みに戦うものは、戦闘に突入する勢いによって勝利を得ようとし、兵士の個人的勇気には頼らずに、軍隊を運用する。
敵をうまく誘導することが出来たならば、勝利はもはや目前である。勝利を確信した軍は、個人の性質に関わらず、勢いがある。将軍は、勢いを個人的性質に頼ることがあってはならないのである。
孫子 虚実篇
善く戦う者は、人を致すも人に致されず
巧みに戦う者は、敵軍を思うがままに動かして、決して自分が敵の思うがままに動かされたりはしない。
虚実の戦法とは、敵兵の厚い箇所を避けて、敵の手薄な箇所を攻撃することである。そのためには、敵の利点・弱点を把握していなければならない。それだけではない。敵の利点を消し、弱点を新たに作り出すことも虚実の戦法の一つである。
孫子は虚と実の解釈として、「虚=戦備が手薄なこと」「実=戦備が充実していること」としている。
進むも迎う可からざる者は、其の虚を衝けばなり
自軍が進撃しても決して敵軍が迎え撃てないのは、その進撃路が敵の兵力配備の隙を衝くからである。
これも虚実の戦法を説いている。敵に利益を見せて動かしたり、逆に害があるかのように見せて敵を釘付けにするなどして、会戦を敵軍に強要したり、会戦を自軍が回避するということも虚実の戦法である。
能く寡を以て衆を撃つ者は、則ち吾が与に戦う所の者約なればなり
小兵力で敵の大軍を撃破できるのは、個々の戦闘において合同して戦う自軍の兵力が一つに集結しているからである。
かの有名な各個撃破という戦法である。たとえ敵が自軍の五倍あったとしても、敵軍を十箇所に分散させ、自軍を一箇所に集結させてそれぞれに当たれば、相対的に各戦闘において自軍は優位に立つことができる。このようにして、小兵力であっても敵の大軍を打ち破ることができるのである。
之れを蹟けて動静の理を知り、之れを形して死生の地を知り、之れを計りて得失の計を知り、之れに角れて有余不足の処を知る
敵の兵力を分散させるためには、まず敵情の把握が必要だから、敵軍を尾行してその行動基準を割り出し、敵軍の態勢を把握してその死活を分ける土地を割り出し、敵軍の置かれている状況を洞察して、敵にとっては何が利益で何が損失なのか、その利害・得失の計謀を割り出し、敵軍と軽く接触してみて兵力の優勢な所とを割り出すのである。
訳を見ていただければわかるであろう。敵の状況を把握することがまずは大切なのである。
兵を形すの極みは、无形に至る
軍の態勢を現わす極致は、無形に到達することである。
無形とは決して態勢が全く無いということではない。自軍の今現在の態勢が、自軍の今後行なおうとしている意図と直結しない形をもって無形と称すのである。そういう態勢を作ることができたならば、たとえスパイが進入してもこちらの意図を知られることがないからである。
兵の形は水に象る
軍の形は水を模範とする。
決まった勝利の形というのは存在しない。常に時代や敵によって変化するのである。これを理解せずに、安易に既成の枠に当てはめようと考え、思考停止の殻に安住しようとするならば、そこに待っているのは敗北の二字である。軍を率いる者は、常に頭を働かせていなければならないのである。
孫子 軍争篇
軍争の難きは、迂を以て直と為し、患いを以て利と為せばなり
軍争の難しさは、迂回路を直進の近道に変え、憂いごとを利益に転ずる点にある。
軍争とは、敵と戦場にどちらが早く到着するかを争う行為である。しかし、時には敵に戦場へ先んじられる場合もある。このときに用いるのが迂直の計と呼ばれるものである。この戦術は非常に高等な戦術であるが、内容としては以下の通りである。敵に戦場を先んじられたとき、自軍は明らかな迂回路をとりつつ、敵軍が自軍の方向へ向かわなければならない材料を作る。それに成功すると、引っかかった敵はせっかく戦場へ先に到着したのに、それを捨てて自軍の方へひきつけられるのである。このときに軍を強行すれば、輜重部隊や体力のない者を置き去りにすることとなる。これは孫子の禁じている「軍を委てて利を争う」結果になり、敵に勝つことができる。これが迂直の計の内容である。
諸侯の謀を知らざる者は、予め交わること能わず
諸侯たちの利害計算の腹づもりが読めないのでは、あらかじめ親交を結ぶことはできない。
第三国に対し、自国に味方してもらおうと考えたり、敵国に利益となるようなことをやめてもらおうと考えた時、その第三国がいったい何を考えているのか予想もできないのでは、外交で親睦を結ぼう等ということはできないのである。
兵は詐を以て立ち、利を以て動き、分合を以て変を為す者なり
軍事行動は敵を欺くことを基本とし、利益にのみ従って行動し、分散と集合の戦法を用いて臨機応変の処置を取るのである。
大軍をそのまま動かしていたのでは、明らかに敵に怪しまれ、警戒される。それを防ぐために、一つの軍を幾つかのグループに分け、集合地点で合流するといった方法が必要である。つまり、相手には自軍の意図がわからぬように行動し、敵を欺きながら進軍するような高度な機動戦が将軍には要求されるのである。
鼓金・旌旗なる者は、民の耳目を壱にする所以なり
太鼓や鉦、旗さしものなどは、兵士たちの耳で聞き目で見る働きを、将軍の指令する方向に統一するための手段である。
ここでは戦闘の入り方について説かれている。指揮・命令系統の整備や敵の気力の有無、敵の態勢などを良く知っておく。そのうえで、こちらの有利な方向に戦闘を進めるのが良いということである。
衆を用うるの法は、高陵には向かう勿れ、倍丘には迎うる勿れ、佯北には従う勿れ、囲師には闕を遺し、帰師には遏むる勿れ
大兵力を運用する方法としては、高い丘の上に陣取っている敵軍に攻め上がったりしてはならず、丘を背にして攻撃してくる敵軍を迎撃してはならず、偽って敗走する敵軍を追撃してはならず、包囲した敵軍には逃げ口を残しておき、故国に帰還しようとする敵軍を遮り留めたりしてはならない。
ここでは戦ってはならない状況を説いている。上に書いてあるようなことすれば、必ず手痛い打撃を被るからである。どのような風に戦闘に入れば自軍に有利なのかを将軍はよく考察しなければならない。
孫子 九変篇
将の九変の利に通ずる者は、兵を用うることを知る
将軍の中で九種の応変の対処法が持つ利益に通暁する者こそは、軍隊の運用法を真にわきまえているのである。
九変を知ることが重要であることを説いている。もし、君主がこれらの対応をわきまえすに無謀な命令を下した場合、兵を率いる将軍は国家の利益のためにも、それを拒絶するだけの勇気が必要である。
九変とは、次の9つの状況を指す。それは泛地(足場が悪く、行軍に難渋する、不安定な地形のこと。ここで軍を休めてはならない)、衢地(四方の諸国に通ずる大道が交差する十字路、交通の要衝のこと。ここに到着したら、天下の諸侯と親交を結ぶのが良い)、絶地(本国から隔絶し、敵国の領内奥深く入り込んだ土地のこと。留まらないですばやく通り過ぎたほうが良い)、囲地(三方を山岳や丘陵などに囲まれ、わずかに狭い道が外側に通じている土地のこと。このような地形では、脱出のための計謀をめぐらせなければならない)、死地(背後と左右の三方を、断崖絶壁などの峻険な地形で完全に囲まれ、しかも前面に強力な敵軍が陣取っている土地のこと。このような環境では、必死に力戦をするほかにない)、経由をしてはならない道路(途中に行軍が渋滞する難所があって、浅く侵入すれば難所の手前で行軍が滞って、それ以上の進軍がはかどらず、戦闘部隊が無理にその難所を越えて深入りすると、今度は後続部隊が難所で立ち往生して、軍が分断されてしまうような道路のこと)、攻撃をしてはならない軍(彼我の兵力上は正面攻撃によって撃破できる目算が充分立っても、よく深謀遠慮してみると、他にもっと巧妙なてがあって、労せずして撃破できる可能性のある軍のこと)、攻略してはならない城(第一に、兵力上は充分攻め落とせる目算は立つが、それを抜いてもそこから先の前進に別段の利益がなく、たとえ攻略してみても以後その城を守りきれる成算のない城。第二に、いかに力攻めしてみても攻略できそうにもなく、素通りして前進し、先方で勝利を収めた場合には、自動的に戦意を失って降伏してくる城、またよしんば先方で勝利が得られなくても、あと自軍の害と恐れのない城のこと)、争奪してはならない土地(水や食糧が得られぬ劣悪な環境で、たとえ奪い取ってみても、所詮、長くは占領を維持できない不毛な土地のこと)である。
智者の慮は、必ず利害を雑う
智者の思慮は、ある一つの事柄を考える場合にも、必ず利と害の両面をつき混ぜて洞察する。
あらゆることにいえることであるが、何事にも利益と害の両面が存在する。本当に頭の良い人間は、見た目に惑わされずに利害両面から物事をよく考察した上で判断を下す。また、相手に対しては利益のみ、または害のみがあるように見せかけて、正しい判断ができないように仕向けるのである。
兵を用うるの法は、其の来たざるを恃むこと無く、吾が以て待つに恃むなり
軍事力を運用する原則としては、敵がやって来ないことをあてにするのではなく、わが方に敵がいつやって来てもよいだけの備えがあることを頼みとするのである。
一言で言うならば、いつ何が起きてもよいだけの準備を整えよ、ということである。自軍の状況が相手に依存していたのでは、主導権を相手に取られることになるからである。
将に五危有り。必死は殺され、必生は虜にされ、忿速は侮られ、潔廉は辱められ、愛民は煩わさる
将軍には五つの危険がつきまとう。思慮に欠け決死の勇気だけなのは殺され、勇気に欠け生き延びることしか頭にないのは捕虜にされ、怒りっぽく短気なのは侮蔑されて計略に引っかかり、名誉を重んじ清廉潔白なのは侮辱されて罠に陥り、人情深く兵士をいたわるのは兵士の世話に苦労が絶えない。
真の名将と呼ばれるものは、相矛盾した性質を同時に併せ持つ人物のことをいうのである。もし何か欠けた面があるならば、何らかの危険が伴ってしまう可能性が大きいのである。
孫子 行軍篇
四軍の利は、黄帝の四帝に勝ちし所以なり
山岳・河川・沼沢・平地の四種の地勢にいる軍隊の戦術的利益こそは、黄帝が四人の帝王に勝った原因なのである。
それぞれの地形には、それに伴う利点がある。ゆえに、軍を率いる者はその利点を充分に生かして戦うべき、ということである。なお、「黄帝」「四帝」とは、中国の黄帝伝説に出てくる人物のことである。
ここで言われている四軍の利とは、山岳(山を越えるときには谷沿いを進み、高みを見つけては高地に休息場所を占め、戦闘に入る際には高地から攻め下るようにし、決して自軍から攻め上ったりしてはならない)、河川(川を渡り終えたならば必ずその川から遠ざかり、敵が川を渡って攻撃してきた時には、敵軍がまだ川の中にいる間に迎え撃ったりはせず、敵兵の半数を渡らせておいてから攻撃を加えること)、沼沢地(すばやく通過するようにして、そこで休息してはならない。もし敵と遭遇し、沼沢地の中で戦う事態になったならば、飲料水と飼料の草にある近辺を占めて、森林を背にして布陣すること)、平地(足場のよい平坦な場所を占めて、丘陵を右後方に置き、低地を前方に、高みを後方に配して布陣すること。なお、丘陵を右後方にするのは、兵士の大半が右利きであることが前提である)の各地形で得られる利益を言う。
軍は高きを好みて下きを悪み、用を貴びて陰を賤しみ、生を養いて実に処る
軍隊は高地を好んで低地を嫌い、日当たりのよい南に面した場所を最上として、日陰になると北に面した場所を最悪とし、兵士の衛生に気を配りながら、水や草の豊な地域を占める。
軍を駐屯させる場所についての記述である。衛生の悪いところに駐屯しておくと、兵士たちの健康状態を維持することはできないからである。
上に雨水ありて、水流至らば、渉るを止めて其の定まるを待て
上流で雨が降り、増水した水流がすでに渡河地点に及んだならば、渡河を中止して水かさが減るまで待機せよ。
端的に言えば、増水した危険な川を渡るなということ。
絶澗に天井・天窖・天離・天陷・天郄に遇わば、必ず亟かに之れを去りて、近づくこと勿れ
断崖絶壁にはさまれた谷間で行動中に、天然の井戸や天然の穴倉、天然の仕掛け網、天然の陥し穴、天然の切り通しなどに遭遇したときは、必ずすばやくそこから離脱して、接近してはならない。
ここでは、はまり込むと危険に陥る地形を示している。自軍はこのような地形を避ける一方、敵にはそのような地形に誘導するのが望ましい。
軍の行に険阻・潢井・葭葦・小林・翳薈の伏匿す可き者有らば、謹みて之れを復策せよ。姦の処る所なり
軍隊の進路に、険しい場所やため池、窪地、葦原、小さな林、草木の密生した暗がりなど、身を隠して潜むことができる地形があるときは、慎重に捜索を反覆せよ。悪巧みを抱く敵兵が潜伏する場所だからである。
身を隠せるような地形に差し掛かった場合、敵が何らかの策を設けているかも知れない。よって、被害を未然に防ぐためにも慎重に周囲を捜索すべきである。
敵の近くして静まるものは、その険を恃むなり
敵軍が自軍の近くにいながら、平然と静まり返っているのは、彼らが占める地形の険しさを頼りにしているのである。
ここでは、敵軍の動きからその意図しているものを読み取る方法を教えている。注意深く敵を観察し、何をたくらんでいるのかを見抜くことが大切なのである。
杖きて立つ者は、飢うるなり
兵士が杖にすがってやっと立っているのは、その敵軍が飢えて衰弱しているからである。
敵兵を見て敵がどんな状態にあるのかをよく見よ、ということである。そこから、自軍がどんな対策を取ったらいいのか判断することが大切である。
兵は多益に非ざるも、武進すること毋ければ、以て力を併せ料るに足りて、人を取らんのみ
たとえ兵力数は圧倒的に多くなくても、軽率に猛進しさえしなければ、少ないながらも戦力を集中して敵情を読むには充分であって、最後は敵を思い通りに屈服させることができよう。
ただ数が多いだけの烏合の衆では駄目なのである。軍全体の団結があって、初めて勝利を手にすることができるのである。そのため、将軍たる者は軍全体の団結を心がけなければならない。人は必ずしも人の下につくことを嫌がりはしない。ただ、信用の置けない無能な上司の下では働きたくないだけなのである。
孫子 地形篇
凡そ此の六者は、地の道なり。将の至任にして、察せざる可からざるなり
およそこれら六つの事柄は地形についての道理である。将軍の最も重大な任務であるから、明察しなければならない。
将軍というのは、各地形における対処の仕方を知っていなければならない。その知識の有無が、戦の勝敗を大きく左右するからである。
孫子は地形に関する六つの事柄として、四方に広く通じている地形(敵よりも先に高地の南側に陣取って、食糧の補給路を有利に確保する形で戦うと有利になる)、途中に行軍が渋滞する難所を控えている土地(難所の向こう側に敵軍の防禦陣地がない場合には、難所を越して出撃して勝てる。しかし、敵軍の防禦陣地が存在する場合には出撃しても勝てず、難所を越えて引き返すのも難しくなるので不利となる)、脇道が分岐している土地(敵の誘導には乗らず、軍を後退させて分岐点を離れ、逆に敵軍の半数を分岐点を過ぎて進出させておいてから攻撃すると有利になる)、道幅が急に狭くなっている土地(先に自軍が占拠してれば、隘路に自軍を隙間なく密集させて敵を待ち受けるとよい。しかし、敵が隘路に隙間なく軍を密集させていた場合には攻撃せず、隘路を敵が占拠していても隙間がある場合には攻めかかるとよい)、高く険しい土地(高地の南側に陣取ったうえで、敵の来攻を待ちうける。敵が高地の南側に陣取っていた場合は軍を後退させ、攻めてはならない)、双方の陣地が遠くへだたっている地形(先に攻撃を仕掛けた側が不利になるので、こちらから攻撃を仕掛けないこと)を挙げている。
凡そ此の六者は、天の災いには非ずして、将の過ちなり
全てこれら六つの事柄は、天が降した災厄のせいではなく、将軍自身の過失のせいである。
ここでは六種類の敗走の形態を示しながら、敗北するのは将軍の責任であることを教えている。敗北したのは天運が味方しないなどと言いながら、責任を運命や神様などに押し付けるなどというのは責任転嫁も甚だしいということ。そういった連中は、いつまでも天運のせいにしながら何度でも敗北し続けるのである。
孫子は敗北に至る六つの事柄として、四方に逃げ散る軍隊(軍の態勢が互角で、十倍近くも兵力が多い敵を攻撃するような軍隊のこと)、規律がだらける軍隊(兵士の向こう意気が強いのにも関わらず、それを監督する官吏が弱腰な軍隊のこと)、士気が落ち込む軍隊(監督する官吏が強腰で、兵士が弱腰の軍隊のこと)、組織が崩壊する軍隊(軍吏と将軍の中が悪く、敵に遭遇した時に軍吏が勝手に行動しても、それをどうしたら良いのか将軍がわかっていない軍隊のこと)、統制が混乱している軍隊(将軍が弱腰で威厳に欠け、方針も明確に伝わらず、兵に規律がなく陣立てもばらばらな軍隊のこと)、決まって敗北する軍隊(精鋭部隊を保有していないにもかかわらず、敵を見れば何も考えずに攻撃を仕掛けようとする将軍に率いられた軍隊のこと)を挙げている。
進みて名を求めず、退きて罪を避けず、唯だ民を是れ保ちて、而も利の主に合うは、国の宝なり
君命を振り切って戦闘に突き進むときでも、決して功名心からそうするのではなく、君命に背いて先頭を避けて退却をするときでも、決して誅罰を免れようとせず、ひたすら民衆の生命を保存しながら、しかも結果的にそうした行動が君主の利益に叶うような将軍こそは、国の財宝である。
状況を多角的に分析し、その上で国家の利益となると判断した場合は、たとえ君主が戦闘を禁止していてもそれに背いて構わないし、国家にとって損害になると判断した場合は、戦闘を命じられていても退却してもかまわないということ。そのような状況判断のできる将軍は、国家にとって何物にも代えることのできない存在である。
卒を視ること嬰児の如し
平素から将軍が兵士たちに注ぐまなざしは、まるでいとおしい赤ん坊に対するようである。
将軍は、通常から兵士をいたわって過ごしていかねばならない。しかし、ただいたわるだけでは兵士たちは慢心するので、時には谷底に突き落とすようなこともしなくてはならない。これも、全ては戦争で生死を共にするためである。
地を知り天を知らば、勝は乃ち全うす可しと
土地の状況が軍事に持つ意味を知り、天界の運行が軍事に持つ意味を知っていれば、勝利は計算通り完璧に実現できる、といわれるのである。
訳を読んだとおりである。謀攻篇の「彼れを知り...」に付け加えて、地形効果までを考慮に入れるならば、必ず戦を思う通りに動かすことができるのである。
孫子 九地篇
地形とは、兵の助けなり
土地の形状とは、軍事の補助要因である。
この章では、九つの地勢についての特徴を記している。地形効果というのは、あくまで補助要因であって主要因ではない。戦における主要因は勢や策謀にあることをお忘れなく。
孫子は九地について、散地(諸侯が自国の領内で戦うこと。ここでは戦闘をしてはならない)、軽地(敵国内に侵入しても、まだ深入りをしていない場所のこと。ここでぐずぐずしていてはならない)、争地(奪い取った側が有利となるような土地のこと。奪われた場合は、そこにいる敵を攻めてはならない)、交地(自軍も敵軍も自由に往来できるような場所のこと。ここで軍の隊列を切り離してはならない)、衢地(諸侯の領地に三方に接していて、先着した側が諸侯の支援を受けられるような土地のこと。ここに到着したら、直ちに天下の諸侯と親交を結ぶのが良い)、重地(敵国の奥深くに進入し、多数の敵城を後方に背負っているような土地のこと。ここは敵城などに構わず、すばやく通り過ぎること)、泛地(足場が悪く、行軍に難渋する、不安定な地形のこと。ここで軍を休めてはならない)、囲地(三方を山岳や丘陵などに囲まれ、わずかに狭い道が外側に通じている土地のこと。このような地形では、脱出のための計謀をめぐらせなければならない)、死地(背後と左右の三方を、断崖絶壁などの峻険な地形で完全に囲まれ、しかも前面に強力な敵軍が陣取っている土地のこと。このような環境では、必死に力戦をするほかにない)を挙げている。
利に合わば而ち動き、利に合わざれば而ち止む
敵の戦闘態勢が自軍に有利になれば戦闘を仕掛け、有利にならないときは合戦に入るのを中止したのである。
こちらが戦闘を仕掛ける時、相手の態勢が撹乱された状態であるのが最も好ましい。相手が万全の態勢では勝利を確信できないからである。
其の愛する所を奪わば、則ち聴かん
敵が重視している地点を奪い取れば、敵はそこを奪い返そうとして、せっかく整えた態勢を崩すので、その後はこちらの望み通りになるでしょう。
敵が大勢力かつ整然とした態勢でやってきたらどうすればよいのか、という問いに答えた文である。相手の態勢を崩したいときに、敵が重要視しているものを攻め立てれば、相手はいても立ってもいられなくなる。そういう相手の心理を利用するのである。
謹み養いて労すること勿く、気を并わせ力を積み、兵を運らして計謀し、測る可からざるを為し、之れを往く所毋きに投ずれば、死すとも且た北げず
慎重に兵士たちを休養させては疲労させないようにし、士気を一つにまとめ戦力を蓄え、複雑に軍を移動させては策謀をめぐらして、自軍の兵士たちが目的地を推測できないように細工しながら、最後は軍を八方塞がりの状況に投げ込めば、兵士たちは死んでも敗走したりはしない。
戦闘意欲の低い軍において、無理やりにやる気を出させるためには、まずは生きては帰れないようなところに兵士たちを誘導するとともに、そういった意図が兵士たちに解らないように仕向けるのである。
剛柔皆な得るは、地の利なり
剛強な者も柔弱な物も、そろって存分の働きをするのは、兵士たちをそのようにさせる地勢の道理による。
どんな者でも一致団結して物事に当たらせるためには、地勢の効果を利用するのが良いということ。すなわち、兵士達を死地に追い込むなどをして決死の覚悟で戦わせようとさせるのが良いのである。
能く士卒の耳目を愚にして、之くこと無から使む
士卒の認識能力を巧みに無力化して、逃亡しないように持ってゆく。
もし兵士達が自分が死地に追い込まれようとしていることに気か付いたら、命惜しさに逃亡してしまう。それを防ぐために、兵士達の認識能力を無力化できるようにしなければならないのである。
諸侯の情は、邃ければ則ち禦ぎ、已むを得ざれば則ち闘い、過ぐれば則ち従う
諸侯たちの心情としては、侵攻軍がまだ自国の中心部から遠くを行動していれば、それ以上の侵入をその線で防ぎ止めようとするし、奥深くまで侵入を許し、国都など需要拠点を攻撃されて、のっぴきならない窮状に追い込まれれば、初めて主力軍を繰り出して決戦しようとするし、侵攻軍が自国の中心部を通り過ぎて危機が去ってしまえば、今度は追撃したがるものである。
諸侯たちの行動を示している文である。この心理効果を利用して敵の主力を誘き出すと共に、自軍を死地に追い込んで兵士達が勇戦奮闘をせざるを得ない状況に追い込む。そして、大会戦で一気に勝負をつける。これも、長期戦を避けて短期決戦へと敵を追い込むための作戦なのである。
衆は害に陥りて、然る後に能く敗を為す
兵士達は、とてつもない危険な場所にはまり込んだのちに、ようやく敗れかぶれの奮戦をするものである。
あらかじめ設定された目的を達成するためには手段などを選んでいる暇はない。兵士達に否が応でも奮戦してもらうには、あえて危険な場所に陥れる必要があるのである。
始めは処女の如く、敵人戸を開くや、後は脱兎の如くにして、敵は拒ぐに及ばず
最初のうちは乙女のようにしおらしく控えていて、いざ敵側が侵入口を開いたとたん、後は追っ手を逃れる兎のように一目散に敵国の懐深くまで侵攻してしまえば、もはや敵は防ぎようがないのである。
この章では何度もくり返されているが、とにかく短期決戦で一気にカタを付けてしまう方法が最善である。よって、戦が始まったら迅速に行動して、一気に決着をつけるべきなのである。
孫子 用間篇
爵禄百金を愛みて、敵の情を知らざるは、不仁の至りなり
間諜に爵位や俸禄や賞金を与えることを惜しんで、決戦を有利に導くために敵情を探知しようとしないのは、民衆の長い労苦を無にするもので、民を愛し憐れむ心のない不仁の最たるものである。
戦争のために莫大な準備をしていても、たった一日の敗北ですべて無に帰してしまうのである。敵側の情報をつかもうと努力し、戦争をより有利に進めようと努力すべきなのである。間違っても間諜(スパイ)を卑怯だと罵って用いようとしないのは、愚人のやることである。
間を用うるに五有り
間諜の使用法には五種類ある。
間諜の様々な使用法を述べている文である。状況に応じて使い分けることが重要である。
孫子は5種類の間諜として、因間(敵国の民間人を手づるに諜報活動をすること)、内間(敵国の官吏を手づるに諜報活動をすること)、反間(敵国の間諜手づるに諜報活動をすること)、生間(繰り返し敵国に進入しては生還し、情報をもたらすこと)、死間(虚偽の軍事計画を部外で実演させて見せ、配下の間諜にその情報を告げさせておいて、欺かれて計略に乗ってくる敵国の出方を待ち受けること。生還する望みがほとんどないのでないのでこの名前がある)を挙げている。
三軍の親は、間よりも親しきは莫く、賞は間より厚きは莫く、事は間よりも密なるは莫し
全軍のうちでも、君主や将軍との親密さでは間諜がもっとも親しく、恩賞では間諜に対するのが最も厚く、さまざまな軍務では間諜を扱うのが最も秘密裡に進められる。
戦争の行方を決定付ける情報を収集する間諜というのは、全軍の中でも最も厚遇されるべき人間である。間諜を冷遇しているような軍というのは、それだけ勝利から遠ざかることになる。
軍の撃たんと欲する所、城の攻めんと欲する所、人の殺さんと欲する所は、必ず先ず其の守将・左右・謁者・門者・舎人の姓名を知りて、吾が間をして必ず索りて之れを知ら令めよ
攻撃したい軍隊や、攻略したい城邑や、暗殺したい要人については、必ずその軍隊指揮や城邑守備や要人警護などの任に当たる将軍や、左右の側近、謁見の取り次ぎ役、門衛、雑役係などの姓名を事前に割り出したのち、配下の間諜に必ず彼らの身辺に探りを入れさせて、それらの人物の履歴・性癖・境遇などを調べ上げさせよ。
敵将がどんな人物か、どんな人物を用いているのかなどを調べた上で、その人物に隙があるかなどを調べることが重要である。
反間は厚くせざる可からざるなり
反間は、是非とも厚遇しなければならない。
敵に怪しまれなくて済む二重スパイを手に入れられるかどうか、これが情報戦に置いて決定的な役割を果たす。ゆえに、二重スパイは最も厚遇すべき存在なのである。
唯だ明主・賢将のみ、能く上智を以て間者と為し、必ず大功を成す
ただ聡明な君主や智謀にすぐれた将軍だけが、非凡な知恵者を間諜として敵国の中枢に送り込んで、必ず偉大な功業を成し遂げることができる。
情報を収集する間者というのは、非凡なる優秀な人物でなければならない。間者の重要性を知る者の間者というのは、知恵者であることは間違いないのである。
孫子 火攻篇
火を攻むるに五有り
火を用いる攻撃方法には五種類ある。
一言に火攻めと言っても、その方法は五種類ある。また、火がつきやすく、燃え広がりやすい天気を選んで行なうことが火攻めの成功に繋がっていくのである。
孫子は火計を次の5種類に分類している。それは火人(兵舎に火を放ち、敵兵を焼き撃ちする方法)、火積(野外にある物資の集積場を焼き払うこと)、火輜(敵の輜重部隊を焼き撃ちすること)、火庫(屋内にある物資を保管している倉庫を焼き払うこと)、火隧(甬道や桟道などの行路を焼き撃ちすること)である。
軍に必ず五火の変有るを知り、数を以て之れを守る
軍事には、必ず五種の火攻めの対処法があることを熟知し、技術を駆使してそれらの攻撃法を遂行するのである。
敵の兵舎を焼き討ちした場合には、五種類の対処法がある。その状況によって、軍の進撃を考えなければならない。
孫子は焼き討ちを、次の5つの状況に分類している。それは内応者や工作員の放った火が兵舎内で燃え出した場合(待機中の部隊は、外にすばやく出火に呼応して攻撃すると良い)、出火したにもかかわらず、敵兵が平静な場合(ただちに攻めあがってはならず、その広がり具合を見てその火災に乗ずることができるかを判断する)、敵陣に強風が吹いて、外から放火が可能な場合(火の手が上がるのを待たずに、好機を見計らって火をつける)、 放った火の手が風上から燃え広がった場合(呼応して風下から攻撃してはならない)、昼間に終日風が吹いていた場合(夜になると風が止んだりするので、夜の火攻めは中止する)である。
火を以て攻を佐くる者は明なり
火を攻撃の補助手段にするのは、将軍の頭脳の明敏さによる。
この文は、火攻めが優れた攻撃手段であることを示している。水攻めなどは、火攻めに比べて費用も財力も必要となる。しかし、水攻めでは敵の兵力を取り除くことはできない。費用・人員などもかからずに、敵兵力を取り除くことができる火攻めは優れているのである。
怒りは復た喜ぶ可く、慍りは復た悦ぶ可も、亡国は以て復た存す可からず、死者は以て復た生く可からず
怒りの感情はやがて和らいで、また楽しみ喜ぶ心境に戻れるし、憤激の情もいつしか消えて再び快い心境に戻れるが、軽はずみに戦争を始めて敗北すれば、滅んでしまった国家は決して再興できず、死んでいった者たちも二度と生き返らせることはできない。
孫子は一番最初に軍事についての重要性を説いている。そして各章で兵法について語った後、最後に戦争は感情で軽がるしく起こしてはならないことを説いている。まさに、孫子を締めくくるのにふさわしい言葉であると思う。
最新の画像もっと見る
最近の「ノンジャンル」カテゴリーもっと見る
最近の記事
カテゴリー
バックナンバー
人気記事