この記事の末尾へ 新しいアルバムの目次へ 古いアルバムの目次へ 神々を訪ねて目次へ
思いついて、梅雨の晴れ間の五日間、(前回お伝えした)高越山、忌部氏の里を歩いてきました。すでに説明的なことは記していますので、(下手ですが)写真をお楽しみください。
高越山は、へんろ道保存協力会の地図では、90-2に載っています。

高越山 田植えの時期でした

奥が山頂です

振り返ると山川町が

登山口
参道ですが、登山道でもあります。道標を見ると、いろいろのグループ、団体が道の整備にかかわっているのがわかります。

遍路札

登山道標

丁石がかなり残っています

石仏
「四国西国秩父坂東納経供養」とあり、明和五(1769)の年号が刻まれています。
木札には「三の休場跡」とあります。

道標
高越寺へ2.7キロ、徒歩で約1時間
山川まで2.2キロ、徒歩で約50分、と表示されています。

高越山 中野郷 中前寺
高越山の「肩」の部分を中野郷と言い、中前寺があります。標高550㍍ほど、ほぼ道半ばの所です。

覗岩
中野郷から、(寄り道になりますが)、5分弱の所に行場、「覗岩」があります。
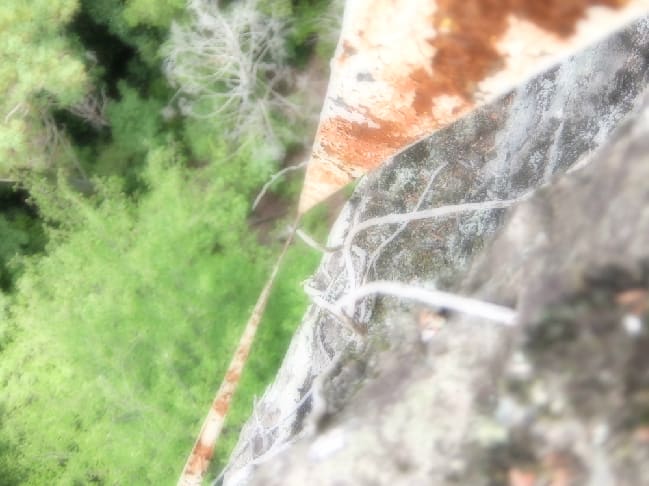
下の景色
カメラを差し出して写してみました。梯子が2本、かかっているようです。

赤樫
中前寺に戻り、高越山への登りを再開しますが、20㍍ほど奥まった所に、樹齢1000年とも言われる赤樫の木があります。見事な樹相でした。根元には板碑がおいてあります。

番小屋?
だいぶ寺が近づいてきました。
最近の補修の跡が見えます。(前回お伝えした)「十八山」(じゅうぱっちゃま)で使われるからでしょうか?用途を尋ね忘れました。
追記:7/3付け徳島新聞によると、・・・山頂付近の登山道で、唯一残る休憩所が住民有志の手で改修された。・・・とのことです。「休憩所」だったようです。他にも3ヶ所の休憩所がありましたが、今は(前述しましたが)木札のみになっている、と伝えています。

女人堂跡?
元は何だったのでしょうか?新しい女人堂は、これも前回お伝えしましたが、別の所に在ります。

赤門
レンガ造りです。結界門。
何と書いてあったのか、もう読めませんが、これより聖域であることを宣言し、葷酒、女人、入るべからず、というのでしょう。

下山道 道標
「右 奥川田」「左 種穂拝村」とあります。
奥川田という地名は現在も残っています。これは「ふいご温泉」に出る道で、今も多くの人が使っています。
種穂(たなぼ)も、神社、山の名前として残っています。拝村(はいむら)は、種穂山の西麓の地名です。この道は、今はほとんど消えているようです。種穂山にも種穂忌部神社があり、覗岩などの行場が見られるそうです。

行場入口
5分ほど下ると逼割禅定があります。
赤い服装の人は前回(H21)、山頂付近を案内してくださった方でした。またお目にかかれました。4年半ぶりの、うれしい再会でした。

逼割禅定

逼割禅定

西山上 高越大権現
行場入口に戻り、ふたたび登ると、やがて鳥居に出ます。

山門下
登山口からここまで、覗岩や逼割禅定に寄りながら、ゆっくり登りました。3時間半かかっています。標準より1時間以上遅いようです。今日は山川泊まりなので、急ぐ必要はないのですが。

高越寺
変です。妙に寂しい感じがすると思ったら、・・・

前回撮影の写真
鳥居がなくなっていたのです。ご住職がいらっしゃれば、訳を尋ねたのでしたが・・・。というのも、前回、鳥居談議を少ししたからなのですが・・・。

子抱きの狛犬

天狗さま
高越大権現にお仕えしているのでしょう。

心経塔

護摩堂
前回訪ねたときは、護摩堂の裏から善入寺島が望めました。

善入寺島
今回は曇で、まったく眺望が得られませんでしたので、平成21年撮影の写真をご覧ください。

護摩場
奥に役行者が座しておられます。

鐘撞き堂 石段
高越神社に通じる石段です。千年杉を経て、神社石段下に出ます。

千年杉
表示も何もありませんが、天狗さまが棲む「燈明杉」だと教わりました。ただし「燈明杉」と呼ばれる杉は、(後に見ますが)、別にもあります。

高越神社
祭神は忌部氏の祖神、天日鷲命。

高越神社
忌部氏との関わりなどは、前号をご覧ください。

三角点へ
社殿の左側から登ると、道がT字に分かれます。右方向へ社殿を見下ろしながら進むと、三角点です。

一等三角点
1120㍍地点です。登山口が100㍍弱ですから、実質1000㍍強を登ってきたことになります。

大師像
引き返して、T字路を左に登ると大師像があります。
ここは1133㍍地点で、ここが山頂です。

山頂からの眺望
古い写真でご覧ください。脇町、曽江谷川が見えます。左奥の山が(たぶん)、別格20番大滝寺がある大滝山です。川沿いの道は、塩江街道とか曽江谷街道と呼ばれる道です。
高越山と大滝山が石合戦をしたという民話が残っています。両山が投げ合った石が積もって、阿讃山地や四国山地が生まれました。

子安地蔵
大師像の背中の方に回ると、まっすぐ延びた馬の背道があり、その先に子安地蔵塔が在ります。

行場の上
地蔵塔は行場の上に立っているらしく、崖状に落ちています。

小さな道標
子安地蔵塔を回り込んで、やや険しい道を下ると、足元に小さな道標がありました。奥の院まで143㍍、とあります。

窟
(奥の院は後回しにし)、道標から左方向に険しい道を下ると、窟があります。弘法大師の修行の跡と伝わるそうです。

窟
不動明王が祀られています。
この下方にも何かがありそうでしたが、降りるのを止めました。

大きな道標
小さな道標に戻り奥の院方向に進むと、やや広い道に出ました。写真右の道を、私は降りてきたのです。
大きな道標が見え、高越寺←→奥の院、と表示してあります。

鳥居
表示に従い奥の院へ向かうと、木製の鳥居が見えてきました。

奥の院
一番奥の石室に高越大権現が祀られています。

高越大権現

龍王
大きな道標まで戻り、高越寺の方向に進むと龍神窟がありました。

窟

高越寺
道なりに進むと、高越寺境内の奥、休憩所の裏に出てきます。

地蔵菩薩
下山前、すこし余裕があったので、地蔵平(駐車場)方向に進んでみました。
合掌姿の地蔵菩薩に出会いました。

燈明杉
公式には、これが「燈明杉」です。

薬師如来像と十二神将
この崖を「薬師岳」と呼んでいます。

鎖
薬師岳を登る鎖がかかっています。
・・・これより高越寺に戻り、下山します。

帰着
下りは、高越寺山門から1時間20分でした。
高越山は富士山型ですから、上り道はひたすら登り、下り道はひたすら降ります。けっこう膝に「来る」わけです。
歳を考え、急がないよう心掛けましたが、けっこう「来て」しまいました。
続 忌部氏の里

大神宮山
忌部氏の里は大神宮山を挟んで、高越山の全容が見える西側地域と、(大神宮山に阻まれて)見えても頭だけという東側地域に分かれています。
大神宮山の名称は、天照皇大神宮があることから来ているのですが、今、この神社を訪れる人はほとんどいないようです。私も行こうとしましたが、草繁茂で、諦めざるを得ませんでした。

高越山
大神宮山がつくる傾斜に立って振り返ると、高越山が見えます。
が、・・・だんだん見えなくなってきます。

・・・神社
天照皇大神宮の(草繁茂する)参道下にあります。上から降ろしてきたのかもしれません。

淤縢夜末神社本殿
そのすぐ側に、珍しい名前の神社があります。今は祇園神社と呼ばれているようですが、本来の社名は、淤縢夜末神社(おどやま)です。
母・伊弉冉尊を焼き殺して生まれたとして、父・伊弉諾尊に斬り殺されるた火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ)からは幾柱もの神が生まれますが、胸から生まれたのが淤縢山津見神(おどやまつみのかみ)です。この神に由来する社名です。

阿讃山脈
大神宮山の麓から、吉野川を挟んで阿讃山脈が見えます。中央が城王山です。左の、デコポンのヘソのように見えるのが伊笠山。山峰と山峰が入れ違った狭間が讃岐に通じる街道です。大窪寺を打った遍路の多くが、この道を通って切幡寺に向かいます。

大神宮山
東側から見た大神宮山です。こちら側からは、高越山は見えていません。
川は、御祓川です。

山崎忌部神社
さて、長くなりますので、忌部氏に関わる「石」をいくつかご紹介し、今回を終えたいと思います。

さざれ石
実はこの石、神社の駐車場の角にあります。
この駐車場、今でこそ駐車場だが、以前はもっと神社にとって重要な場所だったに違いありません。でないと、さざれ石がここに在る意味が理解できません。
では、ここはどんな場所だったか、(私には)それは分からないのですが・・・。
なお、私は神社を訪ねるとかならず本殿の後を見ることにしているのですが(意外なものを発見することがあります)、忌部神社の本殿裏には、理解しにくい木造家屋(廃屋)があります。駐車場と共に「謎」のスペースです。

青樹杜の立石
「おあきのもり」と読むようです。
ひっそりと、前回ご紹介した玖奴師(くぬし)神社のやや下方にあります。
忌部氏の祖神、忌部神社の祭神、そしてまた高越神社の祭神でもある天日鷲命の廟所ではないか、と言われています。

聖天さんの磨崖仏
忌部神社から400㍍ほど上ったところの聖天寺境内にあります。3体の石仏は、前回、ご紹介しました。

黒岩遺跡
黒岩は忌部神社の故地と考えられています。

真立(またて)石
上古、黒岩忌部神社の鳥居であったと考えられています。

忌部山古墳群
6世紀後半のものと考えられています。240㍍の高所の尾根を占拠し、古墳群を形成しています。

金勝寺古墳石室
麓にある古墳ですが、忌部山式石室です。
なお、金勝寺の若い住職さんにはお世話になりました。

天岩戸神社の神籠石(こうごいし)
(前回にも紹介しましたが)延命水を溜める岩です。麻笥岩(おごけ)とも。

忌部氏の四至石
四至(しいし・しし)とは、所領などの東西南北の境界を言うそうです。つまりは、結界石なのでしょう。

陽石
左の方です。大写しは多少はばかられますので・・・。

立石
忌部氏関連の「立石」です。

山崎八幡神社の矢磨石
部民が矢尻を磨いた石、と考えられています。

忌部氏の矢竹
忌部氏が矢柄を作るのに用いた竹(篠竹)、と伝わっています。

恵比寿神社跡 「忌部の市」跡
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回の更新予定は、2週間後の7月17日です。いよいよ藤井寺から焼山寺道を登ります。
この記事のトップへ 新しいアルバムの目次へ 古いアルバムの目次へ 神々を訪ねて目次へ
















とくに吉野川流域はたびたび洪水の被害もあったでしょうが、大河がもたらす恩恵で古代より文化が発達し、大いに栄えたことは想像できます。 江戸期、徳島藩における藍の奨励で、吉野川をはさんで北岸の撫養街道、南岸には伊予街道が平行に走り、吉野川の水運とともに四国の大動脈が形成されて その最たるものが藍と繭で富を築いた美馬市脇町の富商たちの趣ある街並みで、商家の繁栄ぶりを示す象徴としての「うだつ」は、現在も当時のまま残されているそうです。
これまで二巡しても前だけ向いて歩いたことに気がつきました。 高越寺は根性や性根を鍛え直すには最適な修験道場。善入寺島には遍路道以外にも潜水橋もあったんですね。 ちょっと視点を変えて、回り道するだけで楽しく遍路ができそうで、来年は一生「うだつ」があがらない人生を送った天恢めに、自戒を込めて?撫養街道でもっとも栄えた脇町を訪れたいと願っております。
吉野川の洪水がもたらす自然客土は藍の育成に適していたようなのです。そのため蜂須賀藩は藍の畑が広がる辺りには堤防を築かなかったらしい!のです。むろん、守るべき所、卯建があがる富商の街並みなどは、いわゆる「差別堤防」で護られていたのでしょうが。
堤防が無いと、洪水時の水位が低くなりますから、善入寺島にも人が居住できたのだと思います。ところが一転、大正4,堤防を築くことになります。となると水位が上がりますので、住民は強制移住させられるわけです。善入寺島全島移住の背景を、私はこんな風に推理しています。
「修験」に関心を示す天恢さんが、剣山に「回り道」しないで脇町を訪れることはないでしょう。これは楽しい遍路になりそうですね。このプラン、私もいただきます。
伊予街道のご指摘ありがとうございます。そうです。私は伊予街道を歩いたのでした。
春の吉野川流域は、菜の花が黄色に染めるのどかな田園風景が広がり、お遍路の心を和ませてくれますが、上流から運ばれてきた土砂などが堆積した日本一の川中島である善入寺島は、《今は畑地ばかりで、人は住んでいませんが、大正4までは500戸3000人が住んでいたと言います。小学校もあり、立派な寺社も建っていたそうです。》 と、「その2」の最後にありました。 それが吉野川の改修工事のため全戸強制立ち退きで無人島にされたようで、追われた善入寺島民の失われた歴史やそこでの生活の営みなど、これまた興味が尽きません。
次回ブログは、最初の「遍路ころがし」である焼山寺への道に舞台が移るそうで、この「吉野川物語」が終わってしまうのが残念です。 いつの日か、どこかで復活されることを願っております。
そうなんです。割り算すると1戸当たり6人の、核家族化した今日では考えられないような家族が暮らしていた島なんです。その人達が去って行きました。
ところで不埒な考えが浮かんでいます。(文字通り渡りに船とでも言いますか)、天恢さんの「吉野川物語復活の願い」に乗らせていただいて、次回、もう一度、その去った跡の善入寺島に触れてみようかしらん・・・などと思い始めています。そろそろ山登りもしなければならないのですが・・・。