
なにかと話題を呼んでいる『アマゾン・ドット・コムの光と影』(横田増夫著/情報センター出版局)を読了。いまや業績絶好調のオンライン書店の配送センターにアルバイトとして潜り込み、現場からの視点を盛り込みつつその実態をレポートした“潜入ルポ”である。
一読して驚かされるのは、IT企業の中でも知名度の高さでは群を抜いているアマゾン・ジャパンの徹底した秘密主義である。「もと流通業界紙記者」という経歴をもつ筆者は、それゆえ、アマゾン・ジャパンという会社の現場レポートに執念を燃やしたようなのだが、そもそも、私のような“本の虫”の消費スタイルを激変させた“身近な存在”である会社の実態が、「なんかの秘密結社なのか?!」と勘ぐりたくなるくらい分厚い謎のベールに包まれている、という事実に驚かされる。
ちなみに、IT企業の常として「情報を明かさない」ウラには、外野が想像しているよりもお粗末な実態を隠す……という思惑が潜んでいることが多い(ような気がする・笑)が、この会社の場合、どうも実情は違うようで、「周囲が考えている以上のレベルに達した実力」を、さまざまな意味で“マークされない”ようにするため、ひた隠しにしている……という印象が強いようだ。そうした経緯は、かの悪名高き“取次会社”(出版関係の仕事をしたことのある人間なら、みなその恐ろしさが身に染み付いているハズ)でさえ、数をバックにした同社の実力の前に、いわば「軍門に下った」格好になっている(らしい)実態からも読み取ることができる。
で、まさに“飛ぶ鳥を落とす勢い”の同社を支えている配送センターの労働の実態とは? これがまぁ、「さむい」の一言に尽きる砂漠のような職場なのだという。アルバイトばかりの現場は「1分間に3冊ピックアップ」のノルマにがんじがらめにされ、そこには「アマゾンで本を買ったことのある人間」など、1人もいないんだとか……。極限までマニュアル化された単純労働の繰り返しに、筆者自身も鎌田慧の名著『自動車絶望工場』を引き合いに出しつつ、「希望の存在する職場にこそ、絶望が存在する。ここには、なにもない」と喝破するに至る。読んでいる側が「IT化を核とするニューエコノミーって、本当に人を幸せにするのか?」と思わずにいられなくなる、まったく救いようのない過酷な現実が、そこにある。
さらに事態を複雑にしているのは、筆者自身が「アマゾン配送センターでの仕事を憎悪」しつつ、「アマゾンのサイトでの買い物にたまらない魅力を見出し、ハマっていく」過程だ。当初は、アマゾンの仕組みを実体験する目的でアマゾンで買い物していた筆者が、その魔性のような利便性の魅力に絡め取られ、ヘビーユーザーになっていく……。おそらく、問題の本質は、ここにこそある。
被害者と加害者が溶け合い、混ざりあって、もはや何がなんだかわからない状態。それでも、現実社会の歯車は回転を続け、事態はどんどん進展していく。そして、こういった感想をblogに書き込むという図式そのものが、おそらくは、ITだとかニューエコノミーだとか、そういった波に飲み込まれているということ……。ボクたちは、そういう時代に生きている。
……な~んてことを、たまには考えてみるのも面白いのかもね、と思った休日の午後でありました。ちなみに、この本を私は(たまたま)リアル書店で購入しましたが、けっこう売れてるみたいです。おそらく、千葉県は市川塩浜にあるというアマゾン・ジャパンの配送センターでは、今日も大勢のアルバイトたちが、この本をピックアップし、梱包し、発送しているのでしょう。果たして彼ら自身の目に、この本がどのように映っているのか……ちょっと質問してみたい気がします。
一読して驚かされるのは、IT企業の中でも知名度の高さでは群を抜いているアマゾン・ジャパンの徹底した秘密主義である。「もと流通業界紙記者」という経歴をもつ筆者は、それゆえ、アマゾン・ジャパンという会社の現場レポートに執念を燃やしたようなのだが、そもそも、私のような“本の虫”の消費スタイルを激変させた“身近な存在”である会社の実態が、「なんかの秘密結社なのか?!」と勘ぐりたくなるくらい分厚い謎のベールに包まれている、という事実に驚かされる。
ちなみに、IT企業の常として「情報を明かさない」ウラには、外野が想像しているよりもお粗末な実態を隠す……という思惑が潜んでいることが多い(ような気がする・笑)が、この会社の場合、どうも実情は違うようで、「周囲が考えている以上のレベルに達した実力」を、さまざまな意味で“マークされない”ようにするため、ひた隠しにしている……という印象が強いようだ。そうした経緯は、かの悪名高き“取次会社”(出版関係の仕事をしたことのある人間なら、みなその恐ろしさが身に染み付いているハズ)でさえ、数をバックにした同社の実力の前に、いわば「軍門に下った」格好になっている(らしい)実態からも読み取ることができる。
で、まさに“飛ぶ鳥を落とす勢い”の同社を支えている配送センターの労働の実態とは? これがまぁ、「さむい」の一言に尽きる砂漠のような職場なのだという。アルバイトばかりの現場は「1分間に3冊ピックアップ」のノルマにがんじがらめにされ、そこには「アマゾンで本を買ったことのある人間」など、1人もいないんだとか……。極限までマニュアル化された単純労働の繰り返しに、筆者自身も鎌田慧の名著『自動車絶望工場』を引き合いに出しつつ、「希望の存在する職場にこそ、絶望が存在する。ここには、なにもない」と喝破するに至る。読んでいる側が「IT化を核とするニューエコノミーって、本当に人を幸せにするのか?」と思わずにいられなくなる、まったく救いようのない過酷な現実が、そこにある。
さらに事態を複雑にしているのは、筆者自身が「アマゾン配送センターでの仕事を憎悪」しつつ、「アマゾンのサイトでの買い物にたまらない魅力を見出し、ハマっていく」過程だ。当初は、アマゾンの仕組みを実体験する目的でアマゾンで買い物していた筆者が、その魔性のような利便性の魅力に絡め取られ、ヘビーユーザーになっていく……。おそらく、問題の本質は、ここにこそある。
被害者と加害者が溶け合い、混ざりあって、もはや何がなんだかわからない状態。それでも、現実社会の歯車は回転を続け、事態はどんどん進展していく。そして、こういった感想をblogに書き込むという図式そのものが、おそらくは、ITだとかニューエコノミーだとか、そういった波に飲み込まれているということ……。ボクたちは、そういう時代に生きている。
……な~んてことを、たまには考えてみるのも面白いのかもね、と思った休日の午後でありました。ちなみに、この本を私は(たまたま)リアル書店で購入しましたが、けっこう売れてるみたいです。おそらく、千葉県は市川塩浜にあるというアマゾン・ジャパンの配送センターでは、今日も大勢のアルバイトたちが、この本をピックアップし、梱包し、発送しているのでしょう。果たして彼ら自身の目に、この本がどのように映っているのか……ちょっと質問してみたい気がします。











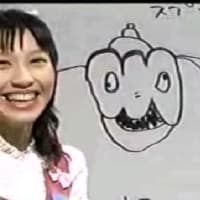




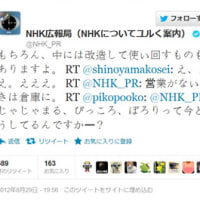










「アマゾン・ドット・コムの光と影」について、1〜2週間程前のA新聞で取り上げられていました。著者の方は、現在、ご家族とパリに住んでおられるとか…(ど〜でもいい話ですが)。
“被害者と加害者が溶け合い、混ざりあって…”の件、いいですね。言わんとされていることが理解できます。
実はまだ読んでいないのですが、読んでみようかなぁ…もちろん、アマゾン・ドット・コムで注文して(笑)
その後も、なんとか続けてますよ~(笑)。
『アマゾン~』読もうかな、とのこと。
こういうとき、リアル知り合い同士だったら
「今度会うとき、もってくよ!」で済むのに、
このあたりが“デジタルな悲しみ”と言いますか……。
でも、ご一読をオススメします!
この本の筆者って、ルポの名著『自動車絶望工場』とかを引き合いに出しつつも、決して、ありがちな
“左寄りのスタンス”からのレポートに陥らない、
ある種の淡々とした報告に徹していて、
そこに、すごい好感が持てるんです。
「批判してやれ」「叩いてやれ」ってのではなく、
「好奇心のおもむくまま、覗いてやれ」って感じです。
そうしたスタンスの人間にさえ、一種の
“薄気味悪さ”を感じさせてしまう現実、
そして、その現実が、あまり知られないまま、
着々と地歩を固めつつあるという事実……。
いろんな意味で、深い一冊です。
でも、アマゾンでの買い物って、
便利ですよね~、たしかに(笑)。
最近、あまり読んでいなかった泥くさいルポルタージュで、結構楽しめました。
僕もAmazonは好きで良く利用しているのですが、その「仕掛け」にまで深く思いを巡らせることはなかったですね。この本読むまでは。まぁ、その仕掛けにいくら問題があろうとも、やっぱり利用者にとって「便利」で「オトク」なのは変わらないわけで、やっぱり使い続けてしまう自分がいるのですが。
たとえ「仕掛けに問題があった」としても、
そのことが「便利なシステムの利用を取りやめる」
理由にはならない(なりえない)。
仮に、今回の事例を契機に
「アマゾン不買!」を叫ぶ人がいるとしたら、
そういった単純思考そのものが、
従来の“左巻き”運動がもつ
ある種の限界を示しているのだってことを、
想起するべきなのかも……。
それどころか、いまのご時世、
アマゾンでバイトしてる人の中からは
「仕事ないより、マシ!」って声すら
聞こえてくるのかもしれない。
でも、こういった形で運営されてる職場が
世の中にあるということ。そして、
おそらくは我々だって、そうした
システムの中に着々と組み込まれつつあること。
で、「いったいどうしたらいいんだ?!」って
ところで、思考停止しておる、と(笑)。