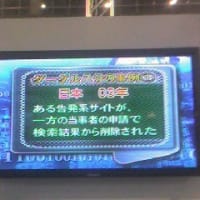本題に入る前に。柏崎刈羽原発では東電の狂気が進行している。
柏崎刈羽原発1号機、原子炉から水があふれていた
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/b4e56c9ed06aa05e93570b4e15a19a66
保坂議員は見た~社民党第3次原発調査団が柏崎刈羽原発の損壊+損壊隠しを発見!
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/8be811189fc7be03f039932fb5e6ce58
東電のこういった補修とも点検ともつかぬ説明のない工事の数々が「隠蔽」でなくてなんだというのだ。ろくな検証もせず、IAEA到着前の化粧直しで突貫工事をしたあげく、再稼動まで持っていくつもりか。それがどれだけ危険な行為か、本人たちは「承知しているつもり」なのだろう…。
参院選で惨敗した社民党が、まともに野党として仕事ができているのが口惜しい。私は過去のわだかまりがあって無所属に投票したが…。
本題に入ろう。
社民党内で、執筆というものを知っている人間がそれなりに居るのなら、今のようにブログでの報告も大切だが、ネットを含めたマスメディアを通じてより多くの人に訴えるべく「報道発表資料(プレスリリース)」の作成と公式サイトでの掲載に力を入れて欲しいものだ。
マスメディアは今回、柏崎刈羽原発の報道をする際、おおむね2種類の情報源に頼っていた。一つは、ご存知の記者会見。まぬけ面の記者が雁首そろえて東電のお題目を拝聴する場所。もう一つは記者クラブに配布されたり、Webサイトに掲載されるプレスリリースだ。
プレスリリースは、マスメディアに流したい情報をまとめ、適当に編集すればそのまま記事になるような文章と画像のセットだ。いまや企業や官庁の広報担当はこれをどのくらいうまく作れるかが腕の見せ所となっている。
特にWebサイトに載ったプレスリリースは、マスメディアにとって最も使いやすい資料だ。なにせ自分で取材する手間もメモを作る手間もなく、文章に起す手間もパソコンで打ち込む手間もなく、いわば便利なレトルトの「記事のモト」で、これが今のマスメディアの速報体制と、取材の手がかりの中心になっている。
増して記者クラブに入れないブロガーや、livedoorニュース(というと脊髄反射で拒否反応が出そうだが)のような新興ネットメディアにとっては必須のネタモトだ。
「そんなものに頼るとはなんとなさけない記者たちよ」と嘆くより、プレスリリースを通じて「敷居が高い」政党の情報源をマスメディアに使いやすくする方が得策だ。
すでに経産省と東電は優れたプレスリリースの発表体制を構築している。
http://www.meti.go.jp/press/
http://www.tepco.co.jp/tepconews/
こうやってWebサイトに公開しておけば、マスメディアの側はRSSリーダーなどの巡回ソフトを利用して情報を収集し、すばやく記事にする。速報ではあまり自主規制は入らないし、印刷した資料を記者の手に押し込むよりも受け入れられやすい。なによりも記者の側は公開された資料をもとに作成しているという安心感があるため、報道までの敷居はかなり低くなる。
そして、いったんどこかに報道されてしまえば、マスメディアの悲しいさがで、ほかの媒体も自主規制をかなぐりすてて後追いせざるを得ない。規制のゆるいネットメディアに先行報道させられれば、出し抜かれるのに耐えられない既存メディアもすぐ食いつく。
米国ではこうしたWebサイトのプレスリリースを専門に集め、有料で掲載する媒体としてPR Newswireが成長し、日本でも
News2u
日経プレスリリース
共同通信PRワイヤー
@press
といった試みが始まっている。
こういう媒体には、新製品を売りたい企業だけでなく、政府系や業界団体系の非営利法人も情報を出稿している。非政府系や政党系の非営利法人はほとんどないが、環境や災害問題といったニュートラルな問題なら入り込む余地はある。
プレスリリースが選ばれるのに大切なのは、(扇情的な)ニュース価値のある情報を、主義主張はなるたけ裏に退かせ、事実を正確に、客観的に、淡々と、分かりやすく書くことだ。そう。つまり愚鈍な記者たちのために、広報担当たちが「ジャーナリスト」の役割を担わねばならない。
当面は政党のWebサイトで報道発表資料を整備すること(あとから議員たちも自由に利用できるように正確で慎重な内容で)が第一だが、いずれは「開かれた記者クラブ」とでもいうべきWebサイトを作って、各政党がそれぞれの調査の平明なレポートを出せるようにするのが望ましい。やがて、ネタを求める記者だけでなく、情報を求める大衆の興味をも引けるかもしれない。
「調査」だけでなく「公表」にも、議会中継や講演会、パンフレット以外の手法が必要とされている。それはブログだけにとどまらないはずだ。
柏崎刈羽原発1号機、原子炉から水があふれていた
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/b4e56c9ed06aa05e93570b4e15a19a66
保坂議員は見た~社民党第3次原発調査団が柏崎刈羽原発の損壊+損壊隠しを発見!
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/8be811189fc7be03f039932fb5e6ce58
東電のこういった補修とも点検ともつかぬ説明のない工事の数々が「隠蔽」でなくてなんだというのだ。ろくな検証もせず、IAEA到着前の化粧直しで突貫工事をしたあげく、再稼動まで持っていくつもりか。それがどれだけ危険な行為か、本人たちは「承知しているつもり」なのだろう…。
参院選で惨敗した社民党が、まともに野党として仕事ができているのが口惜しい。私は過去のわだかまりがあって無所属に投票したが…。
本題に入ろう。
社民党内で、執筆というものを知っている人間がそれなりに居るのなら、今のようにブログでの報告も大切だが、ネットを含めたマスメディアを通じてより多くの人に訴えるべく「報道発表資料(プレスリリース)」の作成と公式サイトでの掲載に力を入れて欲しいものだ。
マスメディアは今回、柏崎刈羽原発の報道をする際、おおむね2種類の情報源に頼っていた。一つは、ご存知の記者会見。まぬけ面の記者が雁首そろえて東電のお題目を拝聴する場所。もう一つは記者クラブに配布されたり、Webサイトに掲載されるプレスリリースだ。
プレスリリースは、マスメディアに流したい情報をまとめ、適当に編集すればそのまま記事になるような文章と画像のセットだ。いまや企業や官庁の広報担当はこれをどのくらいうまく作れるかが腕の見せ所となっている。
特にWebサイトに載ったプレスリリースは、マスメディアにとって最も使いやすい資料だ。なにせ自分で取材する手間もメモを作る手間もなく、文章に起す手間もパソコンで打ち込む手間もなく、いわば便利なレトルトの「記事のモト」で、これが今のマスメディアの速報体制と、取材の手がかりの中心になっている。
増して記者クラブに入れないブロガーや、livedoorニュース(というと脊髄反射で拒否反応が出そうだが)のような新興ネットメディアにとっては必須のネタモトだ。
「そんなものに頼るとはなんとなさけない記者たちよ」と嘆くより、プレスリリースを通じて「敷居が高い」政党の情報源をマスメディアに使いやすくする方が得策だ。
すでに経産省と東電は優れたプレスリリースの発表体制を構築している。
http://www.meti.go.jp/press/
http://www.tepco.co.jp/tepconews/
こうやってWebサイトに公開しておけば、マスメディアの側はRSSリーダーなどの巡回ソフトを利用して情報を収集し、すばやく記事にする。速報ではあまり自主規制は入らないし、印刷した資料を記者の手に押し込むよりも受け入れられやすい。なによりも記者の側は公開された資料をもとに作成しているという安心感があるため、報道までの敷居はかなり低くなる。
そして、いったんどこかに報道されてしまえば、マスメディアの悲しいさがで、ほかの媒体も自主規制をかなぐりすてて後追いせざるを得ない。規制のゆるいネットメディアに先行報道させられれば、出し抜かれるのに耐えられない既存メディアもすぐ食いつく。
米国ではこうしたWebサイトのプレスリリースを専門に集め、有料で掲載する媒体としてPR Newswireが成長し、日本でも
News2u
日経プレスリリース
共同通信PRワイヤー
@press
といった試みが始まっている。
こういう媒体には、新製品を売りたい企業だけでなく、政府系や業界団体系の非営利法人も情報を出稿している。非政府系や政党系の非営利法人はほとんどないが、環境や災害問題といったニュートラルな問題なら入り込む余地はある。
プレスリリースが選ばれるのに大切なのは、(扇情的な)ニュース価値のある情報を、主義主張はなるたけ裏に退かせ、事実を正確に、客観的に、淡々と、分かりやすく書くことだ。そう。つまり愚鈍な記者たちのために、広報担当たちが「ジャーナリスト」の役割を担わねばならない。
当面は政党のWebサイトで報道発表資料を整備すること(あとから議員たちも自由に利用できるように正確で慎重な内容で)が第一だが、いずれは「開かれた記者クラブ」とでもいうべきWebサイトを作って、各政党がそれぞれの調査の平明なレポートを出せるようにするのが望ましい。やがて、ネタを求める記者だけでなく、情報を求める大衆の興味をも引けるかもしれない。
「調査」だけでなく「公表」にも、議会中継や講演会、パンフレット以外の手法が必要とされている。それはブログだけにとどまらないはずだ。