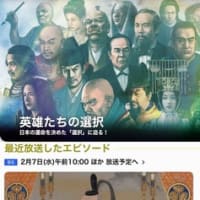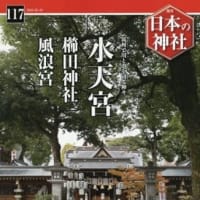要塞都市の完成は
『終わりの始まり』?(c)20世紀少年
福岡城下
みなさん、こんばんは。
ここのところ、ご無沙汰してしまいました。
今週のミステリーハンター・Gです。
福岡城の概要については前回、加藤キヨマサさんがレポートしてくれた通り。
黒田如水・長政父子を祀る光雲神社にある福岡城の説明では「天守閣もなく(これが書かれた当時は天守閣はなかったというのが定説だったのでしょう)城というより城主をとりまく重臣クラスの団地と呼ぶにふさわしかった」と評してるのが笑えます。
そういう訳で(どういう訳だか)、今回は要塞都市としての福岡城下を見てみましょう。
 Googleマップへ
Googleマップへ福岡城の堀:Googleマップに当時の堀をざっくり重ねたもの
※参照「史跡福岡城」パンフレット(福岡市教育委員会文化財整備課)
まずは堀。
いちお、“内堀”としときましょう。
当時の堀は今より幅があって、西側は草香江と呼ばれる入り江の入口を塞いで底をさらって大堀としていました。
東側は、今の大名、天神をぶち抜いて、西中洲の薬院新川のところまで中堀(紺屋町堀)、肥前堀という堀が続いてました。
堀は城を囲むものとばかり思ってましたが、中堀、肥前堀はただ東に延びて南北を分断しているだけ。
いったいどういう戦略的意図があったんでしょう。
 | 明治通りのお堀端の歩道にある怪しげな地下への入口。 |
 | 地下にはお堀の石垣が。外側の石垣なので、お城の方を向いている。緑がかっているのは水に浸かっていたところなのだとか。つまり、堀はもともとここまであったということで、明治43年に路面電車を敷設したときに埋め立てられて、後の地下鉄工事の際に発見されたそうな。 |
 | 大堀の跡を、周囲を埋め立ててできた大濠公園。1926(大正15)年、日比谷公園などを手がけた“日本公園の父”こと東大教授の本多静六とかいう人が西公園を訪れた際に大堀跡の沼地を見つけ、こここそ公園にすべきだとして、弟子の永見健一(後の九大教授)が中国の西湖をモデルに設計。2年後に予定されていた「東亜勧業大博覧会」の会場にするとして公園整備が実現したそうな。 |
 | 大濠公園の中の島に設けられている浮見堂。かつて東公園にあり、第2次大戦で閉鎖された動物園のオットセイの池にあったものを移設したもの。その筋の人によると、なかなか強力なパワースポットらしい。僕はその手のものは全然感じないんですけどね。 |
 | 天神地下街の石積みの広場。このあたりがかつての肥前堀のあった場所に当たるということで、石垣風のデザインになったそうな。肥前堀は埋め立てられて、1910(明治43)年の九州沖縄八県連合共進会(産業博覧会)の会場となった。ちなみに、この共進会にあわせて路面電車も整備され、それまで熊本、長崎、鹿児島にリードされていた福岡が九州の中心都市となるきっかけになったと言われている。 |
CMのあとは、“外堀”と城下町の話です。
チャラチャチャ~
<CM>

福岡城は、キヨマサさんもご指摘の通り、東は那珂川、西は樋井川を“外堀”に見立てているといわれています。
また、福岡は京都に次いでお寺の多い都市らしいですが、これもこの“外堀”と海沿いにお寺を集中させ、いざというときの防衛拠点にしたためと言われます。
実際、マップにお寺を点打ちすると、こんな感じになります。
 Googleマップへ
Googleマップへ 福岡・博多の寺社:単純にGoogleマップにあるお寺や大きな神社を点打ちしたもの。
これで見ると、確かに樋井川から当時の海岸線あたりにはお寺が集中しています。
東はもともと聖福寺の寺中町や寺町があった御笠川(石堂川)沿いが特に集中しています。
ざっくり調べてみると、城下に移転してきたお寺は、だいたい1640年前後に移転したものが多いようです。
ということは、お寺による防衛ライン構想は、如水でも長政でもなく、第二代藩主・忠之によるものだったということでしょうか。
それとも長政からそういうふうにしろと生前に指示があっていたのでしょうか。
1632年の黒田騒動(家臣が忠之を謀反の疑いありと幕府に訴えたお家騒動)の後なだけに、ひょっとしたら一方で東照宮を造って恭順姿勢を示しつつ、裏では一戦構える準備もしていたのかもしれません。
東の“外堀”が那珂川というのは、ここに桝形門という堅牢な門を設け、福岡を商人の町・博多と明確に分けたことによるものでしょう。
ここでの出入りは厳しく制限されたため、わざわざ荒津あたりから船を出して博多や中洲にでかけていた藩士もいたらしいです。


金龍寺。創建の地は糸島の高祖。一時荒津山(荒戸山)にあったが、東照宮建設のため1647年に現在地に移された。樋井川側の備えにしたんだと思う。貝原益軒(江戸時代前~中期の学者。「筑前国続風土記」『養生訓』などを著す)の墓がある。ちなみに東照宮は明治になるとつぶされて、跡に前述の光雲神社が造られた。


1671年に現在地に移された浄萬寺。樋井川側の備えにしたんだと思う。創建の地は春吉あたり。亀井南冥(江戸時代中~後期の学者。西学問所・甘棠館の学長。志賀島で発見された金印を後漢の光武帝が奴国王に贈ったものと比定した人)一族の墓がある。


大圓寺。創建の地は西入部。一時荒津山にあったが、東照宮建設のため1647年に現在地に移された。海側の備えにしたんだと思う。本堂の上(屋上)には五重塔が、中には大仏(高さ4.85mの木造坐像)ある。


浄念寺。創建時期など未確認。周囲のいくつかのお寺とともに城の北側にあり、海側の備えにしたんだと思う。長政と決別した後藤又兵衛基次の身代わりになって処刑されたといわれる空誉上人を祀る空誉堂がある。ちなみに又兵衛はその後浪人となり、大坂の陣に参戦して戦死した。


安国寺。1600年(江戸時代初期)、黒田家の筑前入りに伴って豊前中津から現在地に移転。この時期はまだ福岡城構想はなかったと思うが、周囲にもお寺が集中しており、結果的に海側または那珂川側の備えにしたんだと思う。『飴買い幽霊』伝説にちなむ墓あり。
このほか、今泉や、渡辺通と春吉の間のその名も寺町通りにもお寺が集中しているところがあり、南側の備えにしたものだと思われます(それにしても南の防御は薄いような気がするけど)。


現在の西中島橋。歩道にある石のベンチ(?)には西中島橋と桝形門の説明と、仙さんの『博多図並びに賛』が焼かれた陶板が埋め込まれている。この橋の西側に、高さ10mの石垣と櫓門で造られた桝形門があった。これが福岡城の実質の大手門だったと言われている。堅牢な桝形門に対し、かつての西中島門は敵が攻めて来たらすぐに落とせるように、木造の貧弱な造りだったらしい。
さて、福岡の城下町といえば、まず思い浮かぶのは大名じゃないでしょうか。
大名といっても、普通に考えれば大名は黒田家そのものなんですが、ここでいう大名とは黒田家の上級家臣ということですね。
昔は大名と言えば今の大名2丁目あたりで、1丁目の方はそれこそ紺屋町(こうやまち)や薬院町(やくいまち。現在の薬院とはえらく場所が違う)など。
紺屋町のジョーキュー醤油の裏には肥前堀が通っていたようです。
空襲のなかった田舎の城下町のように武家屋敷が残ってるなんてことはありませんが、かつての街路は結構残っています。
大名にT字路やクランクがやたらと多いのはそのためで、これは敵の視界を妨げたり、いざというときには片側を板塀などで塞いで単なる直角な曲がり角に見せかけて敵を追い込むなど、城下町にありがちな工夫なんですね。
 | 西鉄グランドホテル前のシケイン。今でこそだいぶ滑らかなS字になっているが、かつてはほぼクランクだったらしい。 |
 | ジョーキュー醤油そばのクランク。今は角地が駐車場になってしまって、全然目隠しになってません。 |
さらに、奥の手としては、那珂川上流の老司の堰を決壊させて、低地を水浸しにするということも想定されていたらしいです。
 | 現在の老司の堰。当時の堰(なんちゃって)はどんなものだったのか…。 |
ここまでして要塞都市を築き上げた黒田藩でしたが、せっかく貿易拠点・博多を手に入れたにも関わらず、幕府の鎖国政策によっておいしいところは長崎(天領なので=幕府)にもっていかれ、福岡・博多は急速に日本史の檜舞台から引きずり降ろされ、郷土史レベルの街になっていきます。
以後、二度と表舞台に立つことはありませんでしたが(たぶん)、実は裏の舞台では日本をひっくり返す大立ち回りがありました。
その件については僕もこれまであまり気にしてなかったので、今回でこの『福岡おもしろ~』本編は終わりにしようと思ってたのですが、とある先生の話を聞いて、これをやらねば終われないことに気づきました。
最終的には大立ち回りの甲斐なく、おいしいところはよその人にもっていかれちゃうんですが(だから裏舞台)、次回はそのもっていっちゃった張本人のレポートでお届けします。
レポーターは…、サカモトリョーマさんです!
福岡城跡堀石垣
 大きな地図で見る
大きな地図で見る大濠公園(浮見堂)
 大きな地図で見る
大きな地図で見る天神地下街 石積みの広場
 大きな地図で見る
大きな地図で見る金龍寺
 大きな地図で見る
大きな地図で見る 浄満寺
 大きな地図で見る
大きな地図で見る 大圓寺
 大きな地図で見る
大きな地図で見る 浄念寺
 大きな地図で見る
大きな地図で見る 安国寺
 大きな地図で見る
大きな地図で見る 西中島橋
 大きな地図で見る
大きな地図で見る西鉄グランドホテル前シケイン
 大きな地図で見る
大きな地図で見る紺屋町クランク
 大きな地図で見る
大きな地図で見る(つづく)
←ひとつ前へ--CONTENTSへ