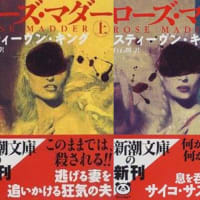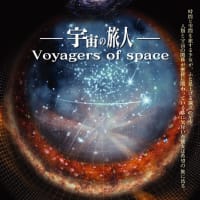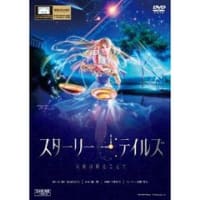地球観測衛星による東日本大震災をはじめとした利用事例の紹介」
開催日時:2011年6月20日(月) 18時半~ 約2時間
会場:府大中之島サテライト 2階ホール
主催:Kansai Space Initiative:特定非営利活動法人関西宇宙イニシアティブ
講演者:石館和奈氏((財)リモートセンシング技術センター 利用推進部)
■無色の色
確かに。
予算がついたからと言って、それで無条件に技術開発が進むというもの
でもないだろう。
原子力に対して、実際に研究開発に携わる科学者・技術者の大半がどの
ような思いを抱いていたかは、先述した通りである。
それでも。
科学技術そのものに、色や匂いがついている訳ではない。
潤沢な研究予算を与えられ、(純粋に科学的な意味で)面白く遣り甲斐の
あるテーマが与えられた研究者が、一体どれほど抗えるものなのか?
無論。
そこに個々人の差はあるが、しかし。
以降、日本の原子力研究が急速に伸長したことが、如実にその答えを
物語っているのではないか。
そして。
生み出された電気に、色が付いている訳でもない。
市井の人々にとって、原子力に対する嫌悪感はあっても、それと自分の
頭上に明かりをともしてくれている電気とをリンクさせて考えるという
ことは、想像の埒外であったろう。
かつて。
小平は、有名な猫論を唱えたが。
「不管猫白猫,捉到老鼠就是好猫」
~白い猫でも、黒い猫でもいい。
ネズミを捕まえることが出来る猫がいい猫だ~
科学者は確信犯的に、人々は意識せずして。
原子力に対して、猫論に沿った立場を取ることとなった。
かくして。
日本人の原子力アレルギーは、あくまで概念的なものとならざるを
得なかったのである。
しかし、誰であれそのことを問責できる道理もない。
終戦後の混乱期に、自らの職業理念に則り闇物資を拒否し続けた末に、
栄養失調により死去した山口義忠裁判官達の悲劇が物語るように。
人は誰も、霞を食べて生きていく訳にはいかないのだから。
産業界の、そして国民の。
生活レベルの向上を実現する手段としての電力への渇望の方が、原子力に
対する忌諱の徹底よりも、より具体的な命題として位置づけられたことは
当然の帰結であったといえるだろう。
このように、原子力については。
日本の(引いてはアメリカの)国家としての意向が明示され、最初期に
おけるアメリカからの基礎技術の移転と研究予算の手当てが為されたこと
により、研究開発の進展とそれに伴う産業の成長が国土の復興と歩調を
合わせるように伸長していくこととなった。
その状況を示すデータを紹介しよう。
日本の名目GDPの増加と、原子力関連の国家予算、ならびに原子力産業の
売上高の推移をまとめたものである(クリックすると拡大します)。

(データ出典:原子力産業実態調査報告』(日本原子力産業協会 年刊))
このグラフを見れば。
原子力産業の売上高が、ほぼ日本の名目GDPと同じベクトルで伸長して
きていることがよく分かる。
しかも、その伸び率は、原子力関連の国家予算のそれを大幅に凌駕して
いる。
特に1968年(昭和43年)以降は常に、原子力産業に投じられた国家予算
よりも原子力産業の売上高が上回っており、その乖離幅は最大で5.6倍
(1986年(昭和61年))にも及んでいることが良く示されている。
2000年(平成12年)までの平均を取れば、約2.9倍である。
これは、原子力産業が戦後から高度経済成長期を通じて、その市場の
裾野をしっかりと拡大形成してきたことを意味する。
このようにして。
原子力は、日本の産業分野の一角を担っていったのである。
一方。
宇宙技術は、どのような戦後史を辿ったのか。
ともに、20世紀の代表的な先端科学技術でありながら。
戦後期における両者の立ち位置には、大きな相違点があった。
それは。
先にも挙げたとおり、原子力が生活インフラを支える電力という必然性
をもって日本の社会に浸透していったことに対して。
日本にとって。
宇宙開発は、そうした属性を(少なくとも戦後期においては)持ち得な
かったということである。
戦後の冷戦期只中にあって、米ソは。
宇宙開発を国家の威信を誇示するフラッグシップとして位置づけ、
それゆえに世界初の栄誉と、制空権ならぬ制宙権を支配しようとして
鬩(せめ)ぎ合った。
アメリカの国際政治学者ジョセフ・ナイが命名し、北海道大学公共政策
大学院准教授の鈴木一人(@KS_1013)が、その著書「宇宙開発と国際政治」
岩波書店刊で紹介した”ハードパワー”を希求したのである。
それに対し、ヨーロッパでは。
政治学上では、米ソ両大国の間にあって自らのカラーをどう位置づける
かを常に模索する立場にあり。
かつ、地政学上では。
複雑に入り組んだ域内の国境線がもたらす過去からの因縁の歴史を、その
DNAに刻みこみながらも、なお。
同じ自由主義陣営でありながら、アメリカに技術隷属することを拒否し、
既にアメリカが先行していた衛星通信にヨーロッパとしての楔(くさび)を
打ち込むべく、通信衛星シンフォニーを1967年(昭和42年)にフランスが
打ち上げたことを皮切りに、一つの欧州を具現化するための宇宙開発の
商業化を必然的に進めていった。
鈴木一人が、”社会インフラ”として定義した宇宙開発の力の一つの
具現化の形である。
いずれも、国家戦略として宇宙開発をどう位置づけるかを明確に定義し、
それに則った研究開発の深化を進めていったものであるが。
それらと異なり、日本の宇宙開発は国家的な戦略視点ではなく、純粋に
技術開発視点からスタートした。
それは、先の敗戦によって、ハードパワーとしての国家の意思の発露を
放棄させられ、かつ国土面積が人口と比して狭隘という日本の地理上の
特性から通信衛星等の必要性が乏しく、社会インフラの構築を宇宙に
求めることがなかった日本ならではの道程であった。
先に紹介した鈴木一人の「宇宙開発と国際政治」は、宇宙開発先進国の
国別開発史を第1部でまとめている。
その各章の副題は、各国の特徴を見事に表現している。
順を追って紹介しよう。
第1章 アメリカ -技術的優位性の追求
第2章 欧州 -政府間協力からの変容
第3章 ロシア -冷戦時代からの遺産の活用
第4章 中国 -大国の証明
第5章 インド -途上国としての戦略
第6章 日本 -技術開発からの出発
この副題に、各国の、なべても日本の宇宙開発の特徴が端的に表現
されている。
そして。
その揺籃期の土台こそが。
故糸川英夫博士の創設した、東京大学宇宙科学研究所(ISAS)であった。
(この稿、続く)
 | 宇宙開発と国際政治 |
| 鈴木一人 | |
| 岩波書店 |
 | ソフト・パワー 21世紀国際政治を制する見えざる力 |
| ジョセフ・ナイ | |
| 日本経済新聞社 |