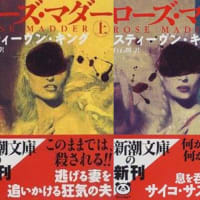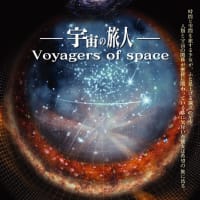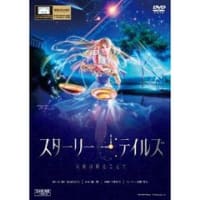※ イオンエンジンスラスタの実物
(TOP画像提供:日経BP)
日時:平成22年7月8日(木) 午後4時~5時
場所:NEC関西支社(大阪市OBP内)
講座タイトル:NECソリューション公開講座 in 関西2010
「『はやぶさ』の帰還、そして新たな旅立ち」
話者:小笠原雅弘(日本電気航空宇宙システム株式会社
宇宙・情報システム事業部)
サブタイトル:
2010年6月13日、深夜。
ウルル・カタジュの上空を二条の流れ星が西から東へ流れた。
一個は途中で爆発を繰り返しながら砂漠の闇に消えていった。
そして小さな輝きだけが残った。
60億Kmもの旅をして「はやぶさ」が届けてくれたものは…
■技術者の矜持(後編)
2009年11月。
イオンエンジンの不調の顕在化を受けて。
JAXA、ならびにエンジンメーカーであり、はやぶさプロジェクトの
プライムメーカーでもあるNECとの間で、その救済方法についての
大激論が為されていた。
このあたりの事情は、NECでイオンエンジン開発を担当されていた
シニアマネージャーの堀内氏が、NECのHPで詳しく振り返って
くれている。
堀内氏は、学生時代からイオンエンジンの研究を続けていた、正に
μ10エンジンにとっては生みの親の一人とも言える存在。
就職するときも、イオンエンジンの開発を続けたいと氏の言葉を聞いた
NECより勧誘を受けて入社したほどに、イオンエンジンにどっぷりと
漬かった人生を送られてきた方である。
一方。
JAXA側の登場人物は、イオンエンジンといえばこの人。國中教授。
この國中教授と堀内氏は、大学の先輩と後輩に当たる。
堀内氏が研究室に入ったときに、國中氏が博士課程の3年ということで
4年先輩にあたるそうな。
大学時代から一緒の対象を研究してきて、それが就職して立場が変わって
からもずっと継続していく。
なんとも、仕事冥利に尽きる関係ではないか。
その両者の絆の深さは。
堀内氏の
「今でも個人的には『國中先生』というより
『國中さん』というほうがしっくりします。」
というご発言に、表されているような気がする。
(※ E-NEWS
「はやぶさ」のイオンエンジン担当・堀内康男・
NECシニアマネジャー(45)インタビュー。 より)
この両者が。
あの、2009年11月に。
はやぶさのイオンエンジンDの停止という事実を前にして、上述のとおり
大激論を行った。
議論の対象は、かの有名なAの中和器とBのイオン源の合体運用の是非。

(※ 図は、JAXA提供)
そうした事態を想定して組み込まれた、祈りのようなダイオード。
とはいえ。
その電磁的な性質から、地上では検証も十全には行えない。
ぶっつけ本番といってもよい、究極のエマージェンシー運用。
既に、ハード的にも随所に金属疲労が出ていたはやぶさのボディが、
その運用に果たして耐えられるのか?
下手をすれば、その起動をトリガーにして、高電圧の負荷により完全に
はやぶさのハードが破壊されることにも為りかねないのだ。
せっかく。
数多の困難を乗り越え、ここまでたどり着いたはやぶさを。
もっと、確実に。
もっと、安全に。
地球へと導ける、そんな手段はないのか?
最後の最後まで、考えつくしたといえるのか?
例えば、推力は低下しているものの、まだ稼動はできるCをだまし
だまし運用すれば。
2010年は無理でも、もう3年後をターゲットにした軌道計算は
出来るのではないか?
Cが3年持たないリスクと、今全損を覚悟で二個一運用をするリスク。
どちらを果たして選ぶべきなのか…?
と、こうした僕のような素人が思いつくようなレベルを遥かに凌駕した
様々な仮説とそれに対する反証が、両者の間では交わされたのだろう。
二個一運用については。
当初は、あまりにもリスクが高いとして堀内氏は反対。
最終的には、國中教授の「やろう!」という判断と、それに対する
堀内氏の同意で実行されたこの起死回生の策が、見事成功裏に終わった
ことは、周知の事実ではある。
一般には、如何にも当初より「こんなこともあろうかと」万全の対策と
して用意され、満を持して登場したような印象で受け止められている
二個一運用も、様々なリスクと裏腹なものであり、その実行は技術者
としての矜持を賭けた真摯な議論の末のものであったことを。
氏の語るエピソードから知ることが出来たことは、大きな喜びだった。
恐らくは。
Cエンジンのみでの運用策とした場合には、更に3年の運用期間を
持たせることは困難だったであろう。
何よりも、エンジン以外のはやぶさ自体のメインメモリにもエラーが
出始めてきていたことを考えると、あの時点では二個一運用が最良
最善の策だったということは、今なら誰にでも言える。
ただ。
2005年のあのイトカワ上空でのトラブルから。
直線距離にして3億1千万Kmの彼方から、ようやく帰ってきつつ
あったはやぶさである。
その運命を、自分たちの決断が決めることになると。
その意思決定は、相当に呻吟したした上での結論だったのだろう。
もちろんそれは、一か八かの破れかぶれなものではなく。
あらゆる可能性を吟味した上で、これが最適という判断の上での
合意だったのだろう。
それでも。
堀内氏としては、この策が成功するかどうかは最後まで半信半疑の
思いだったという。
國中教授にしても、そこは同様で。
この運用が成功し、推力の確認が行えたときに。
「これで最後の正月が越せる」
と思った、と述懐されている。
(JAXA’s No.031より)
もとよりそれは、両氏の技術者としての判断を云々するものでは
断じてない。
自らの。
半生を賭けて開発してきたイオンエンジンだからこそ。
真摯に、あらゆる可能性を踏まえて。
その運用の成功のみを一途に求め続けた技術者達ならではの、判断
であったと思う。
そこに、僕は身震いするほどの感動を覚えたのだった。
(この稿、続く)
(余話として)
氏の講演会にて。
堀内氏は、四つのイオンエンジンに、それぞれ自分の家族の名前の
密かに付けていた、というエピソードも開陳された。
Aがお父さん。Bがおかあさん。CとDが子供たち。
Aは、出立直後に不調となり。
後は、嫁さんと子供が力を合わせてきたけれど。
最後の最後で、お父さんがお母さんと力を合わせることで、帰って
くることができたという落ちは。
あまりにまとまり過ぎて、これまた泣けてくるのだ。
(上記のエピソードは、NECのHPでも堀内氏の談話として
紹介されている)
(TOP画像提供:日経BP)
日時:平成22年7月8日(木) 午後4時~5時
場所:NEC関西支社(大阪市OBP内)
講座タイトル:NECソリューション公開講座 in 関西2010
「『はやぶさ』の帰還、そして新たな旅立ち」
話者:小笠原雅弘(日本電気航空宇宙システム株式会社
宇宙・情報システム事業部)
サブタイトル:
2010年6月13日、深夜。
ウルル・カタジュの上空を二条の流れ星が西から東へ流れた。
一個は途中で爆発を繰り返しながら砂漠の闇に消えていった。
そして小さな輝きだけが残った。
60億Kmもの旅をして「はやぶさ」が届けてくれたものは…
■技術者の矜持(後編)
2009年11月。
イオンエンジンの不調の顕在化を受けて。
JAXA、ならびにエンジンメーカーであり、はやぶさプロジェクトの
プライムメーカーでもあるNECとの間で、その救済方法についての
大激論が為されていた。
このあたりの事情は、NECでイオンエンジン開発を担当されていた
シニアマネージャーの堀内氏が、NECのHPで詳しく振り返って
くれている。
堀内氏は、学生時代からイオンエンジンの研究を続けていた、正に
μ10エンジンにとっては生みの親の一人とも言える存在。
就職するときも、イオンエンジンの開発を続けたいと氏の言葉を聞いた
NECより勧誘を受けて入社したほどに、イオンエンジンにどっぷりと
漬かった人生を送られてきた方である。
一方。
JAXA側の登場人物は、イオンエンジンといえばこの人。國中教授。
この國中教授と堀内氏は、大学の先輩と後輩に当たる。
堀内氏が研究室に入ったときに、國中氏が博士課程の3年ということで
4年先輩にあたるそうな。
大学時代から一緒の対象を研究してきて、それが就職して立場が変わって
からもずっと継続していく。
なんとも、仕事冥利に尽きる関係ではないか。
その両者の絆の深さは。
堀内氏の
「今でも個人的には『國中先生』というより
『國中さん』というほうがしっくりします。」
というご発言に、表されているような気がする。
(※ E-NEWS
「はやぶさ」のイオンエンジン担当・堀内康男・
NECシニアマネジャー(45)インタビュー。 より)
この両者が。
あの、2009年11月に。
はやぶさのイオンエンジンDの停止という事実を前にして、上述のとおり
大激論を行った。
議論の対象は、かの有名なAの中和器とBのイオン源の合体運用の是非。

(※ 図は、JAXA提供)
そうした事態を想定して組み込まれた、祈りのようなダイオード。
とはいえ。
その電磁的な性質から、地上では検証も十全には行えない。
ぶっつけ本番といってもよい、究極のエマージェンシー運用。
既に、ハード的にも随所に金属疲労が出ていたはやぶさのボディが、
その運用に果たして耐えられるのか?
下手をすれば、その起動をトリガーにして、高電圧の負荷により完全に
はやぶさのハードが破壊されることにも為りかねないのだ。
せっかく。
数多の困難を乗り越え、ここまでたどり着いたはやぶさを。
もっと、確実に。
もっと、安全に。
地球へと導ける、そんな手段はないのか?
最後の最後まで、考えつくしたといえるのか?
例えば、推力は低下しているものの、まだ稼動はできるCをだまし
だまし運用すれば。
2010年は無理でも、もう3年後をターゲットにした軌道計算は
出来るのではないか?
Cが3年持たないリスクと、今全損を覚悟で二個一運用をするリスク。
どちらを果たして選ぶべきなのか…?
と、こうした僕のような素人が思いつくようなレベルを遥かに凌駕した
様々な仮説とそれに対する反証が、両者の間では交わされたのだろう。
二個一運用については。
当初は、あまりにもリスクが高いとして堀内氏は反対。
最終的には、國中教授の「やろう!」という判断と、それに対する
堀内氏の同意で実行されたこの起死回生の策が、見事成功裏に終わった
ことは、周知の事実ではある。
一般には、如何にも当初より「こんなこともあろうかと」万全の対策と
して用意され、満を持して登場したような印象で受け止められている
二個一運用も、様々なリスクと裏腹なものであり、その実行は技術者
としての矜持を賭けた真摯な議論の末のものであったことを。
氏の語るエピソードから知ることが出来たことは、大きな喜びだった。
恐らくは。
Cエンジンのみでの運用策とした場合には、更に3年の運用期間を
持たせることは困難だったであろう。
何よりも、エンジン以外のはやぶさ自体のメインメモリにもエラーが
出始めてきていたことを考えると、あの時点では二個一運用が最良
最善の策だったということは、今なら誰にでも言える。
ただ。
2005年のあのイトカワ上空でのトラブルから。
直線距離にして3億1千万Kmの彼方から、ようやく帰ってきつつ
あったはやぶさである。
その運命を、自分たちの決断が決めることになると。
その意思決定は、相当に呻吟したした上での結論だったのだろう。
もちろんそれは、一か八かの破れかぶれなものではなく。
あらゆる可能性を吟味した上で、これが最適という判断の上での
合意だったのだろう。
それでも。
堀内氏としては、この策が成功するかどうかは最後まで半信半疑の
思いだったという。
國中教授にしても、そこは同様で。
この運用が成功し、推力の確認が行えたときに。
「これで最後の正月が越せる」
と思った、と述懐されている。
(JAXA’s No.031より)
もとよりそれは、両氏の技術者としての判断を云々するものでは
断じてない。
自らの。
半生を賭けて開発してきたイオンエンジンだからこそ。
真摯に、あらゆる可能性を踏まえて。
その運用の成功のみを一途に求め続けた技術者達ならではの、判断
であったと思う。
そこに、僕は身震いするほどの感動を覚えたのだった。
(この稿、続く)
(余話として)
氏の講演会にて。
堀内氏は、四つのイオンエンジンに、それぞれ自分の家族の名前の
密かに付けていた、というエピソードも開陳された。
Aがお父さん。Bがおかあさん。CとDが子供たち。
Aは、出立直後に不調となり。
後は、嫁さんと子供が力を合わせてきたけれど。
最後の最後で、お父さんがお母さんと力を合わせることで、帰って
くることができたという落ちは。
あまりにまとまり過ぎて、これまた泣けてくるのだ。
(上記のエピソードは、NECのHPでも堀内氏の談話として
紹介されている)
 | 小惑星探査機 はやぶさ 特別メッキ版 (1/32 スペースクラフト No.SP) 【Amazon.co.jp限定販売】 |
| クリエーター情報なし | |
| 青島文化教材社 |