芦屋市立美術博物館で、「震災から15年」展が始まった。

第1部は、 カメラ・アイ 阪神・淡路大震災「市内の情景」記録写真展
第2部は、 コレクション展3 震災と美術
第2部でとりあげられた作家はデヴィッド・ナッシュ(英1945~)と、中山岩太(1895~1949)・堀尾貞治(1939~)・津高和一(1911~1995)の4人。
1995年1月、芦屋市立美術博物館では、「デイヴィット・ナッシュ展-音威子府(オトイネップ)の森-」が開かれていた。震災直後の、作品が倒れて床に転がった写真が、痛々しい。
私が勝手に「アダムとイブ」と呼んでいる、いつも2階コーナーに立っているチェーンソーで樺の木をくり抜いた作品「内側/外側」は、地震の後、作者から美術館に贈られたものらしい。ナッシュさん、ありがとう。
芦屋市にあった中山岩太のスタジオは全壊し、作品は瓦礫の中に埋没した。そこで、日本で初めて文化庁の後援による文化財レスキュー隊が組織され、瓦礫の中から貴重な昭和初期のガラス乾板が掘り出された。その後の多くのボランティアによる細かい作業によって、ガラス乾板は復元され、昭和初期阪神間モダニズムを代表する写真家のゼラチンシルバープリントの作品を私たちは見ることができる。
地震国であるこの列島の文化財で、今に残っているものは、その多くが、地震の度に、それを救出し復旧しようとした人々の意志が、それを宝物と呼ばせているのかもしれない。
堀尾貞治の、神戸の街のスケッチは、2008年のコレクション展Ⅲ「目撃者」にも出品されていた。震災後の1年間、私がリュック背負って通勤途中横切っていた神戸の街の姿そのもの。ほこりっぽい空気が蘇る。
そして、津高和一である。
芦屋市立美術博物館の目録を見てからずっと、私は、彼の作品が出てくるのを待っていた。
今回の出品は、「月と人と」1948・「風化」1956・「鋭角」1961・「作品」1972・「軌跡」1993の5点。
 「月と人と」1948
「月と人と」1948
~芦屋市立美術博物館収蔵品目録(モノクロ印刷)より
初めて目にした津高の具象画に近い作品。黄色い上弦の月に向かって男が立っている。男の肩に添う女。二人はまるで透明人間。月の光がすべてを見透かしている。やがて月の光が絵の前に立つ私にも届く。私も透明になる。そして元旦の月を思い出す。
絵の前においてあるリーフレットにはこんな津高自身の言葉が載っていた。
「ぼくの逆算する美意識というのは、死を起点にして、そして生きている現在まで逆算してくることなんです。そのことによって、生きていること、存在していることがより鮮明になってくるからです。人間は必ず一度地上から姿を消すのだという事実を確認しての、生きているということを直視することで、ぼくはなんだか自分の絵が描けると思うのです。」(「みづゑ」No825 p70、1973)
「あらゆる事象をのみ込んで、無限に豊かになっていくもの、それは突き詰めていきますと、結局は一本の線になるんですね。世のすべての喧騒も、宇宙への大きな感動も、僕自身の人生も、一本の線の中に入ってしまう。一本の線を引いて、そこに僕のすべてが入ってしまえば、絵はそこで完成する。単純になればなるだけ、絵は一層豊かになる。」(神戸新聞1994年12月25日「会いたかった人」より)
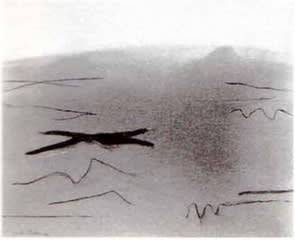 「軌跡」1993 ~収蔵品目録より
「軌跡」1993 ~収蔵品目録より
人が生きた軌跡。一本の線は、どこかから始まり、どこかで途切れる。
この絵の線は、何人かの人の軌跡のようでもあり、砂に潜っては現れる一人の人間の軌跡のようでもある。
父はどんな線を描いたのか。私は今どんな線を描いているのだろう。
西宮に住んでいた画家は、震災の日倒壊した日本家屋の下で、夫人と共に亡くなった。
展覧会では、津高の作品5点の間に、吉野晴朗氏が撮った、震災前の自宅の写真と、震災直後の自宅の写真があった。
震災前の1962~81、津高和一は、「既成の美術館・画廊だけが美術作品を発表する場所だという固定概念に対して、自他共に反省を促すため」に、秋には自宅の庭・アトリエを開放し「対話のための作品展」を開いていた。その時の写真で、庭にはオブジェ作品が数個、人々が集っている。緑の木の前には、カメラに向かってポーズをとっているような、凛々しい大きな黄色いネコさんがいる。
もう一枚の1995年の写真では、完全に木材の瓦礫と化した家屋を背景に、傾いた庭のオブジェ作品の上に、こちらを無邪気に見ている黄色い子猫が、ちょこんと座っているのだった。
このカメラ目線の、フサフサの金色毛色の2匹のネコさんは、親子のようだ。
すぐさっきまで、主のいなくなった庭で、子猫は泣いていたのかもしれない。
残念ながら、津高和一の残した絵に、ネコの絵はないが、絵の中の黄色い線のどれかは、この黄色いネコさんのような気がする。

第1部は、 カメラ・アイ 阪神・淡路大震災「市内の情景」記録写真展
第2部は、 コレクション展3 震災と美術
第2部でとりあげられた作家はデヴィッド・ナッシュ(英1945~)と、中山岩太(1895~1949)・堀尾貞治(1939~)・津高和一(1911~1995)の4人。
1995年1月、芦屋市立美術博物館では、「デイヴィット・ナッシュ展-音威子府(オトイネップ)の森-」が開かれていた。震災直後の、作品が倒れて床に転がった写真が、痛々しい。
私が勝手に「アダムとイブ」と呼んでいる、いつも2階コーナーに立っているチェーンソーで樺の木をくり抜いた作品「内側/外側」は、地震の後、作者から美術館に贈られたものらしい。ナッシュさん、ありがとう。
芦屋市にあった中山岩太のスタジオは全壊し、作品は瓦礫の中に埋没した。そこで、日本で初めて文化庁の後援による文化財レスキュー隊が組織され、瓦礫の中から貴重な昭和初期のガラス乾板が掘り出された。その後の多くのボランティアによる細かい作業によって、ガラス乾板は復元され、昭和初期阪神間モダニズムを代表する写真家のゼラチンシルバープリントの作品を私たちは見ることができる。
地震国であるこの列島の文化財で、今に残っているものは、その多くが、地震の度に、それを救出し復旧しようとした人々の意志が、それを宝物と呼ばせているのかもしれない。
堀尾貞治の、神戸の街のスケッチは、2008年のコレクション展Ⅲ「目撃者」にも出品されていた。震災後の1年間、私がリュック背負って通勤途中横切っていた神戸の街の姿そのもの。ほこりっぽい空気が蘇る。
そして、津高和一である。
芦屋市立美術博物館の目録を見てからずっと、私は、彼の作品が出てくるのを待っていた。
今回の出品は、「月と人と」1948・「風化」1956・「鋭角」1961・「作品」1972・「軌跡」1993の5点。
 「月と人と」1948
「月と人と」1948~芦屋市立美術博物館収蔵品目録(モノクロ印刷)より
初めて目にした津高の具象画に近い作品。黄色い上弦の月に向かって男が立っている。男の肩に添う女。二人はまるで透明人間。月の光がすべてを見透かしている。やがて月の光が絵の前に立つ私にも届く。私も透明になる。そして元旦の月を思い出す。
絵の前においてあるリーフレットにはこんな津高自身の言葉が載っていた。
「ぼくの逆算する美意識というのは、死を起点にして、そして生きている現在まで逆算してくることなんです。そのことによって、生きていること、存在していることがより鮮明になってくるからです。人間は必ず一度地上から姿を消すのだという事実を確認しての、生きているということを直視することで、ぼくはなんだか自分の絵が描けると思うのです。」(「みづゑ」No825 p70、1973)
「あらゆる事象をのみ込んで、無限に豊かになっていくもの、それは突き詰めていきますと、結局は一本の線になるんですね。世のすべての喧騒も、宇宙への大きな感動も、僕自身の人生も、一本の線の中に入ってしまう。一本の線を引いて、そこに僕のすべてが入ってしまえば、絵はそこで完成する。単純になればなるだけ、絵は一層豊かになる。」(神戸新聞1994年12月25日「会いたかった人」より)
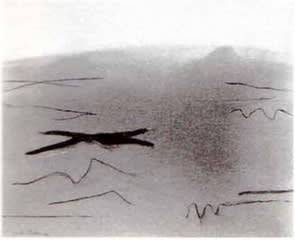 「軌跡」1993 ~収蔵品目録より
「軌跡」1993 ~収蔵品目録より人が生きた軌跡。一本の線は、どこかから始まり、どこかで途切れる。
この絵の線は、何人かの人の軌跡のようでもあり、砂に潜っては現れる一人の人間の軌跡のようでもある。
父はどんな線を描いたのか。私は今どんな線を描いているのだろう。
西宮に住んでいた画家は、震災の日倒壊した日本家屋の下で、夫人と共に亡くなった。
展覧会では、津高の作品5点の間に、吉野晴朗氏が撮った、震災前の自宅の写真と、震災直後の自宅の写真があった。
震災前の1962~81、津高和一は、「既成の美術館・画廊だけが美術作品を発表する場所だという固定概念に対して、自他共に反省を促すため」に、秋には自宅の庭・アトリエを開放し「対話のための作品展」を開いていた。その時の写真で、庭にはオブジェ作品が数個、人々が集っている。緑の木の前には、カメラに向かってポーズをとっているような、凛々しい大きな黄色いネコさんがいる。
もう一枚の1995年の写真では、完全に木材の瓦礫と化した家屋を背景に、傾いた庭のオブジェ作品の上に、こちらを無邪気に見ている黄色い子猫が、ちょこんと座っているのだった。
このカメラ目線の、フサフサの金色毛色の2匹のネコさんは、親子のようだ。
すぐさっきまで、主のいなくなった庭で、子猫は泣いていたのかもしれない。
残念ながら、津高和一の残した絵に、ネコの絵はないが、絵の中の黄色い線のどれかは、この黄色いネコさんのような気がする。


























遠く九州の地で震災を知り、すぐに神戸の弟と友人達へと電話を入れたのですが、通じるわけもなく(そんな当たり前の事に気付かぬ程動揺していたのです)後ろ髪引かれる思いで出勤した事が、ありありと蘇えります。
その後、被災者達からの連絡があるまでの何日か何時間か、私自身と私の家族とは、心情としての被災者でした。現地のあわただしさは、彼らの生活の変化と、行動とにより、遅ればせながら、ほんの少しではありますが理解しましたが。
友人は、全壊した西宮の借家を引き払い九州に戻り、当時高校球児だった彼の息子は、今では元気に長唄を教えています。時は留まる事がありません。
ラミーさん達もご無事で何よりでした。
昨年の10月、家族で長崎を旅行しました。私にとっては久しぶりの長崎でした。
地下の駐車場からエレベーターで昇ると、出口の真横が平和祈念像です。正面に回り、手をあわせ黙祷を終え、浦上さんに向かって裏道の階段を下っている時、娘に聞かれました。
「お父さん、何を長いこと祈っていたの?」と。
「お礼を言っていたんだよ。」私は答えました。
「長崎の人たちと、この下で眠っている人たちが、原爆を引 き受けてくれたから、私たち家族が今在るんだから。」
私たち家族は、今一緒に住んでいない私の弟も含めて、長崎の被爆がなければ存在していなかったでしょう。
運命とは皮肉なものです。いや、戦争とは。
娘に、私の気持ちは伝わったでしょうか。
ラミーさん、これからもブログを通して色々な事を語って下さい。物言わぬ若い読者も多くいるでしょうから。
阪神淡路大震災から○年と聞くと、もう一つの同じ年数を悟ります。
1995年2月、同じ年、大切な人と別離れました。
あなたの○回忌は、震災後○年と同じです。出来の悪い息子が決して忘れる事のないように、誰かが手配してくれたのかも知れません。許されるのなら、月の光を辿り大切な人達を訪ねたいものです。
長々とルール無視の長文コメント、ご容赦を。他に手だてを知らないものですから。
良い夢を。
娘さんにとって忘れられない長崎旅行に、きっとなったことでしょう。一方的に与えられた言葉ではなく、自らの疑問に答えてくれた言葉って、心の奥に届いている気がします。
「それは私だったかもしれない、私の代わりに…」という思いは、あの日のことだけでなく、普段通る道端に、供えられた花束を見た時にも、湧いてきます。
慰霊という、手をあわせ祈る行為には、必ずそんな思いを込めています。
ハイチ・チリと、大地は何に怒っているのでしょう。彼の地の人々の新しい朝に希望の光がさしますように。