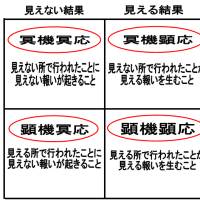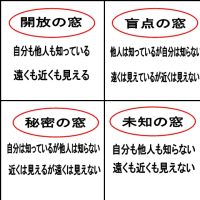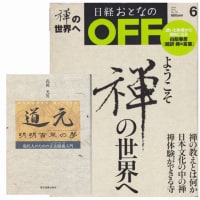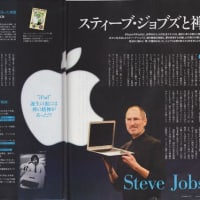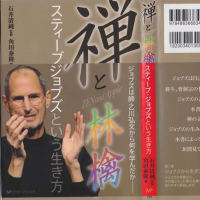澤谷 鑛
ある人がフェイスブックに、こんなことを書いていました。
病気になられているようです。
【今までは、症状が出るたび怖くて、やっぱり治らないんじゃないかと不安になりました。
不安なものだから、なんとかして治そうといっしょうけんめいになりました。
でも、「治そう」と頑張ることは、「治らない」といった確信と背中合わせ。】
ここまで読んで、えっ! と思いました。
症状というのは、不完全に現われるから治したい、と思うのですよね。その不完全な症状を認識できているのは、不完全な症状をみている自分が完全を知っているから不完全がわかるのですね。もし不完全が不完全をみても不完全と感じないので、それで当たり前だから、そのままにして治そうとも思わないでしょう。だから、治そうという意欲は、治らないという確信からではないことがわかります。
これは、入江富美子氏のご著書『へそ道』(サンマーク出版)の魂=「たま」と「しい」の世界にヒントがあります。(このことは、私のフェイスブックでも書きました)
『へそ道』のP.68の“第2章「なんとなくの世界」を知る”の「見える世界と見えない世界で人生を織り上げていく」の中で、著者の入江氏は、魂=「たま」「しい」のことを、このように書かれています。
「たま」に関しては、
【……「魂」という言葉には大切な意味が含まれていました。
魂=「たましい」という言葉は、「たま」と「しい」に分けられます。
「たま」とは、「御霊=みたま」のことで、「みたま」とは、天であり、すべてのもとのこと。「みたま」を天そのものとして表現しますが、私たちの中にも、「みたま」と同じものがあり、それを「分けみたま」と言います。これら両方が「たま」なのです。
私たち一人ひとりの内にある「みたま」は、植物でいう種と同じことで、これが「種の教え」というものです。
それは、種の中には、根、幹、葉、花、実などの情報がすべて入っています。つまり、みたまには、その人自身の役割を生きるための情報すべてが入っているのです。ですから、「たま」はもって生まれたとおり、自分がこの世に生まれてきた役割をただ果たそうとするものです。】
「しい」に関しては、
【そして、もう一つの「しい」とは、各自の心や感情のことを表しています。
「うれしい」「かなしい」「欲しい」「惜しい」「悔しい」「楽しい」など感情を表す言葉には、「~しい」がついていますよね。
このように、私たちはこの天来の「たま」と、心や感情である「しい」の両方をもたされて生まれてきます。この二つで「魂=たましい」というのです。
「たま」だけでは自覚はなく、「しい」を伴うことによって、この世に生まれてきた役割を果たそうとします。】
フェイスブックに書かれていた方の話に戻りましょう。
私のフェイスブックに、このことで桜 美穂さんからコメントがありました。
【この方は、ご病気なのですね。^^
「しい」と「しい」が絡まって混乱されているのかもしれません。このようにご表現されると適切かなと思いました。
不完全と見える症状の表れの奥に完全な自分がいるのだ、と安心すれば良いのに、それを思わず、治そう治そうと過度に執着し、焦る心は、「治るはずがない」という恐れから生まれています。
心に思った通りの現状が展開されます。「本当に治るのだろうか」「悪くなるのではないだろうか」という恐れに突き動かされて行う、治ろうとする努力は、効果を生み出すどころか、逆に、著しく治癒を妨げるのですね。ゆえに、頑張れば頑張るほど、「治らないのではないか」という確信は強化され、頑張れば頑張るほど、治癒から遠ざかっていたのでした。うーん、長い(笑)。お読みくださり、ありがとうございました。】
私はすぐにコメントを返しました。
【そうなのですね。「しい」ワールドは、ドロドロの泥沼から永遠に濁らないまっさらさらに澄んだ世界まで、グラデーションでありますからね。「たま」ワールドに超入すべく、道元のいう「仏向上(ぶっこうじょう)」と出会うことが出来る「仏向上心」までに「しい」の世界を澄ませなければなりません。】
また桜 美穂さんは、ご自分のフェイスブックにも、このように書かれました。
【「治そうという意欲は、治らないという核心からではない」と、お書きくださいました。
たとえば私は先日ケガをしましたが、その時は、治るかどうかについて、まったく不安を感じませんでした。その程度の治癒は何度も経験しているから疑わなかったということもあるでしょうが、それ以上に、「治って当たり前」「けがのない方が本来の姿」だと確信があったからなのだと思います。その時も、「治そう」という意欲を持って、ケガの手当てを致しました。しかしその時のように「治って当たり前」の「治そう」ではなく、「治らないのではないか」という恐れから発する焦りの「治そう」とでは、同じ「治そう」という意欲でも、手当でも、恐らく結果は真逆になるでしょう。恐れていたということは、治癒すると信じられず、自分が本来完全な存在であるということを疑っていたのですから、治らないのは当然なのだと思います。「しい」に振り回されず、自在に使いこなすことが求められているということではないかと感じます。】
私は、またすぐにコメントを返しました。
【「たま」の世界のことでなく「しい」の世界のことをいわれているのですね。とは言え、「たま」の世界への言及もあります。ということは、いかに表現するか? の問題でしょうか?】
すると、桜 美穂さんからふたたびコメントがきました。
【症状という不完全な状態を見て、ああ、不完全だと悲しんだり恐れたりするのではなく、不完全さを押し出している完全さが自分の内側にあると気付き、そちらを見るということですね。】
またまたすぐにコメントを返しました。
【その通りです。そこ、ですね。そこを「いかに表現するか?」ということですね。】
コメントでは短すぎるのか、桜さんからメールが届きました。
【『「治そう」と頑張ることは、「治らない」といった確信と背中合わせ』との件で、表現について深く考える機会をお与えくださりありがとうございました。
表現を工夫し、考え抜くことのなんという楽しさかと思います。
苦しみも伴いますが、なにものにも代えがたい、本当にしあわせな作業です。
先に、先生にお送りしたご対談(魂の対談)の感想文(「なんとも恐ろしく、たまらなく懐かしい」)の中で、言葉は本来、「真実を語り、望みを実現していく道具」なのだと思いますが、あまりにも不用意に軽々しく使われて、望まない現実を展開する道具になってしまっている。と、書きましたが、正しい表現をとことん突き詰め、表現を研ぎ澄ませて精度を高めていくということは、自分が、どのような現実を望んでいるかをはっきりさせていくことであり、何より、自分がなにものであるのか、ということをはっきりさせていくことなのだと気付いて、震えました。
正しく表現するということの奥深さと、言葉によって、本当にすべてが成っていくのだということの凄さ。創造の力を持っているということは、その力を適切に管理する重大な責任が伴っているということ。だからこそ、正確な表現をすることが大事なのだと気付いたとき、あまりの重大さ、凄さを感じて、またまた震えました。
命をどう表し出し、どう展開していくかにより、どのような人生を作り上げていくかが決まってしまう。つまり、表現とは、命がけ。命をかけることなのですね。
引き寄せの法則を初めて知った時、確かに自分が引き寄せてる。自分が展開している。でも、人間は創造主だ、とまで言うのは言い過ぎだろう、と思いました。
でも今は、人はまさしく創造の力を神から分与されており、それは言葉であるのだということがわかります。言葉で何を語られるか、どう語られるかということの重大さは言わずもがな、一音一音の文字の音そのものが力を持っているという考え方も波動療法を学び、すべてが固有の周波数を持っていること、すべてが振動するエネルギーであるとわかった今では、なんの不思議もなくすっきりと腑に落ちるのです。
世界はなんとシンプルであるのだろうと、感じさせられます。このような深い世界にお導きいただき、本当に感謝です。
そうそう、先生がおっしゃっていた岡潔さんについて少し調べてみました。小林秀雄さんとのご対談のご本も、出版されているのですね。
Amazonの説明に、このようにありました。十識どころか、なんと十五識にまでも言及しておられることに驚嘆しました。
【日本の国という水槽の水の入れ替え方―憂国の随想集 単行本 – 2004/4 岡 潔 (著)
この本の章末にある『夜雨の声』(やうのせい)では、以下に列挙する『春雨の曲』(はるさめのきょく)の原案が記されている。
金星の娘との出会い、生命と物質の関係、天衆の挨拶、第一の心である自然科学の顕在識(第一識から第六識)と西洋人に存在する潜在識(無明の入る第七識)、第二の心である東洋人に存在する悟り識(第八識から第十五識)、世間智を用いる自他の別、分別智を用いる時空の框、分別智と無差別智を用いる発見(インスピレーション型発見と梓弓型発見と情操・情緒型発見)、無差別智(大円鏡智・平等性智・妙観察智・成所作智)を用いる純粋直観(知的純粋直観と情的純粋直観と意的純粋直観)、九識論を上回る日本人に存在する第十識「真情」への到達(情が知や意より先であることの当然性)、早死にを招く抜き身を自浄其意で起こすことによる第十一識「時」への到達(道元の別時)、男女の別を懐かしさと喜びから生じる好みで超えることによる第十二識「主宰性」への到達(天照大神と天月読尊の見神)、第十三識「造化」、第十四識「帰趣」、第十五識「内外」等の最晩年の境地も描かれている。】
岡 潔のAmazonの説明は、よく理解できませんが、すぐに返信しました。
【この裏づけが大切ですね。
しかし、岡 潔の唯識は、八識から十五識までも、あくまで識の世界としてあつかっているのですね。すなわち、「たま」ではなく「しい」ワールドなのですね。とは言え、この説明だけでは、わかりかねますが。それにしても、面白い世界ではありますね。】
ある人がフェイスブックに、こんなことを書いていました。
病気になられているようです。
【今までは、症状が出るたび怖くて、やっぱり治らないんじゃないかと不安になりました。
不安なものだから、なんとかして治そうといっしょうけんめいになりました。
でも、「治そう」と頑張ることは、「治らない」といった確信と背中合わせ。】
ここまで読んで、えっ! と思いました。
症状というのは、不完全に現われるから治したい、と思うのですよね。その不完全な症状を認識できているのは、不完全な症状をみている自分が完全を知っているから不完全がわかるのですね。もし不完全が不完全をみても不完全と感じないので、それで当たり前だから、そのままにして治そうとも思わないでしょう。だから、治そうという意欲は、治らないという確信からではないことがわかります。
これは、入江富美子氏のご著書『へそ道』(サンマーク出版)の魂=「たま」と「しい」の世界にヒントがあります。(このことは、私のフェイスブックでも書きました)
『へそ道』のP.68の“第2章「なんとなくの世界」を知る”の「見える世界と見えない世界で人生を織り上げていく」の中で、著者の入江氏は、魂=「たま」「しい」のことを、このように書かれています。
「たま」に関しては、
【……「魂」という言葉には大切な意味が含まれていました。
魂=「たましい」という言葉は、「たま」と「しい」に分けられます。
「たま」とは、「御霊=みたま」のことで、「みたま」とは、天であり、すべてのもとのこと。「みたま」を天そのものとして表現しますが、私たちの中にも、「みたま」と同じものがあり、それを「分けみたま」と言います。これら両方が「たま」なのです。
私たち一人ひとりの内にある「みたま」は、植物でいう種と同じことで、これが「種の教え」というものです。
それは、種の中には、根、幹、葉、花、実などの情報がすべて入っています。つまり、みたまには、その人自身の役割を生きるための情報すべてが入っているのです。ですから、「たま」はもって生まれたとおり、自分がこの世に生まれてきた役割をただ果たそうとするものです。】
「しい」に関しては、
【そして、もう一つの「しい」とは、各自の心や感情のことを表しています。
「うれしい」「かなしい」「欲しい」「惜しい」「悔しい」「楽しい」など感情を表す言葉には、「~しい」がついていますよね。
このように、私たちはこの天来の「たま」と、心や感情である「しい」の両方をもたされて生まれてきます。この二つで「魂=たましい」というのです。
「たま」だけでは自覚はなく、「しい」を伴うことによって、この世に生まれてきた役割を果たそうとします。】
フェイスブックに書かれていた方の話に戻りましょう。
私のフェイスブックに、このことで桜 美穂さんからコメントがありました。
【この方は、ご病気なのですね。^^
「しい」と「しい」が絡まって混乱されているのかもしれません。このようにご表現されると適切かなと思いました。
不完全と見える症状の表れの奥に完全な自分がいるのだ、と安心すれば良いのに、それを思わず、治そう治そうと過度に執着し、焦る心は、「治るはずがない」という恐れから生まれています。
心に思った通りの現状が展開されます。「本当に治るのだろうか」「悪くなるのではないだろうか」という恐れに突き動かされて行う、治ろうとする努力は、効果を生み出すどころか、逆に、著しく治癒を妨げるのですね。ゆえに、頑張れば頑張るほど、「治らないのではないか」という確信は強化され、頑張れば頑張るほど、治癒から遠ざかっていたのでした。うーん、長い(笑)。お読みくださり、ありがとうございました。】
私はすぐにコメントを返しました。
【そうなのですね。「しい」ワールドは、ドロドロの泥沼から永遠に濁らないまっさらさらに澄んだ世界まで、グラデーションでありますからね。「たま」ワールドに超入すべく、道元のいう「仏向上(ぶっこうじょう)」と出会うことが出来る「仏向上心」までに「しい」の世界を澄ませなければなりません。】
また桜 美穂さんは、ご自分のフェイスブックにも、このように書かれました。
【「治そうという意欲は、治らないという核心からではない」と、お書きくださいました。
たとえば私は先日ケガをしましたが、その時は、治るかどうかについて、まったく不安を感じませんでした。その程度の治癒は何度も経験しているから疑わなかったということもあるでしょうが、それ以上に、「治って当たり前」「けがのない方が本来の姿」だと確信があったからなのだと思います。その時も、「治そう」という意欲を持って、ケガの手当てを致しました。しかしその時のように「治って当たり前」の「治そう」ではなく、「治らないのではないか」という恐れから発する焦りの「治そう」とでは、同じ「治そう」という意欲でも、手当でも、恐らく結果は真逆になるでしょう。恐れていたということは、治癒すると信じられず、自分が本来完全な存在であるということを疑っていたのですから、治らないのは当然なのだと思います。「しい」に振り回されず、自在に使いこなすことが求められているということではないかと感じます。】
私は、またすぐにコメントを返しました。
【「たま」の世界のことでなく「しい」の世界のことをいわれているのですね。とは言え、「たま」の世界への言及もあります。ということは、いかに表現するか? の問題でしょうか?】
すると、桜 美穂さんからふたたびコメントがきました。
【症状という不完全な状態を見て、ああ、不完全だと悲しんだり恐れたりするのではなく、不完全さを押し出している完全さが自分の内側にあると気付き、そちらを見るということですね。】
またまたすぐにコメントを返しました。
【その通りです。そこ、ですね。そこを「いかに表現するか?」ということですね。】
コメントでは短すぎるのか、桜さんからメールが届きました。
【『「治そう」と頑張ることは、「治らない」といった確信と背中合わせ』との件で、表現について深く考える機会をお与えくださりありがとうございました。
表現を工夫し、考え抜くことのなんという楽しさかと思います。
苦しみも伴いますが、なにものにも代えがたい、本当にしあわせな作業です。
先に、先生にお送りしたご対談(魂の対談)の感想文(「なんとも恐ろしく、たまらなく懐かしい」)の中で、言葉は本来、「真実を語り、望みを実現していく道具」なのだと思いますが、あまりにも不用意に軽々しく使われて、望まない現実を展開する道具になってしまっている。と、書きましたが、正しい表現をとことん突き詰め、表現を研ぎ澄ませて精度を高めていくということは、自分が、どのような現実を望んでいるかをはっきりさせていくことであり、何より、自分がなにものであるのか、ということをはっきりさせていくことなのだと気付いて、震えました。
正しく表現するということの奥深さと、言葉によって、本当にすべてが成っていくのだということの凄さ。創造の力を持っているということは、その力を適切に管理する重大な責任が伴っているということ。だからこそ、正確な表現をすることが大事なのだと気付いたとき、あまりの重大さ、凄さを感じて、またまた震えました。
命をどう表し出し、どう展開していくかにより、どのような人生を作り上げていくかが決まってしまう。つまり、表現とは、命がけ。命をかけることなのですね。
引き寄せの法則を初めて知った時、確かに自分が引き寄せてる。自分が展開している。でも、人間は創造主だ、とまで言うのは言い過ぎだろう、と思いました。
でも今は、人はまさしく創造の力を神から分与されており、それは言葉であるのだということがわかります。言葉で何を語られるか、どう語られるかということの重大さは言わずもがな、一音一音の文字の音そのものが力を持っているという考え方も波動療法を学び、すべてが固有の周波数を持っていること、すべてが振動するエネルギーであるとわかった今では、なんの不思議もなくすっきりと腑に落ちるのです。
世界はなんとシンプルであるのだろうと、感じさせられます。このような深い世界にお導きいただき、本当に感謝です。
そうそう、先生がおっしゃっていた岡潔さんについて少し調べてみました。小林秀雄さんとのご対談のご本も、出版されているのですね。
Amazonの説明に、このようにありました。十識どころか、なんと十五識にまでも言及しておられることに驚嘆しました。
【日本の国という水槽の水の入れ替え方―憂国の随想集 単行本 – 2004/4 岡 潔 (著)
この本の章末にある『夜雨の声』(やうのせい)では、以下に列挙する『春雨の曲』(はるさめのきょく)の原案が記されている。
金星の娘との出会い、生命と物質の関係、天衆の挨拶、第一の心である自然科学の顕在識(第一識から第六識)と西洋人に存在する潜在識(無明の入る第七識)、第二の心である東洋人に存在する悟り識(第八識から第十五識)、世間智を用いる自他の別、分別智を用いる時空の框、分別智と無差別智を用いる発見(インスピレーション型発見と梓弓型発見と情操・情緒型発見)、無差別智(大円鏡智・平等性智・妙観察智・成所作智)を用いる純粋直観(知的純粋直観と情的純粋直観と意的純粋直観)、九識論を上回る日本人に存在する第十識「真情」への到達(情が知や意より先であることの当然性)、早死にを招く抜き身を自浄其意で起こすことによる第十一識「時」への到達(道元の別時)、男女の別を懐かしさと喜びから生じる好みで超えることによる第十二識「主宰性」への到達(天照大神と天月読尊の見神)、第十三識「造化」、第十四識「帰趣」、第十五識「内外」等の最晩年の境地も描かれている。】
岡 潔のAmazonの説明は、よく理解できませんが、すぐに返信しました。
【この裏づけが大切ですね。
しかし、岡 潔の唯識は、八識から十五識までも、あくまで識の世界としてあつかっているのですね。すなわち、「たま」ではなく「しい」ワールドなのですね。とは言え、この説明だけでは、わかりかねますが。それにしても、面白い世界ではありますね。】