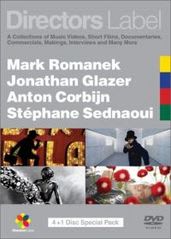去年公開された音楽系のドキュメンタリーはいずれも劣らぬ見応えのあるものばかりだったが、今月半ばに観たマーティン・スコセッシ監督のボブ・ディランの『No Direction Home』ほど、個人的に大きなフィードバックがあったものはない。何せ、この半月ばかり当ブログの更新に身が入らないほど、私の好きな「ディラン周辺の人」関連をほじくり始めてしまったのだから。
一言断るなら、私はディラン自身のファンではない。というか、彼のような存在はファンとか好きとか嫌いを超越したものだと思っている。ビートルズやローリング・ストーンズ、或いはエルヴィス・プレスリー等のある種「歴史的偉人」という位置付けだ。
ただ正直なところ、私はずっと彼の「唄声」が苦手だった。あの特徴的な、硬質でザラついてひしゃげた声。歌うというよりは、言葉を投げ、ぶつけている感じ。唄が上手い下手は好みと関係がないが、声のトーンの好みはある。ディランの声は、私にとって耳馴染みの良いものではなかった。けれど、その詩は凄いと思う。彼の唄は詩が主体だ。メロディではない。現代の吟遊詩人とは彼のような存在を言うのだろう。但し悲しいかな、英語圏の人間ではないから、詩はダイレクトに耳に入ってはこない。曲だけ聴いてる分には、彼のフォーク・ソングは単調で素朴過ぎて、ひっかかりが無かった。そうして、彼の唄をちゃんと聴き始めた頃は、アルバムを2枚ほど買っても、さほど聴き込みはしなかった。
ところがである。おそらく現代のロック・ミュージシャンで、ディランの影響を受けてない人は殆ど存在しないはずで、私の好きなアーティストも例外ではなかった。それどころか、我が最愛のギタリスト、ミック・ロンソンは、ディランの70年代のツアー【ローリング・サンダー・レヴュー】に参加していたので、殆ど仕方なく(苦笑)ツアーのライヴ・アルバム『ハード・レイン』と、ブートレッグを何枚か、そしてTVのライヴ中継のブートビデオなどを買った。このときのライヴ、ツアー・メンツはビジュアル的にもかなり私は好きで、“ロック”なディランを堪能できるが、いかんせん興味が彼でなく脇だったため、持っててもあまりありがたみを感じたことはなかった。
その時期と前後して、当時NHKで放送されたD.A.ペネベイカー監督の『ドント・ルック・バック』('67)を観ることになる。'65年の英国ツアー時のディランのバックステージものドキュメンタリーだけど、これがベラボウに面白かったのである。“サブタレニアン・ホームシック・ブルース”の「歌詞の紙芝居」から始まるところから、グッと気持ちを持っていかれる。まだ若く、青くて繊細な色気のあるディランの姿。相手が誰であろうと無礼な態度や気に障ることがあれば、辛辣な言葉を浴びせる。カメラが回ってることなど気にも留めないかのように。常に緊張感をまとった彼の眼差し、佇まいは、ある意味既にフォーク・シンガーというより、ロック、パンクであった。しかし、仲間うちでは時折無愛想な表情を崩して、屈託ない笑顔を見せる。ツアーに同行していた当時の恋人、ジョーン・バエズの美貌(そして美声)やコケティッシュさも印象的だった。(彼女は先述の【ローリング~】のツアーにも参加している。そして『ノー・ディレクション~』でもインタヴューに応えているが、歳はとってもやはり知的美人であり、現在でもバリバリ現役・貫禄の女性活動家オーラを放っていた。余談だが、そんな彼女に対してディランは今でもロマンティックな気持ちを抱き続けているらしいのが、なんだか微笑ましいというか、イメージよりも可愛いいなあ、と好感度アップなのだった)
それでもやはり、ファンではない私には特に掘り下げる気にもならず、それでも次なるディラン・アイテムを購入するハメになったのは'92年。【30周年記念コンサート】のブート・ビデオだった。コレはもう、当然ながらゲストの顔触れが凄過ぎた。個人的目玉はパール・ジャムのエディ・ヴェダー&マイク・マクレディ・コンビと、ルー・リード出演だったが、予想外に目と耳を奪われのはカッコ良過ぎる白髪鬼(笑)ジョニー・ウィンターと、凄まじいブーイングに晒されたシニード・オコナーだった。当のディランは・・・何か今一つ精彩にかけるというか、主役なのにやっぱり不機嫌そうな印象で、盛り上がってるのは客とゲストだけみたいで何だかなあ、と感じたものだ。
だが、一番熱が入ってしまったのは、同じスコセッシ監督によるザ・バンドの『ラスト・ワルツ』DVD廉価版を購入して、観返してしまったことに尽きる。すっかり忘れてたが(笑>ヒドイ~)ディランとザ・バンドには浅からぬ縁があったのだった。おかげで、ゆるーーく続いてたザ・バンドへの愛が沸々と湧きあがってきてしまった---が、これはまた次の機会に。
そんなこんなで、手元にあるこれらのディランものを改めて総ざらいしてしまうほど、いろいろと思うところの多かった『ノー・ディレクション・ホーム』だが、まずこの作品の面白さというのは、ディラン本人の来歴・歴史を振り返ること自体がアメリカン・ルーツ・ミュージックからポピュラー~フォーク、ロックへの変遷を見事に物語っている、ということなのであった。
今作では、60年代までのディランの活動に絞られているのだけど、彼自身の当時のパフォーマンスに限らず、当時彼が影響を受けた音楽/アーティスト達の貴重な映像、インタヴューも盛りだくさんで、米国音楽史の資料的価値という意味でも、ディランのみならずアメリカン・ミュージックのファンは必見!といった内容になっている。(そして、それこそがスコセッシの目指したものであるように感じた)3時間余りの長丁場が苦にならないほど、興味深く音楽好きには楽しめるはずだ。
そしてディランの何が、その他大勢のフォーク・シンガーと彼を決然と分けるものであったか、その孤高にして唯一の存在たらしめたのかも理解できる作品でもある。現在のディランは今も尚こう語る。「歌い始めたのは、ずっと自分の"home"(魂の故郷、という意味かと思う)は此処(出身地ミネソタの小さな街)ではないと感じたからだ。今でも、俺は自分の"home"を見つけるために唄っている」 ------それは、N.Y.に行った彼がプロテスト・フォーク・シンガーの新旗手として人気を得たとしても、時代の波にのって「世代の代弁者」的位置に祭り挙げられることを拒否した姿勢、仲間やフォロワーとされる人たちとさえ決して「つるまない/馴れ合わない」態度、何より多くのフォーク・ファンから「裏切り者!」と罵声を浴びせ掛けられても、自ら選んだエレクトリック・ギター・サウンド(ロック)への道を突き進んだことにも繋がるのだろう。ときに息切れしたり回り道をしたとしても、決して辿り付くことはないかもしれない、まだ見ぬ"home"を目指して旅を続ける。だからこそディランという存在は、芸能としてのパフォーマーに留まらない、正しく現代最高峰の吟遊詩人として揺ぎ無い位置に在るのだろう。
改めて思うに"home"というのは、特にアメリカ人にとっては、普通よりも意義深い言葉かもなのかもしれない。建国300年余りの彼の国の、殆どの国民は移民なのだから。彼らは故郷を捨てて、あるいは理想を夢見てアメリカに来た。捨てた故郷には帰ることは出来ないし、理想とは違ったからといって簡単に戻れる訳でもない。やがて血は様々に混じりあい、遠ざかるほどに望郷の念は強まれど、ではその故郷とは何処なのか---或いはその"home"への道程こそが、彼の国の表現者にとって創造の源、命となっているかもしれない。
一言断るなら、私はディラン自身のファンではない。というか、彼のような存在はファンとか好きとか嫌いを超越したものだと思っている。ビートルズやローリング・ストーンズ、或いはエルヴィス・プレスリー等のある種「歴史的偉人」という位置付けだ。
ただ正直なところ、私はずっと彼の「唄声」が苦手だった。あの特徴的な、硬質でザラついてひしゃげた声。歌うというよりは、言葉を投げ、ぶつけている感じ。唄が上手い下手は好みと関係がないが、声のトーンの好みはある。ディランの声は、私にとって耳馴染みの良いものではなかった。けれど、その詩は凄いと思う。彼の唄は詩が主体だ。メロディではない。現代の吟遊詩人とは彼のような存在を言うのだろう。但し悲しいかな、英語圏の人間ではないから、詩はダイレクトに耳に入ってはこない。曲だけ聴いてる分には、彼のフォーク・ソングは単調で素朴過ぎて、ひっかかりが無かった。そうして、彼の唄をちゃんと聴き始めた頃は、アルバムを2枚ほど買っても、さほど聴き込みはしなかった。
ところがである。おそらく現代のロック・ミュージシャンで、ディランの影響を受けてない人は殆ど存在しないはずで、私の好きなアーティストも例外ではなかった。それどころか、我が最愛のギタリスト、ミック・ロンソンは、ディランの70年代のツアー【ローリング・サンダー・レヴュー】に参加していたので、殆ど仕方なく(苦笑)ツアーのライヴ・アルバム『ハード・レイン』と、ブートレッグを何枚か、そしてTVのライヴ中継のブートビデオなどを買った。このときのライヴ、ツアー・メンツはビジュアル的にもかなり私は好きで、“ロック”なディランを堪能できるが、いかんせん興味が彼でなく脇だったため、持っててもあまりありがたみを感じたことはなかった。
その時期と前後して、当時NHKで放送されたD.A.ペネベイカー監督の『ドント・ルック・バック』('67)を観ることになる。'65年の英国ツアー時のディランのバックステージものドキュメンタリーだけど、これがベラボウに面白かったのである。“サブタレニアン・ホームシック・ブルース”の「歌詞の紙芝居」から始まるところから、グッと気持ちを持っていかれる。まだ若く、青くて繊細な色気のあるディランの姿。相手が誰であろうと無礼な態度や気に障ることがあれば、辛辣な言葉を浴びせる。カメラが回ってることなど気にも留めないかのように。常に緊張感をまとった彼の眼差し、佇まいは、ある意味既にフォーク・シンガーというより、ロック、パンクであった。しかし、仲間うちでは時折無愛想な表情を崩して、屈託ない笑顔を見せる。ツアーに同行していた当時の恋人、ジョーン・バエズの美貌(そして美声)やコケティッシュさも印象的だった。(彼女は先述の【ローリング~】のツアーにも参加している。そして『ノー・ディレクション~』でもインタヴューに応えているが、歳はとってもやはり知的美人であり、現在でもバリバリ現役・貫禄の女性活動家オーラを放っていた。余談だが、そんな彼女に対してディランは今でもロマンティックな気持ちを抱き続けているらしいのが、なんだか微笑ましいというか、イメージよりも可愛いいなあ、と好感度アップなのだった)
それでもやはり、ファンではない私には特に掘り下げる気にもならず、それでも次なるディラン・アイテムを購入するハメになったのは'92年。【30周年記念コンサート】のブート・ビデオだった。コレはもう、当然ながらゲストの顔触れが凄過ぎた。個人的目玉はパール・ジャムのエディ・ヴェダー&マイク・マクレディ・コンビと、ルー・リード出演だったが、予想外に目と耳を奪われのはカッコ良過ぎる白髪鬼(笑)ジョニー・ウィンターと、凄まじいブーイングに晒されたシニード・オコナーだった。当のディランは・・・何か今一つ精彩にかけるというか、主役なのにやっぱり不機嫌そうな印象で、盛り上がってるのは客とゲストだけみたいで何だかなあ、と感じたものだ。
だが、一番熱が入ってしまったのは、同じスコセッシ監督によるザ・バンドの『ラスト・ワルツ』DVD廉価版を購入して、観返してしまったことに尽きる。すっかり忘れてたが(笑>ヒドイ~)ディランとザ・バンドには浅からぬ縁があったのだった。おかげで、ゆるーーく続いてたザ・バンドへの愛が沸々と湧きあがってきてしまった---が、これはまた次の機会に。
そんなこんなで、手元にあるこれらのディランものを改めて総ざらいしてしまうほど、いろいろと思うところの多かった『ノー・ディレクション・ホーム』だが、まずこの作品の面白さというのは、ディラン本人の来歴・歴史を振り返ること自体がアメリカン・ルーツ・ミュージックからポピュラー~フォーク、ロックへの変遷を見事に物語っている、ということなのであった。
今作では、60年代までのディランの活動に絞られているのだけど、彼自身の当時のパフォーマンスに限らず、当時彼が影響を受けた音楽/アーティスト達の貴重な映像、インタヴューも盛りだくさんで、米国音楽史の資料的価値という意味でも、ディランのみならずアメリカン・ミュージックのファンは必見!といった内容になっている。(そして、それこそがスコセッシの目指したものであるように感じた)3時間余りの長丁場が苦にならないほど、興味深く音楽好きには楽しめるはずだ。
そしてディランの何が、その他大勢のフォーク・シンガーと彼を決然と分けるものであったか、その孤高にして唯一の存在たらしめたのかも理解できる作品でもある。現在のディランは今も尚こう語る。「歌い始めたのは、ずっと自分の"home"(魂の故郷、という意味かと思う)は此処(出身地ミネソタの小さな街)ではないと感じたからだ。今でも、俺は自分の"home"を見つけるために唄っている」 ------それは、N.Y.に行った彼がプロテスト・フォーク・シンガーの新旗手として人気を得たとしても、時代の波にのって「世代の代弁者」的位置に祭り挙げられることを拒否した姿勢、仲間やフォロワーとされる人たちとさえ決して「つるまない/馴れ合わない」態度、何より多くのフォーク・ファンから「裏切り者!」と罵声を浴びせ掛けられても、自ら選んだエレクトリック・ギター・サウンド(ロック)への道を突き進んだことにも繋がるのだろう。ときに息切れしたり回り道をしたとしても、決して辿り付くことはないかもしれない、まだ見ぬ"home"を目指して旅を続ける。だからこそディランという存在は、芸能としてのパフォーマーに留まらない、正しく現代最高峰の吟遊詩人として揺ぎ無い位置に在るのだろう。
改めて思うに"home"というのは、特にアメリカ人にとっては、普通よりも意義深い言葉かもなのかもしれない。建国300年余りの彼の国の、殆どの国民は移民なのだから。彼らは故郷を捨てて、あるいは理想を夢見てアメリカに来た。捨てた故郷には帰ることは出来ないし、理想とは違ったからといって簡単に戻れる訳でもない。やがて血は様々に混じりあい、遠ざかるほどに望郷の念は強まれど、ではその故郷とは何処なのか---或いはその"home"への道程こそが、彼の国の表現者にとって創造の源、命となっているかもしれない。