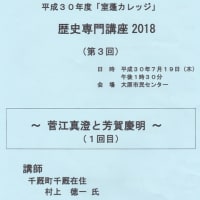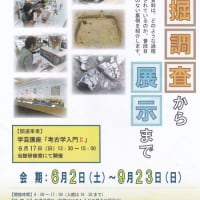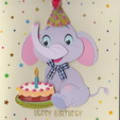5/11(木)、昨日から雨降り続きで生憎の天候ながら、我が同行者は朝早くから、1つでも多くの古墳などを見ようと意気盛んである。
近鉄橿原線・橿原神宮前駅を出発して近鉄吉野線・飛鳥駅に着いたのは8:30頃。駅前の飛鳥総合案内所もまだ開いていない。

奈良バスの周遊バス「赤かめ」で周遊すると便利だとガイドブックに書いてあったので、乗り降りが何度でもできる「赤かめ」の周遊券(650円)を買う。赤い表紙の「パスポート」なるものは100円。
最初にやってきた周遊バスに乗り、いざ出発。5分もしない中に1つ目のバス停である「高松塚」に着く。

立派な公衆トイレがあったので早速使わせていただきましたが、早くも「ヤマボウシ(山法師)」が咲いていました。


国営飛鳥歴史公園館が建っていましたが、後回しにして先ず「高松塚古墳」を見るため、方向板に従って歩くことにしました。(590mと書いてある)







白い花弁のように見えるのは「総苞片」といわれるもので、花は4枚の苞片の真ん中にある緑色のもの。苞片が落ちた後、果実がおおきくなり、秋には赤く熟し食べられる。
ヤマボウシ(山法師)ミズキ科 ミズキ属 Cornus kousa
山地に生える落葉高木で、高さは普通5~10m、大きいものは15mにもなる。樹皮は赤褐色で丸い鱗片となって剥がれる。よく庭園樹や公園樹にされている。
葉は有柄で対生し、長さ4~12cmの楕円形~卵状楕円形で、縁はやや波打つ。5~7月、白い花のように見える4個の緑色を帯びた白い総苞片がよく目立ち、その中心に小さな花が多数(20~30個)球状に集まってつく。総苞片は長さ4~6cm。
和名は、法師の白い頭巾と頭に見立ててつけられたといわれる。
果実は集合果で、花が終わると球形の果実が大きくなり、秋に赤く熟し食べられる。甘酸っぱくておいしい。総苞片が淡紅色のものがあるが、「ベニヤマボウシ(紅山法師)f.rosea」という。
分布:本州、四国、九州、朝鮮、中国、台湾