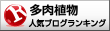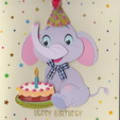2012年10月14日(日)、水沢市街から北上川に架かる四丑橋を渡って県道水沢・玉里線を玉里方面へ進むと、江刺市内・羽田線と交差しますが、その傍にあるJOMO・SS(ガソリンスタンド)で給油するために行ったとき、隣接する江刺ふるさと市場(奥州市江刺区愛宕字金谷83-2)に立ち寄りました。すぐ近くにある休耕田に大群生したセタカアワダチソウ(脊高泡立草)が、黄色い花を咲かせ始めていました。最盛期はこれからです。
http://jaefurusato.jaesashi.or.jp/s000001/home/ [江刺ふるさと市場:市場概要]










セイタカアワダチソウ(脊高泡立草) キク科 アキノキリンソウ属 Solidago altissima
北アメリカ原産の多年草(帰化植物)。各地の土手や荒れ地、休耕田などに大群落をつくる。日本に渡来したのは明治の頃だといわれているが、戦後、各地で目立つようになり、一時は日本全土を覆うのではないかと心配されたが、現在は少し鎮静化したようで、今ではすっかり日本の秋の風景に溶け込んでいる。
北九州では、炭鉱の閉山が相次いだ頃、猛烈な勢いではびこりはじめ、辺りを黄色一色に埋め尽くしたので”閉山草”と呼ばれていたという。種子でも繁殖するが、地下茎が地中を横に走り、しかもそこからほかの植物が育つのに害になるような物質を分泌しながら、自分の勢力範囲を広げているきわめて攻撃的な植物で、その猛烈な繁殖力などの故に各地で嫌われているが、秋の蜜源植物としては貴重。
草丈は名前の如く大きく、1~3mになる。花の部分以外は普通枝分かれせず、短毛を密生してざらつく。葉は密に互生し、長さ6~13㎝の披針形でやや厚く、短毛があってやはりザラザラする。10~11月、茎の先端に10~50㎝もある大きな円錐状の花序をつけ、直径6㎜ほどの黄色の頭花をびっしりと開く。[山と渓谷社発行「山渓カラー名鑑・日本の野草」&同「山渓ポケット図鑑3・秋の花」より]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=38445503&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:一関市狐禅寺のセイタカアワダチソウ(脊高泡立草)]
https://app.blog.ocn.ne.jp/t/app/weblog/post?__mode=edit_entry&id=32609538&blog_id=82331 [peaの植物図鑑:一関市川崎町のセイタカアワダチソウ(脊高泡立草)]