
石木川はシーボルトの川。この川の魚から日本の淡水魚の名前がつけられて世界は日本の川を知った。その川にダムが計画されている。この川には60名13世帯が住みが強制収用の執行が進む。人々の普通の生活を守る行為は、日本の原風景、自然そのものを守る戦いでもある。
シーボルトの川 2015年10月4日
ほとんどの生き物には名前がある。世界で共通するのが学名と呼ばれるラテン語の名前だ。
日本にいる淡水魚で最初に学名がつけられて、世界に紹介された魚の一種がカワムツだ。今から169年前の1846年。その学名の元となった魚の標本は現在もオランダ国立自然史博物館に収蔵されている。
なぜ、日本の淡水魚がオランダにあるのか、それは江戸後期、長崎の出島に滞在したオランダ商館医シーボルトの存在がある。シーボルトの数万点という標本をもとに発表された日本の生物はトキ、オオサンショウウオなどたくさんある。魚類ではアユ、ウナギ、タイなどよく知られた魚が350種余り、淡水魚では19種に学名がつけられた。
淡水魚の採集地はどの川かはわかっていなかった。近年、川の規模、そして現存する魚の種類などから、長崎県、大村湾に注ぐ川棚川の流域。そして、希少種が含まれることから支流の石木川が主な採集地ではと考えられている。
その石木川には50年前にダムが計画された。高度成長期に立案され、必要性の乏しい公共事業は予備調査から40年を経過してなお住民が建設に反対し、現在も13世帯60名が計画地に生活している。ダム計画をすすめる長崎県・佐世保市は本年8月農地の一部を強制収用した。しかし、住民たちは連日、心をつなぎ肩を寄せて、「人の鎖」が工事の開始を阻止している。
ダムが計画された川の自然は美しい。それはダム建設を前提として不要な河川工事などが行われないからだ。とても皮肉な事実なのだが、ダム計画によって石木川の自然は保たれ、シーボルトが世界に紹介した日本の川の姿をそのままに残すことになった。
収穫間近の稲穂が光る。石木川では今日も里の普通の生活を守るための戦いが続く。人々が守り続けているは日本の原風景、そして日本の自然そのものでもあるのだ。(魚類生態写真家)












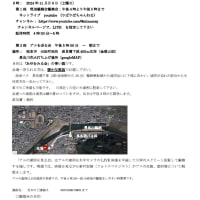













※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます