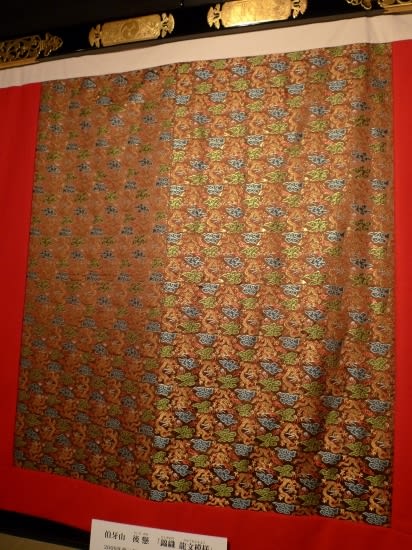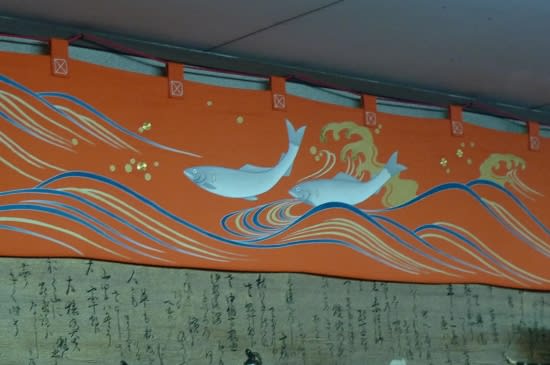祭りといえば露店。
祇園祭は範囲が広いので、そこここの通りに露店がひしめいています。
昔ながらの食べ物系もあれば、雑貨もあり、レストランがちょっとした食べ物をお店の前で売っていたり・・・。
さらには街中に多い呉服屋さんも、食べ物と同じようなノリで、浴衣の激安セールをしていたり・・・。
ほんと、バラエティ豊かです。




明るいうちは割と空いていてスイスイ歩けましたが、暗くなるにつれ、思うように進めなくなってきました。
ただでさえ、それほど幅のない道の両側に露店が並ぶものですから、人の流れは遅々として進まず、
満員電車の様相を呈してきます。
ちょっと右に曲がりたい・・・と思っても、
「こちらは一方通行になっておりまーす!このまま真っすぐお進み下さーい!!(by警察官)」
といった具合で、もう一筋向こうの道までギュウギュウと進まざるをえないのです。


↑夜店も多国籍ですね。 辺りにスパイシーないい香りが漂ってました!

↑人混みでギュウギュウです。 まさに風船の顔の気分 (>_<)

↑懐かしい金魚すくい。 金魚のプールもちょっと混み気味?

↑これまた懐かしいヨーヨー。 カラフルで可愛い。
私も何か買って食べようかと思ったのですが、あまりの人に立ち止まれなかったり、
おいしそうと思った屋台は長蛇の列だったりで、結局諦めました・・・。
いやはや、本当にものすごい人混みでしたが、久々の人混みもまた日本らしく、少し嬉しくもあるぺにゃんでした。
祇園祭は範囲が広いので、そこここの通りに露店がひしめいています。
昔ながらの食べ物系もあれば、雑貨もあり、レストランがちょっとした食べ物をお店の前で売っていたり・・・。
さらには街中に多い呉服屋さんも、食べ物と同じようなノリで、浴衣の激安セールをしていたり・・・。
ほんと、バラエティ豊かです。




明るいうちは割と空いていてスイスイ歩けましたが、暗くなるにつれ、思うように進めなくなってきました。
ただでさえ、それほど幅のない道の両側に露店が並ぶものですから、人の流れは遅々として進まず、
満員電車の様相を呈してきます。
ちょっと右に曲がりたい・・・と思っても、
「こちらは一方通行になっておりまーす!このまま真っすぐお進み下さーい!!(by警察官)」
といった具合で、もう一筋向こうの道までギュウギュウと進まざるをえないのです。


↑夜店も多国籍ですね。 辺りにスパイシーないい香りが漂ってました!

↑人混みでギュウギュウです。 まさに風船の顔の気分 (>_<)

↑懐かしい金魚すくい。 金魚のプールもちょっと混み気味?

↑これまた懐かしいヨーヨー。 カラフルで可愛い。
私も何か買って食べようかと思ったのですが、あまりの人に立ち止まれなかったり、
おいしそうと思った屋台は長蛇の列だったりで、結局諦めました・・・。
いやはや、本当にものすごい人混みでしたが、久々の人混みもまた日本らしく、少し嬉しくもあるぺにゃんでした。