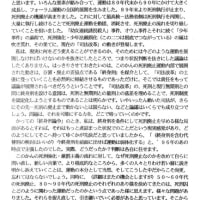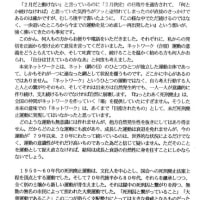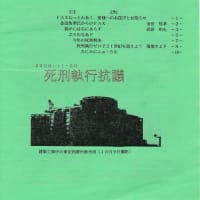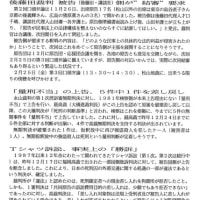永山則夫支援者だった武田和夫さんが永山さんから追放された後、武田和夫さんが「風人社」という死刑廃止団体を立ち上げ、『沈黙の声』という会報を発行してました。その内容を載せます。
「続・死刑廃止論ノート(その1)」
「続・死刑廃止論」ノートヘの序 〝死刑廃止はすでに論議の段階ではなく着手の段階であるといわれて久しい″といわれて久しい、今の死刑廃止運動にあって、我々が真剣に運動をすすめていく上でどうしても避けられない″論議″に、次のものがある。
ひとつは、「死刑制度」とはそもそも何であり。何によって成り立っているのかを明らかにしていく作業―いわゆる「死刑廃止論」が〝何故死刑を廃止すべきか″という「当為」の議論であるのに対し、より客観的な「死刑本質論」である。われわれが運動をすすめる過程で″それこそが死刑を支える思想だ″ということがよくあるが、そこのところをあいまいな感覚的言辞にとどめておかず、より掘り下げていく作業だ。
いまひとつは、現在の死刑存置論のほぼ唯一のよりどころでもある「被害者感情」の問題を、逃げないで真正面からとりくんでいくことである。―それはまた、人を殺した死刑囚の真のしょく罪とは何かを、ともに考えていくことでもある。
われわれは、今の死刑廃止の闘いが、死刑囚とともに闘ってきたものであることの意義と、闘いの前進のためにはその共闘を更に強いものにしていかねばならないことを、くり返し訴えてきた。
ところで、共に闘うためには、仲間としての死刑囚に真剣に向き合っていかなければならないが、この″向き合う″とは、とりもなおさず《死刑》に向き合うことであり、〈事件の被害者〉に向きあうことでもあるのだ。〈死刑〉に向き合わず、〈被害者〉に向き合うこともない「死刑囚との関わり」は、死刑廃止運動にとって、必ずしもつねに有益なものとはならないだろう。 死刑の本質論-″死刑とは何か″については、 『沈黙の声』2号~5号及び7号の「死刑廃止論」で若干の展開を試みたつもりである。
そこでは死刑を、国家―とりわけ、天皇制近代国家日本との関係からとらえた。
然しながら、国家が死刑(刑罰)を「正義」として行使しうるためには、その対象となる人間があらかじめ、その社会によって「反社会的」であるとみなされる条件、彼が「悪」として認識されうる社会通念が存在していなければならない。
死刑(刑罰)を論ずるには、社会がある種の行為を「悪」とみなし、排斥すべき反社会的行為と認識していく過程と、権力がそれを「犯罪」として刑罰の対象とし、その処罰権を専有することで、支配の正当性をわがものとしていく過程、その双方からのとらえ返しが必要である。
「犯罪」=悪を自明の前提とするのでなく、それが社会にとり、人間にとりどの様な「悪」であり、そうであるが故に社会的排除の対象となってきたのか。―そうしたいみでの「犯罪」のとらえかえしは、死刑囚の「事件」に対する責任をより明確にする事につながり、また《被害者感情》をより深く考えることにもつながっていくだろう。 死刑廃止運動が、全国的な大衆運動の段階に入ろうとしている今、このようないみでの本格的な″論議″が必要になってきていると思うのである。
一、
さる6月11日に発足した死刑執行停止連絡会議の代表世話人である菊田幸一氏が、三一書房より『死刑―その虚構と不条理』と題する著書を出した。私は執行停止連の一部の傾向には批判的だが、菊田氏自身に関して特にこれといった先入感はない。勿論、停止連による死刑執行停止全国署名は全面的に支持し、参加協力している一人である。そのこととは別に、菊田氏の本著は現在の死刑廃止に関する諸問題を全面的に提示しており、またそこでどの様な議論がなされているかについて、最先端の水準を知りうるものである。
それゆえ、本著を批判的に(断わるまでもないが、「批判」とは「非難」ではない。それは全ゆる論述に接する、基本的な姿勢である。多くの人が「批判」と「非難・否定」をとりちがえたまま「批判」をしたりうけたりしている現状があるが、逆に「無批判に」というのがどういう態度かを考えれば「批判」の真意はよく分ろう)読みこむことは、死刑廃止をめぐるわれわれの観念を点検しなおすことにつながるであろう。
まず「序」の冒頭において、我々は著者の基本的な死刑観に接する。
『わたくしは、死刑は道徳的な「罪悪」であると考えている』(P1)
異和感を覚えた。私は「犯罪」は「罪」=人間による過ちであるが「死刑」は「悪」=本来的にあってはならないもの、と考えている。「死刑」を「罪」と同一地平に論じることが、「罪」の重さゆえの「死刑」、という論理を根底的に批判しうるかどうか。-この「直感」が妥当かどうかは、読みすすむ中ではっきりしてくるだろう。 『数万年におよぶ人類の歴史において死刑は残された人間の弱さの象徴であり、未開社会の遺物である。』(P1・2~3行)=傍点筆者。
さきの「直観」は、更に少し具体的なものになる。著者は〝人間の弱さ″と″未開社会″を否定的概念とし、それを用いて死刑を批判している。しかし、人間の歴史において、一貫して〝人間の弱さ″の発露であったものこそ、その時々の国家社会によって「犯罪」として処罰されてきた行為そのものではなかったろうか。
さらに「犯罪」は、動物的=未開的であるが故に、〝社会の進歩″を害するものとして、抹殺されてきたのだ。 実際には、未開社会とはまだ「死刑」の存在しない社会であった。国家が発生する以前の氏族制社会における「血の復讐」は、加害者(氏族)と被害者(氏族)の直接的争闘であって「刑罰」ではない。そうであるが故に、それはしばしば、双方の話し合いで解決することがあった。国家が発生し、人間同士の矛盾対立に国家が介入し「刑罰」によって対処するようになって以降、加害者と被害者は決して出会うことのない両極に分断されていったのだ。
未開社会の〝血の復讐″と死刑制度の根本的な違いは、前者は被害者(死者)の魂を鎮めるための同胞の〝義務″であり当時の彼らの死生観においてあくまで当事者としての解決方法であるのに対し、後者―死刑制度は「第三者」たる国家が介入してもう一方の当事者にも「死」を与えるのであって、死刑の実行者たる国家と、双方の当事者、というところに軸をすえてみるならば、一方には死者に加うるに刑死者、ではこれに対応する国家自身にとってそれは如何なる行為か、という問題が考えられねばならないのである。そこにあるのは、被害者(死者)に対する遺族の「義務」ではなく、その遺族にとって代って殺害をなしうる国家の「権利」=刑罰権であり、その権利を行使することによって国家に与えられる権力支配の正当性、という″漁夫の利″なのだ。
つまりそれは、国家支配に正当性を与えるひとつのカラクリ(イデオロギー)であって「罪」=過ちではない。矯正の対象たる「犯罪」と同一の次元で語られるべきものではなく、全ゆる処罰を越えた「権利」としての殺人行為であるといういみで、国家による「侵略」行為と同一レベルの「悪」ということがいえるのである。そのいみで、「序文」末尾近くの次の様な言い方は、「死刑制度」のカラクリを支える「国家」への問いかけを放棄したもの、といわざるをえない。
『…その犯罪者よりも品位を落してまで国家が人を殺すことが許されてはならない』(PI.8行) 死刑廃止に、様々な主張の仕方があってもそれは構わないと思う。然し、人々が「犯罪」を指弾すると同一の価値概念で「死刑」を断罪する時、それを強調すればする程、死刑存置の側の論理をも部分的に強調している事になるのである。いま必要なのは、その価値概念そのもののとらえ直しなのだ。 死刑廃止とは、未来のわれわれの人間観の問題なのである。
*エングルス「家族・私有財産・国家の起源」 戸原訳、岩波文庫P127
二、
本著は序文と末尾の「付・わたしの死刑廃止論」をのぞいて十章に分れ、一、抑止力とならない死刑 二、世論は死刑を支持しているか 三、死刑を待つ死刑囚 四、死刑執行の実態 五、死刑執行人の人権 六、教誨師と死刑囚 七、法的根拠に疑問のある死刑執行 八、死刑は日本国憲法に違反する 九、死刑と無期には限界がない、「意思」「責任」と死刑となっている。
死刑の「犯罪抑止力」の問題については、すでに″論議の段階ではない″といってさしつかえないだろう。それは数多くの研究、統計によって、根拠のないものであることが論証されてきた。一九八〇年八月の第六回犯罪防止と犯罪者の処遇に関する国連会議のワーキングーペーパーでは、「人々に、死刑の犯罪抑止効果が不確実であることを啓蒙することは…政府、業界、マスメディアその他の公共団体の重要な義務であると思われる」とのべられており、この義務を一切遂行しようとしない日本政府が、その不確実な「抑止効果」への国民のバク然とした依存を根拠に、死刑を強行しようとしている事実そのものを、全ゆる実践の場で公表し、糾弾していかなければならない。
「世論」の問題は、その″不確かさ″一般の問題ではなく、一般社会の人々が如何に多くの真実を隠され、虚偽の情報を(主としてマスコミ報道によって)流され、その認識を操作されているか、という問題である。権力との具体的な闘いが重要なのは、宣伝能力では圧倒的に非力なわれわれが、道理をもって闘うことによって、権力側の非道な本質を多くの人々の眼にみえる形で引き出し、それを支配権力自らの手によって「宣伝」させることができるからである。
『世論とは何であるか、に即答することは正直いって困難であるが、少なくとも「死刑」という悪に対応できるほどの確固たる基盤を有していないことは明らかである。かくして、われわれは、このような「世論」を問題にするような「死刑」そのものの否定論から「世論」そのものを指導していくことが許されねばならないし、また必要であると考える』(P52)という論述を否定するつもりはないが、社会制度の変革は、真実をつかんだ人民大衆じしんが、統計的数字で括られた「世論」という枠組みそのものを突破し、生きた主体として活性化していく高揚の中でこそ可能であるという事が、強調されなくてはならないだろう。
そして人民大衆にとってその解放であるのは、死刑制度か、死刑廃止か。それに究極の解答を与えるものこそが「被害者の問題」である。
「被害者感情」ということが、どれだけ掘り下げられているだろうか。
いわゆる「被害者感情」とは加害者に対する憎悪の感情である。それは肉親を殺された悲しみと怒りに発している。その悲しみ、怒りは、(勿論それが我々自身に起った場合のことも含めて)絶対的に否定できない。問題は、その悲歎が直接の加害者のみに向かい、これを死刑にせよと叫ぶ感情そのものも「絶対的」とされることである。
『「三人も殺した男です。同情の余地はまったくないはずです。母もあんなやつは早く死刑にしてもらわなくっちゃと口癖のようにいっています」(福岡保険金殺人事件高裁判決に対する被害者遺族の声。『読売新聞』一九八四年九月四日夕刊)このような声に真剣に耳を傾けなければならない。』(P59)と著者はいう。
しかしその遺族の悲歎に正面から向き合う時、その怒りが加害者だけに向かっているかぎり、その怒りはどこまでいっても満たされぬまま、遺族自身の心をせめさいなむのみなのだという事実をも見すえなければならない。
『しかし私見では、その気持ちを無視してはならないと考えるが、死刑という極刑制度を存置しておいて抑止力で人殺しをやめさせるといったような架空の根拠なき手段ではなく、死刑のない社会においてでなければ、人の生命を大事にする人間を育てることはできないのだという思想を国民の間に満たさせることがなければならない』(同)これ自体にも異論はないが、ここで問題になっているのは将来の解決策ではなく、被害者遺族の悲しみ、怒りをどうするのか、という事だ。
『よくいわれる言葉に「もし、自分の子供や家族が許されても犯人を許せるか」というのがある。……しかし、事件後かりに三年も四年もたってピストルを渡され、殺してもよいといわれて殺すことのできる人が何人いるだろうか。』(P57) これも問題のすりかえである。仮に何年たとうとピストルを渡されたら殺すという人がいても、死刑制度とは別問題である。 問題は、肉親を奪われた悲しみ、怒りはどこに向けられるべきか、という事でなければならないだろう。
太古の〝血の復讐”であがないえた様な、殆んど純粋に個対個の問題として、現代の殺人はあるのではない。何故愛しい家族が突如として無残に殺されなければならなかったか。その答えは、「犯人」を形成したぼう大な社会的諸関係の総体をみないと分らないのだ。
「もし、自分の子供が……」への答えはまず、「では、他人の子供ならよいのか」という事でなければならない。
げんに毎年、多くの子供たちが、残酷な殺人事件の犠牲となっているのである。我々は子供たちに、安全な、のびのびと成長できる《社会》を与えてやることも出来ないでいる。加害者は、かつてはもっと別の隠蔽された形において抑圧された子供だったであろう。殺し、殺される関係が全面化している殺人社会。それは殺された者の怒りが、その様な社会の在り様とそれを成り立たせるカヘと向かわない事によって、再生産される。「犯人」のみに向かう限りどこまでいってもあきたらぬ怒り、憎しみであるゆえに、それをまた裁判官は最大限に利用し、死刑判決の絶対的な理由とするのである。
死刑制度とは、イデオロギーの問題である。われわれ自身の、「犯罪」に対する偏見、そこからくるところの「裁判・刑罰制度の自明さ」という先入見のなかで、われわれは被害者遺族に対しても、真剣に向き合うことなく、その悲しみ・怒りが「犯人を殺せ」という行き場のない怒りとして、権力にからめ取られていくのを「自明のこと」とし、そのことによって権力に「支配の正当性」を附与するという、死刑制度のイデオロギー性に負けつづけてきたのである。
本書の第三~六章、死刑と死刑囚の現実をとりまく問題は、豊富な資料が引用され、説得力、迫力に富む内容となっている。またそれ以下の法的問題に関しては、法律の専門的議論に筆者は及ぶべくもない。ただ終章の「意思」「責任」の問題については、死刑囚自身の責任―反省の問題も含むので、これについては稿を改めて論じたい。
(抜粋以上)
ちょっと管理人がひっかかってしまった部分
>「もし、自分の子供が……」への答えはまず、「では、他人の子供ならよいのか」という事でなければならない。
…うっ…う…うん…(´д`ι)