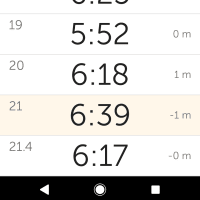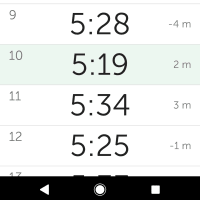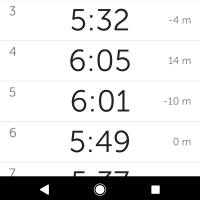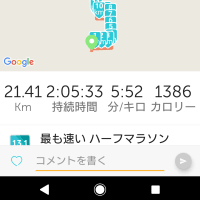http://shuchi.php.co.jp/article/1535
「心身脱落」「只管打座」 ~ 道元のたどりついた悟りとは
2013年07月18日 公開
ひろさちや
《『新訳 正法眼蔵』より》
○道元の開悟
『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』は道元の主著です。そして未完の大著です。
彼は、自分のライフ・ワークとして、全百巻の『正法眼蔵』を制作するつもりでいました。建長5年(1353)に道元が執筆した「八大人覚」の巻の奥書に、その構想が明かされています。だが、その構想は残念ながら実現しません。なぜなら、彼はその年の8月に、54歳で示寂しているからです。
彼の死によって、『正法眼蔵』はどうなったのでしょうか? しかし、それを語る前に、われわれは道元の生涯を瞥見しておきましょう。
道元は、正治2年(1200)1月、京都の貴族の名門に生まれました。近年は異説も出されていますが、従来の説によるなら、父は内大臣久我通観、母は関白太政大臣藤原基房の娘伊子で、彼は3歳にして父を、8歳にして母を失いました。
たぶんそのことも理由になるのでしょう、道元は14歳で比叡山に上り、出家しました。貴族すなわち政治の世界から、宗教の世界へと身を転じたのです。
だが、比叡山に入ってすぐに、彼は1つの疑問に逢着します。
仏教においては、
「人間はもともと仏性(仏の性質)を持ち、そのままで仏である」
と教えているはずだ。それなのに、われわれはなぜ仏になるための修行をせねばならないのか?
そのような疑問です。
彼はこの疑問を比叡山の学僧たちにぶつけますが、誰も満足な答えを与えてくれません。そこで彼は比叡山を下りて、諸方の寺々に師を訪ねて歩きます。それでも求める答えが得られないので、ついに彼は宋に渡ります。貞応2年(1223)、道元が24歳のときでした。
けれども、宋においても、なかなかこれといった師に出会えかった。道元は諦めかけて日本に帰ろうとしますが、そのとき、天童山に新たに如浄禅師が人住されたことを聞き、天童山を再訪します。じつは道元は、中国に来て最初に天童山に行ったのですが、そのときは良師に巡り合えなかったのです。
如浄禅師に会った道元は、
〈この人こそ、自分が求めていた師である〉
と直感し、如浄の下で参禅し、豁然大悟しました。宝慶元年(1225)、彼が26歳のときでした。ただし、宝慶元年は中国の元号です。道元が大悟するきっかけは、大勢の憎が早暁坐禅をしているとき、1人の雲水が居眠りをしていたのを如浄が、
「参禅はすべからく身心脱落なるべし。只管に打睡していん恁麼(いんも)を為すに堪えんや」
と叱ったことでした。何のために坐禅をするかといえは、身心脱落のためだ。それを、おまえはひたすら(只管)居眠りばかりしている。そういうことで、どうなるというのだ!? そういう意味の叱声です。そして如浄は、その僧に警策を加えました。
その瞬間、道元は悟りを得たのです。自分に向かって言われたのではない言葉、他の雲水を叱るために如浄禅師が発した言葉が触媒になって、道元に悟りが開けたのてす。
おもしろいといえばおもしろい、皮肉といえばすごい皮肉ですよね。
○「身心脱落」
ともあれ、道元が悟りを開いたきっかけは、彼が聞いた、
-身心脱落-
という言葉てす。そして、まちがいなくこの言葉が、道元思想のキイ・ワードになります。ある意味で、この言葉さえ分かれば、道元の思想が理解できるのです。
では、「身心脱落」とは、どういうことでしょうか……?
これは、簡単にいえば、
-あらゆる自我意識を捨ててしまうことだ-
と思えばいいでしょう。われわれはみんな、〈俺が、俺が……〉といった意識を持っています。〈わたしは立派な人間だ〉〈わたしは品行方正である〉と思うのが自我意識です。一方で、〈わたしなんて、つまらない人間です〉というのだって自我意識。自我意識があるから、自分と他人をくらべて、優越感を抱いたり、劣等感にさいなまれたりします。そういう自我意識を全部捨ててしまえ! というのが「身心脱落」です。もちろん、意識ばかりでなしに、自分の肉体だって捨ててしまうのです。
わたしは、自我意識というものを角砂糖に譬えます。わたしというのは角砂糖です。そして他人も角砂糖。わたしと他人との接触は、角砂糖どうしのぶつかり合いです。それで角砂糖が傷つき、ボロボロに崩れます。修復不可能なまでに崩れることもありますが、普段は崩れた角砂糖をなんとか修復して、それて「自我」を保っているのてす。
道元の身心脱落は、そんな修復なんかせず、角砂糖を湯の中に放り込めばいいじゃないか、というアドヴァイスです。
湯の中というのは、悟りの世界です。
わたしという全存在を、悟りの世界に投げ込んでしまう。それが身心脱落てす。そうすれば、わたしたちには迷いもなくなり、苦しみもなくなります。
いや、そういう言い方はおかしい。迷いがなくなり、苦しみがなくなるのではなしに、わたしたちは大きな悟りの世界の中でしっかりと迷い、どっぷりと苦しめばいいのです。迷いや苦しみをなくそうとするから、かえってわたしたちは迷いに迷い、苦しみに苦しむのです。そんな馬鹿なことを考えず、迷っているときはただ迷う、苦しいときはただ苦しむ。それこそが身心脱落にほかなりません。
けれとも身心脱落は自己の消滅ではありません。角砂糖が湯の中に溶け込んだとき、角砂糖が消滅したのではないのです。ただ角砂糖という状態 - それが〈俺が、俺が……〉といった自我意識です - でなくなったたけです。砂糖は湯の中に溶け込んでいるように、自己は悟りの世界に溶け込んでいるのです。身心脱落とはそういうことです。
だとすれば、道元が悟りを開いた - といった表現はちょっとよくない。道元は身心脱落して、悟りの世界に溶け込んだのです。道元の悟りというものがそういうものだということを、読者は忘れないでください。
○仏が修行をしておられる
そして、ここのところに、若き日に道元が抱いた疑問に対する解答があります。
われわれは、仏教の修行者は悟りを求めて修行すると思っています。若き日の道元もそう考え、われわれに仏性があるのに、なぜ悟りを求めてわざわざ修行しないといけないのか、と疑問に思ったのです。
だが、道元が達した結諭からいえば、それは逆なんです。「悟り」は求めて得られるものではなく、「悟り」を求めている自己のほうを消滅させるのです。身心脱落させるのです。そして、悟りの世界に溶け込む。それがほかならぬ「悟り」です。道元は、如浄の下でそういう悟りに達したのです。
だから、わたしたちは、悟りを得るために修行するのではありません。
わたしたちは悟りの世界に溶け込み、その悟りの世界の中で修行します。悟りを開くために修行するのではなく、悟りの世界の中にいるから修行できるのです。「悟り」の中にいる人間を仏とすれば、仏になるための修行ではなく、仏だから修行できる。それが道元の結論です。
わたしたちはついつい、これはいけないことだと知っていながら、でもこれぐらいのことはしてもいいだろう……と思ってしまいます。それは自分を甘やかしているのです。その背後には、自分は仏ではなしに凡夫なんだという気持ちがあります。しかし、自分が仏だと自覚すればどうでしょうか? もちろん、仏といっても、悟りの世界に飛び込んだばかりの新参の仏、赤ん坊の仏です。しかし、仏だという自覚があれば、〈自分は仏なんだから、こういうことはしてはいけない〉と考えて、悪から遠ざかることができます。それが、仏になるための修行ではなく、仏だからできる修行です。
道元はそういう結論に達したのです。
そして彼は、その結論を、
- 修証一等・修証不二・修証一如・本証妙修 -
と表現しました。修行と悟り(証)が一つであって別のものではない。“本証”とは、われわれが本来悟っていることであり、その悟りの上で修行するのが “妙修”です。
そうだとすれば、坐禅というものは、悟りを求める修行であってはならないのです。いや、そもそもわたしたちが何のために仏教を学ぶかといえば、
- 仏らしく生きるため -
です。その意味では、悟りを楽しみつつ人生を生きる。それがわれわれの仏教を学ぶ目的です。
ですから、坐禅が、禅堂に坐ることだけをいうのであれば、道元はそんなものは必要ないと言うでしょう。道元にとっては、行住坐臥(歩き・止まり・坐り・臥す)のすべてが坐禅でなければならないのです。日常生活そのものが坐禅です。食べるのも坐禅。眠るのも坐禅。いわば仏が食事をし、仏が眠るのが坐禅です。そのことを道元は、
- 只管打坐(あるいは祇管打坐とも表記されます)-
と呼んでいます。“只管”“祇管”とは宋代の口語で、「ひたすらに」といった意味。ただひたすらに坐り抜く、眠り抜き、歩き抜く、その姿こそが仏なのです。仏になるための修行ではなしに、仏が修行しておられるのです。道元がたどり着いた結論はそのようなものでした。
ひろさちや
(ひろ・さちや)
1936年、大阪府生まれ。東京大学文学部印度哲学科卒業。同大学院人文科学研究科印度哲学専攻博士課程修了。1965年から85年まで気象大学校教授を務める。膨大で難解な仏教思想を、逆説やユーモアを駆使してわかりやすく説く語り口は、年齢・性別を超えて幅広い人気を得ている。
著書に『釈迦とイエス』『釈迦物語』(以上、新潮社)、『ひろさちやの「維摩教」講話』(春秋社)、『がんばらない、がんばらない』『「がんばらない」お稽古』(以上、PHP研究所)など多数。
--------------------------------------------------------------------------------
<書籍紹介>
[新訳]正法眼蔵
迷いのなかに悟りがあり、悟りのなかに迷いがある
道元 著
ひろさちや 編訳
本体価格 950円
曹洞宗の開祖・道元が、長い年月をかけ、多くの人々に仏教を正しく読み取るための智慧(眼)をまとめた書。
「心身脱落」「只管打座」 ~ 道元のたどりついた悟りとは
2013年07月18日 公開
ひろさちや
《『新訳 正法眼蔵』より》
○道元の開悟
『正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)』は道元の主著です。そして未完の大著です。
彼は、自分のライフ・ワークとして、全百巻の『正法眼蔵』を制作するつもりでいました。建長5年(1353)に道元が執筆した「八大人覚」の巻の奥書に、その構想が明かされています。だが、その構想は残念ながら実現しません。なぜなら、彼はその年の8月に、54歳で示寂しているからです。
彼の死によって、『正法眼蔵』はどうなったのでしょうか? しかし、それを語る前に、われわれは道元の生涯を瞥見しておきましょう。
道元は、正治2年(1200)1月、京都の貴族の名門に生まれました。近年は異説も出されていますが、従来の説によるなら、父は内大臣久我通観、母は関白太政大臣藤原基房の娘伊子で、彼は3歳にして父を、8歳にして母を失いました。
たぶんそのことも理由になるのでしょう、道元は14歳で比叡山に上り、出家しました。貴族すなわち政治の世界から、宗教の世界へと身を転じたのです。
だが、比叡山に入ってすぐに、彼は1つの疑問に逢着します。
仏教においては、
「人間はもともと仏性(仏の性質)を持ち、そのままで仏である」
と教えているはずだ。それなのに、われわれはなぜ仏になるための修行をせねばならないのか?
そのような疑問です。
彼はこの疑問を比叡山の学僧たちにぶつけますが、誰も満足な答えを与えてくれません。そこで彼は比叡山を下りて、諸方の寺々に師を訪ねて歩きます。それでも求める答えが得られないので、ついに彼は宋に渡ります。貞応2年(1223)、道元が24歳のときでした。
けれども、宋においても、なかなかこれといった師に出会えかった。道元は諦めかけて日本に帰ろうとしますが、そのとき、天童山に新たに如浄禅師が人住されたことを聞き、天童山を再訪します。じつは道元は、中国に来て最初に天童山に行ったのですが、そのときは良師に巡り合えなかったのです。
如浄禅師に会った道元は、
〈この人こそ、自分が求めていた師である〉
と直感し、如浄の下で参禅し、豁然大悟しました。宝慶元年(1225)、彼が26歳のときでした。ただし、宝慶元年は中国の元号です。道元が大悟するきっかけは、大勢の憎が早暁坐禅をしているとき、1人の雲水が居眠りをしていたのを如浄が、
「参禅はすべからく身心脱落なるべし。只管に打睡していん恁麼(いんも)を為すに堪えんや」
と叱ったことでした。何のために坐禅をするかといえは、身心脱落のためだ。それを、おまえはひたすら(只管)居眠りばかりしている。そういうことで、どうなるというのだ!? そういう意味の叱声です。そして如浄は、その僧に警策を加えました。
その瞬間、道元は悟りを得たのです。自分に向かって言われたのではない言葉、他の雲水を叱るために如浄禅師が発した言葉が触媒になって、道元に悟りが開けたのてす。
おもしろいといえばおもしろい、皮肉といえばすごい皮肉ですよね。
○「身心脱落」
ともあれ、道元が悟りを開いたきっかけは、彼が聞いた、
-身心脱落-
という言葉てす。そして、まちがいなくこの言葉が、道元思想のキイ・ワードになります。ある意味で、この言葉さえ分かれば、道元の思想が理解できるのです。
では、「身心脱落」とは、どういうことでしょうか……?
これは、簡単にいえば、
-あらゆる自我意識を捨ててしまうことだ-
と思えばいいでしょう。われわれはみんな、〈俺が、俺が……〉といった意識を持っています。〈わたしは立派な人間だ〉〈わたしは品行方正である〉と思うのが自我意識です。一方で、〈わたしなんて、つまらない人間です〉というのだって自我意識。自我意識があるから、自分と他人をくらべて、優越感を抱いたり、劣等感にさいなまれたりします。そういう自我意識を全部捨ててしまえ! というのが「身心脱落」です。もちろん、意識ばかりでなしに、自分の肉体だって捨ててしまうのです。
わたしは、自我意識というものを角砂糖に譬えます。わたしというのは角砂糖です。そして他人も角砂糖。わたしと他人との接触は、角砂糖どうしのぶつかり合いです。それで角砂糖が傷つき、ボロボロに崩れます。修復不可能なまでに崩れることもありますが、普段は崩れた角砂糖をなんとか修復して、それて「自我」を保っているのてす。
道元の身心脱落は、そんな修復なんかせず、角砂糖を湯の中に放り込めばいいじゃないか、というアドヴァイスです。
湯の中というのは、悟りの世界です。
わたしという全存在を、悟りの世界に投げ込んでしまう。それが身心脱落てす。そうすれば、わたしたちには迷いもなくなり、苦しみもなくなります。
いや、そういう言い方はおかしい。迷いがなくなり、苦しみがなくなるのではなしに、わたしたちは大きな悟りの世界の中でしっかりと迷い、どっぷりと苦しめばいいのです。迷いや苦しみをなくそうとするから、かえってわたしたちは迷いに迷い、苦しみに苦しむのです。そんな馬鹿なことを考えず、迷っているときはただ迷う、苦しいときはただ苦しむ。それこそが身心脱落にほかなりません。
けれとも身心脱落は自己の消滅ではありません。角砂糖が湯の中に溶け込んだとき、角砂糖が消滅したのではないのです。ただ角砂糖という状態 - それが〈俺が、俺が……〉といった自我意識です - でなくなったたけです。砂糖は湯の中に溶け込んでいるように、自己は悟りの世界に溶け込んでいるのです。身心脱落とはそういうことです。
だとすれば、道元が悟りを開いた - といった表現はちょっとよくない。道元は身心脱落して、悟りの世界に溶け込んだのです。道元の悟りというものがそういうものだということを、読者は忘れないでください。
○仏が修行をしておられる
そして、ここのところに、若き日に道元が抱いた疑問に対する解答があります。
われわれは、仏教の修行者は悟りを求めて修行すると思っています。若き日の道元もそう考え、われわれに仏性があるのに、なぜ悟りを求めてわざわざ修行しないといけないのか、と疑問に思ったのです。
だが、道元が達した結諭からいえば、それは逆なんです。「悟り」は求めて得られるものではなく、「悟り」を求めている自己のほうを消滅させるのです。身心脱落させるのです。そして、悟りの世界に溶け込む。それがほかならぬ「悟り」です。道元は、如浄の下でそういう悟りに達したのです。
だから、わたしたちは、悟りを得るために修行するのではありません。
わたしたちは悟りの世界に溶け込み、その悟りの世界の中で修行します。悟りを開くために修行するのではなく、悟りの世界の中にいるから修行できるのです。「悟り」の中にいる人間を仏とすれば、仏になるための修行ではなく、仏だから修行できる。それが道元の結論です。
わたしたちはついつい、これはいけないことだと知っていながら、でもこれぐらいのことはしてもいいだろう……と思ってしまいます。それは自分を甘やかしているのです。その背後には、自分は仏ではなしに凡夫なんだという気持ちがあります。しかし、自分が仏だと自覚すればどうでしょうか? もちろん、仏といっても、悟りの世界に飛び込んだばかりの新参の仏、赤ん坊の仏です。しかし、仏だという自覚があれば、〈自分は仏なんだから、こういうことはしてはいけない〉と考えて、悪から遠ざかることができます。それが、仏になるための修行ではなく、仏だからできる修行です。
道元はそういう結論に達したのです。
そして彼は、その結論を、
- 修証一等・修証不二・修証一如・本証妙修 -
と表現しました。修行と悟り(証)が一つであって別のものではない。“本証”とは、われわれが本来悟っていることであり、その悟りの上で修行するのが “妙修”です。
そうだとすれば、坐禅というものは、悟りを求める修行であってはならないのです。いや、そもそもわたしたちが何のために仏教を学ぶかといえば、
- 仏らしく生きるため -
です。その意味では、悟りを楽しみつつ人生を生きる。それがわれわれの仏教を学ぶ目的です。
ですから、坐禅が、禅堂に坐ることだけをいうのであれば、道元はそんなものは必要ないと言うでしょう。道元にとっては、行住坐臥(歩き・止まり・坐り・臥す)のすべてが坐禅でなければならないのです。日常生活そのものが坐禅です。食べるのも坐禅。眠るのも坐禅。いわば仏が食事をし、仏が眠るのが坐禅です。そのことを道元は、
- 只管打坐(あるいは祇管打坐とも表記されます)-
と呼んでいます。“只管”“祇管”とは宋代の口語で、「ひたすらに」といった意味。ただひたすらに坐り抜く、眠り抜き、歩き抜く、その姿こそが仏なのです。仏になるための修行ではなしに、仏が修行しておられるのです。道元がたどり着いた結論はそのようなものでした。
ひろさちや
(ひろ・さちや)
1936年、大阪府生まれ。東京大学文学部印度哲学科卒業。同大学院人文科学研究科印度哲学専攻博士課程修了。1965年から85年まで気象大学校教授を務める。膨大で難解な仏教思想を、逆説やユーモアを駆使してわかりやすく説く語り口は、年齢・性別を超えて幅広い人気を得ている。
著書に『釈迦とイエス』『釈迦物語』(以上、新潮社)、『ひろさちやの「維摩教」講話』(春秋社)、『がんばらない、がんばらない』『「がんばらない」お稽古』(以上、PHP研究所)など多数。
--------------------------------------------------------------------------------
<書籍紹介>
[新訳]正法眼蔵
迷いのなかに悟りがあり、悟りのなかに迷いがある
道元 著
ひろさちや 編訳
本体価格 950円
曹洞宗の開祖・道元が、長い年月をかけ、多くの人々に仏教を正しく読み取るための智慧(眼)をまとめた書。