今日は西原医院で勉強会の講師をさせていただきました。久美浜から来てくれたジョージ君もすばらしい山田の案山子レクを教えてくれました。ありがとう!ジョージ
メデシン仙人の活躍する「生活リハビリの達人」への道 掲載されましたので読んでみてください。
Mission5 待テバ介護ノ日和アリ
業務がひと段落して、タバコを吸っていると、灰皿から立ち昇る煙の中から仙人が現れました。
メデシン仙人
新人介護職の「僕」になれなれしく話しかけてくる自称、生活リハビリの達人。
動作を見極める目、介助する腕、やる気を引出し支える心、このメ・ウデ・シンが名前の由来。
的確にアドバイスしてくれるが、だじゃれがうっとおしい。
「今回は介助の仕方について考えてみるぞ。さぁ、この写真を見るのじゃ」
差し出された写真には職員が二人がかりでお年寄りを持ち上げて、車椅子に移している写真がありました。
写真)お年寄りが二人がかりで「せーの、よいしょ!」と持ち上げられている場面
仙人は聞きました。「これみて、お前はどう思う?」
「たまに、ぼくもこうやってます。どこかいけないんですかね?」
「いや、もちろん他に方法がなくて、こうやって介助することもあるじゃろう。ワシが言いたいのは、どこまで力が残っているか、こうやって持ち上げる前に職員がしっかり確かめたのか?ということじゃ」
「介護現場は忙しい、時間がない、人手が足りない、そんな事情がある。それは確かに由々しき問題じゃ。しかし、だからといってお年寄りの残っている力を無視した関わりは避けねばならぬ。ひょっとしたら、職員の都合でこうなってないか?
そういって一枚メモを手渡されました。
そこには耳の痛いことが書かれていました。
時間がない→動きを待たずに抱える→お年寄り、力を使わない→体力低下→さらに介助が必要になる→時間がない→・・・
「わー、ぐるぐる回っていきますね」
「な、これ悪循環じゃろ。こうやっているうちに、お年寄りが元気を失うわ、業務はさらにきつうなるわ、という施設ができあがるのじゃ。介護はきつい、給料が安い、職員が消える、3Kだといわれてしまっても仕方がないのう。」
「ジュウゼロ介護」にお別れを
「わしはこの写真の介護を『ジュウゼロ介護』と呼んでおる。」
「ジュウゼロ介護???どういう意味ですか?」
「介助をする時に職員の力が10(ジュウ)、お年寄りの力が0(ゼロ)になってしまうことじゃ。思い当たる節はないか?このジュウゼロをやめていくにはどうしたらいい?」
「うーん、難しいな。ゼロじゃなくてイチでもお年寄りさんに力を出してもらえたらと思います。」
「ご名答!ワシはお年寄りの力を適切に引き出して、段階的に変わっていく介助が理想のリハビリ介護だと考えておる。」
0→3→5→6・・・とお年寄りの力が段階的に増えていく??
「どうすればこのように変えていけるんですか?」僕は知りたくて聞きました。
「そうじゃな。そのためにはゆっくり始まるお年寄りの動きを『待つ』ことが大切じゃ。『待てば海路の日和あり』という言葉をもじって『待てば介護の日和あり』とワシは言っておる。『立ちますよ、せーのっ』なんて言いながら、職員のペースでお年寄りを引っ張り上げているのをよくみかけるのお。お年寄りの動きは、もっとゆ~っくりと始まるんじゃ。それを待てん奴が多すぎる!最近の若い奴はとくに、待てんのう。」
そして遠い目をしながら仙人は語り始めました。
「まずケータイがあるから、ガールフレンドとすぐに連絡がとれるのもイカン!イチャイチャとメールしやがって!ワシの時代はな、ありったけの小銭を持って、寒い夜に公衆電話に走ったんじゃぞ。そしたら相手のお父さんが出て、『娘とはどういう関係だ』って聞かれて、ビビったこともあった。なんとか彼女と待ち合わせして、彼女のことを今か今かと待ち侘びて、待ちくたびれて、待ちぼうけ・・・。狂おしいほど待ち焦がれたんじゃ!その彼女ももう去ってしまった。おまえにこの気持ちがわかるか!」
話しているうちに、興奮してきた仙人は僕の首を両手で締めて、ものすごい力でぐいぐい振り回してきました。
「わか、わかったから、やめてください。」僕はありったけの力で仙人を押しのけました。「殺す気ですか! ぜぇぜぇ」ぼくは必死で声をあげました。
仙人は「あ、ワシ、えらい興奮してしもうた」と我に返ったようです。
「もう勘弁してくださいよ!こっちはあなたのフラレ話を聞かされた上、首を絞められて殺されかけたんですよ!」
仙人は全然悪びれた様子もなく、明るい声で聞いてきました。「で、ワシ、何の話をしとったかの」
「あのですね(ちょっとは謝らんのか、この仙人)。我々若者が待てないとか、どーたらと」
「お、そうそう」仙人は目を輝かせて言いました。「環境を整えたり、介助の腕を磨いたりすることも大事だが、なによりも、そのかすかな動きの始まりを『待つ』こと、それが大切じゃという話をしておったのじゃ!」
「さっきの写真の人はどうするんですか?」僕は写真の二人がかりで持ち上げられていたお年寄りのことが気になっていました。
「そうじゃな。さっきの人も残った力を引き出して、ジュウゼロからシチサン、シブロクと劇的に変化をしていったのじゃ」
「ど、どうやったんですか?教えてください」
僕は前のめりになって仙人に言いました。仙人はニタリと笑って「お前、そんなに知りたいか」「はい、知りたいです」仙人は顔を近づけて、勝ち誇ったように言いました。「待て!次号」
・・・この仙人、どうしても『待つ』大切さを教えたいようです。
参考文献
「生活リハビリ術」 松本健史 ブリコラージュ (2010)
拙著『生活リハビリ術』では、試行錯誤のなかで思わず笑いがこみあげる、気持ちがほっこりするようなエピソードを満載しています。本書の「時ニハ刑事ノヨウニ」(p110)や 「尿意表現ハ自由ダ!」(p34)などをぜひ読んでみてください。きっと、明日からのケアの種(タネ)にしていただけることと思います。













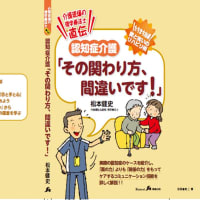
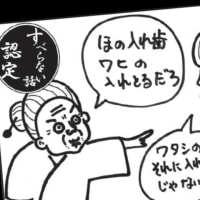







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます