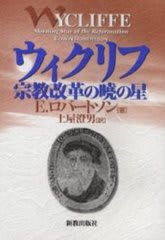
コメニウスが所属していた「モラヴィア兄弟教団(チェコ兄弟教団)」について、もう少し触れておきましょう。
宗教改革運動といえば、16世紀のドイツのルターやジュネーヴのカルヴァンが有名ですが、腐敗したカトリックを批判し、キリスト教本来の精神に立ち戻ろうという運動は、14世紀のイングランドにおいてすでに開始されていました。「モラヴィア兄弟教団」の起源は、このイングランドで開始された宗教改革に連なるものなのです。
14世紀のイングランドの司祭ジョン・ウィクリフ(1320頃~1384)は、当時のカトリックが聖書の教えからかけ離れていると主張し、ローマ教皇の権威を否定し、聖書の内容を唯一の権威としました。当時一部の特権的知識階級にしか読むことのできなかったラテン語の聖書を誰にでも読めるように英語に翻訳しました。当時の教会は国で最も富裕な土地所有者となっていた一方で農民はペストや飢餓に苦しんでいました。ウィクリフは教会財産を没収して、貧しい農民を苦しめていた税金の軽減に使うべきだと主張しました。
ウィクリフの晩年、1381年にロンドンでは農民蜂起ワット・タイラーの乱がおこりました。ワット・タイラーについては詳しいことはわかっていませんが、彼の指導者であるジョン・ポール司祭の次の言葉は有名です。
「アダムが耕し、イブが紡いだとき、誰がその時ジェントルマン(貴族)だったのか?」
ウィクリフとジョン・ポールとは直接の交際はなく、ジョン・ポールは独自に聖書に立ち戻れという主張をしていました。すでに貧窮に苦しんでいた農民たちを蜂起に駆り立てたのはひどい重税でした。聖書の中で述べられている平等主義は、農民たちの要求と結びついたのでした。
ウィクリフは農民たちの破壊行為を表立って支持することはありませんでしたが、農民たちの苦しみに同情的で、教会財産を貧しい農民の救済に充てることを主張し続けました。そのため彼は教鞭を執っていたオックスフォード大学から追放され、2年後に故郷で亡くなりました。
ウィクリフの死後、聖書を英語に翻訳することは禁じられ、ウィクリフの著作と英訳された聖書を読むことは死に値する異端とされました。彼の弟子たちが何人も火あぶりにされました。厳しい迫害を受けてウィクリフの信奉者は社会の最下層に身を潜めざるを得なくなりました。
一方、ボヘミアでも宗教改革運動が独自に始まっていました。その指導的役割を務めたヤン・フス(1369–1415)は、ウィクリフの著書を手に入れると、たちまちその影響を受け、ウィクリフの説を公然と擁護するようになりました。フスは、当時行われていた「免罪符」の販売を批判し、それを推進するローマ教皇を「反キリスト」と呼んで弾劾しました。フスは祖国を追放され、亡命生活を送っていましたが、その間も多くの著作を記しました。しかしながら、ローマ教皇によって「異端」と見なされ、自説を撤回しなかったために火あぶりにされてしまいました。
フスの死後、ボヘミアに広がった彼の信奉者たちは、神聖ローマ帝国の支配に抗して「フス戦争」(1415~1436)をおこしました。これが鎮圧された後もフス派の一部は生き残り「モラヴィア兄弟教団」を結成したのです。
コメニウスの父もこの「モラヴィア兄弟教団」の団員でした。父親を早くに失ったコメニウスは、宗教改革運動の歴史を背負ったこの教団の中で育ってきたのでした。
(鈴)



















