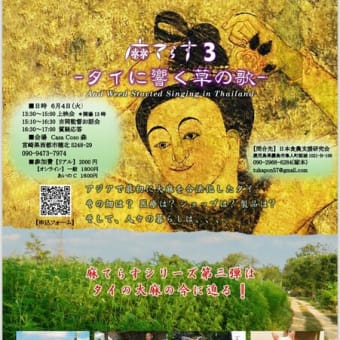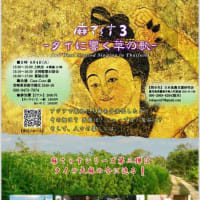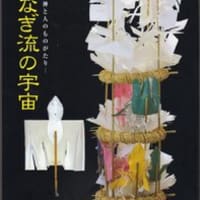ドクダミの花が盛りである。
純白の四枚の花びらの真ん中に細長い突起状の穂があり、小さな黄色い粒々が付いている。
白い花びらに見えるのは「苞(ほう)」であり、黄色い小さな点々が「花」だという。
花言葉を「白い追憶」といい、清楚な趣を持つ花に「ドクダミ」という名は似つかわしくないが、「毒矯み」すなわち毒を矯めるほど強い薬効をもつことがその語源だと知れば、納得できる。
古名は「シブキ=之布岐」といい、平安時代ごろにはすでにその名が用いられている。ドクダミと呼ばれるようになったのは、江戸期頃のことらしい。
生薬名を「十薬」という。十種の薬効を持つからだという。生葉をすりつぶして湿疹、かぶれなどに用いる。患部に貼り付けるとよい。乾燥させた「十薬」は、臭気も消え、その名にふさわしく薬効は利尿・緩下作用、血圧調整作用、毛細血管強化作用、消炎作用の4つの重要な作用があり、万病に対応する。主に煎じてお茶代わりに飲む。
アジアでは広く食材として用いられる。ベトナム料理ではザウゾプカー(rau giấp cá)と称し、主要な香草として重視されている。ただし、日本に自生している個体群ほど臭気はきつくないそうだ。
中国四川省・成都の四川料理では、根を水に晒してサラダに混ぜたものや、トウガラシなどの香辛料で辛い味付けをした和え物が美味しかった。四川省や雲南省では主に葉や茎を、貴州省では主に根を野菜として用いるという。

ここまでは少し調べればわかる。が、このドクダミの花をホワイトリカーに漬け込んでおくと、一年目には透明感のある琥珀色の「花酒」となることはあまり知られていない。
「花酒」とは、花びらを無色・無臭・透明のホワイトリカーに漬け込み、半年以上経過したところで布またはコーヒーの紙フィルターで漉して花びらを捨て、さらに半年寝かせたものをいう。
花びらの色、微妙な花の香り、花に含まれていた蜜などが混合し、芳醇な薬種が出来上がるのである。
一つ一つにどのような薬効があるかはまだ未調査だが、ほのかな酔いが、酒客を夢幻の境地へと誘ってくれることだけは確かである。
ちなみにここ二、三日、腹具合がよろしくなかったので、このブログに載せる写真を撮るために持ち出してきた、5年もののドクダミの花酒を少しだけ飲んでみた。味は、予想したほど濃くはなく、むしろさらりとした感じで、口当たりはやさしい。茎や葉のあの臭気や個性的な味から、濃厚な味と香りの薬酒を連想していたのだが、その予想は外れた。そして思わず酒量が増えた。朝から酔っ払うほど飲んだわけではないが、気のせいか、腹の具合は治まってきたようだ。これが薬効によるものか、自然治癒によるものかは、今回は保留しておこう。
器は古伊万里矢羽根文猪口。