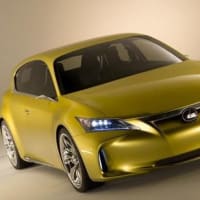米国でトヨタがいろいろとトラブルに巻き込まれている。「陰謀論」的な見方もある。米国政府や米国の一部にそうした思惑をもってそうした行動に出ている勢力が存在するのか否かは知らないが、今、米国にある種の「雰囲気」というか「動き」みたいなものが生まれつつあるのではないだろうか。
つまりそれはトヨタに対してだけではない、「排外」というやつだ。
かつて90年代の始めにも米国衰亡論が論じられ、米国内では国産品購入が推奨されたことがあった。これに似たやつだ。しかも、今後のそれは、かつて米国経済に回復とともに消えてしてまったものとは大きくことなる動きをみせることになり、日本企業はその大波に、おそらく今後当分続く円高の波とともに、翻弄されることになるだろう。つまり、米国は、自由貿易主義を手前勝手にかなぐり捨て、保護主義的な方向に走るだろう。建前では自由主義貿易の放棄なんて決して言うまい。でも、実質的には国内産業保護、外国企業・製品排除の方向に向かうだろう。なぜなら、米国景気は今後当分回復しないからだ。「本音と建前」は日本人の専売特許のように言われるが、実は、欧米人こそ狡猾にそれを使い分けるという事実を知るべきだ。表向きは耳触りのいい原理原則や理想を雄弁に語りながら、裏では一般の日本人には考えの及ばないようなえげつないことをするのが欧米人なのだ。
かといって、戦後の日米関係をすっかり清算してしまえば良いという単純なものではない。残念ながら、我が国にそうする力も準備もない。ただ、米国に対する見方、姿勢をもっと計算づくの怜悧なものに切り替えていく必要はある。おかしな対米幻想を抱かないことだ。米国から学ぶべきを学ぶのは良い。今後も続けようでないか。しかし米国は理想郷ではないし、「友人」でもない。あくまでも、互いの計算づく、狐と狸の化かしあいをしながらの、関係でしかないのだから、所詮。所詮、人種、宗教等の壁は越えられない。あの人たちは、我々とは「違う」、完全に理解しあうなんてはムリ。でも、まだ利用価値はある、ということなんだろうなあ・・。いかに米国が対外的な軍事的なプレゼンスを縮小せざるを得ないとはいえ、アジア地域をそっくりそのまま中国の覇権にゆだねるなんてことは、オバマが余程の馬鹿でもない限りしないでしょう。まあ、もっとも、ゲイツみたいな間抜けが国防長官やっている限り若干のブレが生じ、それが対外的にも波風を立てることはあるだろう。でも、キルギスの件しかり、米国は中国の今後の動向に備えて、東アジアから安易に引くなってことはしないだろう。
その中国は、残念ながら、ダメ。今がムリしすぎで、早晩ボロが出る。それでも「地域」としての中国は発展し続け、国際的なプレゼンスを拡大し続ける。しかし、「国家」としてはこれからさまざまな苦難に喘ぐことになるだろうなあ・・。「地域」として相対的に発展し続け、「国家」として苦悩する? どういうこっちゃ?と思う人もいるだろうが、あの国、地域の歴史を振り返れば、政治的にはハチャメチャでありながら、経済的・文化的には発展を続けるなんてことはよくあったことで、今後しばらくはそういうことになるのではないかと。まあ、だからこそ、台湾有事の可能性は高まるだろうけど。
インド、も期待薄。そもそも、あの国に何を期待するというのだ? 市場としての価値、あるいは中国をけん制するうえでの戦略的価値以外にはなにもない。まあ、それだけあれば十分なのだが、それだけ。世界秩序の構築ないしは維持に何らかの役割を期待?あの自己中度では中国人に負けないインド人にそんなことを期待すること自体、猫にワンと鳴けというようなものだ。それに、あの国はあの国で、発展はするのであろうが、いろいろと問題を抱えていて、混沌も同時並行で続いていく。
では、EU? いや、あそこもダメ。欧州の金融・経済はとてつもなく大変なことになっているはずなのだが、あまりにも平穏すぎる。これこそが、怪しい。しかし、今「隠蔽」されている危機は必ず噴き出して、あの地域を混乱に陥れることになるだろう。最近のドバイの危機に対する欧州の動揺をみるにつけ、やかり導火線は中東か? あそこには、導火線が何本もあるから。どこかで火がつけば、欧州はたちまちに・・。
ロシア? はは、御冗談を。
ブラジル? 所詮ラテンアメリカ。まあ、それなりに発展は続けるだろうが、所詮ちゃらんぽらんですから。
では、残るは神州日本? いや、これもダメ。もっとダメ。米国にイジめられ、円高と輸出減でガタガタ。財政はもう一縷の望みもなし。結局、堕ちるところまで堕ちるしかない。そして、そこから明治維新なみの国家改造を行うしかないでしょう。きっと、後10-20年は苦しみ続けると思うけどなあ。「政権交代」なんてなまやさしいことでは、この国は変わらないし、救われることもないでしょう。
というわけで、世界中が苦しむことになる。でも、苦しみは永久ではない。終わらない冬はない。結局は、柔軟性とダイナミズムに富む米国あたりが、一抜けして、かつてにような存在感は回復できないにしても、やはり大国、超大国の一つとして存在感を示していくのでは?
だから、嫌でも、どんな嫌なヤツでも、米国とはそれなりに付き合っていかなくてはならない。それが日本のみならず、各国の宿命では? 特に、隣にやっかいな国々を持つ我が国は、太平洋をはさんだ隣国の大国との関係はおざなりにはできないでしょう? 米国をいかにうまく利用し、いかに国益を損なわない程度に利用されるか、ってのが日本の対外政略の要であり続けるでしょう、きっと。
つまりそれはトヨタに対してだけではない、「排外」というやつだ。
かつて90年代の始めにも米国衰亡論が論じられ、米国内では国産品購入が推奨されたことがあった。これに似たやつだ。しかも、今後のそれは、かつて米国経済に回復とともに消えてしてまったものとは大きくことなる動きをみせることになり、日本企業はその大波に、おそらく今後当分続く円高の波とともに、翻弄されることになるだろう。つまり、米国は、自由貿易主義を手前勝手にかなぐり捨て、保護主義的な方向に走るだろう。建前では自由主義貿易の放棄なんて決して言うまい。でも、実質的には国内産業保護、外国企業・製品排除の方向に向かうだろう。なぜなら、米国景気は今後当分回復しないからだ。「本音と建前」は日本人の専売特許のように言われるが、実は、欧米人こそ狡猾にそれを使い分けるという事実を知るべきだ。表向きは耳触りのいい原理原則や理想を雄弁に語りながら、裏では一般の日本人には考えの及ばないようなえげつないことをするのが欧米人なのだ。
かといって、戦後の日米関係をすっかり清算してしまえば良いという単純なものではない。残念ながら、我が国にそうする力も準備もない。ただ、米国に対する見方、姿勢をもっと計算づくの怜悧なものに切り替えていく必要はある。おかしな対米幻想を抱かないことだ。米国から学ぶべきを学ぶのは良い。今後も続けようでないか。しかし米国は理想郷ではないし、「友人」でもない。あくまでも、互いの計算づく、狐と狸の化かしあいをしながらの、関係でしかないのだから、所詮。所詮、人種、宗教等の壁は越えられない。あの人たちは、我々とは「違う」、完全に理解しあうなんてはムリ。でも、まだ利用価値はある、ということなんだろうなあ・・。いかに米国が対外的な軍事的なプレゼンスを縮小せざるを得ないとはいえ、アジア地域をそっくりそのまま中国の覇権にゆだねるなんてことは、オバマが余程の馬鹿でもない限りしないでしょう。まあ、もっとも、ゲイツみたいな間抜けが国防長官やっている限り若干のブレが生じ、それが対外的にも波風を立てることはあるだろう。でも、キルギスの件しかり、米国は中国の今後の動向に備えて、東アジアから安易に引くなってことはしないだろう。
その中国は、残念ながら、ダメ。今がムリしすぎで、早晩ボロが出る。それでも「地域」としての中国は発展し続け、国際的なプレゼンスを拡大し続ける。しかし、「国家」としてはこれからさまざまな苦難に喘ぐことになるだろうなあ・・。「地域」として相対的に発展し続け、「国家」として苦悩する? どういうこっちゃ?と思う人もいるだろうが、あの国、地域の歴史を振り返れば、政治的にはハチャメチャでありながら、経済的・文化的には発展を続けるなんてことはよくあったことで、今後しばらくはそういうことになるのではないかと。まあ、だからこそ、台湾有事の可能性は高まるだろうけど。
インド、も期待薄。そもそも、あの国に何を期待するというのだ? 市場としての価値、あるいは中国をけん制するうえでの戦略的価値以外にはなにもない。まあ、それだけあれば十分なのだが、それだけ。世界秩序の構築ないしは維持に何らかの役割を期待?あの自己中度では中国人に負けないインド人にそんなことを期待すること自体、猫にワンと鳴けというようなものだ。それに、あの国はあの国で、発展はするのであろうが、いろいろと問題を抱えていて、混沌も同時並行で続いていく。
では、EU? いや、あそこもダメ。欧州の金融・経済はとてつもなく大変なことになっているはずなのだが、あまりにも平穏すぎる。これこそが、怪しい。しかし、今「隠蔽」されている危機は必ず噴き出して、あの地域を混乱に陥れることになるだろう。最近のドバイの危機に対する欧州の動揺をみるにつけ、やかり導火線は中東か? あそこには、導火線が何本もあるから。どこかで火がつけば、欧州はたちまちに・・。
ロシア? はは、御冗談を。
ブラジル? 所詮ラテンアメリカ。まあ、それなりに発展は続けるだろうが、所詮ちゃらんぽらんですから。
では、残るは神州日本? いや、これもダメ。もっとダメ。米国にイジめられ、円高と輸出減でガタガタ。財政はもう一縷の望みもなし。結局、堕ちるところまで堕ちるしかない。そして、そこから明治維新なみの国家改造を行うしかないでしょう。きっと、後10-20年は苦しみ続けると思うけどなあ。「政権交代」なんてなまやさしいことでは、この国は変わらないし、救われることもないでしょう。
というわけで、世界中が苦しむことになる。でも、苦しみは永久ではない。終わらない冬はない。結局は、柔軟性とダイナミズムに富む米国あたりが、一抜けして、かつてにような存在感は回復できないにしても、やはり大国、超大国の一つとして存在感を示していくのでは?
だから、嫌でも、どんな嫌なヤツでも、米国とはそれなりに付き合っていかなくてはならない。それが日本のみならず、各国の宿命では? 特に、隣にやっかいな国々を持つ我が国は、太平洋をはさんだ隣国の大国との関係はおざなりにはできないでしょう? 米国をいかにうまく利用し、いかに国益を損なわない程度に利用されるか、ってのが日本の対外政略の要であり続けるでしょう、きっと。