反日デモのすさまじさを見ておどろかれている人も少なくないはずです。
現地にいる邦人は戦々恐々でしょう。見境なしの暴力、破壊、掠奪ですから。
でも、これは今に始まった話ではありません。TVのコメンテーターのなかには「反日教育がモンスターを作り上げた」なんていうこと言っている人もいます。確かにそういう一面もあるでしょうが、もし群衆を「モンスター」というのであれば、中国民衆には昔からそのモンスター性が
宿っているということになります。
私はあえて、モンスターとはいいませんが、あの国には昔から日本人にはいささか感覚的に理解しがたい暴力性があるというのは否定できないでしょうね。
例えば、帝国主義の時代、しばしば教案というキリスト教伝道師や教会、協会付属施設、中国人キリスト教徒に対する虐殺という行為をも含めた集団暴力が19世紀の後半にたびたびおこったのですが、その類の大規模排外暴力は日本では起こっていません。
似たような集団暴力は、辛亥革命の際、そしてその後1910年代、20年代を通して繰り返し発生します。そのうち最も知られているのが、1927年のいわゆる南京事件、1928年の済南事件ではないでしょうか。今映像で見ている以上の直接的な暴力が邦人やその他の外国人に、老若男女の別を問わず降りかかったのです。そして、事件処理にあたって容易に謝罪しない、賠償に応じないのも、あの国の昔ながらの姿勢です。
排外はさておいても、集団暴力というのは、共産党支配下においてある意味あの国の日常だったことを忘れてはなりません。1949年人民共和国以前のいわゆる解放区での諸政治運動は、たびたび大衆動員というかたちでおこなわれましたが、それにもやはり流血を含む暴力が伴いました。
人民共和国成立後も、暴力を肯定した太守運動は文革終焉まで繰り返し続きます。しかも、その暴力は地方にいくたびにむき出しの残虐性を帯びていきます。存命の老共産党員のなかには、反右派闘争、大躍進や文革で自ら暴行、殺人に関与した人は少なくないはずですよ。政治運動、政治闘争が暴力を伴うことが日常ですし、そうしないと彼ら自身生き残れなかったのですから。
そうした政治的、社会的DNAを受け継いだ民衆、群衆が今、自分たちの先祖、祖父母、親と同じことを繰り返しているのです。
本来ならそうした集団暴力性は公教育によって是正されてしかるべきですが、共産党政権はそれを十分してこなかった。いや、共産党自身にとっても、暴力とはごく当たり前の政治の手段ということなのではないでしょうか。それに、共産党は、政治における暴力を全面否定はできないのかもしれません。なぜならば、暴力の行使は少数民族支配や宗教団体への弾圧に典型的にみられるように、国家統治のための欠くべからざる手段だからです。更に、暴力の否定は、毛沢東の否定につながりかねません。共産党にとって部分的批判はできても、全否定はできない、それが毛沢東なのです。毛をスターリン批判のようにやり込めてしまえば、それは小平批判にもなります。そうなれば、江沢民も胡錦濤も同じ穴のムジナ。一蓮托生になりかねません。
だからといって、「シナ人は怖い」というのは、短絡過ぎるのかもしれません。いえ、確かに怖いです。暴力に対してあれほど寛容かつ慣れ親しんだ大群衆を隣人に持つ日本人が、恐怖したとしても、それも致し方のないことでしょう。
が、我々日本人が平和ボケしているという部分もあるのではないでしょうか。政治と暴力は古今東西を問わず不可分であることを我々は忘れるべきではありません。暴力は政治の一手段です。そして暴力は日常生活のどこにでもあることです。そう考えれば、「シナ人、中国人は怖い!」が少しは和らぐのでは?
え、和らがない?
確かに、かくいう私も、言葉とは裏腹に政治と暴力の関係を皮膚感覚で認識できていないんですよねえ・・・。
現地にいる邦人は戦々恐々でしょう。見境なしの暴力、破壊、掠奪ですから。
でも、これは今に始まった話ではありません。TVのコメンテーターのなかには「反日教育がモンスターを作り上げた」なんていうこと言っている人もいます。確かにそういう一面もあるでしょうが、もし群衆を「モンスター」というのであれば、中国民衆には昔からそのモンスター性が
宿っているということになります。
私はあえて、モンスターとはいいませんが、あの国には昔から日本人にはいささか感覚的に理解しがたい暴力性があるというのは否定できないでしょうね。
例えば、帝国主義の時代、しばしば教案というキリスト教伝道師や教会、協会付属施設、中国人キリスト教徒に対する虐殺という行為をも含めた集団暴力が19世紀の後半にたびたびおこったのですが、その類の大規模排外暴力は日本では起こっていません。
似たような集団暴力は、辛亥革命の際、そしてその後1910年代、20年代を通して繰り返し発生します。そのうち最も知られているのが、1927年のいわゆる南京事件、1928年の済南事件ではないでしょうか。今映像で見ている以上の直接的な暴力が邦人やその他の外国人に、老若男女の別を問わず降りかかったのです。そして、事件処理にあたって容易に謝罪しない、賠償に応じないのも、あの国の昔ながらの姿勢です。
排外はさておいても、集団暴力というのは、共産党支配下においてある意味あの国の日常だったことを忘れてはなりません。1949年人民共和国以前のいわゆる解放区での諸政治運動は、たびたび大衆動員というかたちでおこなわれましたが、それにもやはり流血を含む暴力が伴いました。
人民共和国成立後も、暴力を肯定した太守運動は文革終焉まで繰り返し続きます。しかも、その暴力は地方にいくたびにむき出しの残虐性を帯びていきます。存命の老共産党員のなかには、反右派闘争、大躍進や文革で自ら暴行、殺人に関与した人は少なくないはずですよ。政治運動、政治闘争が暴力を伴うことが日常ですし、そうしないと彼ら自身生き残れなかったのですから。
そうした政治的、社会的DNAを受け継いだ民衆、群衆が今、自分たちの先祖、祖父母、親と同じことを繰り返しているのです。
本来ならそうした集団暴力性は公教育によって是正されてしかるべきですが、共産党政権はそれを十分してこなかった。いや、共産党自身にとっても、暴力とはごく当たり前の政治の手段ということなのではないでしょうか。それに、共産党は、政治における暴力を全面否定はできないのかもしれません。なぜならば、暴力の行使は少数民族支配や宗教団体への弾圧に典型的にみられるように、国家統治のための欠くべからざる手段だからです。更に、暴力の否定は、毛沢東の否定につながりかねません。共産党にとって部分的批判はできても、全否定はできない、それが毛沢東なのです。毛をスターリン批判のようにやり込めてしまえば、それは小平批判にもなります。そうなれば、江沢民も胡錦濤も同じ穴のムジナ。一蓮托生になりかねません。
だからといって、「シナ人は怖い」というのは、短絡過ぎるのかもしれません。いえ、確かに怖いです。暴力に対してあれほど寛容かつ慣れ親しんだ大群衆を隣人に持つ日本人が、恐怖したとしても、それも致し方のないことでしょう。
が、我々日本人が平和ボケしているという部分もあるのではないでしょうか。政治と暴力は古今東西を問わず不可分であることを我々は忘れるべきではありません。暴力は政治の一手段です。そして暴力は日常生活のどこにでもあることです。そう考えれば、「シナ人、中国人は怖い!」が少しは和らぐのでは?
え、和らがない?
確かに、かくいう私も、言葉とは裏腹に政治と暴力の関係を皮膚感覚で認識できていないんですよねえ・・・。











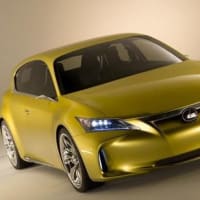












当局が規制を指示しただけで、デモが収まる・・・この事実が、かの国の現実を表しています。革命ですら、次の皇帝を狙う理由でしかない国ですから、当然ですか・・・。